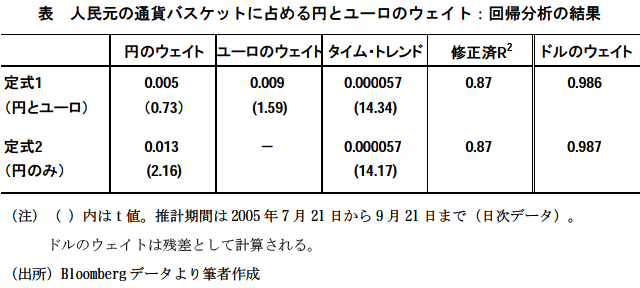変動よりも管理に重点が置かれた中国の為替政策
中国は2005年7月21日夜、翌日に人民元の2%程度の切り上げを実施するとともに、これまでのドルペッグ制を改め、「市場の需給を基礎とし、通貨バスケットを参考に調整される」管理変動制に移行すると発表した。中国人民銀行貨幣政策委員会委員である余永定氏は、今回採用された新しい為替制度について、国際金融の教科書にも登場するBBC方式であり、変動幅(Band)、通貨バスケット(Basket)、そしてクローリング(Crawling:ある方向性を持って為替レートを微調整していくこと)に基づく管理変動制だと解説している(「人民元為替制度改革という歴史的決定」、『金融時報』、2005年7月23日)。しかし、新しい制度が導入されてからも、人民元の対ドル上昇は当局の市場介入によって抑えられ、為替政策の運営にあたっては変動よりも管理に重点が置かれており、BBCのCの部分はクローリングというよりも、むしろコントロール(Control)という色彩が強い。
一方、新しい制度の下では、毎日、前日の終値を基準に、+/-0.3%のバンドが設けられ、取引はその中に制限されているが、このバンドをフルに活かせば、人民元を毎日最大0.3%上昇させ、短期間に大幅な上昇を実現することが可能になった(図1)。現段階では、人民元の実際の変動幅は、+/-0.3%よりさらに狭くなっているが、将来的には、政府が市場への介入を控えることで、バンド内における為替レートの変動幅が大きくなり、いずれはバンド自体も段階的に広げられるだろう(注)。
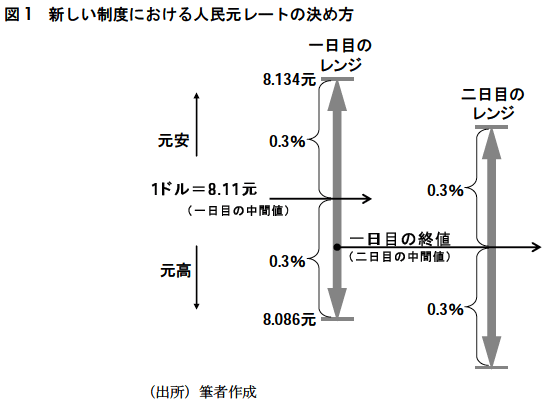
また、為替レートの決定において、通貨バスケットが参考の対象となっている。その構成通貨には、ドル、ユーロ、日本円、韓国ウォン、シンガポールドル、英国ポンド、マレーシアリンギット、ロシアルーブル、オーストラリアドル、タイバーツ、カナダドルが含まれていると周小川・人民銀総裁が示唆しているが、それぞれのウェイトについては明らかにされていない。新しい制度に移行してからも人民元の対ドルレートが安定していることからもわかるように、通貨バスケットに占めるドルのウェイトは高く、円やユーロなどそれ以外の通貨のウェイトは低いと考えられる(図2)。この結論は回帰分析を行うことによっても確認できた(BOX参照)。しかし、このままでは、せっかく期待された通貨バスケットによる輸出の自動安定装置としての効果が限られてしまう。中国は、貿易や直接投資を通じて日本を始めとする経済関係が緊密化している中で、今後、通貨バスケットにおけるこれらの通貨のウェイトを上げていくことを通じて、域内通貨に対する安定性を高めていくことは自然な流れであろう。
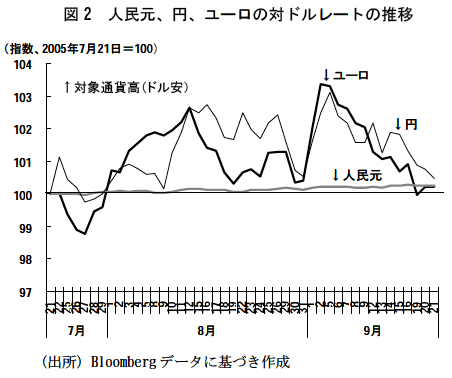
さらに、為替を安定化させるためには、政府が引き続き市場に介入しなければならず、その結果、外貨準備も増え続けるだろう。中国の外貨準備は2005年6月に7110億ドルに達し、しかも月間200億ドルほどのペースで増えていることを考えれば、来年の初め頃には中国が日本(2005年8月現在、8478億ドル)を抜いて世界一の外貨準備保有国となろう(図3)。これがニュースとして世界中のメディアに大きく取り上げられることになれば、人民元の切り上げ期待、ひいては人民元に対する投機が一層高まるきっかけになりかねない。一方、介入に伴う国内のマネーサプライの増加を抑えるために、中央銀行は引き続き、短期証券を大量に発行する形で、不胎化を行わなければならない。その結果、人民元改革により期待された金融政策の独立性の向上も実現できていない。
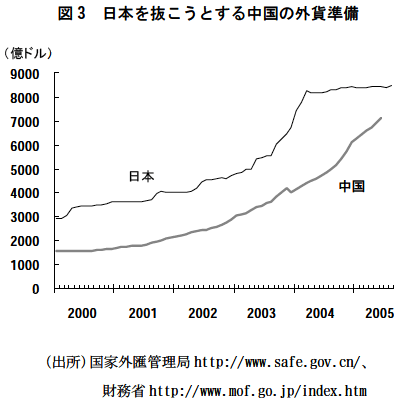
真の変動為替制に向かってさらなる改革を
このように、今回の為替制度の変更は、あくまでも人民元改革への第一歩にすぎず、今後、できるだけ介入を減らし、為替レートの決定を市場に任せる方向で「管理」を緩め、本当の意味での変動為替制に近づけなければならない。その結果として、これまで見られた外貨準備の上昇の代わりに、中長期にわたって人民元がドルに対して上昇傾向を辿ることになるだろう。
【BOX】 通貨バスケットの推計
中国が為替政策を運営する際に参考としている通貨バスケットにおける各通貨のウェイトは、人民元の対ドルレート(対数値)を被説明変数に、円やユーロといった主要通貨の対ドルレート(対数値)を説明変数に回帰分析を行うことによって推計することができる。推計された各説明変数の係数が通貨バスケットに占めるそれぞれのウェイトに当たり、計算単位であるドルのウェイトは(100%から他の通貨のウェイトを引いた)残差として求まる。ただし単純化のために、説明変数となる通貨はウェイトの高いと思われる円とユーロに絞った。またクローリングのスピードを確認するために、説明変数にはタイム・トレンドを加えている。その結果、円のウェイトが0.5%、ユーロのウェイトが0.9%と、両者を合わせてもわずか1.4%にとどまっていることがわかった(定式1)。推計されたタイム・トレンドは人民元が平均1日0.000057%上昇していることを示している。この上昇率は、為替市場の営業日が年間250日であると仮定して換算すると、年率1.4%であり、非常に緩やかなペースになっている。説明変数からユーロを除いた推計(定式2)では、タイム・トレンドは変わらないが、円のウェイトが1.3%と若干大きくなる。いずれのケースにおいても、残差として計算されるドルのウェイトが非常に大きいことが示されている。(表)