今日、我が国の少子化は急速に進み、2007年の合計特殊出生率は1.34と、依然として先進国で最も低い水準にある。2005年からは死亡数が出生数を上回る長期の人口減少過程に入り、2055年には我が国の総人口は9000万人を割ることが見込まれている(2009年版『少子化社会白書』)。
特に戦後ほぼ一貫して三大都市圏より人口増加率が低かった地方圏では人口減少がより顕著であり、我が国全体に先駆けて2002年から人口減少が始まっている(平成18年度『国土交通白書』)。人口の減少および人口構造の変化に伴い、労働力人口が高齢化しながら減少していき、経済成長にマイナスの影響を及ぼす可能性も指摘されている(同白書)。
このような人口減少経済の到来を受け、都市への人口集積を行うことによる成長戦略が注目されている。八田(2006)は、従来の都心抑制策から都心回帰可能型政策への転換が行われた場合、都市集積がもたらす生産性向上の便益は通勤混雑増加の費用を大幅に上回ることを指摘している(注1)。また、Albouy and Seegert(2009)は、現状の大都市の人口規模は、経済的に最適水準である人口規模を下回っている可能性を指摘している(注2)。
そこで本コラムでは、主に成長戦略の観点から、人口集積が経済成長に与える影響を分析した先行研究や筆者の研究成果を紹介しつつ、人口減少下での都市政策のあり方について考察したい。
成長起爆剤としての「人口集積」
そもそも、人々は自己の効用を最大化するため、最適な地域を探して移動する誘因をもつ。この意味を明確に理解するため、簡単なケースを考えよう。いまA地域(都市部)と、そこから少し離れたB地域(過疎地)があるとする。また、都市部Aの生産性は高く、その集積効果から公共財も効率的に供給できるものの、過疎地Bはそうでないとする。そして、A地域の賃金は20、アメニティ(例:多様なショップ)5、公共財供給にかかる税負担は住民一人当たりf6(=公共財5+行政コスト1)である一方、B地域は賃金11、アメニティ(例:自然)4、税負担8(=公共財5+行政コスト3)であり、人口規模が2倍の都市Aから過疎地Bに地域間移転4があるとしよう。このとき、A地域の住民の効用は20(=20(賃金)+5(アメニティ)+5(公共財)-6(税負担)-4(地域間移転))であり、B地域の効用は20(=11(賃金)+4(アメニティ)+5(公共財)-8(税負担)+4×2(地域間移転))であるから両地域の効用は同じとなっている。ここで、都市部Aから過疎地Bへの地域間移転を縮減していくと、何が起こるだろうか。その場合、地域Aの住民の効用の方が地域Bよりも高くなるから、過疎地Bから都市部Aへの人口移動が起こる。そして、同じ生産や公共財を供給する場合でも、集積地域の方が物流・行政コストは低いから、経済はより効率的となり、両地域を合わせたGDPは増加するのが一般的である。つまり、人口集積は、経済成長を促進させる。
この単純な法則は、人口減少下の日本が成長戦略との関係で、今後の都市政策を検討する際、最も重要な視点となる。もっとも、あまり過密な人口集積はさまざまな混雑費用を増加させ、逆に経済成長を低下させてしまう恐れもある。その場合、政府は最適な人口集積を目標に、都市部への過度な人口流入を抑制する必要がある。この目標を達成する政策手段の1つが、地方交付税に代表される地域間移転政策とみることもできる。もし地方交付税に代表される地域間移転政策を縮減すると、地方財政は過疎地よりも都市部の方が豊かだから、地域間の格差は拡大する。さらに、過疎地よりも都市部の方が経済活力も高いので、より豊かな生活を目指して、より多くの人々が都市部に流入してくる。すなわち、地域間移転政策は都市部への過度の人口流入を抑制する機能を持つものの、逆に、都市部の人口集積を図るには、過疎地への地域間移転を段階的に縮減していけばよい。
国全体に波及する特定地域の経済成長
ところで、戦後日本の人口移動と経済成長については、近年の縄田(2008)をはじめさまざまな先行研究があるが、以下の図表1のように、三大都市圏への人口移動と経済成長の推移は概ね連動している(注3)。この図表をみると、70年代以降に経済成長が屈折しているが、この要因について八田(2001)は「70 年代以後の『国土の均衡発展』論に基づいた分散政策は、生産性の低い地域に資源を引き留めるための政策であり、それがその後の日本の低成長をもたらした」と指摘している(注4)。また、増田(2004)は、「70 年代前半に大都市圏への人口移動と経済成長率の減速が同時進行したのは、この頃地方での公共事業が急拡大されたから」としている(注5)。なお、そもそも、三大都市圏への人口移動と経済成長に関する因果関係に対する問題もあるが、上述の縄田(2008)は、これら八田(2001)や増田(2004)等の先行研究を紹介し、1970 年代以降の経済成長率の低下の理由を国土の均衡ある発展を求める政策にのみ帰すことについては異論があろうと留保しつつも、地方から都市への人口移動を抑制する政策が企業の経済活動の柔軟性を低下させたと結論付けている。
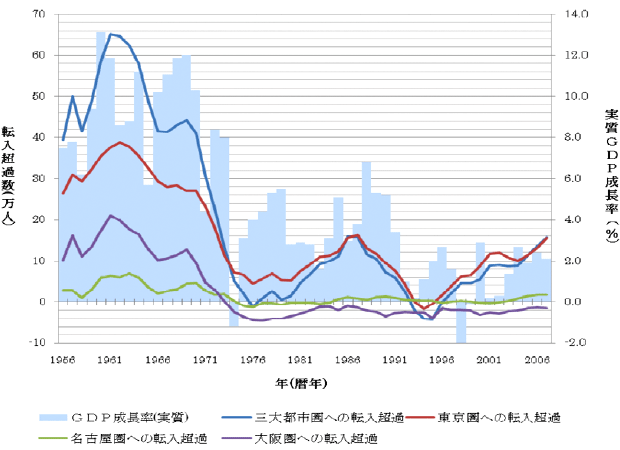
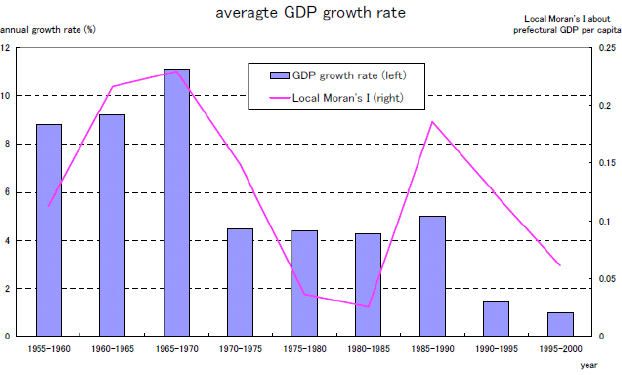
しかも、石田(2009)等の研究によると、特定地域での経済成長が活発な方が国全体の成長は高いことが明らかになってきた(注6)。上の図表2は、戦後日本の国全体の経済成長率と県別経済成長率データから空間解析という手法を用いて分析した結果だが、これをみると、県別経済成長の空間集積度が高い時期、すなわち経済活動が一部地帯で活発な時期の方が、各県の経済成長率が比較的均質な時期よりも、国全体としての経済成長率が高い傾向にあることが読み取れよう。
これらの研究は都市圏への人口集積が、都市圏だけでなく日本全体の経済成長につながる可能性を示唆している。同様に、三大都市圏への人口集積だけでなく、中核都市(各地方における中核的な機能を担う都市)への人口集積も地方の経済成長を促進させる。以下、この点もみておこう。
まず三大都市圏においては、昭和40年代から50年代にかけて、ドーナツ化現象が進み、東京23区等では、人口は転出する一方だった。しかし、最近では、地価下落等による都心部におけるマンション供給の著しい増加等を背景に、東京23区内への転入が超過しており、その数も年々増加している。同様の現象は名古屋市、大阪市においても見られ、名古屋市では2002年より4年連続、大阪市では2001年より5年連続で転入超過が進み、三大都市圏において「都心回帰」が進んでいるといえる。
また、地方圏においても、中核都市の求心力が高まっている状況が見られる。たとえば、福岡県の人口の九州ブロック総人口に占める割合が、1950年の27.1%から、2005年には34.3%まで上昇しており、中枢都市である福岡市の拠点性の向上に伴う人口動向が観察される(平成18年度『国土交通白書』)。
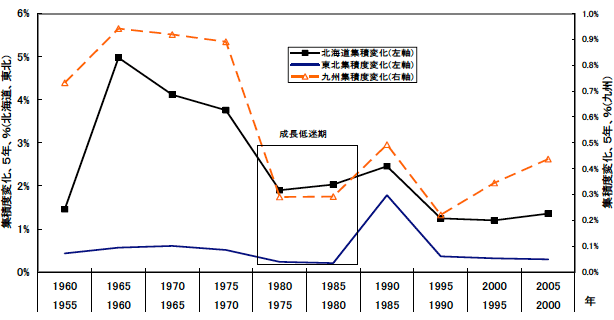
このような状況において、筆者らは、中核都市への人口集積が地方経済にもたらす影響を分析した。まず北海道・東北・九州地方における人口集積度を計算した。ここで人口集積度とは、人口のうち中核都市の占める人口の比率(%)を指すことにし、中核都市とは具体的には札幌市、仙台市および福岡市を指すことにした。人口集積度の変化をみると、上の図表3のとおり、北海道・東北・九州地方では戦後ほぼ一貫して人口集積度が増加しているが、成長低迷期には人口集積度の増加が鈍化している傾向がみられる。
実際、北海道・東北・九州地方の経済成長率と人口集積度変化を比較すると、以下の図表4のとおり、人口集積度変化と地方経済成長率には正の相関が確認できる。人口集積度変化が経済成長の原因であるか結果であるかはこれらの分析からだけでは断言できないものの、日本全国における分析と同様、北海道・東北・九州地方についても中核都市への人口集中が地方経済成長につながる可能性を示唆する(注7)。
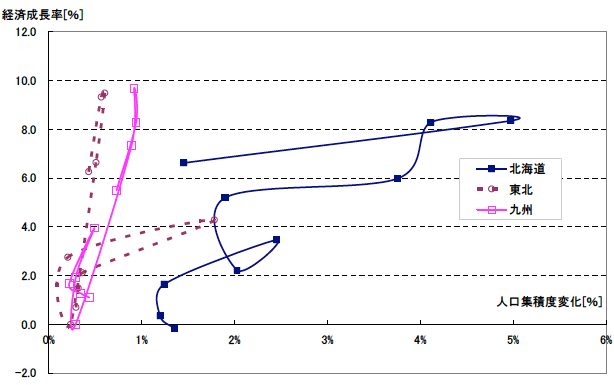
(参考)直線近似
・北海道 経済成長率[%]=1.824×人口集積度変化[%]-0.2671[%], R2=0.6196
・東北 経済成長率[%]=2.034×人口集積度変化[%]+3.229[%], R2=0.0732
・九州 経済成長率[%]=11.39×人口集積度変化[%]-2.256[%], R2=0.9078
地域間移転の選択と集中を進め、各成長戦略に資する総合的な都市政策を
以上のとおり、三大都市圏への人口集積は経済成長、また地方中核都市への人口集積は地方経済成長を促進させる可能性を持つ。さらに、三大都市圏や地方中核都市への人口集積を促進するためには、地方交付税に代表される地域間移転の選択と集中を図っていく政策が必要となる。もっとも、既に大都市が最適人口規模を超過している場合、そのような政策は望ましくないが、冒頭の八田(2006)やAlbouy and Seegert(2009)が指摘するように、現状の大都市の人口規模は、経済的に最適水準である人口規模を下回っている可能性が高い。
さらに、これから日本はますます人口減少が進み、過疎地の高齢化はさらに進むことが予測される。このような状況においては、資源を大都市・中核都市に集約することが効率的かつ効果的である。特に、高齢者にとっては、自宅から徒歩で移動できる範囲に、スーパー・ドラッグ・病院・介護施設などさまざまな商店が集約的に立地している環境が望ましい。また、職をもつ若い世代にとっても、自宅・職場・娯楽施設が隣接している方が、快適な暮らしができよう。このような発想で、国土交通省は2006年、「コンパクトシティ」推進のため、1998年制定のまちづくり3法の一部を改正し、大都市・中核都市の集約を促進しようとしているが、それら制度は十分に機能していないとの指摘も多い。その背景にはさまざまな要因があるが、たとえば、移動コストも関係している。実際、移動コストには住宅などのサンク・コストも含まれるから、人口移動が実際に起こるのは、移動の限界便益がそのコストを大幅に超過し一定の臨界点に到達した場合に限るだろう。この限界便益を変化させる最も簡単な方法は、都市部と過疎地の地域間移転の見直しである。すなわち、人口集約の促進には、過疎地への非効率な資源分配を段階的に縮減しつつ、地域間移転の選択と集中を推し進め、都市部に移動する方が得となる誘因を構築することが不可欠である。
以上に加えて、成長戦略の観点から、日本全体の都市政策を検討する際には、「成長戦略→ワークプレース→建物→立地」という流れに沿って検討を進めていく必要があるかもしれない。所詮、都市政策は、IT産業・教育・医療・農業などの各戦略をサポートする手段に過ぎない。どの地域を東アジア最先端の医療センターにし、どの地域を世界トップ水準の教育センターにするのか、各目的に沿った形での人口集積、そして都市政策が求められるからである。また、中国やインドなどの新興国が台頭しつつある今、これからの日本に求められるのは、知識経済化しつつあるグローバル経済で勝利をおさめることができる「クリエイティブ」な構想力を多く創出する環境整備であろう。たとえば、高度な政策立案やコンサルティングなどのクリエイティブな職に就く人々にとっては、似た問題意識を持つ者同士が気軽に意見交換ができ、イノベーションを創り出す環境が不可欠であり、そのような職に没頭するには移動時間はできる限り少ない方がよい。また、成果主義で勤務時間が自由な人々にとっては、ニューヨークのように、地下鉄等の交通機関は24時間稼働していることが望ましい。このような視点も含め、人口減少下の都市政策のあり方を検討していくことが望まれる。
最後に、上記の分析は、あくまでも過去の人口動態および経済成長率に基づくものである。人口政策と経済成長については、都市経済学等のより深い研究が行われるとともに、建造物の各種規制政策、地方交付税による所得移転政策、公共事業政策など多岐にわたる関連政策を視野に入れつつ、冷静かつ積極的な議論が進められていくことを期待したい。


