中国の漸進的改革は、(1)改革の進展に合わせ、改革の目標モデルも絶え間なく変化する、(2)諸改革は「双軌制」(体制の二重構造)による移行方法を取り入れている、(3)改革当初の国有経済改革は基本的に自主権の付与に限られていた、といった特徴を持っている。ここでは各々の特徴について分析する。
一、改革目標の調整と進化
漸進的改革の基本的な特徴の一つは、改革の進行と深化や主観的・客観的状況の変化に伴い、改革の目標が修正・調整されることである。
中国は改革当初、永久不変の目標モデルを打ち出さなかった。東欧諸国には「欧州に復帰する」という明確な目標があった。現在のロシアも、私有制を認めた自由な市場経済を創るという明確な目標を持っている。しかし、中国の改革には、終始一貫した目標モデルがあるわけではない。ただ、これは中国人が誰一人として(官僚や学者を含む)、いかなる時も心の中に終始一貫した改革目標を持っていないということではなく、一種の公共選択の結果として政府および社会の大多数者に受け入れられる改革目標が、当初は不明確であり、その後、絶えず調整され、変化し、予想される将来も一層調整されて変化するということである。政府の発表(「政府文書」を公共選択あるいは「妥協」の結果の現れとして捉えてもよい)をたどってみると、改革目標は、「計画経済を主とし、市場調節を補助とする」段階から、「計画経済と市場調節が結合する」段階を経て、現在の「社会主義市場経済」に至っている。これは、まさしく目標モデルが不明確で、常に調整されていることを反映している。
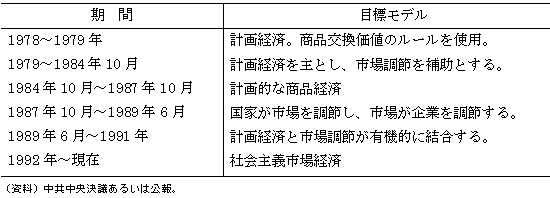
ここ二十数年の改革の基本的な成果は、市場経済メカニズムの初歩的段階が形成されていることである。しかし、改革当初、多くの人々、特に政策決定者の目標は、市場経済を確立することではなく、従来の体制に若干の市場的要素を導入するに過ぎなかった。言い換えれば、市場的要素の良い面をある程度利用することである。当時(およびその後)の中国の状況と、他の計画経済国の五、六十年間の発展の結果がはっきりと示しているのは、古い経済体制は成功せず、従来の体制と政策手段だけで経済の諸問題を解決することができないため変える必要があり、新しいもの、すなわち市場という要素を少なくとも導入する必要がある、ということである。その後、計画経済の制度的枠組では、市場はその機能を十分に発揮することができず、中国が直面する経済問題を解決するには計画経済を放棄し、経済運営全体を市場メカニズムに委ねなければならないということが認識された。鄧小平氏の有名な「石を探りながら川を渡る」との考え方は、実践的な立場から目標論の意味を含んでいる。すなわち、「川を渡らなければならない」ことは明白だが、「川を渡る」ことは問題の解決を指しているだけであり、どこに上陸するのか、川の向こう側はどのような経済体制であるのかについてすでに分かっているというわけではない。「石を探る」ということは、方法論の面において困難を避けるという意味合いを持っているだけではなく(この点については後に詳しく述べる)、具体的な改革目標の可変性と調整可能性を示唆している。
しかし、徹底された案も明確な目標もないため、全面的かつ総合的な改革案を打ち出すことはできていない。多くの人々は、あらゆる改革を網羅した全面的な改革案をあみ出そうとし、政策決定者も改革をより全面的なものにしようとしたが、実行に移すことはなかった。改革は最初から「試行錯誤」(trial and error)という特徴を持っていたのである。
しかし、上述したことは、実際の改革が自覚的にあるいは非自覚的にある一定の方向に向かって前進していることを否定しているわけではない。変革を継続する必然性と政策決定者の実務主義(黒猫でも白猫でもねずみを捕る猫が良い猫)により、中国の改革は当初明確な目標がなかったが、実際には経済建設に向けて市場の要素を絶えず増やし、経済効率を高めるという明確な方向性を持っていたため、改革は当初から市場志向の性質を持っていた。確かに、当初、市場の発展は制限されていたが、一旦動き出すと、自由な取引にとどまらず、非国有経済の発展、対外開放などの定着につながったのである。要するに、改革当初、中国の政策決定者は徹底した明確な改革目標を持っていなかったし、当初の(市場に関連する)政策も細かいものばかりで改革の重点ではなかったが、知らないうちに市場経済化という改革の道を歩み、その後の市場経済の育成と発展に大きな役割を果たしたのである。
二、一般的な改革手法である「双軌制」
「双軌制」は価格改革の分野で最初に実施された。すなわち、「価格双軌制」(二重価格制)である。ほかの多くの改革(例えば農村改革)と同じように、「価格双軌制」(多重価格制の場合もある)は実務家が創り出した改革方式である。「双軌制」の基本的な考え方は、既存の製品は計画価格に基づいて供給、配分されるが、新たに生産された製品については、生産者が市場価格で販売し、定量(定価)による供給に満足しない消費者は自由市場で買う。そして、生産の拡大に伴い市場で取引される分が増えるにつれ、計画価格を逐次的に改革し、最終的には撤廃し、市場価格への収斂を実現することである。「双軌制」は、確かに実施の過程において問題をもたらした。例えば、レント・シーキングの規模の拡大、腐敗の増加による社会の不安定性の増大、「官倒」(不正な商取引を行う役人)という新しい利益集団の発生が市場価格への収斂を妨げたばかりでなく、役人が自らの利益のために計画価格の割合を増大させた時期さえあった。しかし、総体的に見て「価格双軌制」は成功した。食品価格改革を例にとってみると、92年に食糧配給切符や食用油配給を全面的に廃止したが、これにり、なかなか解決できなかった食品価格補填問題は15年間の「双軌制」という過程を経て、比較的少ない痛み(民衆が感じた痛み)で最終的に解決することができた。
「双軌制」はその後、多くの改革分野に応用されている。対外貿易体制改革、労働・雇用制度改革、所有制構造改革、社会保障制度改革、住宅制度改革などである。したがって、「双軌制」による移行は、中国の改革の基本的な方法の一つと見なすことができる。その考え方は、次のように要約することができる。すなわち、旧体制を残したまま増量の部分に新体制を導入し、全体に占める新体制の割合が増えるにしたがって徐々に旧体制を改革し、最終的には新体制へと全面的に移行するのである。
経済全体で見ると、改革の推進と市場メカニズムの発展にとって最も重要で、影響が最も大きい双軌制は、所有制構造における双軌制、すなわち国有制と非国有制、公有制と非公有制からなる双軌制である。当初の所有制改革の出発点は非常に単純で、雇用の拡大や資金の補充などの現実的な問題を考慮し、伝統的な国有部門を補助するために郷鎮企業や個人・民間経済、外資、合弁企業の育成と発展を認めただけであり、国民経済に占める割合は非常に小さかった。しかし、意外にも、非国有経済は認められた途端に国有経済よりも速いスピードで発展し、十数年で工業総生産と国民総生産に占める割合はすでに60%を超えた。中国の市場経済メカニズムの初歩的な段階が形成され、資源配分に重要な役割を果たし、国民経済が比較的速く成長し、人々の実質所得水準は比較的速く上昇している背景には、国有経済の改革だけではなく、非国有経済の発展がある。
非国有経済の成長と国民経済における所有制構造の変化の結果、「双軌」(二重)体制が形成された。中国の非国有経済は伝統体制の隙間をぬって成長してきてはいるが、成長の過程において国有経済と様々な経済関係を結んだことに加え、外部の諸条件や諸制度によって、その運営メカニズムが他の国の民営経済と大きく異なり、財産権の曖昧さが随所に残っているなど、完璧な意味での市場の行動主体にはなっていない。しかし、いずれにせよ、非国有経済は最初から国有企業と違う運営メカニズムであることに違いはない。最も大きな違いは、非国有経済に「良くやればたくさん儲かる」という誘因ではなく、「良くやらなければ破産する」というよりハードな制約がある点である。破産や解雇も可能であり、「親方日の丸」という訳にはいかない。破産できれば、赤字になっても永遠に銀行にツケを廻したり、財政補助や政策的融資に頼って生き残ったりすることもできず、インフレ圧力を増大することはない。確かに、郷鎮企業が借金を踏み倒したり、銀行に返済できなかったりして不良債権になることもあるが、このような不良債権は一般的にこれで終わり、国有企業のように不良債権となってからも借り入れをして不良債権を膨らませることはない。また、倒産できる非国有企業は、マクロ経済の視点から見れば国有経済よりも安定的である。景気が過熱気味の時、非国有企業は予算制約が比較的ハードであるため、投資に慎重となり、熱くなりすぎることがなく、また、景気が冷え込むと(調整期)、破産によってタイムリーに調整することができ、新たな営利機会を探し(国有企業のように調整が難しいということはない)、冷え過ぎになるということがなく、早めに回復することができるのである(1989~91年の調整期に非国有経済は厳しい制限政策の影響を受けたが、91年には成長率が10%にまで回復した)。
三、「放権譲利」のみであった当初の国有経済改革
国有経済の「放権譲利」(decentralization,下級政府や企業に権限を委譲し利益を分ける)という改革は、次のように要約することができる。公有制という基本的な枠組が変わらない状況下で、経営管理メカニズムと利益配分メカニズムを改革し、経営決定権が中央政府から地方政府と国有企業に委ねられ、分権化した公有制とする。この改革は、各種の経営責任制に反映されており、地方政府の財政請負制と企業の請負制もこれに属する。
「放権譲利」により、経営責任制が確立され、高度集権の官僚体制による経済への介入が減少し、生産者・経営者の営利のインセンティブが向上した。この結果、一部の分野で経済技術の効率(X-効率)と配分効率が上昇した。改革以降の国民所得の増加は、国有経済の「放権譲利」と切っても切れない関係にある。分権制は多くの場合、生産性の上昇と経済効率の改善が必ずしも利潤に反映されず、場合によっては利潤率が低下することすらある。しかし、生産額が増え、賃金所得と社会消費総額(各種「公的消費」を含む)が増えれば、社会厚生の水準も上昇する。実際、所有者(国家、政府)の立場で見た利潤率の低下のみ、効率の低下を意味する。しかし、社会厚生の観点から見れば、必ずしもそうではない。利潤率の低下、利益・税金総額の低下、上納利潤の低下、赤字額の増加、財政の赤字補助金の増加、国民所得に対する財政収入の割合の低下などは、生産技術の効率やミクロ的な面での配分効率の悪化を必ずしも意味しないのである。
「放権譲利」がもたらした最大の問題は、所有者の権限と責任が経済活動の中で脆弱化し、経済の動態的効率とマクロ的な配分効率が低下したことである。どの経営責任制も、誰が資本の損失に対して責任を負うかという問題に明確な回答を出していない。国有経済では、管理者にしても労働者にしてもすべての人が資本の使用者であるため、「放権譲利」の実施によって、企業の予算制約がハード化したどころか、資本の利益がかえって侵害され、賃金やボーナス、福祉、各種の「公的消費」、大量のぜいたく品の購入に反映されるような個人所得の伸び率が、生産(付加価値)や利潤総額、利潤・税金総額の伸び率を大きく上回った。この結果、付加価値に対する資本分配率や、国民所得に対する財政収入の比率、投資の原資となる留保利潤の低下をもたらし、多くの資本の減価償却も所得配分の対象とされ、職権の乱用や汚職・腐敗などにより国有資産が大量に流出した。また、権限を委譲する過程で監督コストとエージェンシー・コストが上昇し、国の「現場にいない所有者」としての企業に対する監督、すなわち委託人のエージェント(代理人)と資本使用者に対する監督の有効性が大きく低下し、資本の権利が侵害された。実際、所有制構造を変えずに「放権譲利」を実施することは、資本の権利を自らある程度放棄することを意味する。権限を委譲し、請負制などの資本経営責任制を実施した後、国有企業の問題点はすべて資本に対する権限と責任に関わっている。これは、経営責任制自身に問題があるのではなく、どのような所有制でも資本の委託人と代理人の間の関係を決める責任制が欠かせないことを示唆している。分権制の下で現れた国有経済の問題点は、所有制構造が重要であること、そして、経営責任制の実際の経済効果が所有制に依存していることを反映している。
また、分権制の問題点が、経済の動態的効率を改善するどころかむしろ悪化させたことは明らかである。財政赤字の増大と企業の借入れによる投資資金の調達の増加は、投資総額における自己資金の割合を低下させ、インフレ圧力を高め、マクロ経済の不安定性を増大させた。実際、国有部門の比較的低い利潤率(比較的高い赤字率)と比較的悪い返済能力は、生産的な投資に使う財政支出の減少と、銀行の預金金利の低下による国民貯蓄の伸びの低下をもたらした。結局、一定の投資率を保つためには、通貨供給量を増やして投資資金に対する需要を満たすしか方法がない。マクロ経済の不安定性と経済成長の振幅の増大は、資源が動態的に十分かつ有効に利用されていないことを意味しているのである。
また、分権制により、様々な分野で資源配分の効率性が改善しにくくなった。企業の利潤率の低下、強すぎた消費需要は、消費財市場の需要を拡大し、大量の資金を加工業に引きつけると同時に、政府が支配可能な資源の量を相対的に減少させた。この結果、中央政府が担当するインフラ施設が不足し、交通やエネルギーなどの生産能力の伸びが低下し、国民経済のボトルネックとなってしまったのである。
財産権関係が変わらないという前提の下、「放権譲利」は市場メカニズムの形成と発展を促進する。現体制における取引商品数量と自主権をもつ取引者の数が増えるためである。しかし、公有制を維持しながら、「放権譲利」を推進することは、直接的あるいは間接的に市場経済の発展を妨げる。なぜならば、予算制約が非常にソフトな取引者の市場における無責任な行為は必ず価格のシグナル効果を歪め(低すぎる利潤率や高すぎる贅沢品の価格を含む)、資源配分の非効率性と経済の不安定性を増大させるからである。このことは、無責任な取引者に対する外部の統制(計画的コントロール)を強化する正当な理由となるため、市場経済の発展が権限の回収や再度の集中、整理整頓によって常に中断され、古い体制が再度出現するといったことが発生する。また、このような内部的拘束力のない取引者の生き残り(例えば、赤字の国有企業)を維持するために、多くの資源が各種行政手段を通じて強制的に効率の低い部門に集中され(例えば、大量の政策的融資が国有銀行を通じて効率の低い国有部門に配分された)、長期間にわたって市場が歪んだ状態が続き、新体制の健全な発展を妨げてしまうのである。
四、改革の道筋と改革戦略の再考
最後に、中国の改革を振り返る時、「経済改革が先行する」、あるいは「政治改革が経済改革に後れる」という問題に触れる必要がある。この問題は、改革方法の比較研究において「中国の特徴」として常に挙げられている。しかし、近代政治経済学の視点から考えれば、政治変革は経済変革の一部分あるいは経済変革を具現化したものである。政治闘争の背後にはすべて経済的利益衝突がある。イデオロギーという上層構造も多くの場合(特に、近代人がすでに比較的自覚している場合)、役に立つ(取引コストを下げることができる)ために受け入れられ、あるいは維持されているのであり、経済の「内生変数」なのである。このため、我々にしてみれば、経済改革が先行すべきかどうかという問題は、改革の基本方法という問題の中で分析すべきである。つまり、政治改革の先行は、社会・経済の矛盾が激化し、国内外の環境に直面するに当たって急進的改革を選んだ結果(先決条件ではない)であり、経済改革の先行は、社会・経済の矛盾がまだそれほど激化しておらず、人々がより温和で漸進的な改革を選んだ結果である。民族の特徴、文化・伝統、外来思想の影響、指導者の方針、政権構造などで経済改革と政治改革の先行の理由を論証する人もいるが、我々にしてみれば、これらの理由は二次的なものであって、最大の要因は公共選択の過程における経済的な利益衝突である。このため、政治改革と経済改革の関係は特別な問題として議論しない。
以上の分析を基に、次に改革における政府、あるいは政策の役割について詳しく分析してみる。
多くの論者は、経済改革の過程を政府による政策の結果として解釈し、また「改革戦略」といった類の言葉を使って、改革があたかもある戦略の実現のようにすべて事前に計画され、明確な目標と手段を持っていると改革方法を描写する。
これは、最適化理論に基づく社会計画者の典型的な見方である。この見方の前提は、まず全知全能の計画者がいて、社会厚生を最大化する均衡点を知り、非効率的な現状と効率的な均衡点までの距離を認識し、最良の改革・移行戦略を知り、最良の改革順序と最良かつ全面的な改革政策を持っていることである。また、この論点は、計画者がこの戦略を実施する権限、能力、手段を持ち、この戦略および関連諸政策を有効かつ徹底的に実施することができるということを暗黙のうちに仮定している。このように、改革の全過程は、ある種の戦略を実施した結果に過ぎないのである。
しかし、この二つの前提は非現実的であると考えざるを得ない。現実の生活において、政府の指導者にしても各利益集団にしても、様々な非効率や不公平を不満に思うことがあっても、実際の条件に合った理想的な状況や最良の状況に移行する具体的な道筋は知らないし、各利益集団あるいはその衝突と関係がある政府は、利益が衝突するときにそれぞれが利益を追い求める戦略を持つこともできる。現実には、各利益集団の戦略が衝突し合うことによって公共選択の過程が形成されるのである。経済体制改革は、絶え間のない試行錯誤の過程であると同時に、各利益集団が影響し合い、関係が発展、深化し、調整し合うという「ゲーム」の過程であり、明確な戦略の単なる実施ではない。
急進的改革にしても漸進的改革にしても、一般的に事前の戦略ではなく、事後的な改革過程に対する一種の描写であり、社会計画者による取り決めではなく、人々の自覚的な利益衝突の中から実現された非自覚的な社会の進展なのである。
2003年3月10日掲載


