第53回ヨーロッパ地域学会基調講演
空間経済学の分野における第1人者である藤田昌久RIETI所長は、2013年8月にイタリアのパレルモで開催された第53回ヨーロッパ地域学会 (ERSA)で、標題を"RegionalIntegration and Cultures in the Age of Knowledge Creation―The Story of the Tower of Babel Revisited―"(「知識創造時代における地域統合と文化―バベルの塔の物語再考―」)とする基調講演を行った。ERSAは、欧州全域の各地域の空間経済学や地方・地域の発展などに関心を持つ大学関係者、政策担当者、研究者からなる超国家的な学会で、今回のテーマは"RegionalIntegration: Europe, the Mediterranean and the World Economy"(「地域統合:欧州、地中海、世界経済」)である。藤田所長は講演で、20世紀終わりから到来した「知の時代 (Brain Power Society)」では、最も重要な資源は個々人の頭脳であり、新しい知識の創造や新技術の開発のカギは多様性であると強調した。
本会議のメインテーマである「地域統合:欧州、地中海、世界経済」と関連付けながら、イノベーションと新しい知識創造に基づく世界経済の持続的発展において多様性と文化がいかに重要かについて論じたい。
グローバル化という視点から見ると、「財」の生産・貿易において輸送コストをより低く抑えられるほうが望ましいということに、誰も異論はないだろう。では、知識創造社会の発展における「知識」の生産・伝達についてはどうか。コミュニケーションの障壁が低ければ低いほど良い結果が得られるのだろうか。障壁がなく自由自在に意思疎通を図れること、つまり「エフォートレス・コミュニケーション (eff ortless communication)」できることが知識創造社会の理想なのだろうか。
ヨーロッパの強みは、多様な文化、言語、人々が比較的狭い範囲に集まっていることである。欧州連合のモットーは「多様性の中の統合」である。距離や空間、複数の言語の存在はコミュニケーションの障壁となるが、その障壁があったからこそ、各地域が独自の文化や知識を深化できたのである。
多様性と文化は知識創造社会にとってなぜ重要なのか
知識創造社会の基本的資源は個人の知力、すなわち知識である。しかしながら、全く同じ頭脳が2つあっても相乗効果は生まれない。同様に、イノベーションに向けて国や地域が協力する場合も、文化的多様性があればこそ相乗効果が生まれるのである。
「3人寄れば文殊の知恵」といわれる。すなわち、それぞれの固有知識が共通知識を介して融合することで、素晴らしく新しいアイデアが生まれるのである。しかし、その共通知識が時間の経過とともに相対的に増えていくと、次第にグループ内の異質性が減少してしまう。そのため相乗効果も小さくなり、「3年たてばただの知恵」となってしまうのである。
1980年代、日本経済は急速に成長し、近い将来には、米国経済に追いつき世界一になるだろうといわれていた。当時、私はペンシルベニア大学ウォートン・スクールで教鞭を執っていたのだが、同僚達は一様に日本の成功の秘密について強い関心を抱いていた。私は「飲みニケーション」が、その秘密の1つに挙げられると思っている。当時、東京のサラリーマンは仕事が終わると同僚と居酒屋に出かけ、お酒を飲みながら夜を明かした。日本が欧米諸国を追いかけていた当時、飲みニケーションによる密なコミュニケーションは、日本の成長力を押し上げる上で大いに貢献したのである。
そして1990年代初頭になるとついに日本は、1人あたりGDPで世界有数の国となった。そうした日本が必要としたのは、最先端の知識やイノベーションを探求できる多様な集団だったのだが、日本人はあまりにも多くの濃密なコミュニケーションをとってきたために、最先端のイノベーションを生み出すには同質になり過ぎてしまったのである。このように知識創造に向けた協力には、短期的に見た場合と長期的に見た場合で相反する効果がある。この短期的・長期的影響の二律背反をどう解決すればよいのか。旧約聖書における有名な「バベルの塔の物語」にそのヒントを探ってみよう。
創世記第11章によると、かつてメソポタミア地方に強大な帝国があり、人々は同じ言語を話していたという。傲慢になった彼らは天に届く高い塔を建てて天に近づき、神に挑もうとした。神は怒り、多数の言語を割り当て、お互いの言葉が通じないようにさせてしまった。人類は世界中に分散し、多地域・多言語の世界となった。ここで考えたいのは、これは天罰だったのか、それとも天罰に見せかけての天恵だったのかという問題である。すなわち単一文化の世界は、多様な異文化の地域から成る世界に優るのだろうか。
情報通信技術 (ICT)革命にも似たような問題が投げかけられるだろう。ICTは本当に知識生産性を向上させたのかどうか、という問題である。確かにICTは知識や情報の伝播スピードを劇的に向上させた。しかし、情報が増加しても新しく吸収できる情報や知識には限りがある。ICTの発達によって人類の創造性が向上したのか、あるいは退化したのか定かではない。
多様性と創造性
創造性を生み出すために多様性が重要であることを示す例をいくつか挙げたい。
最初の例は、国際的にも著名な作家、多和田葉子氏のエピソードである。多和田氏はドイツに26年間住んでいたこともあり、日本語とドイツ語の両方で執筆している。芥川賞と谷崎賞を受賞し、ドイツでもレッシング賞とゲーテ・メダルを受賞している。その多和田氏が、ある取材の中で「日本に住んでいた頃は、日本の伝統に対する好奇心も想いも芽生えず自国文化について考えることもなかったが、『海外と日本の文化の違いを知って初めて生産的になれた』」と語っている。
多和田氏の話と対極にあるのが、新幹線が日本にもたらした効果だろう。新幹線は東京オリンピックが開催された1964年に開通した。新幹線の出現は政治や経済だけでなく、文化面でも東京一極集中化を促進させた。では、新幹線は日本社会の創造性の向上に寄与したのだろうか。
現在、首都圏の人口は約3600万人で、世界最大規模の人口密集都市圏である。日本の特許出願総数に占める東京のシェアを見ると、日本全体の出願総数は1982年から一貫して増加していた後、2000年に減少傾向に転じたが、東京のシェアは2008年まで増え続け、減少し始めたのはごく最近のことである(図1)。知識労働者と文化的活動の東京一極集中は、日本人の知識構成を過度に同質化させ、その結果、日本全体の知的生産性が低下に転じている。日本は、2005年まで特許出願数で世界一を維持していたものの、2002年から減少に転じている。対照的に米国、中国、韓国の出願数は急増し、2006年には米国が日本を上回り、2011年には中国が世界一になった。
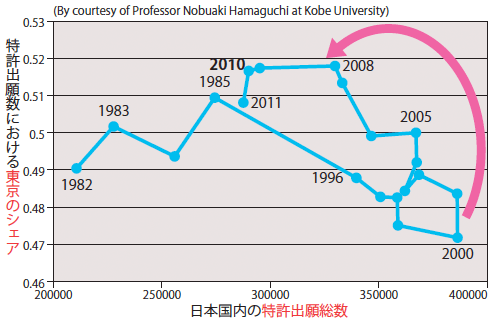
さらに、米国との国際共著論文(米国以外の国の研究者が米国の研究者らと共同で書く論文)に関する過去10年間の各主要国シェアの変化にも、興味深い結果が見られる。今日、米国は学術活動において世界最大の拠点である。米国との共著論文の国別シェアが英国やカナダなどの英語圏で高いのは当然だが、ドイツも高いシェアを維持している。これに対して日本のシェアは相対的に低下してきており、日本の学界が内向きになっていることを示している。また、米国との共著に占める中国のシェアは、中国のGDPと同じく驚異的な速度で上昇している(図2)。
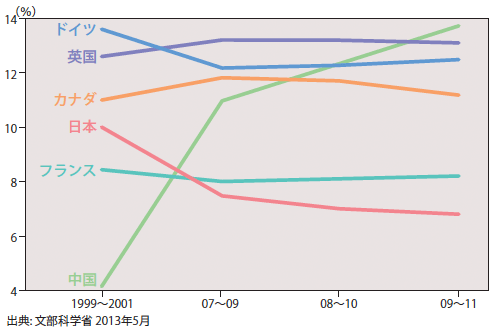
ドイツ・イェーナ大学のFritch教授とGraf教授による研究では、旧東西ドイツの代表的研究都市を比較している。対象の都市はいずれも100万人都市で、それぞれ地域内に優れた研究協力ネットワークを有している。比較の結果、研究機関同士のつながりは旧東ドイツでより密接であることがわかった。密接な知識ネットワークが研究の生産性に重要であるという定説によれば、東ドイツ都市の生産性がより高くなるはずだが、実際はその逆で、1人あたりの特許登録件数は西ドイツが東ドイツの約2倍となっている。東ドイツでは内部の研究協力は密接な分だけ、外部とのつながりが弱い。西ドイツはその対極にある。つまり、よりオープンな研究協力が必要なのである。
文化的多様性と経済成長の間に有意な正の相関関係があることについて、OttavianoとPeriは米国の複数の都市を比較し、他民族文化が米国生まれの市民をより生産的にしていると指摘し、同様にBellini、Ottavianoらはヨーロッパの地域を比較し、多様性が高いほど生産性が高いことを示している。
日本国内の事例に戻ると、創造性にとって多様性が重要であるということを示す好例として、筑波研究学園都市にある物質・材料研究機構 (NIMS)の取り組みがある。つくば市にある多数の研究機関の中でNIMSは外国人研究者の数が約600人と最も多い。2004年に若手研究者の中心拠点に、また2007年には国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 (MANA)に指定されたNIMSは、その後外国人研究者の招へいに取り組み、2001年には4%にも満たなかった外国人研究者の割合が現在では約25%にまで上昇した(図3)。
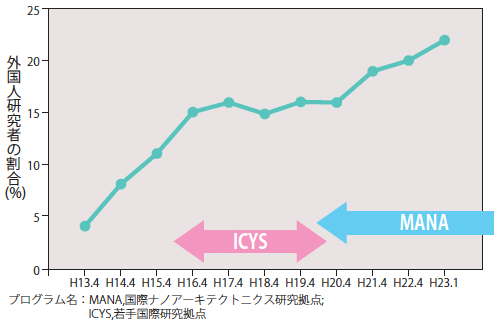
今日、NIMSは材料科学分野における論文の引用数ランキングの上位に位置するようになっている。外国人研究者の招へいに本腰を入れる以前の1994~2004年には、18位に過ぎなかったが、2007~2011年には4位に躍進したのである(表1)。さらに、NIMSの引用数上位31論文のうち、24件が日本人研究者と外国人研究者の共著であった。これは、知識労働者の多様化がいかに研究機関の生産性を高めるかを如実に示している。
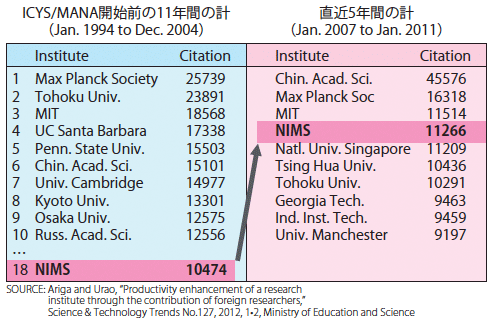
反面で、最近のEUと米国の通商交渉では「文化的特例 (culturalexception)」が障害になっている。フランスは2013年6月、映画、音楽、テレビなどの文化的産業を交渉から除外するようEUに働きかけた。ユネスコも、各国政府は文化的表現の多様性保護・推進のために措置を講じる権利を有すると再確認している。自国の文化産業を大国から保護したいと多くの国が望むのも理解できる。
世界規模での音楽消費量と貿易量について1960年以降の動向を調査したFerreiraとWaldfogelの研究では、大国による音楽市場独占が懸念されているのにもかかわらず、実際には自国の音楽に対する相当な偏好が確認された。過去半世紀のICTの急速な発展は、外国音楽ではなくむしろ自国の音楽消費量増加に寄与したのではないかとの推測が示されている。つまり重要なのは、自国の文化産業の保護ではなく、その創造性を高めることであり、また世界中の国と地域がより創造的に自国文化の振興に取り組めば、世界全体の文化がより豊かになるということであろう。
知識創造社会の動学的モデル
私の最近の研究における知識創造社会の動学的モデルでは、知識労働者と地域文化の多様性がいかに内生的な成長を引き起こし、ひいては社会全体の知識増加につながり、世界全体に経済成長をもたらすのかを取り上げている。ここでは、知識と地域文化の多様性がどのようにして社会全体の知識増大に寄与するかという問題に着目したい。
この分野について、私はMarcus Berliantといくつかの論文を共同執筆している。最初に執筆した論文は、Knowledge Creation as a Square Dance on the Hilbert Cube(「知識創造のミクロモデル:無限次元空間におけるスクエアーダンスとして」)で、次の論文では、内生的成長理論と融合させ、知識の多様性のダイナミクスについて分析した。そして、つい最近の論文では、単一地域モデルを複数地域モデルに拡張し、文化の多様性と知識創造について考察している。
スクエアーダンスは西部開拓時代に米国で人気のあったフォークダンスで、男女2組8人1セットで、相手を順々に替えながら踊る。8人のフォーメーションには無数の種類がある。Berliantと私は3本の論文を共同で執筆したわけであるが、お互い実際に会うのはせいぜい年に3~4週間程度で、それ以外は、それぞれ他の研究者と仕事をしている。つまり、新しい論文を執筆する上で、国際的なスクエアーダンスを踊っているわけである。これは地域科学や経済学の分野ではごく一般的に行われていることでもある。
実際、Peter Gordonの最近の研究で、地域科学分野の研究者の多くが論文執筆にあたり、「スクエアーダンスを踊っている」ことを裏付ける数字が示されている。たとえば、Journal of Regional Science誌に最近発表された論文のうち、約60%が共同論文である。また、2010~2011年に発表された共同論文のうち、国際的な共同執筆が全体の45%、別の都市にいる著者によって執筆されたものが約30%を占めている(図4)。一方2012年発行のAmerican Economic Review誌に掲載された論文の82%、また同年発行のQuarterly Journal Economics誌では88%が共著論文だった。
執筆者居住地 (1959-2011) による共同執筆の形式 (4種類)
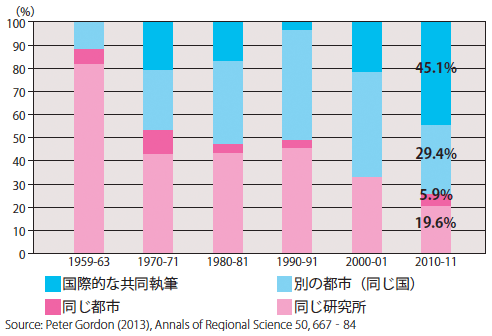
学界のスクエアーダンスを実世界に当てはめ、2地域における文化と多様性に関するモデルを説明したい。地域A(日本)と地域B(米国)に同数の研究者がいると仮定する。当然のことながら、A・Bいずれの研究者もそれぞれの域内ではコミュニケーションが容易なため密接な交流が行われている。しかし移動時間や費用の問題から、AB間、つまり地域間における研究者の協力は容易ではなく、知識移転もあまり行われていない。他国の新聞やTVを読んだり視たりする人は少ないので、Aに住む一般的な人物を2人選んだ場合、その2人の間の共通知識は相対的に大きい。同じことがBにもいえる。
これとは対照的に、AとBから1人ずつ選んだ場合、当然、共通知識は相対的に少なくなる。それぞれの地域内においては大きな共通知識が存在するが、国際間・地域間では知識の違いが際立つということである。漸進的なイノベーションであれば、各地域内における大きな共通知識で達成できるが、新しいバイオ技術やソフトウエア開発などのフロンティア開拓型イノベーションとなると、研究者の多様性が必須で、国際的な協力が極めて重要になってくる。地域ごとに文化が異なるからこそ、幅広い多様性が地域間に現れるのである。このように、コミュニケーションを妨げる空間的な障壁の存在こそが、社会全体の知識創造の生産性を向上させるのである。
バベルの塔の再考
バベルの塔の話をもう一度考えてみよう。「エフォートレス・コミュニケーションの楽園 (Paradise of eff ortlesscommunication)」の住民(2N人)は、この楽園から追放されるまで、ずっと単一国内で自由自在な意思疎通を楽しんでいたとする。この場合、共通知識が大量に蓄積され、各個人の創造性よりも、共通知識を吸収する能力の重要性が相対的に高まる。共通知識吸収能力が過度に大きくなった状況を想定すると、知識の生産性は、理想状態で到達し得るレベル(至福点)をはるかに下回るレベルに留まる。
フェーズ1
住民の傲慢さに怒った神が2N人を楽園から追放し2地域に分けた直後の状況(フェーズ1)を考えよう。それぞれの地域には異なる言語を話すN人が住んでいる。追放直後なので、特に大きな変化はなく、どちらの地域も同じ文化を受け継いでいる。この段階では、地域間で協力するとかえって生産性が下がるため、いずれの地域も域内協力に専念する。その場合、地域間の知識の流出(スピルオーバー)もほとんど無いので、やがて各地域独自の文化が発展しはじめる。
フェーズ2
知識構成における地域間の違いが十分に大きくなり、地域間協力の生産性が地域内協力の生産性と同等になった状況をフェーズ2とする。ここでは、各個人が地域内のみならず、地域外とも協力し始める。各個人が自分の持てる時間を地域内協力と地域間協力に切り分け、また地域内の共通知識と他地域の異なる知識の両方を吸収する。その結果、地域内協力の生産性と地域間協力の生産性がともに上昇する。
フェーズ3
やがて地域間協力の生産性が最高点に到達する。これを「新たな楽園 (New Eden)」と呼ぶ。この段階(フェーズ3)における各個人の知識生産性は、エフォートレス・コミュニケーションの楽園のときと比べ、はるかに高くなっている。つまり、新たな楽園における社会全体の知識の増加率は、エフォートレス・コミュニケーションの楽園における同増加率よりはるかに高いということである。
ちなみに、フェーズ2で地域間の知識の多様性のみならず、地域内の知識の多様性も増加するのは、地域間の相互協力が特定の方法で起きるためである。たとえば、日本人経済学者が米国人経済学者と一緒に働く場合、米国人経済学者全員と等しく働くわけではなく、ハーバード学派、エール学派、シカゴ学派、スタンフォード学派など、さまざまな集団が形成される。各集団内に外部性が生まれるため、各集団は緊密に共同作業を行う。同一集団内の外部性は強力であるが、集団間の外部性は相対的に弱い。たとえば、多数の集団に分かれた日本の経済学者は、それぞれの集団ごとに異質性を発展させる。地域間協力によって地域内の知識の多様性も増大するのはこのためである。
先ほどの例は、1つの地域を2つに分割することで、社会全体として知識創造における生産性が大幅に改善できることを示しているが、地域間の協力における費用が多少高い場合でも同じことがいえる。
さて、最初の質問に戻ろう。エフォートレス・コミュニケーションの楽園から多地域・多言語・多文化世界への追放は天罰だったのか、それとも天罰に見せかけた天恵だったのか。我々の研究したモデルの結果は、後者を示唆している。
結論:多くの塔を開花させよう
塔は忌むべきものなのか。単一の帝国によって建てられる単一の塔は好ましくないかもしれないが、それぞれに異なる地域文化に根ざした数多くの塔が世界中に花開くことは喜ばしいことである。ピサの斜塔はじめ、世界にはさまざまな塔が存在するが、実は動物も塔を建てることができる。たとえば、高さ7メートルにもなる蟻塚もその一例である。それ以上にすばらしいのはスペインの「人間の塔」で、これは正に人間協力の象徴というべきものである。
最後に、August Loschの『経済立地論』のエピローグからの言葉を引用したい。
「あらゆるものが同時に起きるところに発展はなく、あらゆるものが1カ所に存在したら独自性は生まれない。唯一空間のみが独自性を生み出し、それは時の経過とともに広がってゆく。我々は全ての物から等距離にあるわけでなく、全ての物が同時に押し寄せて来るわけでもない。この世界が全ての個人、人々、人類全体に制限されたものであるからこそ、我々は、我々の有限性の中で耐えることができる。空間はこの制限の中で我々を創造し保護する。独自性こそが我々の存在を支えている」


