WTO・ドーハラウンドの低迷の中で、暫くの間、通商分野のルール作りの主たる牽引力は、TPP、日EU、米EU(TTIP)といったメガFTAが担うことが予想される。
他方で、メガFTAは、地域のルールとVCを対象とするものであり、直接にはグローバルな通商ルールは生まれてこない。
メガFTA間で、ルールのスパゲティーボウル現象が生じる危険性も大きい。
1 メガFTAとGVCガバナンスのシナリオ
GVCの確立・ガバナンスとメガFTAとの関係について、4つの考えられるシナリオを見ていこう。
シナリオ1 楽観的シナリオ(Euphoric Scenario)
メガFTAの推進論が、暗黙の前提として描いている「楽観的」シナリオを敷衍して述べてみよう。
前提として、次の点が想定されているものと推測する。
1) メガFTAは、早期に締結される。
2) ルールのスパゲティーボウルは、存在しないか、軽微である。
3) ルールのスパゲティーボウルは、調和が可能であり、調和が実際に行われる。
4) 調和には時間がかからない。
5) 調和の結果は、WTOルールの基礎となる。
6) メガFTA内外(参加国と非参加国)のルールの相違は、大きな問題を生じない。
これらの前提に立つと、メガFTAは早期に締結され、スパゲティーボウルは早期に解決され(注1)、新分野を中心とした新しい通商ルールが生まれ、将来のWTOの基礎となる、という理想のシナリオが書ける。
しかし、それには、上記の前提が正しいことが必要である。
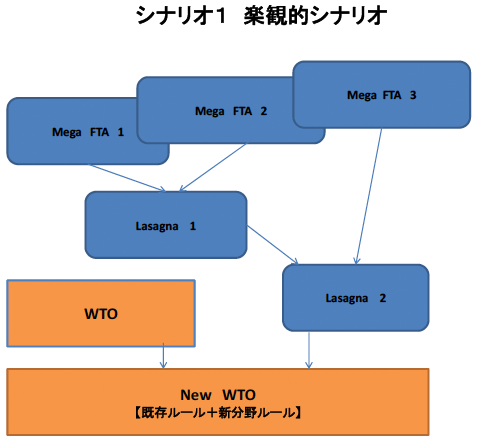
シナリオ2 WTO2.0
次に、Richard Baldwin教授のWTO2.0のシナリオを紹介しよう(注2)。
Baldwin教授は、20世紀型通商ルールを規律するWTOに対し、メガFTAが21世紀型通商ルールに対応したWTO2.0を作り出すという議論を展開しているところである(注3)。
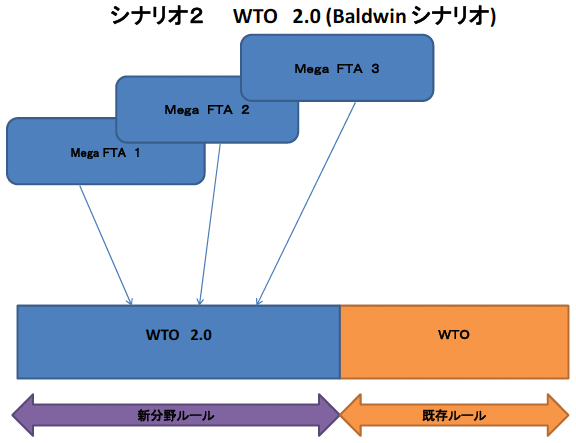
シナリオ3 ルールのスパゲティーボウル(Fragmentation Scenario)
メガFTAについて、過度の楽観的な見方は危険である。
シナリオ1の諸前提を検討しよう。
前提1)については、メガFTAは、その野心の高さ、参加国の多様性等から考えて、一般的に見て「時間がかかる」と見るべきである。
前提2)~4)については、経済システムの違いを調整するメガFTAにおいては、システム間の調和作業は難航することが予想される。
韓国が対EU、対米FTAで、自動車・電子電気分野で、国際標準について異なる定義を用いざるを得なかった例が典型であるが、今後さまざまな分野でメガFTA間でルールの違いが生じることは避けられないであろう(注4)(注5)。
また、前提4)の調整が短期間で行われる保証もなく、前提5)で、調和的ルールが生まれない場合には、WTOルールの基礎となりえない。
前提6)については、VCは、調達・生産・流通の各側面で内容も関係国も日々変化しており(注6)、メガFTA内外のルールの相違は、大きな問題となるという見方も十分に成り立つ。
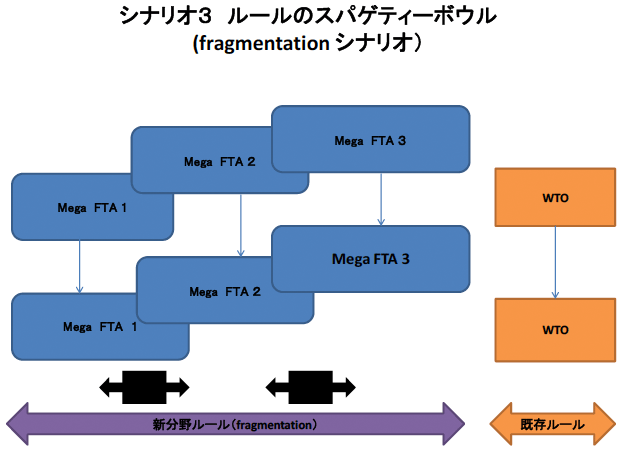
2 調和のとれた通商政策の形成に向けて(シナリオ4)
それでは、今後、メガFTAをグローバルなVCと通商システムの基礎となるようにしていくにはどのような視点が必要であろうか。
第1に、将来の通商システムについて、明確なビジョンを持ち、「地域解」ではなく「世界解」を描くことが必要である。産業界も、FTAによる地域解ではなく、グローバルな解を求めている。必然的に、将来のWTOルールの姿を念頭に置いた戦略が不可欠である。
第2に、「透明性」と「開示」・「情報共有」が極めて重要である。
FTAのマルチ化、WTOルールの地域化が今こそ求められているが、その作業の基礎は、透明性であり、正確な情報の流通である。
第3に、GVCの思想であり、産業界の視点である。GVCの必要性は、国際的に産業界の共通認識となりつつある。
そして、第4に、イッシューベースの、国際ルール作りの思想である(注7)(注8)。
メガFTAの成果をイッシューごとにマルチ化させること、イッシューベースでのプルリ合意(例 ISCA)を活用することが重要である。
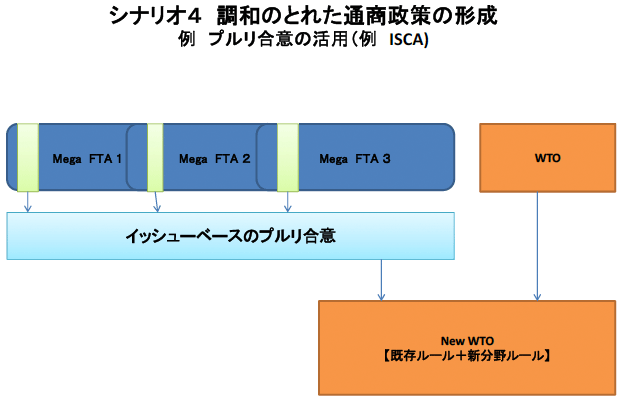
3 ISCAとは
ISCA(International Supply Chain Agreement)は、筆者が、12年11月に提案した、GVCに関する包括的なプルリ協定構想である(注9)。
詳しくは、提案(注10)に譲るが、その概略と考え方について説明したい。
1)基本原則
ISCAを提案するに当たって、筆者は、いくつかの基本原則を設定した。以下に、主なものを述べよう。
- 将来のWTOルールの基礎となるものであること
- ドーハラウンドを阻害(undermine)しないこと
- メリットのMFN均てん(MFN extension of benefits)を基礎とすること
- 原産地やルールの「スパゲッティーボウル」の解消に資すること
- 交渉は短期での終了を目指すこと
- 産業界との密接な連携を基礎とすること
若干補足しよう。1と4とは、表裏一体であるが、GVCの目標はグローバルな環境の整備にあり、異なったルールが乱立することは不適当との観点である。
3の、MFN均てんについては、大きく見解の分かれるところである。
しかしながら、プルリ合意の成功例(ITA、テレコミ・金融サービス合意)は、MFN均てんが基礎となっており、その前例に倣うことが、成功の確率を飛躍的に高めることは間違いない。
5については、ISCAは、スピード感が重要であり、メガFTAの障害が出る前に、交渉を進める必要があるたとえば3年といった交渉期間を区切ることも必要であろう。
2)対象分野
対象分野の詳細は提案に譲るが、GVCの改善が目的であり、産業界と政府との密接な連携調整が鍵となる。重すぎるアジェンダとならないよう交渉対象を定めていくことが不可欠である(注11)。
ISCA提案は、メガFTAの時代にあって、その欠陥を補正し、GVCのガバナンスを確保する道筋を提示したものである。
その根底は、GVCの課題に、政府と産業界とが連携し、イッシューベースでグローバルな解を考え、実現して行くアプローチであり、ITAと同様に必ずや成果を生む現実的な枠組みである。
GVCの円滑化とガバナンスの実現に向けて、本稿、特にISCA提案が参考になることを期待する。
本稿は、2013年8月15日にwww.VoxEU.orgにて掲載されたものを、VoxEUの許可を得て、一部加筆して、翻訳、転載したものです。
詳細版 [PDF:254KB]


