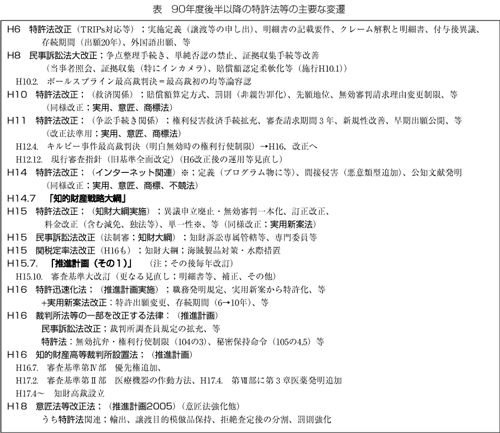はじめに
昨今知的財産権を巡る議論が活発化している。この傾向は2002年に小泉前総理が知財立国を施政方針演説で表明し、それを基にした知的財産基本法や知的財産戦略本部の設立等の動きを背景にしていると思われる。しかしながらプロパテントの動き自体は90年代半ばに遡ることができる。即ち当時はバブル崩壊後で、グローバル化や特に中国等の台頭から経済的に相当厳しい状況にあり、それを克服するには80年代の米国に倣いいわゆるプロパテント化によりイノベーションを促進し、もってわが国の国際競争力の維持発展が必要と考えられていた。なお当時の特許制度は、むしろ普及重視でそれを巡っては、その権利化が遅い、特許権の範囲ないし解釈が狭い、侵害時等の訴訟遅延、仮に勝訴しても賠償が不十分等の問題があった。このような状況の下、特許等に係る日米協議、またウルグアイラウンドでのTRIPs協定の成立を受け、平成6年の特許法改正を皮切りに徐々にプロパテント化へ舵を切り替えていった。
その後の変遷
平成6年改正以後の特許法を巡る主要な制度変遷は表の通りである。この中には特許法改正のみならず民事訴訟法改正や特許庁内規の審査基準の改定、更に裁判所の判例もある。紙幅上極めて概括的であるが、その後の変遷を簡単にまとめると、以下のとおり。
まず「迅速な権利付与」については、現在も処理期間は2年余と大差ないが、他方で出願数等も増加しており、健闘していると言えよう。制度改善(含む料金等)も多々している。ただ審査請求期間を3年に短縮したが施行が平成16年10月で成果が出るのはこれから。また平成16年の特許迅速化法で最終的審査待期間ゼロの目標を設定するが、この成果もこれからである。よって今後を期待したい。
特許権対象としての「新しい技術」の取扱いは、特許法は全ての技術を特許化はせず、特にわが国は世界でも珍しい発明の定義を有する(諸外国も何らかの制限はある)。この関係でソフトウエア発明やバイオ発明、更に医薬発明は、かつては多くは特許対象とされていなかったが、その急速な技術開発やその投資を保護する必要性等から、発明定義解釈や審査基準緩和で順次特許対象化されている。なおこれら新しい技術はいわゆる科学に近く広すぎるクレームの危険性がある。このためその権利化の影響を考え、実運用においてはクレーム範囲設定や開示の手法、更にはその権利行使の範囲について慎重に扱っている。
「クレームの設定」では、まず出願以降の手続きは、平成6年改正で柔軟なクレーム設定が可能となり、また一出願で請求できる発明の数についても単一性基準改善等があり増加。また補正、国内優先、分割等の規定も整備され、手続きでのクレーム「設定」問題は相当改善されている(訂正審判や無効審判手続きも変更されたがこれらは争訟の迅速処理の観点からでプロパテント的)(また実用新案からの特許権への出願変更時期制限緩和等は保護形式選択の余地を広げ、併せ実用新案の期間延長したが当然プロパテント的)。次いで特許庁審査で「クレームの適切さ」の審査するところ、その判断基準として審査基準を平成12年全面改訂(その後も適宜改訂)したが、これは審査の透明性を増し出願人としても予め適切な対処が可能となる。なお審査基準の中には、特に平成6年改正のクレーム記載自体への制限(例えばサポート要件等)のようなところもあるがそれは広すぎるクレーム防止のためで、要は適切なクレーム範囲設定の趣旨で、プロパテントに反するものではない。
「クレーム解釈」については、かつてわが国クレーム解釈は実施例への限定解釈等狭すぎるとの批判があったが、審査基準の整備等もあり、相当改善されていると思われる。なお平成6年改正で機能的クレーム等の新たな形式のクレームの出現や審査基準改訂でクレーム解釈実務も変革し制限的な部分もあるが、基本は開示性等から適切な範囲にするもの。なお均等論についても、かつては認められなかったが、平成10年ボールスプライン事件最高裁判決で認められ、その理由や適用条件についても下級審でほぼ定着しつつある。この均等論は、当然クレーム解釈の幅を広げるものでプロパテント的と言える。ただ均等論自体はクレームの公示機能等から安易に広げるべきではない。この点、判例は節度ある適用をしており特段の問題はないと思われる(なお本家たる米国でも近時は禁反言他その適用に慎重姿勢が見える)。最後に先のキルビー事件最高裁判決を受けて、平成16年改正で「無効抗弁」(第104条の3)が新設され、裁判所が特許の無効認定を独自に行う(その行使を権利乱用として禁止できる)ようになった。これ自体は、侵害訴訟で反訴として無効審判が提起されたような場合での迅速な争訟処理に資するが、反面裁判所判断が重くなる。そもそも特許有効判断における特許庁と裁判所の権限分配問題(改正前は特許庁判断をまず尊重)にも関わり、学術的に詰めるべき論点(原審判で主張しない事項の取扱い等)が種々ある。ただ制度ができた以上は、その適切な運用、特に裁判所での慎重な対応が求められる。
「特許権の効力」については、特許は時代と共にありその変化に応じて変遷するものであるが、平成後の変遷の中には、TRIPsやIT化・インターネット化等に対応したものはある意味当然といえよう。ただ中には若干疑問なものもある。例えば発明の実施概念に「輸出」を入れることは、いわゆる属地性や過去の判例から必要性は(海賊品問題の深刻さをもってしても)やや不明。「職務発明」はいくつか裁判例はあるが、そのイノベーション全体への影響等考えるべきことは多く、また折角の改正ではあるが、具体的適用内容は曖昧で、結局判断を裁判所に委ねただけにも映りあまり意味あるように思われない(そもそも実務に疎い裁判所に任せるに妥当かとの議論もある)。付言するにたしかにこれは従業員個人発明家へのインセンティブになるかもしれないが、実際の企業での研究はチームで行い個々人というのは稀で、わが国全体のイノベーション促進に資し得るかは疑問なしとしない。最後に「消尽」に関し、並行輸入、及び修理・再利用に係る判例が出されたが、これらは今後のわが国企業の生き方、即ちブランド化や消耗品・付帯サービスでの高付価値化、にも関連し、今後の判例動向が注目される(なお制度変遷は他にもあるが略す)。
「訴訟手続き」については、まず特許庁内手続きとして異議制度が廃止され無効審判に一本化された。この一本化で手続的に簡素化・迅速化は期待されるが、他方異議件数は相当数あったところ無効審判だけでカバーしきれるのか懸念される。なお現在、異議申立等の制度の無い米国では、米特許庁の査定の適正化を図るべく逆に異議申立制度の導入を検討している点は注目される。
また裁判は、かつてはその長期化が問題視されていたが、特許法のみならず民事訴訟法自体の改正もあり、相当程度改善されている。これはプロパテント的な成果である。特に計画審理、積極否認、証拠収集、特に営業秘密の扱いの改善、等が大きいように思われる。なお特許事件の専門性にかんがみ、裁判所の管轄の整理また専門部体制の整備、専門委員制度導入、調査官の整備、更に知財高裁の設置等が行われたが、これはまさに技術裁判たる特許裁判の質の向上につながるもので、今後が期待される。
最後の「救済」については、まず損害賠償については平成10年改正で賠償額推定規定(第102条)等の整備がなされ、現に相当実施料率の認定を含め賠償額は増額しており、救済の程度は相当改善されたと言えよう。罰則についても平成10年改正の非親告罪化に始まり、罰金・懲役の強化や法人重科といった強化が行われたが、特に平成18年改正で窃盗等他の財物侵害での罰則とのバランス等から罰金・懲役の更なる引上、及びかつては認めていなかった罰金と懲役の併科を導入した。これには海賊品対策強化が背景にあるように思われる。ただ罰則強化は保護強化であるが、特許権の場合、刑罰が発動されるのは稀で(もっとも近時、海賊製品対策に係る刑事事件は増加傾向)、またその犯情もたまさか先行特許回避に失敗したとかで、いわゆる海賊行為、特に著作権や商標等におけるコピーとは違うように思われる。そして刑法は国内犯を律するもので外国人の海賊製品業者には適用できない面もある。いずれにせよ刑罰は基本的には謙抑的に慎重であるべきと考える。
以上より結論としては、一連のプロパテント化施策の積み重ねで、議論の出発点である90年代半ばに求めた「保護の強化」は概ね達成されたと言えよう。
今後の課題
以上わが国特許権の保護水準は諸外国と比してもかなりのものとなったと言えよう。
他方、知的財産権は排他性を伴うことから、その過度の行使は競争を歪め、時に反イノベーティブとなる。この点、わが国がその範として米国において、近時その見直し議論が行われている。思うに当時と比してパラダイムは更に変化し、技術開発はより複雑化・高コスト化し、今や企業単独で行うは難しく、分野を超えた連携等が主流となりつつある。またモジュール化のように単に技術開発力だけの勝負でもなくなってきている。このような時代、知的財産権の尊重と保護はその大前提ではある。そしてかつてわが国は知的財産権への意識が薄いところもあり、それを喚起する意味でのプロパテント化は大いに意味があった。しかし今後はむしろ保護強化一辺倒(むしろ米の例からして逆に危険ですらある)ではなく、「プロイノベーション的運用」が必要と思われる。それには場合によっては保護・行使の制限といったリバランスが求められるかもしれない。
いずれにせよ知的財産権はイノベーションの結果たる技術の保護の法的手段でしかなく、それ自体がイノベーションではない。むしろ更なるイノベーションには、連携・提携といった戦略的活用が重要であり、これに資するよう知的財産権の活用なり制度運用を考えるべきである。近時いわゆる知的財産経営等が提唱されるが、正しい方向であろう。
注意…意見は筆者個人のもの。詳細は経済産業研究所HPに発表したディスカッションペーパーを参照されたい。なお若干加筆修正した。