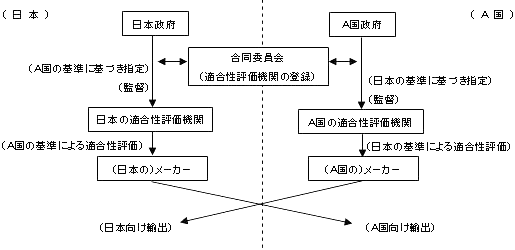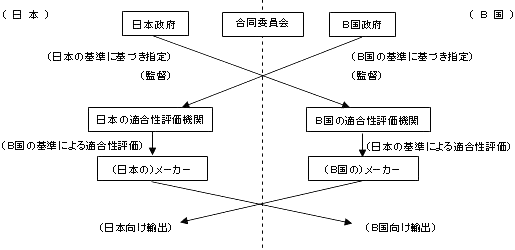国際通商法学において相互承認(mutual recognition)の制度とは、1990年代から政策手段として注目を集め、学術的に高く評価されてきた。しかし、実際の相互承認合意の運用や利用実績について実証的分析を試みた文献は少ない。本研究では*1、日シンガポール新時代経済連携協定(以下、「日星協定」)における相互承認制度をケース・スタディとして両国の関係者に聞き取り調査を行い、交渉の背景と展開、協定実施がどの程度実現したのかを調査した。その結果、相互承認が、理論的にイメージされている政府間合意とは異なり、現実は、二カ国の行政機関が互いの規制内容を知るための継続的な学習プロセスであること、さらに、実際に産業界に幅広く利用されるための制度構築が政策的な課題であることが明らかとなった。
なお、相互承認には、日欧・相互承認協定のような単独協定(mutual recognition agreements、以下、「MRA」)と、日星協定のように地域貿易協定(regional trade agreements、以下、「RTA」)の合意の一部を構成しているものとがあるが、ここではそれを特に区別しない。
相互承認の学術的理解
一般的な理解として、相互承認とは、"negative integration"と"positive integration"の中間として説明される。"negative integration"とは、差別を除去すること(つまり、問題とされる貿易障壁が差別的であるか否かというネガティブ・テスト)のみでマーケット・アクセスを確保する一方で、"positive integration"では、規律権限を国際機構に移譲して法のハーモナイゼイションを行うなど、なんらかの協調的で共通の政策をとることで経済統合をめざす。それに対して、相互承認は、ネガティブ・テストをやめて、相互に産品を受け入れる合意の下、マーケット・アクセスを確保する方法である点において"negative integration"に近いと考えられるが、その一方で、相互に産品が受入れ可能であるかどうか、規律内容や試験方法の同等性を考慮して積極的な協力を行う点において、"positive integration"に近い要素も持ち合わせている。ハーモナイゼイションの達成が非常に困難であることを考えると、相互承認は、法制度が各国で異なることを許容しながら、(単なる無差別原則よりも一層)マーケット・アクセスを確保する方法なので、「マーケット・ガバナンス」のあり方として重要な政策と理解されるようになった。
"negative integration"と"positive integration"という二分的概念を初めて用いたのは、オランダの経済学者ティンバーゲン*2とされる。それが経済統合の文脈で使用されていることが示唆しているとおり、上述の現代的な相互承認の考え方の背景には、ECにおけるハーモナイゼイションの発案・失敗・軌道修正という、1970年代から90年代にかけての長い経験がある。そのEC内での動きは、域外にも様々な影響を及ぼした。ECがハーモナイゼイションを積極的に進めていた1970年代、米国が、EC域内でのハーモナイゼイションの動きが域外には差別的に機能するのではないかと危惧し、それがGATT時代のスタンダード協定(WTOにおける貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)の前身)の締結のきっかけの1つとなったといわれる。さらに、1980年代後半、ECがハーモナイゼイション政策を軌道修正し相互承認という政策も一部採用するようになった後は、世界的にMRAの締結が進む。米欧MRAについては、ここでもECの政策が輸出障壁となることを懸念した米国が先に動いたとも言われている。
日星協定の交渉の背景
シンガポールは、相互承認の政府間合意に積極的な国である。表1は、ECが締結した主要な相互承認合意とシンガポールのそれを、合意された分野別に示したものである。世界的に、電気通信機器及び電気製品分野が相互承認の一般的分野の1つとなっていることが分かる。シンガポールと日本のRTA交渉は、両国専門家による共同検討会合「産官学研究会」(2000年3月)によって着手される。シンガポールも、日本と同様に、シアトルWTO閣僚会議の失敗後にRTA締結に転じた国家の1つであるが、相互承認については、シンガポールは対ニュージーランドとのRTAにおいて既に相互承認を挿入していた他、オーストラリアとは単独のMRA交渉を進めていた。シンガポールが、ニュージーランドとオーストラリアとの相互承認の合意に着手したきっかけは、APECの枠組みで、ニュージーランドとオーストラリアとは、電気製品分野の相互承認の推進国としての関係にあったことにあった。
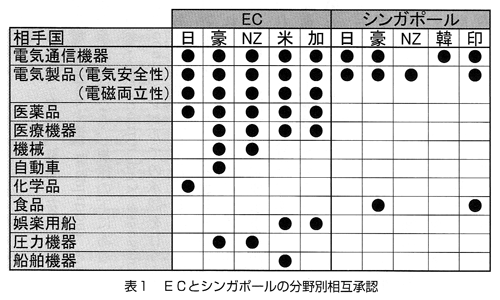
日本も、相互承認については未経験ではなく、ECとの日欧MRAの交渉が1995年から開始、シンガポールとのRTA交渉が本格的に始まる前の2000年中には大枠の合意が完成していた(日欧MRAは2001年4月署名、2002年4月発効)。長期化した日欧MRA交渉では、「『これまでの日本の基準・認証制度を根本から転換しなければならない問題』(外務省幹部)なので、日本での国内調整は難航」*3していると、法整備をめぐる問題が頻繁に報道されていた。「根本からの転換」の1つは、日本が、EC内で既に普及していた「第三者認証制度」を採用し、電気用品安全法を法改正したことである*4。「第三者認証制度」とは、製品が輸入国の安全技術基準に従ったものであるかどうかを国ではない中立の機関が検査する制度のことである。当時、日本では、国が指定した公益法人のみが試験・認証する仕組みになっていた。法改正の結果、登録された検査機関であれば外国の試験機関や民間法人でも試験・認証が可能となった。
かかる両国の背景があって、日星協定の交渉が始まり、2002年1月に署名される。採用されたのは、表2が示すような、先の日欧MRAと同じ型の相互承認であった。
この型は、実は、製品の安全技術に関する規律(law and regulation)それ自体の承認ではなく、規律の下にある適合性評価手続(conformity assessment procedure)レベルでの承認を行うものであり、世界的にもこれが多い。「適合性評価」とは、ISO/IEC17000の定義によれば「製品、プロセス、システム、要員又は機関に関する規定要求事項が満たされていることの実証」であり、現在の先進国での主流は、この手続を、中立の第三者である適合性評価機関(conformity assessment body)が行うことが多い。適合性評価手続レベルでの承認が可能となると、企業は、輸出先の外国の適合性評価機関に対して輸出製品の試験・認証を申請する必要はなくなり、国内で登録された適合性評価機関に対して試験・認証を申請し、手続を国内で済ませて輸出することができる。適合性評価機関が出した認証結果については、外国政府は外国内で行われた適合性評価と同等のものとして無条件で受け入れなければならない。
日星協定の実施
日星協定は2002年11月30日発効した。相互承認の実施の核心は、適合性評価機関の認定にある。結果的には、電気製品分野に限っては、日本とシンガポールそれぞれの適合性評価機関が認定され、日本側は、2004年2月に財団法人・日本品質保証機構(以下、「JQA」)が、シンガポール側では、2004年9月にPSB Corporationが登録された。他方、電気通信機器分野については、適合性評価機関の登録がなく、実施が滞っている。
適合性評価機関の認定の困難さは、この段階において、合意した国家は互いの規制内容を最もよく勉強し、知らなければならないところにある。一般的に相互承認の文脈において適合性評価機関を認定するということは、輸出する側の政府が、「輸入国政府の認定・監督業務の代行を行うこと」すなわち「輸入国政府の機能の一部を保有すること」(経済産業省・産業技術環境局認証課相互承認推進室)になるからである。具体的に電気製品分野の場合、日本側の「指定当局」(同省)が、シンガポールの安全性基準に従って適合性評価を行う機関の認定を行うことになる。つまり、相手国の規制内容をよく知らなければ適合性評価機関を認定できない仕組みになっている。この段階が、互いに相手国の規制法を勉強し、よく知るための詰めの段階となり、相互承認の締結・実施の過程で行政コストが最も集中する。
せっかく構築された制度である。実際に産業界に利用してもらうことが重要であるが、適合性評価機関の登録が済んだ電気製品分野において、実際に両国の適合性評価機関が証明書を発行した件数はゼロである。つまり、両国の企業から申請がまだないという状況である。実は、証明書発行件数という点からみると、日欧MRAも似たような状況にある。日欧MRAは2002年1月に発効しており、JQAは2002年11月に適合性評価機関として登録されているが、証明書(型式)の発行は2006年3月時点で、37件しかない。
展望
世界的にも注目を浴びた米欧MRA(1998年署名)の交渉経緯をまとめた文献に次のような一節がある―"Negotiation of the MRAs was just the beginning of the process. Many issues remained open and required further discussions to determine the terms of the implementation."*5日星協定で表面化した実施の困難さはこの2カ国に限ったことではないのである。相互承認とは、互いの規制に対する理解と共有のプロセスであり、その学習プロセスこそに意味があるのかもしれないが、利用可能な制度の構築までの道のりは長いのが現実である。そうだとすれば、学術的な評価はそうした厳しい現実も勘案したものであるべきである。
他方で、少しでも行政コストを減らすことの模索もされている。これから締結する合意については、「域外認定型」相互承認(表3)という行政コストの少ない型も選択肢の1つと考えられている。これまで輸出する側の国が輸入国の安全技術基準を理解してそれに従った適合性評価機関を指定してきたところを、輸入国側が自国の安全技術基準に従った相手国側の適合性評価機関を指定する仕組みに変えることで、相手国の規制を理解した上で適合性評価機関を指定する行政コストを減らすことができるという。1990年代から注目を集めた相互承認という政策が、今後どのように時代と共に変化していくのか、注目していきたい。