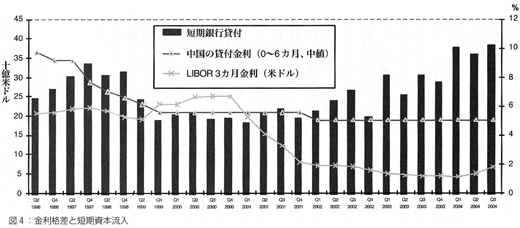はじめに
中国では、一連の国内金融・投資の自由化政策が徐々にだが同時併行的に進められている。その一方で金融業界をとりまく対外競争はますます激化しており、中国にとって、金融サービス貿易自由化における世界貿易機関(WTO)コミットメントを完全に実現しなければならない2007年は、かなめの年となるだろう。
一般に、新興市場に外資系銀行が参入すると、競争力が高まったり技術やスキルが移転されて効率化は進むが、一方で政策決定者は、自由化をどのようなスピードで進めるか、監督能力をいかに上げるか、通貨政策をどうするかといった課題に直面する。過去の例からすれば、1980年代以降、IMF加盟国の3分の2以上が銀行セクターで重大な問題を経験したとの分析もあり、金融自由化プロセスにある国ほど金融危機のリスクも高い。金融自由化と銀行危機の関係に関する研究でも、自由化によって銀行危機が起こる確率が高いことがわかっている他、新興市場経済では、銀行危機は通常、その国の資本収支がオープンな場合、対外収支危機に連動して起こるとみられている。
金融サービス貿易の自由化はたいてい資本移動を伴うので、外資の参入によって、新興市場経済における国内の金融・投資自由化のプロセスは当然ながら複雑化する。仮説としてよく言われるのは、外資系銀行の参加は国内の金融と投資の自由化を加速させ、とくにホスト国の資本規制制度が徐々に有効的に機能しなくなるため、事実上の資本勘定自由化をひきおこすという説だ。新興市場経済においては、為替制度や金融政策の進め方について適切な調整を行わないと政策は基本の部分で一貫性のないものになり、資本収支危機をひきおこしかねない。
本稿では、中国を例にこの仮説を検証し、外資の参入が中国国内の金融投資自由化を促進しているかどうかを明らかにするとともに、政策提言も導き出すこととしたい。
中国のWTO金融サービス・コミットメントとその意味
中国は2001年末のWTO加盟時に「サービスの貿易に関する一般協定」(GATS)に署名した。業務範囲(現地通貨/外国為替銀行業務)、顧客(居住者/非居住者、消費者/企業)、地理的条件についてはコミットメント履行に5年の段階的移行期間があるが、コミットメント全体でみると、東アジア諸国や他の発展途上国と比べ自由度が大きい(図1)。
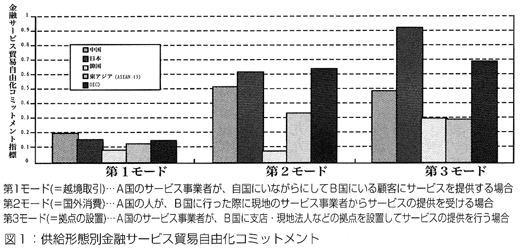
中国における外資系銀行の特徴
(1)規模、参入形態、地域…どの基準で見ても、中国における外銀のプレゼンスは今のところ比較的小さい。外銀の総資産規模が国内銀行資産に占める割合はわずか1.4%で(表1)*1、主な参入形態は支店である。2004年6月末の時点では、支店数162に対し、外資系子会社は14社のみで、その子会社の総資産規模は、中国の総外国資産の六%足らずである。進出地域については、上海と深センという沿岸の2都市に集中している。
(2)参入の動機と顧客…外銀の中国市場参入の動機は、他国の例と同様、顧客の対外直接投資(FDI)活動に対するフォローである。図2が示すように、中国に進出した外銀の国(地域)別資産は、その銀行の本国(出身地域)の対中直接投資の動きと密接に呼応しており、その相関係数も0.8とかなり高い。当然ながら、これら外銀の主な貸付先はFDIを展開している自国企業である(表2)。
(3)財源…外銀による融資の60%以上は米ドルで行われている(表2)。人民元の預金高の伸びと銀行間市場へのアクセス増に支えられる形で、人民元による融資も近年急成長しているものの、各種規制によって妨げられている。例えば外銀の人民元取引は、特定の地域に限り、外資系企業に対してしか認められておらず、中国企業との取引が認められたのはつい最近のことだ*2。各行はこれまで、人民元融資の資金については主に銀行間市場に依存していたが、企業との人民元取引の規制が撤廃されてからは、企業からの人民元預金が主な資金源となっており、銀行間市場への依存度は次第に低下しつつある(図3)。
とはいえ、それでも足りない場合は本社からの借入で賄うしかない。1998年までは銀行間市場からの借入にも制限があったため、預金基盤が強くはない外銀は、2000年までの融資はほぼ全額を本社資金に依存していたのが実態だ。中国の銀行間市場にアクセスできるようになった後も、2003年6月までは本社からの借入資金だけで融資のニーズを満たしていた。また、本社からの純借入額は人民元為替相場の予想ともかなり連動しているようだ。例えば、1997~98年のアジア金融危機の時は人民元の下落が予想されたため、1997年に220億米ドルを超えていた外銀の本社からの純借入額は急速に落ち込み、2002年にはわずか60億米ドルになった。しかし2002年末以降は、主に人民元の評価予想が逆転したことをうけて本社からの借入額は増加に転じ、融資ニーズを上回るほどになった。本社からの直接借入は、各行が中国の対外資本移動に影響を及ぼしうる最重要チャネルの1つである*3。
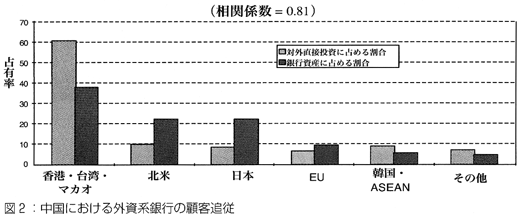
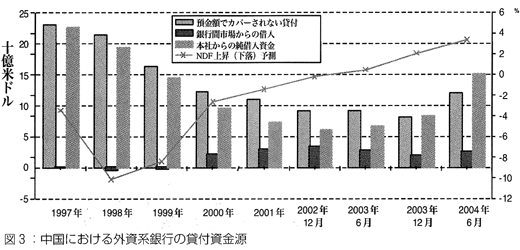
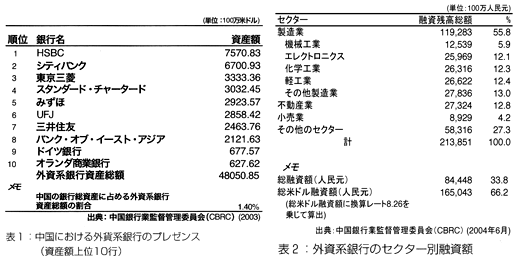
外資系銀行のプレゼンスが中国の国内金融自由化に及ぼす影響
このように、外資系銀行は規模は比較的小さいが、国内金融や金利の自由化、参入障壁の撤廃、業務とセクターの範囲、金融セクターへの国の関与の縮小といった改革を促進する上で、すでに影響を及ぼし始めている。
(1)中国の金利自由化に対する外資系銀行の影響…中国の金利自由化は、基本的に教科書通りのスケジュールに従っている。すなわち、長期金利の前に短期金利を、借入金利の前に貸出金利を、国内通貨の貸出・預金金利の前に外国通貨の貸出・預金金利を自由化するというものだ。現時点では、銀行間金利と国債金利は完全に市場原理で決定されている。2004年1月1日より、銀行貸出金利の変動幅が、中央銀行が設定した年間基準貸出金利のマイナス10%からプラス170%まで認められることになったほか、同年10月29日には貸出金利の上限も撤廃された。預金金利はまだ完全には自由化されていないが、大口預金金利は預金者と銀行の間で交渉可能になっている。こうした一定の順序に従う戦略の根拠は、銀行のフランチャイズ価値を保護し、銀行同士が必要以上に預金をとりあうことがないようにするためとみられる。
外資系銀行は人民元預金基盤が小さいため、1998年以来常に銀行間市場に積極的に参加しており*4、そのことが地域ごとの縦割りをなくし、国内銀行間市場の統合を進める要因となってきた。例えば、上海と深は共に銀行間市場の中心地だが、その銀行間人民元市場に外銀が参入し始めた当初、深センの銀行協会は過当競争を防ぐため、外銀に対する人民元貸出金利は平均基準貸出金利から20%以上下回ってはならないことを取り決めた。これに対し上海の銀行間市場には、こうした反競争的な慣習がなかった。その結果、入手できるデータを見る限り、上海の銀行間金利は2001年には36%も下落、結果、外資系銀行は借入の大半を上海市場で行うようになった。上海に市場占有率を奪われることをおそれた深センの銀行協会は、結局2002年に取り決めを廃止したのである。
(2)手数料ベースの業務…中国が2001年末にWTOに加盟した直後から、中国で営業する外資系銀行は対中国人預金者の外国為替業務を行えるようになった。ところが、外資系銀行の場合、サービスの質は高いが、その分手数料を支払わなくてはならない。これは中国人の顧客にとってはまったく予想外のことだった。例えば、2002年のシティバンクは、月間平均預金残高が5000米ドルを下回った預金者に月額6米ドルまたは50人民元の手数料を課した。HSBCやバンク・オブ・イースト・アジアといった他の外銀にも、形は様々だが預金手数料があった。すると、ほどなく国内銀行が外銀の例に倣って外貨預金に手数料を課し始め、さらに別の銀行グループとのATM取引からも手数料をとるようになったのである。国内銀行は人民元業務についても改革を実施し、大口預金者に独自のサービスを提供し始めている。
(3)銀行業務の範囲への影響…中国の金融サービス貿易自由化協定の重要な特徴の1つは、中国の金融セクターでの営業の認可基準が、健全性に関する手段のみに基づいており、経済的ニーズや認可件数の数量的な制限に関する基準がないことである。その結果、加盟後に相応の規制の変更を行なう必要があった。2002年から03年にかけて、中国銀行業監督管理委員会(CBRC)は、認可を要する銀行業務リストから26業務を削除した。一部の業務については一旦認可されれば、自行の支店にその業務を行わせるかどうかは、当局にあらためて承認を得ずとも本社が決定できるようになったのである。当局の承認が必要な新たなカテゴリーの銀行業務についても、申請後10営業日以内に決定が下される。実際、WTO加盟により中国の規制慣習を国際基準に近づけるプロセスは加速した。透明性や効率も向上している。
(4)金融規制への影響…金融持ち株会社の場合…2003年に改正された中国の商業銀行法により、中国で営業する商業銀行は、信託・証券業務、自社使用でない不動産事業への投資、ごく一部の例外を除きノンバンクの金融機関や企業への投資は禁止されている*5。しかし、中国で営業する大手の外資系銀行はたいてい金融持ち株グループに属しており、国内銀行よりはるかに優位な立場にあると認識されているため*6、金融持ち株グループに関する新たな法律が現在検討されている。また、外資の参入とその金融持ち株グループのプレゼンスを理由に、中国は中央銀行・商業銀行法を、機関間調整と情報共有に重きを置いた内容に修正した。中国人民銀行に新たに設置された金融安定局が、こうした調整を担当することになっている。
(5)金融セクターへの新規参入と国有商業銀行の民営化への影響…中国がWTO上の義務の下で外銀に対し内国民待遇を提供できるとするなら、新設の民間銀行の参入はどのように扱うべきかという議論が、近年強い関心を呼んでいる。銀行規制委員会がとった方法は、新規認可数を増やして国内の新規参入を促進するよりも、民間投資家に既存の銀行の株主になるよう奨励することだった。民間の国内銀行が新たに認可申請をする場合でも、外国の投資家を戦略的パートナーとして持っていることが求められる。新興市場や移行経済から得られた経験則や教訓から見ると、金融自由化後に急増した民間銀行は大半が失敗し、納税者がそのツケを払わされるのがオチだったから、その意味で現在の規制は健全である。しかし、商業都市銀行と国有銀行は、その財政状況に透明性が欠けていたので、民間投資家は株主になることにかなり消極的だった。自分たちの投資が、不良債権の穴埋めに使われるだけでなく、少数派株主であるために意思決定プロセスに事実上参加できないのではないかと懸念したからだ。四大国有商業銀行の民営化プロセスも、政府がこれらの銀行に対する過半数支配の放棄を渋るようだと、同様のジレンマに陥るだろう。
外資系銀行のプレゼンスが中国の国際的資本移動に及ぼす影響
一般的な基準で見れば、中国経済はすでにかなり開放が進んでおり、貿易総額はGDPの60%に迫っている。貿易のリーズ・アンド・ラグズ(Leads and Lags)*7からの資本移動だけで、1700億米ドルに上ると推定される。すでに合弁企業、外資系企業、中国企業のいずれとも取引できるようになった外銀は、中国の資本移動の仲介においても積極的な役割を果たしている。表3に示す通り、2003年における外資系企業と外資系銀行の借入総額は585億米ドルに達し、これは同年の中国の対外債務総額の20%に当たる。
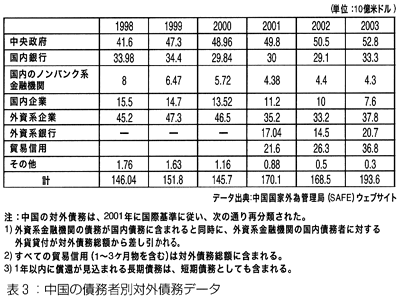
中国に進出した外銀の手によって国際的な資本移動のチャネルが増えたのは確実で、そのおかげで中国の資本統制はより緩やかになった。中国への短期銀行貸付の仲介において、外資系銀行は既に積極的な役割を果たしている例をみてみよう。
2000年の自由化以後の中国での外貨貸付と大口預金の金利は、通常LIBOR(ロンドン銀行間取引公式レート)またはHIBOR(香港銀行間取引公式レート)プラス100~200bpに設定されている。2000年第4四半期以降、主に米連邦準備制度理事会の積極的な金融緩和を反映して、3カ月LIBORレートは急速に落ち込んだ。一方、中国の6カ月未満の人民元短期貸出金利は5%をやや超えた辺りで推移していたため、外資系銀行はサヤ取引の機会を得ることとなった。ロンドン市場から金利2%足らずで借り入れた資金を中国内の外資系や合弁企業、2002年以降は中国企業に対してLIBOR+1~2%で貸せば、最低1~2%の利ザヤを得ることができるというわけだ。こうした貸付は企業側にも好都合である。なぜなら、米ドルで借り入れてすぐ人民元に交換すれば、人民元で借り入れるより最低1~2%の金利分を節約できるからだ。実際、中国の短期借入が1999年末には約200億米ドルだったのが2004年には380億米ドルまで急速に増加した(図4)のは、これが理由とも考えられる。これが機となって、国家外貨管理局は2004年6月21日、外銀と国内銀行双方に対して短期対外債務の額を経営資本の5倍以下に制限する規制を発令した。2004年末時点で外銀の経営資本規模は52億米ドルだったので、この規制による年間の未払い短期債務額は、最大で約260億米ドルとなる。
中国に流入または中国から流出する資本移動のもう1つのチャネルは、外資系銀行支店の本社との間での貸借である。外銀の本社からの純借入額の増減を決定づける要素は主に2つある(図3)。1つは現地通貨の貸出を支えるために現地市場で調達できる現地通貨量であり、もう1つは為替リスクとの関係である。図からも明らかなように、人民元に上昇圧力がかかっているときは、外銀支店は本社から借入れて中国国内の顧客へ貸付を増やす傾向にあるが、下落の圧力があるときは、本社からの借入額は減少傾向にある。
結論と政策提言
このように、中国の金融サービス貿易自由化は、国内の急速な金融自由化への誘発剤となってきた。外資系銀行は、未だその規模は比較的小さいものの、支店と本社間の資本移動や国内市場と海外市場間の取引などを通じて、すでに中国のキャピタル・フローに大きな影響を及ぼしている。今後参入障壁がさらに軽減され、総資産規模が拡大するにつれ、外銀が果たす資本移動の仲介的役割はさらに重要性を増していくであろう。
最後に、重要な政策的インプリケーションをいくつか提示したい。まず、この中国のケーススタディーが示す通り、外資系銀行のプレゼンスは国内の金融機関にスピルオーバー効果、またはデモンストレーション効果をもたらし、効率化につながっている。また、中国経済に必要な人的資源とテクノロジーが持ち込まれることで、国内の制度構築も加速させる。この点で、外資系銀行の国内金融セクターへの参加は歓迎されるべきだと言えよう。
しかし一方で、金融サービス貿易を外国との競争に開放すれば、国内経済により多くの資本移動を招き、既存の資本統制システムの有効性が損なわれるおそれがあることも、政策立案者は認識しなければならない。国際的サヤ取引が大規模に行われれば、内外の金利差が消滅し、国として独立した通貨政策を維持することができなくなってしまう。資本移動の自由を拡大しながら、同時に独立した通貨政策の維持を目指すのであれば、為替相場制度に柔軟性を持たせなければならない。2007年以後は外資系銀行のプレゼンスの大幅な増大が予想されることから、国際的な資本移動の拡大を見込んで柔軟な為替相場制度へ移行していくことこそが、中国の利益につながると考えられる。