| 解説者 | 関沢 洋一 (上席研究員) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0089 |
| ダウンロード/関連リンク |
アベノミクスにより実現が期待される経済の好循環。そのためには個人や企業の消費や投資行動が活発になる必要がある。こうした個人の消費行動と心理状態の関係性については、「景気は気から」という言葉に代表されるように、以前より何らかの関係があるものと考える人はいたものの、経済学的な分析は行われてこなかった。関沢洋一シニアフェローは、認知行動療法などの心理療法を通じて心の健康を増進することは、深刻化するメンタルヘルスの問題への対応策として人的資本の質の向上につながるだけでなく、国全体の景気に対しても良い影響を及ぼす可能性があると指摘する。
――この研究は何を目指して行っているのですか。
この論文はRIETIのプロジェクト「人的資本という観点から見たメンタルヘルスについての研究」の成果の一部です。メンタルヘルスはロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで提言が出されたり、OECDにおけるプロジェクトとして取り上げられたりするなど、経済的観点からも関心の高まっている分野です。RIETIのメンタルヘルスのプロジェクトには2つの目標があります。1つは、薬を使うことなく、多くの人が自分で行える取り組みでメンタルヘルスを改善できないかという問題意識のもと、そのための手法を探すとともに、その効果検証を行うというものです。
もう1つの目標は、消費態度や投資意欲が抑うつ度(うつっぽさ)や不安といった心理状態からどの程度の影響を受けているのかを明らかにしていこうというもので、これが今回の論文のメインテーマにもなっています。仮に、人々のうつっぽさが強まったり、不安に駆られたりした結果として、人々が消費を手控えたり、投資リスクを避けたりしているとすると、精神医学や臨床心理学で使われている手法を使うことによってメンタルヘルスを改善し、それを通じて消費や投資を増やし、最後は経済の活性化につなげていく経済成長戦略があるのではないか。このような問題意識をもって、それを検証しています。
――論文の冒頭に安倍首相のスピーチを引用しているのが印象的ですね。
安倍首相が2013年5月に長嶋茂雄、松井秀喜両氏への国民栄誉賞授賞の際に行ったスピーチは、非常に興味深いと思いました。人々の気持ちを明るくすることが重要だという意志が明確にされていたためです。アベノミクスは心理学だという言い方がされることがありますが、私自身もアベノミクスの心理学的な側面に以前から着目していました。安倍首相のブレーンとされる浜田宏一イェール大名誉教授の研究にはもともと関心がありました。浜田教授が経済に対する感情面からのアプローチを重視しているように思えたからです。浜田教授の主張を私なりに理解すると、「世の中には『楽観的な期待』に支配された『良い均衡』と、『悲観的な期待』に支配された『悪い均衡』があって、失われた20年における日本は長期に渡って悪い均衡に陥っている。人々の将来への見通しが暗く、それが自己実現する形で悪い均衡がずっと続いている。この悪い均衡から良い均衡へとどう移っていくかが問題である」というものです。
私は、悪い均衡から良い均衡に移行するための力として感情が重要なのではないかと考えています。この10年くらい心理学で行われてきた研究では、たまたま抱いている感情や、心配性などといった感情面の性格が、物の見方や意思決定に影響している、ということが指摘されています。たとえば、不安や憂うつだったりすると、何もかも全てが悪く思えてしまう。逆に、明るい気持ちになっていると根拠もないのに将来の見通しまで楽観的になる。こうしたことは多くの人々がしばしば経験することだと思いますが、それが研究によって裏付けられるようになっています。
感情についての以上の見方を前提に政策面をみると、理由は何でもいいのでとにかく国民の気持ちを明るくすれば、消費態度や投資意欲が改善するという仮説が出てきます。「アベノミクス」といわれる現政権の経済政策の本質もこのあたりにあるのではないか、国民に明るい心を持たせることで経済の活性化を狙っているのではないかと感じています。それを象徴的に示しているのがこのスピーチだと思いました。
研究のヒントは認知行動療法から
――どのような経緯でこのような研究を始めることになったのですか。
5年ほど前に精神科の医師と話をしていた際に、精神医学で使われる認知行動療法という治療法を使うことによって景気を回復させられないかという話が先方から出ました。それが私の研究のきっかけになりました。認知行動療法では不安やうつといった感情の落ち込みは、「自分は価値がない」「将来は絶望的だ」といった否定的な思考を信じることから生じていると捉えて、その思考を合理的で健全な方向へと修正することによって感情の落ち込みから脱していこうとします。これを経済学にも応用できないかと考えたわけです。つまり将来に対する弱気な見通しの背景にある思考をもっと前向きな方向に修正できれば、景気改善や経済成長につながるのではないかと考えました。
さらに調べるうちに、感情が意思決定に影響するという研究が増えていることを知りました。こうした研究に接するうちに、認知行動療法などで感情を明るい方向に持っていけば、人々の経済に対する態度が改善し、景気に良い影響を与えるのではないかという考えが膨らんでいきました。
感情が意思決定一般に及ぼす影響についての心理学的な研究は、21世紀に入ってようやく本格化したばかりです。ローヴェンスタインやスロヴィックといった人たちが、「リスク・アズ・フィーリング」や「アフェクト・ヒューリスティック」といった概念を提示しています。また、感情と投資意欲の関係や、メンタルヘルスと消費の関係についても、この数年の間にいくつか論文が出ています。
――具体的な調査の内容について教えてください。
この調査はアンケート調査です。アンケート調査の質問票を自分で作る代わりに、意図的に、これまでに何回も使われた質問票を選んでいます。経済指標では内閣府の「消費者態度指数」を使いました。心理指標としては「抑うつ度」「楽観度」「生活満足度」「一般的信頼尺度」「肯定的感情」「否定的感情」の6つを用いました。
「消費者態度指数」は、4つの質問への回答を指数化したもので、消費支出やGDPと関係があることが研究によって明らかにされています。「抑うつ度」などの心理指標は、精神医学や心理学で標準的に用いられているものを選んでいます。たとえば、抑うつ度は、CES-Dという心理尺度を使って計測しています。CES-Dは、うつ病かどうかをテストする質問票として世界的に使われています。
要は、これまでは別々の学問分野で別々に追いかけられてきたものの間に関連性があるのかどうかを検証しようということです。私が調べた範囲では、こういう調査を過去に行った例は見つかりませんでした。この調査はオンライン上で行われ、3時点のデータをとりました。
――どのくらいの回答を集めたのでしょうか。
この論文と同時に執筆したRIETIのディスカッションペーパー「良いことを毎日3つ書くと幸せになれるか?」(DP 13-J-073 http://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/13110008.html)でもこの調査を利用していますのでそれと併せて説明します。調査ではまずこれら7つの指標に関連する質問に回答してもらい、約6000人から回答を得ました。回答者のうち1000人について、「その日に起きた3つの良いことを書く」グループ(TGT群)と「過去の思い出を書きこむ」グループ(統制群)の2つにランダムに分けて、4週間にわたって、週に2回以上のペースでそのエクササイズをしてもらいました。4週間経過後に改めて同じ質問に答えてもらい、さらにその1カ月後(この間エクササイズはなし)にフォローアップの形で同じ質問に答えてもらいました。脱落があったため、時系列の変化が追えるのは2つのグループ合わせて500人弱でした。
対人信頼度の指標に注目
――どのような分析結果が得られましたか。
まず、「良いことを毎日3つ書くと幸せになれるか?」についてです。この研究は米国のセリグマンという心理学者の提唱するポジティブ心理学で用いられた幸福度を高める手法の効果の検証という狙いがあります。セリグマンらの研究では、毎晩寝る前に3つの良いことを書くというエクササイズを1週間行うだけで、その後半年間にわたって、肯定的感情が高まったり、抑うつ度が減るという劇的ともいうべき効果がありました。日本の研究で同じ結果を再現できれば政策的にも意味があったのですが、実際には今回の研究ではそのような劇的な効果は見られませんでした。具体的には抑うつ度、生活満足度、楽観度については4週間のエクササイズ期間の前後で有意な変化はありませんでした。肯定的感情も「良いことを書いた」グループではいったん向上するのですが、セリグマンの研究ではその効果は持続するはずなのに、今回の調査ではエクササイズ終了から1カ月後には効果が消滅していました。
他方で、他人を信じる程度を表す指標である「一般的信頼尺度」は、2つのグループともにエクササイズ終了後、さらにはその1カ月後にも向上しました。心理指標の中で最も動きが少ないのではないかと予想していたのですが、意外な結果でした。こうしたことが起きた理由として、1つには調査期間中に対人信頼度が向上するようなことが世の中で起きて両グループに影響を及ぼしたという解釈があり得ますが、この時期(2013年6月)にそのような出来事が起きたようには思えず、実際には考えにくいと思います。もう1つの解釈は「良いこと」かどうかに限らず、「書く」ことが効果を生んだということです。(図1)
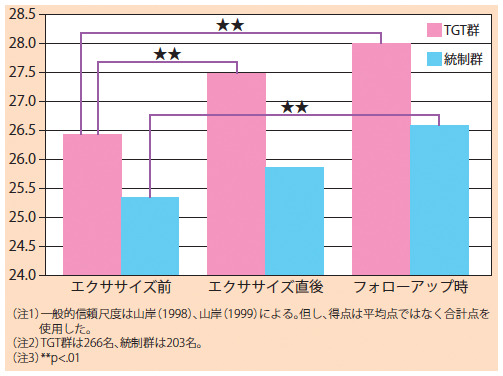
最近、社会科学ではソーシャルキャピタルという概念が注目されています。米国のパットナムという政治学者が最初に指摘したのですが、「人を信じること」や「人とのつながり」は一種の資本として扱われるべきだとされています。人を信じる程度と経済成長には関係があるという研究も出ています。ただ人を信じる程度をどうやって高めていくかという研究は、あまりなされていないようです。もし今回行ったエクササイズで本当に人を信じる程度を向上できるならば、経済成長にとっても意味があることになるので、さらに研究を進める必要があると感じています。
――本論文(「心理指標と消費者マインドはどのように関係しているか?」)の分析結果はいかがですか。
こちらの方は研究前の予想に近い結果が出ています。たとえば抑うつ度が低いほど、生活満足度が高いほど、楽観度が高いほど、対人信頼度が高いほど、肯定的感情が強いほど消費者態度指数が高く、一方で否定的感情が強いほど消費者態度指数は低いという結果が出ています。これらはいずれも1時点(クロスセクショナル)の分析結果ですが、時系列でデータを分析したパネル分析では、抑うつ度については有意な関係がなくなるものの、それ以外の生活満足度、楽観度、対人信頼度、肯定的・否定的感情は依然として消費者態度指数と有意な関係がありました。
この論文は心理指標と経済指標の関係を調べるのが目的ですが、併せて心理指標相互の関連性も調べています。その結果を見ると抑うつ度とその他の心理指標には関係がありますので、パネル分析で抑うつ度と消費者態度の間の直接の関係がなくなるといっても、抑うつ度の低下が生活満足度や楽観度などの改善を通じて、間接的に消費者態度の改善をもたらす可能性を指摘することができます。
期待はずれだった面もあります。「3つの良いことを書く」のエクササイズの結果、心理指標が改善し、その結果として消費者態度指数も改善すると予想していたのですが、「良いことを書く」グループ、「思い出を書く」グループ双方とも消費者態度指数は有意に変化しませんでした。今回のエクササイズは、抑うつ度の改善など心理指標への影響が期待したほど大きくなかったため、心理指標の改善を通じて消費者態度が改善するという仮説は検証できませんでした。ただし「一般的信頼尺度」については両グループとも向上したことは先ほど指摘しましたが、内閣府によるとテスト期間(2013年6月~8月)の消費者態度指数、つまり社会一般の消費マインドは低下しており、このエクササイズに参加した人々は一般的信頼尺度が向上したために、本来は低下するはずだった消費マインドの低下が食い止められた可能性があるとも考えられます。
全体としてみれば心理的な介入の結果、消費マインドを改善させられるかどうかについては明確に肯定されなかったものの、否定もできないということになります。次の研究が必要になります。
――論文に対する反応で印象深いものはありますか。
まだ具体的な反応やコメントはないです。強いて言えば、私の研究一般に対して、人間の行動は合理的という発想に立つべきだというコメントをもらったことはあります。
人間の行動が合理的だという前提に立つのは経済学における伝統的な見方ですが、生身の人間である私としてはどうしてもついていけないところがあります。経済を支える大衆の行動は、感情に支配された1人1人の個人の行動の総和ですので、人々の感情が1つの方向に流れることがあるとすれば、心理は経済に影響すると考えるのが自然だと思います。ケンブリッジ学派など、昔の経済学では景気循環は人間の楽観、悲観の変動によってもたらされるという意見が強かったものが、その後は「合理性パラダイム」が主流になって、そうした考えはあまり主張されなくなりました。
ただ、アカロフとシラーの著作『アニマルスピリット』や、最近流行している行動経済学では、人間の心理を経済学に取り込もうとしています。もっとも、行動経済学では、全ての人間が同じように非合理であるという前提を置いているようで、これには疑問があります。人間の行動パターンは人によって大きく異なるし、同じ人でも行動パターンは時間と共に変化します。仮に、行動パターンに感情などの心理状態が影響を及ぼし、そうした行動パターンが不適切なものであるとすれば、認知行動療法のような取り組みによって感情を好転させることによって、行動パターンも良い方向に変えられる可能性が出てきます。これは突拍子もない話のように思われるかもしれませんが、たとえば、最近の研究では、感情調整(エモーション・レギュレーション)というテクニックを使うことによって、行動経済学の示す人間の特徴の1つである損失回避傾向が減少することが明らかになっています。これが本当ならば、認知行動療法で同じ結果が出ても不思議ではありません。
――今後の研究の方向性について教えてください。
コンピュータを使って認知行動治療を自習する取り組みがイギリスなどで広く行われています。このようなコンピュータ認知行動療法の効果検証研究をRIETIも参加して行えないかと考えていて、精神科医の先生と相談を進めています。この研究の目的は2つあって、1つは、日本語で作られた認知行動療法のコンピュータプログラムの効果を検証することです。もう1つは、このプログラムによって抑うつ度(うつっぽさ)が改善した時点で、「一般的信頼尺度」や「消費者態度指数」といった経済に関連する指標もまた改善するかどうかを検証することです。うつ病対策として認知行動療法への期待は高まっていますが、この治療法を行えるセラピストがとても少ない中で、コンピュータを使った認知行動療法は、多くの人々が安くこの治療法を受けられるというメリットがあります。IT(情報技術)を使った取り組みという意味においても、経済産業省やRIETIにふさわしいのではないかと考えています。
また、この研究によって、メンタルヘルスを改善する取り組みが、本人の健康増進だけでなく、ソーシャルキャピタルの改善を通じ経済全体に対してプラスの影響を及ぼすのかどうかも明らかにされると思います。
解説者紹介
2006年東京大学社会科学研究所准教授、2008年経済産業省通商政策局経済連携課経済連携調査官を経て、2012年5月より現職。主な著作物:「感情が消費者態度に及ぼす影響についての予備的研究」(『行動経済学』第5巻・2012年(桑原進氏との共著)(旧稿RIETI DP12-J-027))、「紹介バイロン・ケイティのワーク」(『精神医学』第54巻第5号・2012年(清水栄司氏・田中麻里氏との共著))、『日本のFTA政策:その政治過程の分析』(東京大学社会科学研究所・2008年)


