| 解説者 | 渡辺 努 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0082 |
| ダウンロード/関連リンク |
日本では長期にわたってデフレが続いているが、下落率は年率にして1%前後と非常に緩やかだ。これは、先進国のデフレの事例として有名な、第二次大戦前の大恐慌時代に米国であったような激しい物価下落とは様相を異にする。このような「緩やかなデフレ」という不思議な現象に対して、海外には日本の消費者物価統計(CPI)そのものの信頼性を疑問視する声もある。
こうした疑問に正面から答えるため、渡辺FFらは膨大な店舗販売データを用いて、総務省が作成するCPIの再現を試みることなどにより、その統計的な信頼性についての検証を行った。更に、米国型の作成方法でも物価指数を算出し両者を比較した結果を踏まえ、渡辺FFは、デフレの脱却を判断するには、慎重な姿勢が欠かせないと指摘する。
――論文の原題は"How Fast Are Prices in Japan Falling?"ですが、ご執筆の問題意識をお聞かせ下さい。
日本では1990年代半ば以降、デフレ状態が続いています。このことが日本のみならず世界経済にとっても大きな問題なのはいうまでもないのですが、その程度を示す消費者物価指数(CPI)を見ると、下落率は毎年1%前後で、最も下落率の激しい時期でも2%程度にとどまっています。
先進国のデフレの事例は極めて限られているのですが、代表的な例である1930年代の大恐慌期の米国では、同じデフレといっても年率7%という大幅な物価の下落が起きました。これに比べると、現在の日本のデフレは、緩やかな物価下落が非常に長期間続いているといえます。このように、10数年にわたって日本の景気が悪いといわれながらも、物価下落の速度がそれほど急激ではないことについては、日本の国内のみならず海外の研究者や実務家も強い関心を持っています。
この理由については、政策担当者や研究者などにより長年に渡り議論が重ねられてきており、色々な考えがあります。その中には、「日本の総務省が作成しているCPIが正確に計測されていないために、デフレ率が低く見えているに過ぎない」といった、日本の物価統計そのものの信頼性について懐疑的な見方もあるのです。このような傾向は、特に欧米で強いように思います。
こうしたことから、日本の物価は緩やかな下落にとどまり、緩やかなデフレという不思議な現象を起こしている原因が、本当に統計そのものの問題であるのか、それともそれ以外の要因なのかを明らかにしたいと考えました。
――統計の信頼性を確認するために、どのような方法を採られたのですか。
統計そのものの信頼性を確認しようとする場合、2つの方法が考えられます。1つは、総務省がCPIを作成する際に使っている個々のデータを自分で見て、それらが適切かどうかを検討するという方法です。しかし、実際にCPIを作成するために使われるデータや統計など詳細な内容について、外部の研究者が簡単にアクセスできるものではありません。また、仮にそうした詳細な情報が入手可能だったとしても、それぞれのデータの妥当性を判断するのは困難です。
そこで、2番目の方法として、総務省のCPIとは異なるデータソースを使いながら、総務省の作成法を踏まえる形で、物価指数を作成することを目指しました。
10年間で36億データにのぼる販売関連情報をもとに分析
――新たに物価指数を作るのは大変ではないですか。
実は、物価指数の算出については、数年前にも試みたことがあるのですが、その際には作業途中で断念しました。総務省ではCPIの作成法を公表しています。しかし、それぞれの手法の細部には文章には書かれていないテクニカルな事柄がたくさんあるのです。それを1つずつ総務省に問い合わせて確認しながら作業を進めていたのですが、あまりにも煩雑で時間もかかりすぎたため、残念ではあったのですが途中で諦めてしまったわけです。
しかし、海外の学会の場などでも、欧米の研究者や実務家が、公然と日本のCPIの信頼性に対して懐疑的な発言をするような現在の状況を鑑みた際、他データを使ってCPIの信頼性を検証することは、研究者にとってのみならず政策当局にとっても有益だと思っていましたので、なんとか総務省からの協力を得られないかとアプローチを続けていました。
もちろん、学術的な研究を進めるわけですから、最終的な結果が総務省の立場からみたプラスになるのか、マイナスになるのかは、研究開始の時点ではわかりません。また、当然ですが総務省の協力を得るために分析にバイアスをかけるような事もできません。しかし、今回、「まずは実態を調べることが必要だ」という共通認識の上にたって、総務省の担当部署の協力を得ることができました。
本論文の共著者である今井氏は、総務省の統計局で消費者物価関連のシステムを担当しています。今回のように研究者と実際の統計作成者が、お互いの情報を全て開示して共同作業するような例は希なのです。そうした意味で、今回のコラボレーションが非常にうまくいったことは、今後同様の分析を行う上で貴重な成果であるといえます。
――データはどのようなものを使いましたか。
CPIの再現を目指すのですから、消費者の買い物情報を大量に集める必要があります。今回の研究で使用した店舗の販売データは、日本経済新聞デジタルメディア社と東京大学が共同でまとめたものです。このデータセットは全国約200カ所のスーパーマーケットで売られた20万種類以上の商品について、2000年から2010年にわたって集計してあります。これらの商品は主に食品や飲料、それ以外の非耐久消費財(シャンプーなどの雑貨)などで、商品の販売情報はPOSシステムと呼ばれる方法を通じて集計されます。
2009年を例にとると、スーパーマーケットの数は260カ所で、その年に売られた商品数は23万個になります。2009年における総データ数は4億2200万にのぼり、調査対象期間全体では36億にまで達します。ただ、店舗も商品も出入りがあります(図表1)。調査対象期間中にずっと存在していた店舗数は103店です。この103店で売られていた商品総数は2000年には20万3000個だったのが、2009年には25万6000個に増えました。
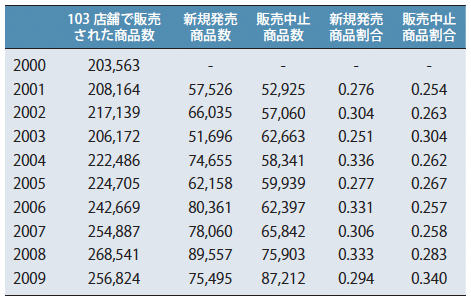
図表1では、毎年約3割の品目が入れ替わっていることがわかります。つまり、2009年でいえば、前年にはなかった7万5495の商品が新たに追加となる一方、前年にはあった8万7212の商品が姿を消しているということです。約3割というのは他国に比べても高い水準で、それだけ売れ筋商品が毎年、入れ替わっていることを意味します。
市場で販売される商品には、老舗和菓子屋の羊羹のように長期間にわたって消費されるものもあれば、カップ麺のようにどんどんと新しい商品が登場するものもあるわけで、そうした商品ごとの新陳代謝を上手に把握しながら価格調査を行わないと、最終的な物価の値が異なってしまうことになりかねません。そうした新陳代謝の影響の程度についても調べてみたいと考えました。
消費者物価指数を独自に作成、CPIの信頼性を検証
――分析の内容について教えて下さい。
集まった膨大なデータを使って、総務省のCPIの作成方法に則って、その再現を試みました。また、その作業と平行して、総務省の方法に基づきながら、少しだけやり方を変えてみて、結果が変わるのかどうかについてシミュレーションをするというやり方で、全部で64通りの方法で分析を行いました。
最後に、統計の信頼性については海外の批判、とりわけ米国からの批判が多いことから、米国で消費者物価指数の作成を担当している労働統計局(BLS)の手法を使って、入手したデータから物価指標を作成したらどうなるかという作業も行いました。共同執筆者である総務省の今井氏は、総務省の担当者としてCPI作成の実務を熟知しているのはもちろんですが、米国BLSの方式についても豊富な知識を持っています。このことが、今回の研究を進める上で非常に大きな助けとなりました。
――結果はいかがでしたか。
まず、総務省の方法に基づいて物価指標を再現するという第1の作業ですが、異なるデータソースを使って作成を試みた消費者物価は、総務省が公表しているCPIと非常に近い指数となりました。このことから、今回の研究で使用したデータおよび手順は、CPIの再現性の点では問題はないといえます。
次に、現行の総務省の方式を少しずつ変えるという第2の作業についてです。たとえば、スーパーなどの小売店では、よく特売を行いますが、総務省のCPIでは「特売の価格」は8日以上続かないと価格データとして採用されないことになっています。この点について問題視する声があるため、3日以上続けばデータとして対象に加えるというような事を行いました。これらの結果も、第1の作業結果と比べてそれほど大きな変化はありませんでした。
最後に米国BLS方式をとった場合についてですが、これも細かい点では総務省方式と異なりますが、似たようなトレンドを追っています(図表2)。
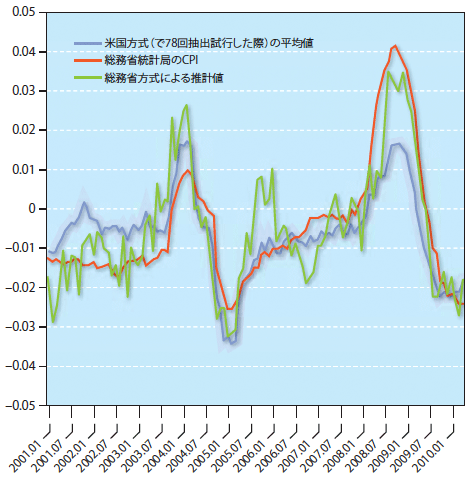
このように異なる測定方法によって再計測しても、日本のデフレ率はせいぜい年率で2%~2.5%程度であって、米国の大恐慌期の7~8%に匹敵するような大幅な物価下落が起きているわけではありませんでした。つまり、総務省方式によるCPIの作成方法に、深刻な統計的エラーは無いといえるでしょう。
デフレ脱却に向けた判断・行動には慎重な姿勢が欠かせない
――総務省方式と米国方式の違いはどこにありますか。
米国方式で測った物価指数を、総務省方式と比べると(図表2)、基本的には似たトレンドを追っていますが、直近では総務省方式(赤線および緑線)に比べて米国方式(青線)の方が、物価の値は低めに出ています。この差に着目して作成したのが図表3です。
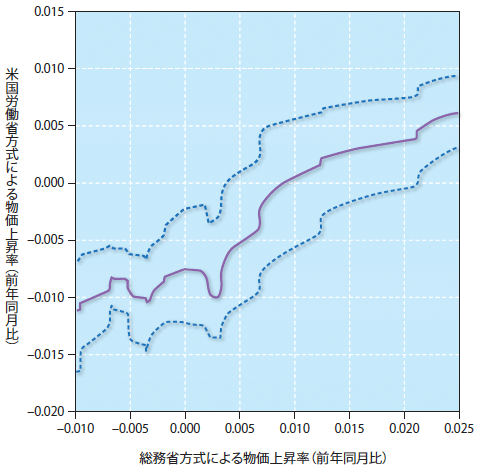
米国方式と総務省方式の1番の違いは、ごく簡単にいうと、サンプルの取り方にあります。米国方式では、価格データの対象となる商品について、調査の回ごとにランダムに抽出するという方法をとっているため、対象となる商品が毎回異なります。この方法は、売れ筋商品を調査対象から完全に外してしまうというリスクを下げるという長所がある半面、抽出は確率的に行われるため、結果にある程度の幅がでてくることになります。
日本銀行が金融政策運営のゴールとしていた消費者物価上昇率1%が注目ポイントなので、その水準に絞ってみましょう。総務省方式で1%の物価上昇になったとして、米国方式で作成した物価上昇率は、どうなっているでしょうか。グラフをみると、米国方式の物価の平均は0.1%とほぼゼロに近いのですが、幅は-0.5%から+0.5%となっています。つまり、総務省方式で物価上昇率が1%のときに、米国方式では80%の信頼区間で-0.5%から+0.5%の範囲にばらつくということを示しているのです。
つまり、総務省方式で1%の物価上昇であっても、米国方式では物価変動がプラスになる確率とマイナスになる確率は五分五分なのです
デフレ脱却に向けた判断・行動には慎重な姿勢が欠かせない
――この結果から導かれる政策的なインプリケーションは何でしょうか。
デフレ脱却に必要な物価上昇率を考える際には、こうした統計の方式による差異について注意が必要だということを強調したいと思います。図表3が示すように、総務省方式で測った物価上昇率がプラス1%だとしても、米国式で測った場合は、まだマイナスのままという可能性がかなりの確率であるのです。
物価変動がプラスであることに確信を持てるようにするためには、総務省の方式で測った場合に物価上昇率がプラス2%であることが必要だと思います。その水準であれば、米国式で測ってもプラスになるからです。
デフレ脱却に向けた判断と行動には、慎重のうえにも慎重を期すことが必要です。総務省方式で測った物価変動がプラス2%となるのを待って、さまざまなデフレ関係の対応策を解除するのがよいと考えられます。
――この論文を書かれた時点では日銀の政策ゴールは物価上昇率1%でしたが、新政権の発足後に2%になりましたね。
この分析結果が示すように、現行の総務省方式で測った物価上昇率が1%では低すぎますので、目標を2%に引き上げるべきだと考えていました。そうした提言の意味合いもこめて論文を仕上げたわけですが、新政権によって、私が望ましいと考えている目標が政府と日銀によって設定されることになりました。その意味では、非常によかったと思います。
物価データの公表頻度も月次から日次へ
――今後の研究についてお聞かせください。
今回の研究の対象でもあるCPIは、「経済の体温計」とも呼ばれるように、経済政策を的確に推進するうえで極めて重要な指標となっています。しかし、残念ながら公表されているCPIは月次ベースなのです。そこで、今回の研究で使用したPOSデータを使って、日次の物価指標ができないものかと考えました。300店舗から集められた全ての価格情報を、その日の夜中に私の研究室に送られてくるように設計することで、翌日には"昨日の物価指数"が得られます。価格情報には、特売のデータも含まれていますので、その意味では、米国式に近いといえます。4月には東京大学のサイトで公開するとともに、RIETIのサイトにもリンクを貼って行く予定ですので、物価について為替で見ているような日次の動きがわかるようになると思います。
こうした日次物価指数のようなデータは、米国のグーグルやマサチューセッツ工科大学(MIT)も開発しているのですが、これらはインターネット上で集めた価格情報をもとに物価指数を算出しています。私たちの試みは、300におよぶ実際の店舗から収集したデータに基づいている点に大きな特徴があると考えています。
私は、「価格」というものに強い関心があって、これまでにも色々な切り口で研究を続けてきています。たとえば2008年には代表的な価格比較サイトの「価格.com」を用いて価格の決定プロセスに関する研究を行いましたし( http://www.rieti.go.jp/jp/publications/rd/036.html )、2009年には家賃のデータをつかって価格の硬直性について分析しました( http://www.rieti.go.jp/jp/publications/rd/054.html )。今後は、上述のデータや指標も活用し、新たな研究課題に取り組みたいと思っています。
解説者紹介
1982年日本銀行入行。1999年一橋大学経済研究所助教授。一橋大学経済研究所教授、一橋大学物価研究センター教授を経て、2011年4月より東京大学大学院経済学研究科教授。主な著書・論文は以下のとおり。
『新しい物価理論:物価水準の財政理論と金融政策の役割』((岩村充との共著)岩波書店・2004年2月)、「ゼロ金利下の長期デフレ」(日本銀行ワーキングペーパーシリーズNo.12-J-3・2012年3月16日)、「価格の実質硬直性:計測手法と応用例」((水野貴之、齊藤有紀子との共著)『経済研究』第61巻第1号・2010年1月・68-81頁)、「企業出荷価格の粘着性-アンケートとPOSデータに基づく分析-」((阿部修人、外木暁幸との共著)『経済研究』第59巻第4号・2008年10月・305-316頁)


