| 解説者 | 渡辺 努 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0054 |
| ダウンロード/関連リンク |
経済政策を的確に推進するうえで、極めて重要な指標である消費者物価指数(CPI)。「経済の体温計」とも呼ばれるCPIは、1980年代の資産バブルの時代において、なぜ安定していたのか――。この点に着目した渡辺FFら3氏は、CPI構成要素の2割以上を占める家賃の価格の硬直性について、不動産広告誌に掲載された家賃データというユニークなマイクロデータを活用して分析した。
日本における家賃価格の硬直性は、米国のみならずドイツに比べても非常に高い。もし、日本の家賃の硬直性がこれほど高くなく米国並みの水準であったならば、CPIインフレ率は資産価格の動きに連動し、バブル期にはもう1%高く、バブル崩壊後にはもう1%低かったであろうという推計結果も得られた。このことは、家賃が物価と資産価格との結節点の役割を果たすことができれば、CPIを指標として、より機動的な政策の実施が可能になることを示唆していると言える。
――どのような問題意識から、この論文を執筆されたのでしょうか。
ミクロ経済学は、需給によって価格が動くという前提です。一方、私の専門であるマクロ経済学では、ケインズ以降、価格は動かずに数量が動くというのが根本的な考え方で、教科書でも「とりあえず、価格は動かないものとして考えましょう」となっています。この「とりあえず」について、どのくらい動かないのか、なぜ動かないのか、という非常に重要な分析が、ケインズ以降の70年間行われてきませんでした。
しかし5年くらい前から、さまざまな商品の価格について、どのくらい硬直的なのか、またその理由がどこにあるのか、データを使った分析がはじまりました。今ではスーパーマーケットの商品など実に多様な商品が分析の対象となっています。
本研究では、普通の商品ではなく、家を賃貸する際の価格である家賃について考えてみました。なぜ家賃を研究テーマに取り上げたのか――。その理由は3点あります。第1に、家賃は東京都区部の消費者物価指数(CPI)の約25%を占める重要な要素ですし、全国どこであってもCPIの2割を超える重要な経済指標です。ですから、価格の硬直性などを調べようとするなら、家賃は非常に重要な研究対象といえます。それほど重要な研究対象であるにもかかわらず、家賃の硬直性などに取り組んだ先行研究はほとんどありません。
理由の第2は、CPIなどマクロの価格の硬直性を議論しようとする場合、家賃は重要なポイントになるということです。家賃の場合、生鮮食料品などのような激しい価格の上下動は考えにくく、店子の入れ替わりや契約更新(地域差がありますが、東京では通常2年に1度)の際にのみ変化すると考えられます。日本より家賃の変化が大きい米国でもせいぜい1年に1度でしょう。だとすれば、CPIの重要な要素である家賃が高い硬直性を持っていることが、マクロの価格に硬直性を生んでいる可能性について定量的に評価したいと考えました。
第3に、バブル経済の前後に、家賃がどのように動いたのかを考えてみましょう。住宅資産価格が上昇(下降)すれば、それに伴って家賃も上昇(下降)すると予想されますが、実際はどうだったのか。もし、資産価格と家賃が連動しているのであれば、家賃が高い割合を占めるCPIも、連動して上昇(下降)するはずです。
このように連動することが良いのかどうかはさておき、連動性があるとするなら、日銀が金融政策をとる際に、利点が出てきます。というのも、日銀の役割は物価の安定なので、株や住宅などの資産価格は金融政策の目安にしないことになっています。しかし、資産価格の動きが家賃を通じてCPIに連動すれば、CPIを見ている日銀は、あたかも資産価格も対象にしているような金融政策を実施できるからです。
しかし、日本の経験を振り返ってみると、実際には、CPIの家賃は住宅価格や地価とは全然連動していません。
日銀の金融政策は、引き締め、ないしは緩和に転じるのが遅れるなど機動性に欠けると指摘されますが、その背景には、CPIと資産価格が連動していないということが大きく作用しているのです。そこで、どうして家賃は資産価格との結節点の役割を果たしていないのか、考えてみたいと思いました。
2種類の物件情報データを併用しながら分析
――分析にはどのようなマイクロデータを使われたのでしょうか。どのような特徴がありますか。
2種類のデータを使いました。まず、リクルートが週刊で発行していた賃貸住宅の情報誌のデータです。現在はネット版に移行し名称もかわったようですが、かつての紙面に掲載されていたデータがリールの状態で保管されていたので、それをお借りすることができました(1986-2006年の東京23区の約71万8000件)。
図1に示されたように、家賃の実勢価格(リクルートのデータから算出したもの)の指数が大きく変動しているのに対して、CPIベースの家賃指数はそれほど大きな上下動をしているわけではありません。つまり、CPIベースの家賃指数は硬直性を示しています。なぜ、このような乖離が起きたのかを解明することが、この論文を書いた重要な動機です。
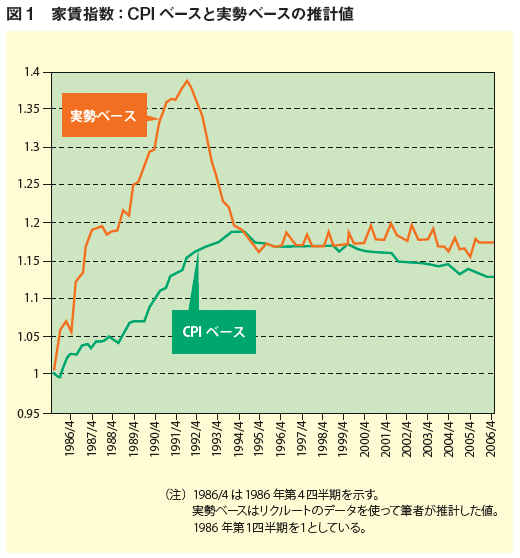
――もう1つのデータはどのようなものを使われたのでしょうか。
リクルートのデータは、部屋が空いたときに新しい店子を探すために物件情報が掲示されるという性格上、新規契約者のデータに限られます。私たちは、継続して居住している場合にも、家賃の硬直性があるかどうかを調べたかったので、別のデータも入手しました。それが、賃貸物件の管理をしている大和リビングのデータです。同社は、物件ごとに居住者の契約書を保管しているので、居住者が変わって別の契約が結ばれる場合と、契約を更新して同じ居住者が住み続ける場合の双方のケースについて価格の動きを観察できます。期間は2008年3月の1ヶ月間に限られますが、たとえ1ヶ月間のデータでも、3月は就職や転勤、進学などにより、1年の中で人が最も動く時期であることを考えると、利用価値が高いと考えられます。全部で約1万5000件のデータが集まりました。
リクルートのデータには、雑誌の性格上、都心部の超高級マンションや企業の社宅用物件などは含まれていません。それでも月額家賃は平均が12万2222円で、標準偏差が8万2794円と比較的大きなばらつきがあります。一方、大和リビングの方は月額家賃の平均が8万7942円で標準偏差が4万3217円と、より均質な印象を受けます。このように性質のちがう2つのデータを組み合わせることにより、分析の精度が上がることが期待できます。
――マイクロデータの入手は大変ではないですか。
価格データを使って研究するには、原データの所有者の許可を得て、使えるデータにしていく作業が欠かせません。昨年RIETIで発表したDP「オンライン市場における価格変動の統計的分析」の際には、価格比較サイト「価格.com」社にお願いし、分析に使うデータを1年間集めていただきました。確かに、こうした手法は困難も多く、手間もかかりますが、企業の多くは持っているデータの性質を完全に分析しきれているわけではないので、私たちのような研究者がデータを緻密に分析した結果、何が見えてくるのかということに関心を持っていただけるようです。分析結果から得られる知見のなかには、ビジネスの現場に役立つものもあるようで、最近は、企業側からデータ提供のお申し出をいただくケースもでてきました。
非常に高い、日本の家賃の硬直性
――家賃改定の分析から、どのような傾向や特徴が見出されるのでしょうか?
ここでは大和リビングのデータを使い、家賃にどの位の硬直性があるのかを、1年間で賃貸住宅全体の何%で家賃が変化しなかったか、という指標を使って測りました(表1)。表に示したのは2008年3月という1ヶ月間の計数ですが、1ヶ月間で家賃が変わらなかった住戸の比率は月次で99%、年率でみると90%になります。この90%という数字を他国と比べると、米国で2003年に政府の公式統計を使った分析結果では29%、ドイツでは78%ですから、日本が最も硬直性が高く、ついでドイツ、そして米国が最も伸縮的ということになります。
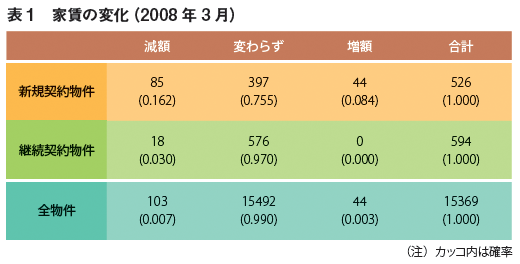
――価格の硬直性はどんな要因によって決まるのでしょうか?
価格の硬直性を考える際、状態依存と時間依存の2つの要因が挙げられます。この論文では、物件の市場価格と現在の価格の乖離を計測することにより、乖離が大きくなると市場価格への接近が起きるかどうかを調べました。起きるとすれば状態依存、そうでなければ時間依存です。
家主は貸している物件の価格が市場の実勢より低ければ何とか変えたいと考えます。特にバブルの時期は市場実勢が上昇するので、そうした気持ちが強まります。しかし、空き部屋が生じる原因となる引越しそのものは、こうした市場価格からの乖離に依存せず、他の要因によって生じます。これらの点を全て勘案して家賃が変わる可能性という確率を弾き出すと、乖離が-0.4から+0.2までは0.007~0.008でほぼ一定、ギャップが+0.2から+0.4までの間は0.011にちょっと上がりますが、全体としてみれば、乖離の変動に伴って大きく変化するわけではありません。つまり、時間依存型ということになります。
これまでの理論研究で、金融政策については、時間依存型の要因の方が効果があるということが明らかになっています。今回の結果はその意味でも重要な含意をもつといえます。
――家賃の硬直性が変わればCPI も変わるのでしょうか?
分析の結果、日本の家賃の硬直性が高いことが明らかになりました。確かに、家賃価格はどこの国でも多少の硬直性があるはずですが、もし、日本の家賃が他国並みの動きを見せたなら、CPIはちがう動きを見せていたのではないか、と考えました。そこで、家賃の変化が米国ないしはドイツ並と仮定して、CPIインフレ率を推計してみたものが図2です。実際のCPIインフレ率と比べると、1998年より前の時点で明らかに大きな変化が見出せます。バブル期に物価が上昇した時期(1987-91年)には、推計CPIのインフレ率2ないしは3の場合、実際のCPIのインフレ率を1987年時点で1ポイント上回って2%台、ないしは3%に近い水準にあります。一方、バブルの崩壊後は、推計CPIインフレ率2ないしは3は、実際のCPIのインフレ率がマイナスに転じるよりも1年早くマイナスとなっていることがわかります。
もし、1993年時点で推計CPIインフレ率のようにマイナスに転じていたのなら、日銀の財政・金融政策によるデフレ策は、より早い時期に講じられていた可能性が高いと考えられます。
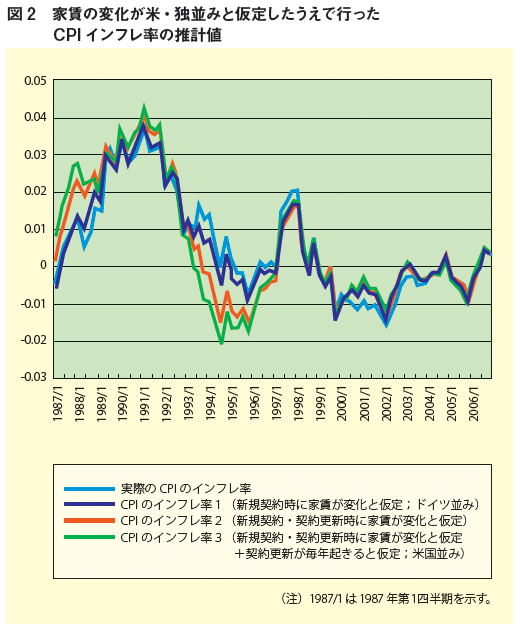
――この結果からどんな政策的なインプリケーションが導き出されるでしょうか?
家賃の硬直性が、借地借家法などの規制によるものだとすれば、より良いCPI策定の観点からは規制緩和が望ましいといえます。
他方、より現実的なインプリケーションとしては、統計の提供の仕方が工夫できるのではないかと思います。CPIの家賃のなかには、実際の賃貸家賃の部分と、持ち家を家賃を払っていると擬制して算出している帰属家賃の部分があります。帰属家賃の部分について、「その家を市場で貸した場合の家賃」という視点からCPIインフレ率を弾き出してみると、バブル期では実際のCPIインフレ率より1ポイント高く、崩壊期には2ポイント低くなりました。これは図2で見られる傾向と似ています。
このように推計値で示される傾向が実際の統計と異なるのであれば、現実的な対応策として、以下のようなことができないだろうかと考えています。それは、CPIを2系列つくり、1系列は継続性の問題を考慮して従来どおりの帰属家賃をベースにしたCPIとし、もう1系列は金融政策専用のCPIとすることです。そうすれば、データの継続性に配慮しつつ、金融政策の観点からも利便性の高いデータを得ることができるはずです。
住宅価格の国際的な研究が課題
――今後の研究の課題は何でしょうか?
サブプライムローンのような問題が今後繰り返されないようにするためにも、住宅価格の動きをきちんと把握する必要があります。しかし、それは意外に難しく、米国ケース・シラーの住宅価格指数ですら、あまり実勢を反映していないといわれています。日本では不動産価格といえば公示地価だけですし、中国を始めとする途上国となると、統計そのものの入手がさらに難しくなります。
国際的に、住宅価格がきちんとわかるような指標を作ろうという考え方が広がっており、そのための統一的なマニュアル作りがBIS(国際決済銀行)や国連などを中心に進められています。こうした統一マニュアルや指標が存在すれば、政策当局者にとってはもちろん、民間銀行にとっても担保価値を適正に判断できるようになるわけですから大変有用です。
こうした流れの一環として、各国の研究者や国際機関の人たちと意見交換を行いながら、日本の住宅価格を精密に測る手法の開発など、住宅価格に焦点をあてた研究にも取り組んでいます。そうした意味からも、今回の研究結果はもとより、利用したデータも貴重なものだといえます。
解説者紹介
東京大学経済学部卒、ハーバード大学Ph.D(経済学)。日本銀行勤務を経て、2002年より一橋大学教授、RIETIファカルティフェロー。主な著作:『検証中小企業金融』(編著、日本経済新聞社2008年)、「物価の反応の鈍さ 注視を」(日本経済新聞2009年12月9日)、「日本のデフレは緩やかだがしぶとい」(『エコノミスト』2010年2月2日)、「金融危機とゼロ金利の壁」(『金融財政』2009年2月19日)、"The Firm as a Bundle of Barcodes," (with Koji Sakai) European Physical Journal B, February 2010, "Real Rigidities: Evidence from an Online Marketplace," (with T. Mizuno and M. Nirei) Research Center for Price Dynamics Working Paper Series No. 44, August 2009など、多数。


