| 解説者 | 森川 正之 (上席研究員) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0025 |
| ダウンロード/関連リンク |
少子高齢化の急速な進展に伴い、今後労働力不足が避けがたい日本において、生産性の向上は喫緊の課題である。
中でもサービス産業の生産性向上がかねてから叫ばれているが、これまでサービス産業の生産性についての実態解明はあまり進んでいなかった。
森川RIETI上席研究員は、マイクロデータを活用した分析により、サービス産業の生産性が必ずしも低いとは断言できないこと、しかし製造業に比べて底上げの余地が大きいことなどを明らかにした。
森川氏は、サービス産業の生産性の高低には、企業の経営力が大きく関わっていると指摘し、その経営力の実態解明を進めることで、生産性向上に寄与したいという。
――サービス産業の生産性をテーマに相次ぎ3本の論文をまとめられていますが、そのきっかけ、目的は何ですか。
日本のサービス産業の生産性は製造業に比べてかねてから低いと言われていました。確かに集計データ、例えばSNA統計などでみると、サービス産業の生産性上昇率は低いです。しかし、サービス産業には多様な業種が存在するうえ統計が未整備で、実態がよくわかっていないのです。日本のサービス産業の生産性向上の処方箋を書くには、まずは産業の実態を解明することが不可欠ですから、産業レベルに集計された平均値のデータを観察するだけではなく、企業・事業所レベルのマイクロデータを用いた分析に取り組んだわけです。
今回の三本の論文では、『サービス産業の生産性は低いのか?』で企業間の生産格差、新陳代謝を通じた産業全体の生産性向上等をサービス産業と製造業の比較により検証し、『生産性が高いのはどのような企業か?』では、企業特性と生産性(TFP)の関連を定量的に分析しました。そして、『サービス業の生産性と密度の経済性』では、サービス業の中でも特に対個人サービス業を対象に、生産関数の推計や生産性格差の要因分解を行いました。
――一連の研究の最初の論文『サービス産業の生産性は低いのか?』では、どのような発見がありましたか。
この論文では経済産業省「企業活動基本調査」の2001年から2004年までの個票データを用いて分析しています。1992年に開始されたこの調査は、近年、サービス産業のカバレッジがかなり拡大し、パネル分析が可能なサンプル数になってきました。
ただし、注意していただきたいのは、本調査のサービス業のカバレッジは限定的であることです。具体的には、情報サービス業、一般飲食店などは対象ですが、通信業、運輸業、金融・保険業、宿泊業、医療・福祉サービス業など専業の企業は対象外です。よって、本論文の分析対象は、狭義のサービス業の一部と卸売業・小売業です。また、従業員50人以上の企業が調査対象なので、零細企業はサンプルに含まれていません。
分析の結果、図1で示したようにサービス業に属する企業の生産性の水準、伸び率ともに、製造業の企業に比べて低いとは言えないことがわかりました。具体的には、サービス業に属する半数以上の企業の労働生産性やTFPの水準、伸び率が、製造業企業の生産性中央値を上回っているのです。製造業とサービス業の比較をする際、トヨタ、キャノン、任天堂といった優良企業とごく普通のサービス企業とを比較してはいけません。
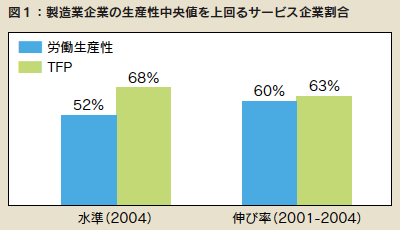
――一方で、集計データでみるとサービス業の生産性上昇率は低いですね。マイクロデータと集計データのずれはなぜ起きるのでしょうか。
これは、サービス企業のうち規模の大きな企業の生産性上昇率があまり高くないのに対して、製造業は大企業の生産性上昇率が高いためです。実際、企業活動基本調査の個別企業のTFP上昇率データを企業規模でウエイト付けして集計すると、サービス業全体のTFPの伸びは製造業の集計値よりも低くなります。もう1つ、サービス業では企業間での生産性のばらつきが製造業に比べて大きいことに注目する必要があります。
私はこのばらつきの大きさに、サービス業の生産性向上のひとつのカギがあると考えています。例えば、生産性の高い企業の手法から、他の企業が学ぶことによって、全体の生産性が底上げされる可能性があります。一方、生産性を上げる努力をしない企業が市場から退出することによって、サービス業全体の生産性が上がることも考えられます。
図2は、非常に粗い計算ではありますが、そうした底上げや退出の効果が、各産業の生産性向上にどれだけ寄与しうるかを示したものです。具体的には、「底上げケース」は産業ごとの中央値未満のTFPの企業を中央値まで引き上げたときの効果、「退出ケース」は中央値未満の企業が退出し、その分のシェアを中央値以上の企業が獲得したときの効果を示しています。製造業に比べて、サービス産業の代表格である卸売業、小売業、狭義サービス業での効果の大きさが目立ちます。
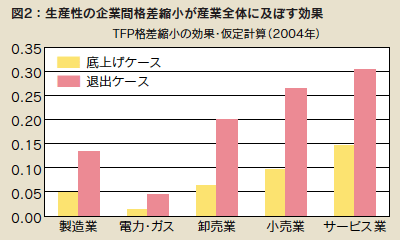
――そこで、2本目の論文「生産性が高いのはどのような企業か?」で、生産性の高い企業の特性を分析しているわけですね。カギを握るのは何でしょうか。
1本目の論文と同様、この論文でも経済産業省「企業活動基本調査」のパネルデータを使っています。各企業のTFPや付加価値の水準および伸び率を様々な変数で説明するという実証分析を行っています。
具体的には、研究開発集約度、情報ネットワークの利用状況、パートタイム労働者比率、日雇・派遣労働者比率、平均賃金、外注費比率、外資比率、本業集中度、企業規模、企業年齢です。
この中で、企業年齢が若い企業ほどTFPの水準が高いことが確認でき、この傾向は特に小売業やサービス業で強いことが分かりました。新陳代謝が各企業の生産性を上げ、ひいては産業全体の生産性上昇につながることは間違いないようです。
一方、情報ネットワークの利用状況、言い換えればITの利活用が必ず生産性を上げるというわけではないことが明らかになりました。また、研究開発投資も生産性向上のカギと言われていますが、サービス業では製造業のような生産性加速効果が確認できませんでした。
それ以外に何がカギを握るのかというと、この論文では、組織の活力・柔軟性、経営者・労働者の能力といった、分析で用いた「企業活動基本調査」から利用可能な限られた企業特性データ以外の特性が企業の生産性に影響をもつ可能性があることを指摘しました。分析上は「企業固有効果」といいますが、「経営力」と言い換えても良いかもしれません。
――経営力がカギを握るというのは納得がいく一方で、それでは生産性向上に向けた対応策が講じにくいということにならないでしょうか。
確かにとらえにくい面はあると思います。ただ、例えば、非常に生産性の高いサービス企業の事例を世の中に知らせていくことで、経営者の意識改革を促し、自らの企業の経営改善に結び付けていただくという実践的な対応ができると思います。
私はRIETI上席研究員と兼務で、サービス産業生産性向上協議会(SPRING)の現場でサービス産業の生産性向上運動に携わっており、SPRINGでは、実際に「ハイ・サービス日本300選」という優れたサービス活動を行う企業を全国から選び、表彰するという活動を行っています。これまでに、(株)公文教育委員会、(株)良品計画などが受賞しました。また、サービス提供プロセス改善の実証事業を通じて、製造業のノウハウをサービス産業に適用するヒントを示していく活動も行っています。
経営力がカギを握るという今回の実証分析から、SPRINGが行っている様々な取り組みが間違っていないことを確信しています。
――ところで、サービス産業の生産性は、製造業の生産性と少し性格が違うのではないかという気もいたします。例えば、同じコンビニエンスストアであっても、大都市のコンビニは来店客が多いので、創意工夫が売り上げに結びつきやすいのに対し、地方都市では必ずしもそうならないですよね。こうした、企業の経営力ではどうにもならない部分についてはどうお考えですか。
まさにその点について分析したのが、3本目の論文「サービス業の生産性と密度の経済性」です。
サービス産業の中でも、特に「対個人サービス業」は、サービスの生産と消費が同時に行われるという特性があります。言い換えれば、対個人サービス業が提供するサービスは在庫が効かないものが多く、この点で製品在庫を持ち、それを国内や海外に配送して販売することが可能な製造業と大きく異なっています。このことは、事業主体の立地条件が売り上げなどに影響を与える可能性を示唆しますので、この論文で分析をしました。
また、この論文では、1番目、2番目の論文とは異なり、経済産業省「特定サービス産業実態調査」の個票データを使っています。「企業活動基本調査」と違って「特定サービス産業実態調査」はより小規模な事業所も全て調査対象に入っています。
さらに、「特定サービス産業実態調査」は事業所統計ですので、企業を対象にした「企業活動基本調査」とは調査対象が異なります。つまり全国展開している企業を例にとると、「企業活動基本調査」では本社が東京であれば、売り上げなどは東京で稼いだものとして認識されてしまいますが、「特定サービス産業実態調査」では、都道府県ごと、市町村ごとの売り上げがわかります。こうしたことから、事業所統計は地域分析に向いている統計といえます。
分析の結果、ほぼすべてのサービス業で「事業所規模の経済性」、「企業規模の経済性」、「範囲の経済性」が存在することがわかりました。
図3を見てください。これは産業ごとに、事業所が存在している地域の人口密度が2倍だと、生産性がどれだけ高くなるかを示したものです。サービス業では16%も高まるのに対し、製造業は3%弱です。サービス業にとって展開する地域の人口密度がいかに重要かがわかります。
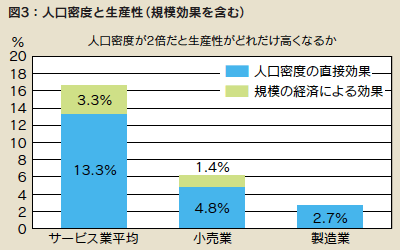
――この論文の中で、「サービス業の生産性向上という観点だけから考えるならば、大都市に人口を集積させていくことが効率的」と書かれていますが、これは政策的に対応が可能なのでしょうか。
私は国土政策の専門家ではないので、明確な答えを持ち合わせていませんが、人口が減少局面に入っている現在、少なくとも生産性という観点からは「国土の均衡ある発展」という分散志向が強い政策は好ましくないということが言えるかと思います。一方で生産性向上が叫ばれ、一方で国土政策では分散化志向が強いという傾向は、今後サービス産業のウエイトが高くなっている日本では、矛盾した政策といえます。
ただし、この分析は東京一極集中が望ましいというインプリケーションを持つわけではありません。事業所間での生産性格差を要因分解すると、都道府県間格差要因は小さく、同じ都道府県の中での市区町村間格差が大きいからです。最近は「コンパクトシティ」という集積の試みも、地方自治体で始まっています。こうした取り組みが生産性向上に寄与していくことに期待しています。
――最後に、サービス産業の生産性に関する研究における今後の方向性および課題をお話ください。
論文としても最近発表したのですが、経営力の中身に立ち入った分析をすでに行っています。1つはコーポレート・ガバナンスとの関連での分析で、株式保有の構造がサービス企業の生産性に影響があることがわかってきました。具体的には上場していない同族企業の生産性の伸びが、企業規模・業種などの違いを調整しても低いという関係です。
もう1つは労働組合の有無です。意外に思われるかもしれませんが、労働組合のある企業ほど生産性が高いという結果が得られています。これは、経営側と労働者側で良好な労使関係があることが、生産性向上に結びついていると解釈できそうです。高度成長期には主に製造業でQCサークル活動、海外視察団の派遣などの「生産性運動」が労使協力の下に展開されました。今回の分析結果は、製造業以外でも労使関係が重要なことを示唆しています。
今後は、ハイ・サービス日本300選の企業数が蓄積されるのを待って、そうした企業と他のサービス企業の経営力の差がどこにあるのかについて分析すると有益だと思っています。
課題については、3本の論文の分析を通じて、サービス産業の実態を捉える基礎統計が不十分だと改めて感じました。実態解明なしに効果的な政策は打てません。米国は統計整備に日本の約10倍の予算を投じています。統計の作成のために、予算・人材などのリソースをきちんと配分する必要があるのではないでしょうか。
例えば、生産性を測るうえで重要なのは、物価変動を調整した実質ベースの伸び率なのですが、この物価変動の計測には多くの課題があります。サービス産業はIT投入が多いのですが、IT財はヘドニック法を使っていることから価格下落が大きく、この結果、実質のインプットが大きく増加します。一方で、サービス産業の産出価格は価格変動が小さく、この結果、実質生産性の伸び率が低めに出る可能性があるのです。これは「サービスの質」の調整の問題で、多くの専門家は認識していますが、実際の統計でそれを正確に補正するのは非常に難しいことです。
前述したように、サービス業の生産性のカギを握るのは経営力ですが、この実態を解明する上で期待しているのが、学習院大学の宮川努教授を中心としたグループによる「無形資産」のプロジェクトです。このプロジェクトは、海外の研究者との連携も行っていますので、国際比較も可能になります。日本のサービス業は製造業との比較だけでなく、諸外国との比較でも生産性が低いと言われていますが、こうした新しいデータが生まれることで、本当にそうなのかどうか実態の解明が進むと思います。
解説者紹介
東京大学教養学部卒業。京都大学経済学博士。1982年通商産業省入省、経済産業省大臣官房政策企画室長、産業政策局調査課長、同局産業構造課長等を経て、2007年より現職。その間に、埼玉大学政策科学研究科助教授、政策研究大学院大学助教授も務める。主な論文は、" Information Technology and the Performance of Japanese SMEs,"Small Business Economics (2004)等。


