はじめに
本稿の目的は、都市銀行において効率性仮説が成立しているかどうかを検証することである。効率性仮説とは、Demsetz(1973)が提唱したもので、市場競争の原理が働く限り、効率的な企業が競争に勝って成長してゆき、その結果、効率的な企業が大規模になり、市場集中度が高くなる、という仮説である。また、こうした企業は、高い市場シェアと同時に高い収益率を達成すると考えるので、この仮説の下では、市場集中度が高い市場ほど効率的であると予想される。
本論文では、市場構造=行動=成果(SCP)仮説とは独立に、より基本的な命題に注目した直接的な検証方法を用いることによって、効率性仮説が成立するかどうかを検証する。その基本的な命題とは、「効率的な企業が競争に勝ち、成長してゆく」という、効率性仮説の核となる命題である。本論文では、費用関数を推定することによって非効率性の指標を計測したうえで、その指標が企業の成長度に与える影響を調べることによってこの関係を検定する。
モデル
本稿の分析は2段階から成る。第1段階は、銀行の効率性の推定であり、第2段階は、効率性がその後の銀行の成長とどう相関しているかである。
(1)効率性の推定
効率性の推定法には、いくつかの方法があるが、ここでは、パラメトリックの方法である、いわゆるstochastic frontier関数の推定を用いる。
費用関数は銀行の生産物として、貸出Lを採用する。要素価格としては賃金率wだけを考慮し、資本設備の価格は含めない。これは、資本設備市場が完全で都市銀行が同一の資本設備価格に直面していると仮定することと同じである。トランスログ関数を仮定するので、推定式は次のようになる。
lnCi,t=a0+a1lnLi,t+a2lnwi,t+a3(lnLi,t)2+a4(lnwi,t)2+a(lnLi,t)(lnwi,t)+ui,t+vi,t (1)
ここで、InLとInwはそれぞれの平均値からの乖離である。
本稿では、非効率性を表すuが(2)式によって表されるメカニズムによって決定されるものと考え、これを(1)式と連立で推定する。
exp(ui,t)=c+β1HIt+β3YOTAIi,t+β4RIZAYAi,t+β5LBRANCHi,t+ωi,t (2)
ここで、HIはハーフィンダール指数、YOTAIは預貸比率、RIZAYAは利ざや、LBRANCHは店舗数の対数値である。
(1)、(2)式の連立推計によって得られた非効率性uの推定値は、いわゆるX非効率性を計測するものである。しかし、uだけでは規模の経済性で表される効率性を捉えられない。そこで本稿ではuの推定値だけではなく、(3)式で定義される規模の弾力性SEも用いることによって、効率性が銀行の成長にどのように影響するかを調べる。このSEは規模の不経済性の大きさを表す。
SEi,t≡a1+2a3lnLi,t+a5lnwi,t (3)
(2)効率性仮説の検定
本稿では、需要と供給が一致するように貸出額が決定されるものと考える。貸出供給に関しては、通常の静学的な利潤最大化モデルで想定される寡占銀行の貸出供給関数を仮定する。このため、貸出供給は、貸出金利、代替資産金利(コールレートrcをとる)、市場の不完全性を表す変数(他銀行の推測変動や需要の弾力性、ここではHIをとる)、(営業費用関数が貸出と規模の積に依存する場合には)銀行の規模変数(ここでは預金)などに依存する。さらに、銀行が貸し倒れリスクを考慮するため、貸出供給が自己資本比率(CR)に正の影響を受けると仮定する。このような前提で、前期に効率的な銀行ほど今期の貸出額が大きいという仮説を検定する。ここでは、その効率性を組織的な非効率性uと規模の不経済性SEの2つに分けて、それぞれの影響を調べる。
一方、貸出需要については、貸出金利と需要者の規模変数(ここではGDPをとる)に依存すると仮定する。需要関数と供給関数を連立させて貸出金利を消去し、貸出の誘導形を求めると次式が導出される。
lnLi,t=γ0+γ1lnGDPt+γ2rct+γ3CRi,t+γ4HIt+γ5ut-1+γ6SEt-1+γ7Dt+εt (4)
われわれの注目する仮説は次のようにまとめられる。
<仮説1>組織的な効率性が高い銀行ほど次期の貸出額が大きい。(4)式において、γ5<0。
<仮説2>規模効率性が高い銀行ほど次期の貸出額が大きい。(4)式において、γ6<0。
その他の係数については、γ1>0,γ2<0,γ3>0,γ7>0が予想される。γ4については、独占的な市場(集中度が高い市場)ほど貸出供給が少ないと考えれば、γ4<0である。
推定結果
本稿は、1974年以降2001年度までの都市銀行と長期信用銀行を分析対象とする。
(1)式と(2)式を連立推定すると、(1)式の全ての係数は有意であり、交差項の係数a5は負、それ以外は正である。規模の弾性値を平均値で評価するとa1となり、この推定では0.536と大きな規模の経済性を示す。
この非効率性の推定値を使って(4)式を推定した結果が表1に示されている。注目する変数である組織的な非効率性は負ではあるが有意でない。一方、規模の不経済性を表す規模弾力性の係数は有意に正である。これは、規模の効率性が小さいほど翌年の貸出額が大きくなるという、効率性仮説と逆の結果である。
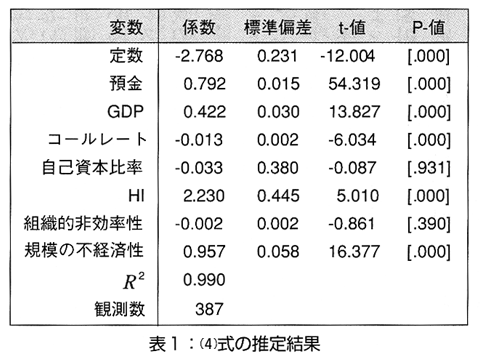
資産を用いた分析
前節では、貸出に焦点を当てて分析を行った。しかし、そこで用いたモデルは、銀行が予算制約を考慮して利潤を最大にするように貸出額を決定すると想定している。そこで預金額を外生として取り扱って分析していることは、預金額を所与として相対的に貸出額を増やすかどうかを検定していることを意味する。しかし、われわれが調べたい効率性仮説は、これとは少し違っているとも考えられる。すなわち、効率的な銀行はその絶対的な規模を大きくしていくかどうかである。ここでは、前節までの分析において規模を代表する変数として採用した貸出の代わりに銀行の資産を用いた分析を行い、結果を評価してみよう。
(1)式に代えて、
lnCi,t=a0+a1lnAi,t+a2lnwi,t+a3(lnAi,t)2+a4(lnwi,t)2+a(lnAi,t)(lnwi,t)+ui,t+vi,t (1)'
(2)式に代えて
exp(ui,t)=c+β1HIt+β3YOTAIi,t+β4RIZAYAi,t+β5LBRANCHi,t+ωi,t (2)'
を仮定する。ここで、lnAは資産の対数値の平均値からの乖離である。規模の経済性は、
SEi,t≡a1+2a3lnAi,t+a5lnwi,t (3)'
で計算される。
(4)式に代えて、次式を推定する。
lnASSETi,t=γ0+γ1InGDPt+γ2rct+γ3CRi,t+γ4HI,t+γ5ut-1+γ6SEt-1+εt (4)'
この非効率性の推定結果を用いて(4)'式を推定した結果が表2に示されている。GDPの係数は予想通り正である。コールレートは負、自己資本比率は正と貸出に与える影響として予想される符号を満たしているが、どちらも有意でない。ハーフィンダール指数(HI)は有意ではないが負であり、市場構造=行動=成果仮説の予想と一致している。
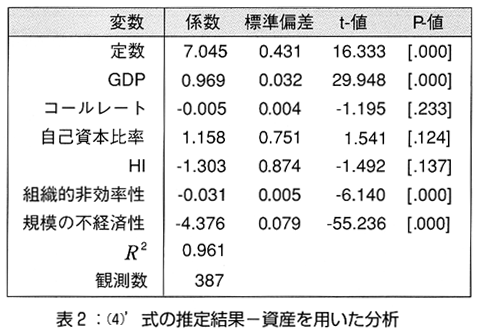
注目すべきは、組織的非効率性の係数も規模の弾力性の係数も高い有意度で負になっていることである。すなわち、効率性仮説の予想は、どちらの尺度についても支持される。
時期による変化
前節で得られた傾向は時期によって変化するのであろうか。1974年から2001年の期間を、1970年代、80年代、90年代の3期間に分けて推定してみると、組織的非効率性は3期間とも有意に負、規模の不経済性は3期間とも有意に正である。その大きさは期間を追う毎に大きくなっている。組織的非効率性が負であることは効率性仮説と整合的であるが、その値が70年代で最も小さいことは、競争圧力が小さいためであるかもしれない。その他の変数では、GDPが90年代では有意でなく係数も小さい点が特徴的である。90年代の貸出の減退(いわゆる貸し渋り)の影響が見て取れる。
資産に関する推定結果によると、組織的非効率性と規模の不経済性は3期間を通じて有意に負であり、効率性仮説が成立することを示している。しかし、組織的非効率性の値は、貸出の場合と同様、70年代、80年代では小さく、とりわけ70年代では有意度が若干小さくなっている。
結論
本稿は1974年以降2001年度までの都市銀行を対象として、効率性仮説が成立するかどうかを検証した。従来は、効率性仮説は市場構造=行動=成果仮説との対比で、利潤や金利といった市場成果が市場集中度と市場シェアのどちらによってよりよく説明されるか、という枠組みで検証することが多かった。われわれはその枠組みの問題点を指摘し、効率性仮説を「より効率的な銀行がより成長する」という命題に集約して、より直接的に検証した。
まず、パネルデータを用いて銀行の組織的非効率性と規模の不経済性を推定した。次に、その推定値が次年度の銀行規模にどのような影響を与えるかを吟味した。
貸出の誘導形に前期の組織的非効率性と規模の不経済性を追加した回帰分析では、組織的非効率性は負の影響を与えるが、規模の不経済性は想定とは逆に正の影響を与えることが見いだされた。これに対し、銀行の資産に対しては、組織的非効率性と規模の不経済性の両方とも負の影響を与えるという、効率性仮説と整合的な結果が得られた。
分析対象期間を、70年代、80年代、90年代の3期間に分けて同様の分析を行ったところ、大体において、3期間を通じて組織的非効率性と規模の不経済性の影響は変わらないことが見いだされた。しかし、結果を詳細に吟味すると、70年代の組織的非効率性の影響は他の年代より小さいことが分かった。このことは、Uchida and Tsutsui(2005)が示すように、70年代の都市銀行の競争度がまだ低かったことを反映しているのではないかと考えられる。



