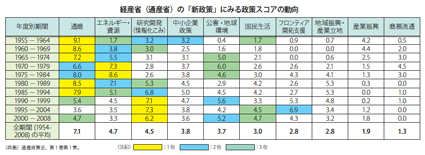イベント概要
概要
RIETIでは、過去7年にわたって『通商産業政策史(第2期) 』の編纂事業に取り組んできた。この内容は、総論の1巻と、通商産業省の機構に対応した各論11巻で構成される『通商産業政策史1980-2000 』として2011年より順次刊行されている。このたび、この全12巻の完成を記念し、シンポジウム「グローバル化と産業政策の転換」を開催した。編纂主幹であり、かつ第1巻総論の著者でもある尾髙煌之助名誉教授をはじめ、編者、著者として事業に参画された方々と、実際に政策に携わってこられた方々双方の参加を得て、この時期の通商産業政策の本質に迫り、今後の経済産業政策のあり方への示唆を得ることを目指した活発な議論が行われた。
報告書
開会挨拶
中島 厚志 (RIETI理事長)
『通商産業政策史(第2期)』は、1945~1979年の日本の通商産業政策史を扱った第1期編纂事業に続くものとして、1980~2000年を中心に通商産業政策の変遷をまとめたものである。客観的な事実録として後世に残すとともに、その分析・評価も試みている。本日は、編纂に携わった方々の講演やディスカッションを通じ、日本の通商産業政策に関する認識を深めるとともに、今後の研究や政策につながれば幸いである。
経済産業省挨拶
佐藤 ゆかり (経済産業大臣政務官・参議院議員)
2012年末に発足した安倍内閣は、経済の再生を「一丁目一番地」に掲げ、大胆な金融緩和、機動的な財政政策、民間設備投資を喚起する経済成長戦略という3本の矢を打ち出し、まさに実行に移そうとしている段階にある。本政策史が扱う80~90年代に我が国が抱えていた問題と、それに対する通商産業政策の歴史的評価は、今後の政策に重要な示唆を与えるものと考えている。
1980~90年代は、まさに日本経済の激動の時代であった。80年代は、高度経済成長時代の終焉とともに幕を開けた。日本経済は構造調整という新たな問題を抱え、1978年の特定不況産業安定臨時措置法の制定を受けて、合成繊維や造船業などの構造調整を進めていった。そして90年代に入ると、対外的な通商政策も管理貿易主義からGATTやWTOを中心としたルール主義へと様変わりし、日本の産業界は世界経済への参画を高めていく。一方、国内ではバブル経済とその崩壊により、過剰債務、過剰雇用、過剰設備投資という3つの過剰を抱えていた。これを受けて、2000年代には経済産業政策の力点が、構造調整からイノベーション、産業創出へと移っていくのである。
こうした歴史的変遷を振り返り、当時の通商産業政策による未踏の政策分野を検証することは、現在抱えている政策的課題の解決に1つの光明となり得る。今回編纂された『通商産業政策史』が、今後のさらなる政策研究に活かされていくことを心から祈念している。
通商産業政策史編纂の意義について「政策変容の事例を介して考える」
尾髙 煌之助 (法政大学名誉教授/一橋大学名誉教授)
1. グローバル時代における通産政策の変化
グローバル時代を迎え、日本の通産政策は、ビジョンを示すものから市場原理を尊重し、原則不介入に徹するというスタンスへと変化した。政策スタイルも、産業単位から企業単位、行政主導から法律中心、縦割りから官庁横断的政策、国際通商における自立性の尊重という姿勢へと変わってきている。その背景には、通産政策は経済環境の変化に応じて敏捷に動く必要があるという考え方があった。
2. 「政策の重点」、予算動向、職員数の動向に現れた政策思想の推移
通商産業省(当時・以下、「通産省」)では、毎年の概算要求を提出する際に、その正当性を立証する「政策の重点」という文書を作成している。ここから、1955~2008年度に重要政策とされたものを11種類に分類し、政策の重点がどのように推移してきたかを調査した。
全体の期間を通じては、通商政策に政策の重点が置かれる頻度が相対的に高かった。しかし、時系列で見ればその頻度は徐々に低下してきていることが分かった。1970年代には通商政策に代わってエネルギー政策が最重点項目となり、その後、日米貿易摩擦の時代に一時的に通商政策が復活しているが、1990年代には科学技術に重点が移った。一方、中小企業政策が一貫して中庸の位置を占めていることも明らかとなった。
政策の変容は、予算動向にも反映されている。一般会計と特別会計では、1970年代の終わりまでは一般会計の方が規模が大きかったが、1980年代以降、その関係が逆転した。これには当然、エネルギー問題が非常に大きく関係している。加えて、1980年代以降は特別会計も一般会計も予算が伸びなくなっている。
さらに財政投融資は会計予算と似たような動きをしているが、その規模は通産省の一般会計・特別会計に比べて非常に大きい。出資・融資対象は物の生産に関するものが大きいが、第3次産業にも時代を問わずかなりの配慮がなされている。今、産業政策として補助金や融資が重要だとよくいわれるが、その傾向は20世紀後半の財政投融資に既に見られていたといえる。
また、通産省およびその後の経済産業省(以下、「経産省」)の組織改編にも、その政策スタンスの変化が現れている。全体の職員数はほぼ横ばいだが、地方分局の職員数が減り、特許庁が人員を増やしている。さらに、省内にあった工業技術院が2001年に再編され、産業技術環境局、経済産業政策局地域経済産業グループ、産業技術総合研究所に分かれている。
3. 通産政策として不変のものとは
通産政策には、一貫して変わらないものもある。時代の要請を先取りする経済政策の立案・執行と、政策立案の中立的専門家集団としての役割である。55年体制がなくなった今、政官スクラム型の政策決定の時代は終わったと論じる人もいるが、優秀な専門家集団としての官僚が政策立案し、政治家がそれを点検し、官僚が実行に当たるという形は、少なくとも今後しばらくの間は必要だと考えている。
基調講演「転換期を迎えた通商産業政策の理念」
武田 晴人 (RIETIプログラムディレクター・ファカルティフェロー/東京大学大学院経済学研究科教授)
1. 経済大国としての通商産業政策への転換
1970年代までの通産政策は、1950年代を典型として、経済の近代化・合理化を産業面から推進するため、市場に対してさまざまな補正的政策介入を展開してきた。しかし、この方針は1960年代に始まる貿易・為替の自由化、資本自由化によって大きく変容することとなった。通産省は、70年代に通商産業政策ビジョンにおいて「知識集約型産業構造への転換」を提唱する。それは、日本経済が成熟した産業社会へと移行しつつあると同時に、対外関係においては自由主義陣営の経済大国として責任ある行動が求められるようになったことを背景とするものであった。
70年代、日本経済は変動相場制への移行と原油価格の暴騰への対応に追われることになったために、このような方向は後景に退いたように見えるが、総需要抑制政策、省エネ努力の浸透、石油価格の沈静化などにより、直面した問題が早期に克服されていくと、新エネルギー開発、情報処理技術の発展、宇宙開発など大規模な研究開発投資を要する分野を重点的な政策課題に定めながら、再び産業構造の転換が推進されることになった。
ただし、1980年代後半になると、原油価格の下落とともに日本の貿易黒字が顕在化し、深刻な貿易摩擦が発生し、国際経済社会への貢献や対外不均衡の是正が、つまり経済大国としての責任ある行動をとることが一丁目一番地の政策として前面に出てくることになる。また、この対外面での政策スタンスが国内政策にも反射し、規制緩和が追求されることになった。
2. 1990年代の新しい動き
このような通商産業政策は、90年代初頭のバブルの崩壊を挟んでも、大きな転換は見られなかった。短命の政権が続いた結果、その政権の目玉になる政策が変わり、地球環境問題への対応が表に出ることもあったが、基本的には、対外均衡を多国間調整で実現する、規制改革を進める、エネルギーの安定供給と経済成長の調和を図り得るという展望が持てるという点に関して、政策基調に変化はなかったといえる。
しかし、不況が長期化する中で、1990年代の後半にかけて、経済構造改革の必要がより強く表に出てきて、不良債権処理、財政再建、景気回復という複数の政策課題を一挙に解決することが求められるようになった。他方で、マクロの景気調整政策は、市場経済が不可避的に内包する累積的な悪循環に対する調整的な市場介入政策を主要な要素とするので、経済産業政策が企業行動の自由を保障するだけでは、十分ではない。その点では、企業自体の改革を視野に入れることが求められているといえよう。
また、通商面では、海外で新しい地域協定や2国間協定の動きが活発化する中、その対応が求められるようになっている。今、経済産業省の担うべき経済政策は、既に第2の転換局面に差し掛かっているのである。
パネルディスカッション
モデレータ:及川 耕造 (一般社団法人発明推進協会副会長)
日本における産業政策レジームの諸局面
岡崎 哲二 (RIETIファカルティフェロー/東京大学経済学部教授)
80年代前半における産業政策は、自らの役割を市場機能の補完と規定し、特定の業界全体を対象に、独禁法の適用を除外して業界の共同行為をサポートする手段を取った。しかし、こうした産業政策に対しては、日米間の経常収支の不均衡を背景に、海外を中心にさまざまな批判があった。そうした状況の中で、産業政策のレジームが80年代半ばに大きく変わったと私は理解している。それを典型的に示したのが1987年の産業構造転換円滑化臨時措置法である。これは、業界全体ではなく特定の企業と特定の地域を対象に、独禁法の適用除外の規定は作らないという特徴を持っていた。
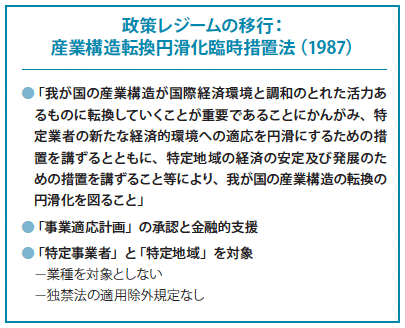
1990年代に入ると、日本経済のプレゼンスが高まった結果、日本の経済構造や社会構造が海外から問題視されるようになった。その中で、通産省が産業政策のかじを切り直したのが橋本内閣時代であった。橋本内閣は明確に規制の排除、撤廃、制度改革を強調している。通産省はこのポリシー形成に強く関与していた。その流れを受けて、2001年の省庁再編の際には経産省の所掌事項として「経済構造改革の推進に関すること」という1項目が入ったのである。
転換期を迎えた通商産業政策の理念
武田 晴人 (RIETIプログラムディレクター・ファカルティフェロー/東京大学大学院経済学研究科教授)
1980年代の後半、通産省が直面した通商貿易面での政策課題は、2国間の問題をどう処理するかであった。しかし、1990年代になると、多国間で明確なルールに基づき処理することを重視し、その限りでは自由貿易体制を維持することを国際通商摩擦への対処の基本的な方針にしたといえる。そこには、政府が関与し得る範囲にはおのずと限定があるのだと主張することで、政府の関与の部分を小さくしていくという意図がうかがえる。
しかし、現実に今起こっている2国間協定や多国間協定の問題にどう対処するかと考えた場合、政府の関与を排除するような議論は恐らくできないだろう。したがって、課題の変化とともに、それに対する対応の仕方、手段の体系について、より柔軟な問題解決の手法を見出していかなければならない。
「産業政策」の変遷
大橋 弘 (RIETIプログラムディレクター・ファカルティフェロー/東京大学大学院経済学研究科教授)
日本の経済発展の歴史は、産業政策の観点から大きく3つに分けられる。戦後の復興時期は、特定の産業に対する重点的な資源配分を行った時期があった。その後、新自由主義という言葉に典型的に示される規制緩和、構造改革の流れの中で、民にできることは民にやらせるべきだという考え方が出てきた。そして2000年代以降は、産業政策という言葉のリバイバルが見られている。ただ、戦後復興のときと異なる点は、市場のルールや公正な競争を侵してまでも政策を行うべきだという考え方には立っていないことと、イノベーションや技術革新がその中に論点として含まれていることである。
現在は、市場が縮小する局面において、市場メカニズムにおける負の側面が目立つ傾向が指摘されている。そうした負の影響をできるだけ抑えるためにも日本企業が海外展開を積極的に進めることが望ましい。また、そのためのスプリングボードとして、規制改革の中で国内市場と国際市場との調和を図っていくことが重要である。
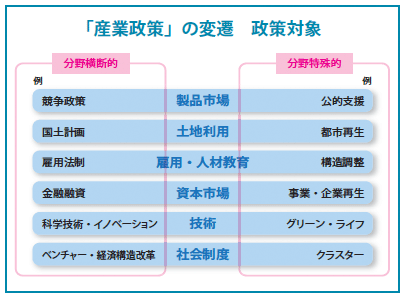
日米通商摩擦から見る通商政策史
今野 秀洋 (三菱商事取締役 (元経済産業審議官))
日米通商摩擦の歴史には3つの節目がある。1971年の日米繊維交渉妥結、1985年のレーガン大統領の新経済政策(NEP)の発表、1995年のWTO成立である。
1969年~71年は通産省が頑強に自主規制に抵抗していた。しかし、これは沖縄返還を決めた日米首脳会談の場でニクソン大統領から頼まれていたため、受け入れざるを得なかった。その後、通産省の通商政策は次々と自主規制を打つことで対米調整を図っていくことになった。
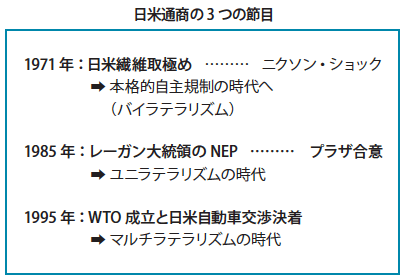
通産省の政策の転換の契機は、1987年の米国の対日制裁だったと思う。日米半導体交渉に絡んで、米国はついに対日制裁に踏み切った。このような米国のユニラテラリズムに対抗するために出てきた対策の1つが、GATTというマルチのルールに則って決着をつけるべきだという議論である。ウルグアイラウンドは1986年に始まったが、その中心は、日本、米国、EC、カナダの四極貿易大臣会合であった。そして、米国のユニラテラリズムの被害を受けていた世界各国の協力の下、WTOが1995年に成立したのである。
この歴史を振り返ると、あらためてWTOのありがたみを感じる。2国間交渉の場合は、交渉のために相手国を政治的に攻撃するので、仮に案件が解決しても国民感情にしこりが残り得る。しかしWTOができたことにより、貿易の世界でも法の支配が強化され、貿易紛争の非政治化が実現した。今、日本の隣国に新しい強権国家が台頭してきているが、そういうときに重要となるのが、やはり法の支配のレベルを高めていくことではないだろうか。
2000年代の経済産業政策と今後の方向(個人の見解として)
石黒 憲彦 (経済産業省経済産業政策局長)
2000年代、私は産業構造課長というポストにあった。当時は、長期的に需要が減退する産業やメガ企業以外は世界で戦えない産業が出てくる中、横並び主義と撤退コストの高さからなかなか大胆な経営改革に踏み切れない状況にあった。
現在の私の見解は、市場との対話を通じて産業政策はその空気を換えられるし、市場機能にある種の増幅効果を与えることができるということだ。そのアナウンスメント効果の一例が、大学発ベンチャー1000社、呼び水効果の一例がエコポイント、エコカー補助金だろう。また、東日本大震災のときには、サプライチェーンの復旧に、中立的第3者として、政府が緊急時の調整機能を発揮することができたと思っている。
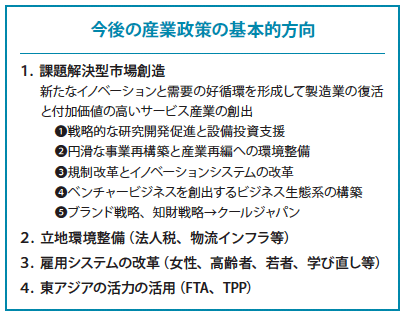
ディスカッション
21世紀の経済産業政策
及川: 21世紀の経済産業政策はどうあるべきかについて、各パネリストからひと言ずついただきたい。
岡崎: :産業政策への関心が世界的に高まっている背景には、世界経済全体の長期停滞、金融危機後の市場経済への懐疑、先進国全般で従来の産業が低迷していることがあると思う。その一方で、環境、エネルギー、ロボットなど、新しい産業の種が出てきている。そこで産業政策の役割が期待されるのだろうが、政府の失敗が非常に深刻なケースを招くこともあることは、留意しておかなければならない。先述のような基盤技術の確立には、イノベーションを促進する環境整備として、競争とレントを両立する形で、うまくインセンティブを作っていくことが肝要である。
大橋: 家電産業などを念頭に置いて議論するならば、市場のつかみ方が20世紀と21世紀で大きく変わってきている。現在の消費者はインターネットの普及を含めて多くの情報を持っており、自分で情報を発信する力もある。しかも需要はほぼ飽和をしている。そうなると、これからの製造業は単に物を売るのではなく、どうやって使うのかまで考えていかなければならない。すなわち、製造業のサービス産業化が鍵になるということだ。そうした流れをどう政策的にサポートするかが重要な視点になるだろう。
武田: 通商政策というのは、経済構造改革という大きな枠の中で、何ができるのかを考えなければならない。すなわち、経産省が政策領域をどう自己限定し、そこから選び出された複数の政策課題をどう順位付けするかという、政策のプライオリティを考えるということだ。そのときに、市場に委ねることで望ましい均衡がもたらされるということと、望ましい革新が出てくることは全く別物だということは注意しなければならない。
50~60年代に経済構造を変えた革新者は、企業のアントレプレナーだけではない。政策立案者たちが、自らが直面した政策課題の解決に向けて政策ツールや政策手段を試行錯誤することで、市場の発展との関係が変わり、市場経済が発展してきたのだ。その意味で、専門家集団としての経産省の官僚が果たす役割は大きく、それぞれが自己革新をしていかなくてはならない。
今野: ドーハラウンドの行き詰まりは、WTOが立法機能不全に陥っていることの象徴である。目下のところ、それを埋めているのがTPPのようなメガFTAであり、日本が自らを蚊帳の外に置こうとしているのは理解しがたい状況である。今はジオポリティクスがどんどん露骨になってきている時代だ。このような時代には、日本もゲーム感覚を磨く必要がある。たとえばOECDで作られたひも付き援助の禁止は日本が円借款を道具にして世界市場に台頭してきたときに、米欧諸国が作ったルールである。中国はOECDには加盟しない。そうすると、新しい時代に則した援助ルールを考えて、これを中国やインドも含んだマルチの場でルール化していくという発想が必要なのではないか。
石黒: 今後の産業政策の基本的方向に関しては、エンターテインメント系のマーケットなど、レッセフェールで十分なところも多いと思う。一方で、ヘルスケアの分野など、課題解決型市場もある。規制改革と公的扶助が絡み合う世界においては、政府自身がリーダーシップを取って一定の制度改革や介入をしなければ、マーケットが立ち上がってこない。また、新陳代謝という意味ではベンチャービジネスも必要である。さらに、法人税や物流インフラの整備、財政再建との調和、雇用の構造調整など、関係省庁と調整をしていかなければいけない。今回、産業競争力会議が経産省に止まるのでなく総理官邸の中に置かれたことは、そういう意味合いも持っている。
閉会挨拶
藤田 昌久 (RIETI所長・チーフリサーチオフィサー (CRO)/甲南大学教授/京都大学経済研究所特任教授)
本日は、これまでの産業政策を踏まえ、真のグローバル化の中で日本が活力を取り戻し、発展していくための産業政策の在り方について議論し、各方面から重要な知見を得た。1つ付言すれば、東京一極集中の政策立案から脱し、地域間で政策を競わせることが、産業政策イノベーションにつながるのではないか。日本1億3000万人全員が、新たなグローバル化時代に適した産業政策を考えていくことが、日本の活性化につながると信じている。