はじめに
研究開発の生産性は、研究開発が新規で有用な知識を生み出す効率性と定義できよう。このような研究開発の生産性は、日本のようにフロンティアに近い国の経済成長に非常に重要である。内生的な成長理論によれば、経済成長率を決定する最も重要な要因は知識ストックの伸び率であり、その重要な決定要因が研究開発の生産性である。
では、各企業の研究開発の生産性を決定する要因は何であろうか。これについての実証的な研究は、最近では特許の書誌データが電子媒体で得られるようになったこともあり、現在さまざまな角度から活発に行われるようになってきている。以下では、企業レベルにおける研究開発のパフォーマンスの基本的な決定要因と考えられるスピードとサイエンス知識の吸収能力について、筆者の研究の一端をご紹介させて頂きたい(nagaoka(2006,2007))。
質の高い特許を得るためには、スピードの高い企業の研究開発が必要
研究開発においては、生産、販売と比べて、先行者の優位性がより重要である場合が多い。研究開発は事業の一番川上であり、研究開発で先行することが、事業における先行者優位性の源泉となる。また、研究開発の成果である特許権には排他性があり、最初に発明した企業のみがその利用の排他権を得られる。最初に発見した者のみが権利を獲得できるルールは、プライオリティー・ルールと呼ばれ、科学の世界を含め知識生産の最も基本的な競争ルールである。
このようにスピードが重要な研究開発においては、研究開発において先行することによって特許権として確保できる権利範囲も拡大すると予想される。実際、以下の図1に見るように、企業の研究開発のスピードが高いことが、質の高い特許を得るために重要である。図1は、米国特許を多く保有している世界主要企業の中から、IT分野で米国特許を保有している世界の約1200社の企業データベースに基づいて、IT分野の研究開発のスピードと特許の質(被引用件数で評価)との関係を示している。ここで、研究開発のスピードは、各企業の特許発明の既存特許文献からのラグ(すなわち、特許の登録時点とその特許が引用している米国特許の登録時点との差の中央値)の大きさである。サイエンス・リンケージ(後述)が高い企業でも低い企業でも、研究開発のスピードが早い上位25%の企業はそれ以外の企業と比べて、平均で約3割から約5割より被引用件数が多い特許を保有している。
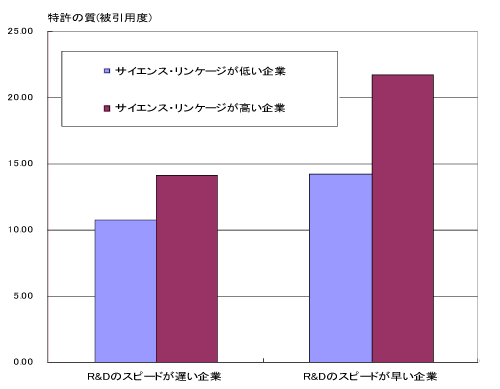
図1 スピードとサイエンスの吸収能力の重要性(IT分野)
注 1988年から1992年に登録された米国特許を対象。
注2 研究開発が早い企業とは、既存特許文献からのラグで評価してこれが最も短い上位25%企業。また、遅い企業とはそれ以外の企業である。
注3 同様に、サイエンス・リンケージが高い企業とはサイエンス・リンケージにおいて上位25%企業であり、低い企業とはそれ以外の企業である。
企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるサイエンスの吸収能力
サイエンスの知識を技術の改善・革新に生かす力も企業の研究開発生産性の決定要因として重要である。科学の進歩が一方向的に技術の進歩をもたらすわけではなく、現実の用途に駆動されながら原理的な解明に至る基礎研究を行うことで、良い基礎研究と良い技術の両方を得ることが出来る場合もある。いずれにしても、科学の力を活用できる能力が、企業の研究開発のパフォーマンスに大きな影響を与えると考えられる。
図1では、発明が先行文献として科学文献を引用する頻度(以下、サイエンス・リンケージ)を指標として利用して、サイエンスの吸収能力が高い企業とそうでない企業を分けてそのパフォーマンスを比較しているが、R&Dのスピードが高い企業群においてもそうでない企業群においても、サイエンス・リンケージが高い上位25%の企業の特許の質は下位25%の企業と比べて、平均で約3割から約5割高いことが分かる。スピードもサイエンス・リンケージも上位25%にある企業は、全体の企業数の約5%であるが、両方とも下位75%に入っている企業(全体の企業の55%)と比べて、特許の質は約2倍である。
日本企業の特徴
最後に、スピードとサイエンスの吸収能力の2つの指標で、日本企業と欧米企業の最近の動向を比較してみよう。以下の図2では、スピードが最も早い日本企業の1983-1987のスピードを10として、その98-2002年での水準および各地域の比較をしている。サイエンス・リンケージでは、その水準が最も高い米国企業の1983-1987の水準を10として同様の比較をしている。
この表が示唆するように、研究開発のスピードでは、米国企業と欧州企業が大幅に早くなり、日本企業との差が最近ではほとんど無くなった。これに対して、サイエンス・リンケージでは、米国企業のそれが急速に高まったので、日本企業との差はむしろ拡大した。
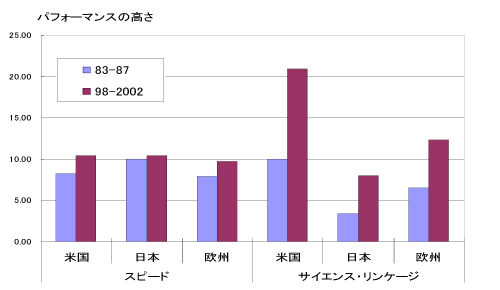
図2 日米欧企業の比較(IT分野)
終わりに
研究開発は高度に競争的な世界である。世界で多くの企業が参入を行い、研究成果を競っている。研究開発のスピードが早い企業、科学進歩の成果を自社の研究開発の成果(発明)に活かせる企業が、より質の高い特許を獲得することが多い。こうした尺度で見て、IT分野において日本企業のパフォーマンスは絶対的に悪くなっているわけではないが、欧米企業のパフォーマンスの改善が著しく、相対的なポジションは悪化しているといえる。
企業のこのようなパフォーマンスの変化と地域別格差の決定要因は何であろうか。新規参入企業の役割、競争、需要面の構造変化、産学連携のシステム、特許制度等の潜在的な要因が指摘されるが、それぞれの役割を識別していくことが、今後の重要な研究課題だと考えられる。


