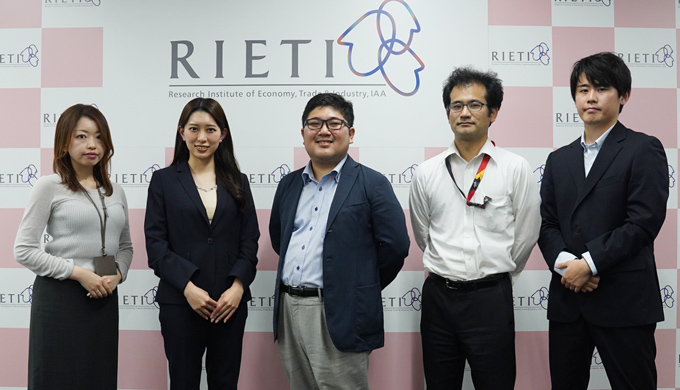経済産業省(経産省)は、2024年3月に「MVV」=ミッション(存在意義:未来に誇れる日本をつくる)、ビジョン(目指す組織像:つながりを力に、進化し続ける)、バリュー(大事にしたい価値観:本質的な課題に挑戦する。自由に個の力を発揮する。多様な力をかけ合わせる。)を定めるとともに、若手による新政策立案プロジェクトPIVOT(ピボット)を同年夏に始動した。2024年度のPIVOTでは6つのテーマが設定されており、イノベーションチームでは、「イノベーション資源の流動化」をテーマに人材、技術、設備の3つの視点から検討を進め最終報告書を取りまとめ公表している。本座談会では、イノベーションチームの各メンバーからPIVOT活動の意義や提言のインパクト、今後の政策的展開の方向性等について語ってもらった。
モデレータ:佐分利 応貴(国際・広報ディレクター:当時)
PIVOTに参加した動機
佐分利:
皆さんがPIVOTに参加された動機は何ですか。
鈴木:
私は入省1年目にスタートアップ政策を担当したのですが、もともとイノベーションがどうやって生まれるのか、イノベーションが生まれる組織風土はどうしたらできるのかにとても関心がありました。今回は、日本のイノベーションの課題を見つけ、その解像度を上げたいという思いから参加しました。(経産省入省4年目:法学)

土川:
イノベーション・環境局の総務課で経産省のイノベーション政策全体の取りまとめをしています。その中で、他の部局の人も集まった形でさまざまな観点からイノベーション政策を立案してみたい、自分の部局が行っている政策をもっと深く知りたいという思いから参加しました。(経産省入省5年目:法学)

小林:
経産省の最も重要なミッションは国富の増大です。国富の増大にはイノベーションが不可欠であり、そのイノベーションを生み出すのは人と考えています。入省1年目に人材政策の担当課におり、イノベーション人材を育てる施策について深く検討したいと思っていたので、参加しました。(経産省入省6年目:生命理工学)

前原:
特許制度はイノベーションを支える制度であり、もともとイノベーションとは深い縁があります。特許制度は発明を公開することによって、それを多くの人々に使ってもらうための制度なのに、実態としてはそうなっていないところがあります。特許制度本来の姿を追及するために参加しました。(特許庁入庁15年目:航空宇宙学)

萩平:
私が産業技術総合研究所(産総研)に新卒で入所したのは、イノベーションを生み出すのは人、特に研究者であり、そういう研究者の皆さんを支えることで貢献したいと考えたからです。研究者が生み出した知財を効果的に活用することでイノベーション創出に貢献できるのではと思い、人事交流の一環で、特許庁企画調査課に出向しました。まさに出向中にPIVOT参加の機会があり、イノベーションに貢献し得る方法を知財観点に加え、全体の政策的視点から考えられるところに魅力を感じ、参加しました。(産総研入所7年目:法学)

PIVOTの取り組みについて:イノベーション資源流動化の必要性
佐分利:
PIVOTの取り組みについて教えてください。
鈴木:
PIVOT(Policy Innovations for Valuable Outcomes and Transformation)は、2024年夏に立ち上げられた新政策の立案プログラムです。経産省の新たなミッション・ビジョン・バリュー(MVV)に基づいた若手有志によるプログラムで、所属する部署を超えて多様な力をかけ合わせ、本質的な課題に挑戦するものです。今回PIVOTで設定された本質的な課題は全部で6テーマありましたが、私たちは「イノベーション資源の流動化」チームとして、イノベーション資源を「人材」「技術」「設備」という3つの側面から検討しました。多様なバックグラウンドを持つメンバーが3チームに分かれ、延べ100人近い外部の方々との意見交換を経て提言を取りまとめました。(イノベーションチームのメンバーは、鈴木絵理子、小林汐織、土川輝、前原義明、萩平耕一、榎丸眞、杉森遥の7名)
土川:
経産省にはイノベーション創出を推進するという大目標があります。イノベーションの担い手にはさまざま主体が想定されますが、われわれはその中でもスタートアップに焦点を当て、どうやってスタートアップに足りない人材、技術、設備等のイノベーション創出のための資源を集めればいいのかを考えました。
まず人材面では、出向などにより現在所属する組織の枠を越え(越境)、異なる環境に身を置くことで、新たな視点を得る「越境学習」に注目しました。技術面では、企業や大学で眠っている特許をスタートアップの人たちが使いやすくするための「休眠特許活用」を検討しました。設備面では、特に研究開発系のスタートアップは多くの実験データが必要になるので、経産省が所管する産総研の設備をスタートアップに開放する「研究設備の共用促進」を考えました。そして、これら3つの方策にそれぞれガイドラインを作り、取り組みを加速化したわけです。
小林:
大企業の経験を持った人材がスタートアップに入ることで、スタートアップにとっては新たな知見が得られ事業を加速できるメリットがあります。さらに、大企業とスタートアップの協力が進み、社会全体のイノベーションが加速する効果も期待できることから、今回は主に大企業からスタートアップに人を送る人材流動化を中心に議論しました。
その中でわれわれは特に越境学習に注目しました。われわれのように本務とは別にPIVOTプロジェクトに参加する場合もそうですし、広義においては週末にPTAや地域のボランティアに参加するのも越境学習の1つと言われていますが、それを越境学習と認識している人はあまりいなくて、意識的に本務外で得られたスキルを事業や社会貢献活動に生かすことがポイントだと思います。
越境学習には人材育成だけでなく、これまでになかった新事業を立ち上げたり、スタートアップとの協業を率先して進めたりする「事業のイノベーション」と、もともと所属していた企業にはない文化を持ち帰ることで企業文化を変える「組織のイノベーション」という2つの効果があると考えています。
今回作成した越境学習の事例集とガイドラインにおいて、越境学習のメリットと活用事例を整理しており、越境学習者が所属していた企業における越境経験の発信機会の創出や企業全体で越境学習を後押ししている事例、それからダイバーシティの戦略に越境学習を入れて社員の挑戦を促進している企業もあり、そのような事例も紹介しています。
鈴木:
重要になるのがスタートアップフレンドリーな風土づくりであり、そのためにはスタートアップの組織風土や価値観を理解し、橋渡しができる人材の育成が不可欠だと考えています。これはスタートアップにとっても大企業にとっても大きなメリットがあると思います。
前原:
技術に関しては、民間企業の研究開発投資額の約9割を大企業が占めていますが、その研究開発で得られた技術のうち6割は事業化されず消滅してしまうと言われています。また、国内大学におけるライセンス収入が英米と比較して非常に少なく、大学の基礎研究が事業化に結び付いていません。2016年の調査ではありますが、日本企業の未利用特許率は46%と他国に比べ顕著に高くなっています。そこで、スタートアップによる未利用知財の積極的活用や大企業の知財を活用したスタートアップ創出が鍵ととらえ、知財の流動化を促進してイノベーションエコシステムを活性化したいと考えました。
特許利用について企業の方々に実態をお聞きしたところ、ライセンス契約時に業界ごとのライセンス料率を参照しながら契約を進めていることが分かりました。そこで、業界ごとのライセンス料率と過去の裁判例における料率の調査を行うとともに、それらを公表することとしました。これにより、ライセンス取引の透明性を高め一層の技術移転を促進することを狙っています。加えて、各企業の持つ未利用特許を集めて、それらをライセンスして収入を得るビジネスモデルに注目し、米国、日本、シンガポールでのビジネス実態を調査・公開しています。これらによって、知財の流動性をより一層高めていきたいと思っています。
萩平:
設備に関しては、現場の方々の声として、研究開発型スタートアップにちゃんとした設備があればさらに研究が進むのに、というものがありました。一方、産総研等の国立研究開発法人にはスタートアップが利用できる最先端の設備がそろっています。この設備をもっと効率よく使ってもらうための方針をとりまとめたガイドラインを作成しました。ただ、それで終わりではなく、現在、産総研とその研究成果を活用するための成果活用等支援法人である株式会社AIST Solutionsが一体となって取り組みを進めています。今後は、民間的な思考も入れた持続可能なビジネスモデルの構築という視点から、産総研グループ全体で取り組みを推進していきたいと考えています。
PIVOTの活動を振り返って
佐分利:
今回のPIVOTの活動を振り返ってみていかがですか。
土川:
政策立案において、いろいろな人を巻き込みながら進めていくことの重要性を感じました。有識者やステークホルダーへの数え切れないヒアリングはもちろんのこと、政策担当部局との調整等、多くの人の支えがあって政策を形にすることができたと思います。
鈴木:
一番大きかったのは、本務とは離れた場所でさまざまな部署のメンバーが集まって議論したことです。PIVOTではゴールも自分たちで決めることができたので、ディスカッションの幅が非常に広くなりました。
萩平:
若手で議論した内容を事務次官や官房長など、これまで経済産業政策に長く携わってきた方々に直接提案する経験ができたのは大きいと思います。
小林:
PIVOTそのものが越境学習だと思っていて、省外の方々と意見交換をし、自分たちの仮説や考察をブラッシュアップしていく機会が得られたのはとても良かったです。PIVOTで得たことを本務にも生かし、本務で得た知識をまたPIVOTで生かすという形で循環ができたと思います。
前原:
大臣官房の方々がPIVOTの活動をしっかりサポートしてくれました。組織の中心のサポートがあったことでサステナブルな取り組みになったと思うので、特許庁で同様の取り組みを進めたいと思いました。
佐分利:
すばらしいですね。PIVOTのようなワーキングチームによる省庁横断的な活動、越境学習はもっとあたりまえに普段から行えないものでしょうか。
鈴木:
日々本務に追われている状況の中では、「あたりまえ」にするには障壁があるように感じます。本務以外のことを自発的に進めるには、今回のように組織の中心に旗振りをしていただかないとなかなか難しいでしょう。民間企業であれば就業時間以外の時間を使って社内副業するといった事例も耳にしますが、役所の場合は業務内容の性質上、その切り分けが難しいように思います。
今後の方向性
佐分利:
最後に今後の課題や取り組みなど、読者の方へのメッセージをお願いします。
鈴木:
イノベーション人材を創出するための企業活動の重要性や、組織に人事制度として越境学習を取り入れる必要性は示せたと思いますが、イノベーティブな組織風土をつくり出すというマクロな視点の検討は今後の課題だと思います。進化を求め続けることがイノベーションとの向き合い方の1つだと思うので、そうした社会風土づくりに貢献したいと考えています。
小林:
今後はガイドラインと事例集をもっといろいろな方に使っていただくために周知していくとともに、越境学習だけでなく新規事業創出に向けて民間企業の方々と議論する場を設定したいと思っています。
前原:
技術の流動化を検討するなら特許庁本体をもっと巻き込む必要があると感じました。特許庁を今後さらに巻き込んでいきたいと思います。
萩平:
PIVOTの活動によって、今後所属が変わっても一緒に議論できる仲間ができたことは本当に良かったと思います。経産省、特許庁、産総研、AIST Solutionsというそれぞれの組織を超えて問題意識を共有すればより良い政策ができますし、現場への還元もできると思うので、そうしたつながりがPIVOTを通じて形成できたのは良かったと思っています。
土川:
今回、3つのイノベーション資源について検討を進め、課題がある程度分かったので、それぞれのガイドラインを経産省の担当原課とも相談しつつ着実に進めていきたいと思っています。他方、人が異動するとその人が持つ知識やノウハウも一緒に移りますし、設備を貸すとアセットだけでなくそれを操る人も一緒に行かないと使えないので、それぞれの資源の連関も今後の課題だと考えています。
PIVOTのような取組は経産省内でもかなり珍しく、若手のポテンシャルを伸ばす上でも非常に有意義だと思います。PIVOTという取組自体も、ノウハウとして社会全体に広め、イノベーションを起こしていけたらと考えています。
佐分利:
最後に皆さんに宿題ですが、測れないものは改善できません。社会問題を解決するためには、それを測るモノサシを創ることがとても大事で、モノサシを創って数値目標を示せば世の中は動きます。越境学習ならどんなモノサシで何を目指せばいいか、設備の共同利用率はいいモノサシなのかなど、ぜひ目指すべき将来を示すモノサシを発明してください。そのモノサシを世の中に広めることは役所は得意なので。PIVOT 1期生として、ぜひ2期生以降の後輩の指導もがんばってほしいと思います。本日はありがとうございました。