金融危機後、米国の経済実績は期待外れであり、大陸欧州と日本の経済実績はそれ以上に不調なことから、長期停滞の可能性について再び注目が集まっている。本稿では、今後、需要不足が原因で米国経済が停滞することはないというコンセンサスが形成されつつあることを述べる。一方、日本と欧州では需要の喚起が必要で、需要不足が停滞の主要な原因といえるだろう。
金融危機後、米国の経済実績が期待外れであり、大陸欧州と日本の経済実績はそれ以上に不調なことから、長期停滞の可能性について再び注目が集まっている。停滞期には実質所得は横ばい、あるいは減少し、国の生産高は以前の上昇傾向をどんどん下回っていく。失業率上昇の可能性もある。Summers(2014)がきっかけとなり、長期停滞の可能性が注目されるようになった。
経済停滞の重要な原因1つは、低金利によって生産や雇用を刺激できるにもかかわらず、中央銀行は適切と思われる水準にまで金利を引き下げることができない、あるいは引き下げに消極的なことである。米国連邦準備制度理事会(FRB)と日本銀行は金融危機以後、わずかなプラス金利を維持してきた。欧州中央銀行(ECB)も同様だったが、最近になってわずかながらマイナス金利に転じた。日米欧はいずれも高失業率と、低水準のインフレ状態にあり、現代金融経済学の標準的な原則から見ると、明らかに金利の引き下げが必要な状態である。
大陸欧州と日本では極度な不況が続いているが、米国では、短期失業率の低下、未充足求人の増加など、労働市場の指標の一部は危機後の不況の終わりを示唆している。一方、長期失業率や非自発的パート労働などの指標はいまだに停滞しているものの、改善が見られ、来年には通常の水準に戻るだろう(注1)。専門家は、FRBが2015年の半ば以降、短期金利を引き上げると予想している。金利先物市場も同様の予想である。
欧州の長期停滞(需要要因)vs. 米国の長期停滞(供給要因)
このように、今後、需要不足が原因で米国経済が停滞することはないというコンセンサスが形成されつつある。一方、日本と欧州では需要の喚起が必要で、需要不足が停滞の主要な原因といえるだろう。
米国の労働市場は通常の状態に戻り、不況は終わったというコンセンサスにもかかわらず、2000年以降、生活水準は向上していないという意味では、米国経済はいまだに停滞状態にあるといえる。家計の購買力は2000年の水準のままである。図1は、家計の購買力が1990年代には大幅に上昇し、危機前に著しく減速し、危機の結果、2000年水準を下回り、最近は緩やかに回復していることを示している。
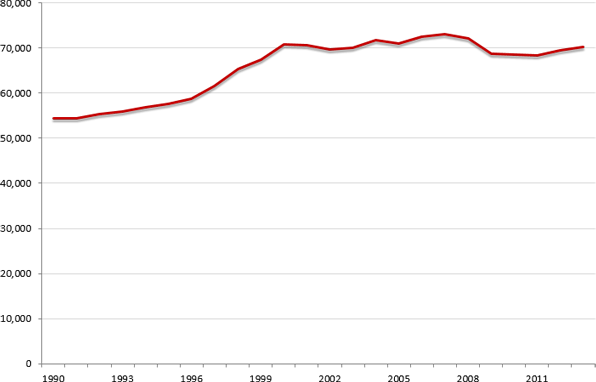
経済成長にもかかわらず、購買力の伸びが小さい時期が2回あったことが図に示されている。2002-2007年(2001年の不況からの回復期)と2010-2013年である(2008-09年の世界同時不況からの回復期)である。失業率は2007年に4.8%に達したが、長期平均の5.8%を下回っており、現在の長期失業率とちょうど同じである。需要不足が一般的な購買力停滞の要因でないことが明白に示されている(ただし、金融危機直後の時期には、需要不足は原因の1つであった)。2014年時点において、米国では供給減少による新たな種類の長期停滞が15年も続いたことになる。
米国の長期的な供給停滞の原因
米国経済の購買力停滞の要因は4つある。1)労働分配率の低下。2)資本の枯渇。3)生産性上昇の減速。4)就労率の低下。以上の要因を示す指標について順に説明したい。どの指標も1989年を起点としたデータである。所得の総購買力の指標は、4つの指標を掛け合わせたものである。
- 労働分配率の低下
図2は、米国の国民総所得に占める雇用者報酬(諸手当を含む)の割合を示す指標である。この指標は不況期には横ばいとなり、続く景気拡大期の前半には低下し、次の不況期までに高いレベルまで回復するという傾向がある。しかしこの傾向に重ねて、この時期全体をとおしてみると、累計で約10%も低下している。全般的な所得の低下傾向と同様に、分配率も2000年ごろから低下し始めたようである。この低下傾向についてさまざまな説明がエコノミストたちの間で行われてきたが、コンセンサスには至っていない。
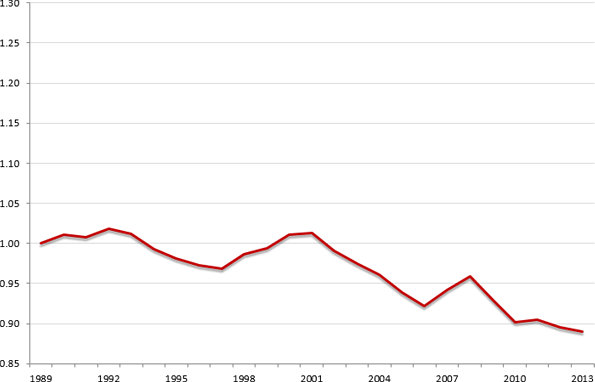
- 全般的な生産性成長の鈍化
図3は生産性が1989年から2007年までの間、急速に伸びたことを示している。世界同時不況によって生産性は急激に低下したが、過去の不況の際と同様、主に設備の遊休によるものである。回復期には生産性は通常の成長率だったが、危機のショックを埋め合わせるには至らず、2006年以降の成長率の平均は水準を下回っている(注2)。世帯家計所得はこれに比例して減少した。生産性については、Fernald(2014)を参照されたい。
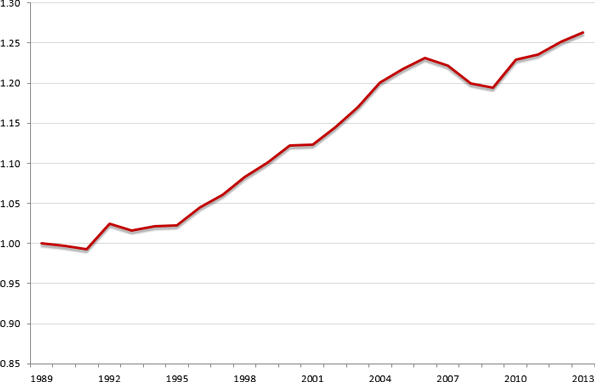
- 世帯あたりの資本量激減
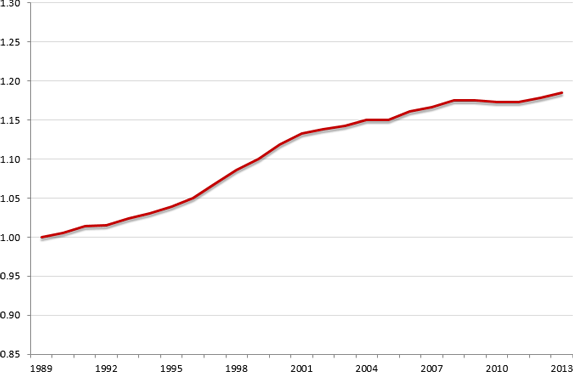
図4は、第3の要因―平均的労働者1人あたりの資本設備の量―を示している。工場、設備、ソフトウエアが増加すれば、労働者はさらに所得が得られる。世帯あたりの資本量は1990年代に急激に増加したが、2000年以降、伸び率は鈍化している。世界同時不況の間、世帯あたりの資本量は実際に減少し、最近は増加しているとはいえ、1990年代のトレンドが続いていた場合の数値には程遠い。
- 低い就労率
図5は、家族の年間労働時間の指標によって計測した、世帯あたりの労働参加の平均である。時間数は2000年までは世帯あたりの労働時間数が急速に増加していたが、当然、2001年の不況期には減少し、その後2002-2007年の好景気の時期には横ばいにとどまり、それ以前の好景気後のように増加に転じることはなく、世界同時不況の際には急落し、現在も続く回復期にあっては上昇している。2000年以降の労働時間の低下は、世帯あたりの所得低下の最大の要因である(注3)。最近、世帯あたりの労働時間数が増加しているため、将来的に所得が回復することが見込まれる。
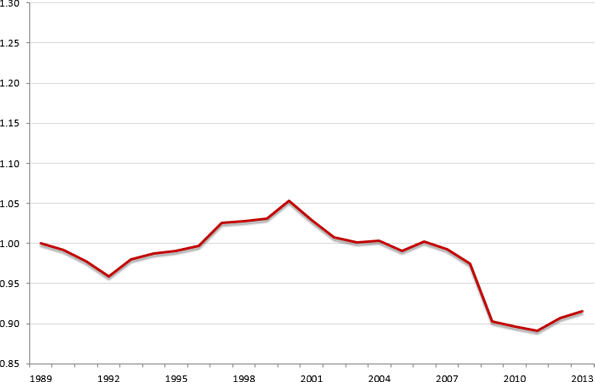
労働時間はなぜ減少したか
労働時間の減少は所得伸び悩みの最大の要因なので、次の3つの要素に分けて、さらに深く考察したい。世帯あたりの就労者数、就労率、そして労働者1人あたりの労働時間である。
- 図6は世帯あたりの就労者数を示す指標である。
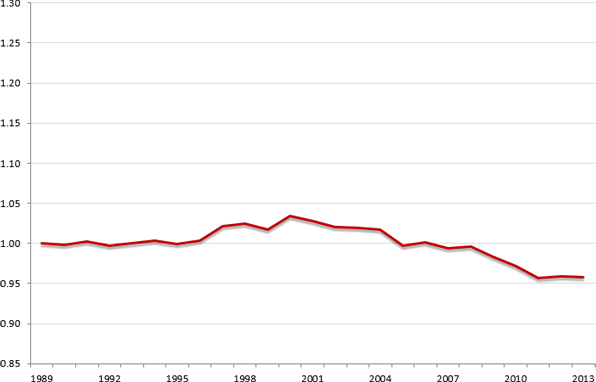
図が示すように、就労者数は1990年代、特に後半に増加したが、その後は減少に転じている。世界同時不況後、世帯あたりの就労者数はわずかな影響を受けただけで、全般的な就労率低下の重要な決定要因とはならなかった。もちろん、世界同時不況当時は実際に就業中の就労者が減少し、求職者が増加した。
エコノミストたちは、就労者数が以前の予測をはるかに上回り、驚くほど減少した原因の解明に努めてきた。労働市場の停滞によるマイナスの効果が比較的小さいというのが、ほとんどの研究結果である。また、生産年齢人口の構成の変化による影響は限定的である。高齢化によるマイナス効果が高学歴化によるプラスの効果を相殺してしまっているからである。フードスタンプ(食料配給券)、障害者手当などのセーフティネットプログラムの恩恵を受けている世帯のうち、課税対象となる世帯が大幅に増えたことも要因の1つかもしれない。
- 図7は実際の就労者の割合を示す指標である。残りは求職中の失業者である。
就労者の割合は、不況時には下落し、その後の回復期には上昇しているが、平均すると横ばいで推移した。最近になって、失業率が5%台後半レベルに下落したため、就労率は回復を見せている。現在のところ、所得の停滞の重要な要因とはなっていない。
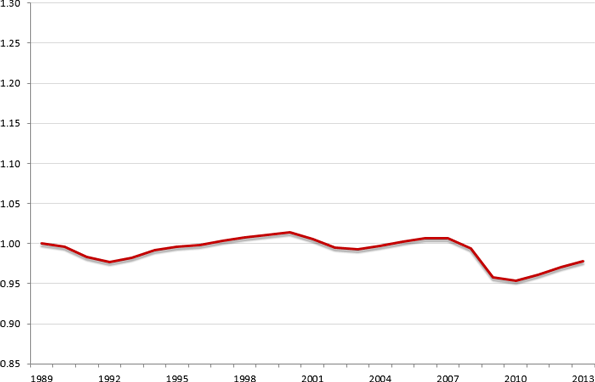
- 図8は平均的世帯の1週間あたりの労働時間の推移を示している。
ほとんどの期間一定を保ってきたが、世界同時不況期は急激に下落し、それ以後、下落分の約半分しか回復していない。労働者1人あたりの労働時間がかつての水準まで戻るのか、あるいは所得の停滞の要因の1つとして今後も残るのか判断するのは時期尚早である。
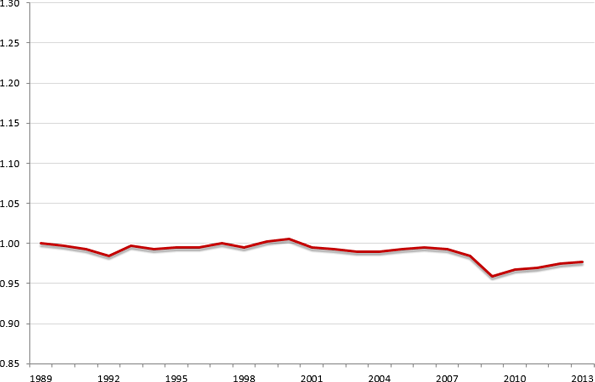
労働vs. それ以外の時間の使い方
2003年に開始されたアメリカ人の時間の使い方調査 (American Time Use Survey) によると、労働とそれ以外の時間の使い方とのバランスが変化している兆候が見られる。表1は、2003-2013年の間に、さまざまな活動に費やされた1週間あたりの時間の変化を示している。
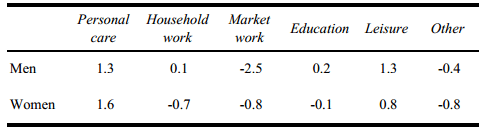
- 男性の場合、1週間あたり2.5時間の労働時間減少が、最大の変化である。通常の労働時間が週に40時間であることを考えると、かなりの減少である。
労働時間の減少は、一部、失業率の上昇で説明できる。失業率は2003年の6.0%から2013年には7.4%まで上昇している。
- 女性の場合、週あたりの労働時間はマイナス0.8時間で、減少幅は男性と比較してかなり小さい。
男女とも、身の周りのこと(睡眠など)と余暇(主にビデオ鑑賞など)に費やす時間が大幅に増加した。教育関連の時間はほとんど変化していない。女性が家事に費やす時間は減少している。。
家計の購買力が通常の成長に戻る可能性はあるのか?
図4が示すように、資本は通常の成長のペースに戻る可能性がある。これ以外の主要な3つのカテゴリーについては、予想することは難しい。国民総所得に占める雇用者報酬の割合が上昇に転じる兆候は今のところ見られず、上昇に転じると予測する研究もない。生産性は明らかに上昇しており、成長率は1970年代、1980年代の数字に近いが、1950年代、1960年代、1990年代の数字と比較すると明らかに下回っている。特に、図3が示すように、生産性上昇に急に弾みがついて、金融危機期に完全に失速してしまった生産性を埋め合わせられる兆候は見られない。
さらに重要なのは、図6が示すように、就労率の下落傾向に歯止めがかかる兆しがないことである。最近の月次データを基に、就労率の回復を宣言する意見もあるが、図9はこのような考えは単なる希望に過ぎないことを示している。就労率は、労働市場の状態が回復している時期も低下し続けており、このことから、就労率と労働市場の状態はまったく関連していないことがわかる。
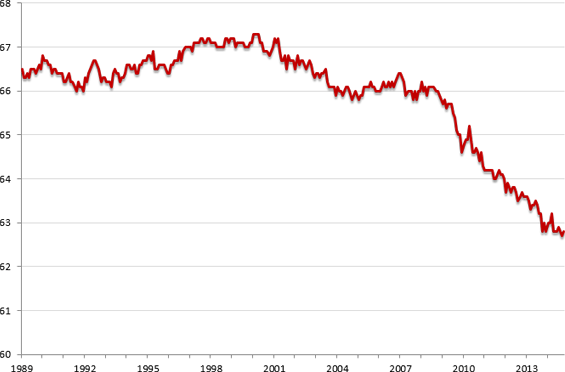
失業率が5.5%以下に下がれば、購買力が上昇する可能性がある。5.5%は完全雇用を示すラインという考え方もある。2000年の失業率は3.8%、2007年には4.4%にまで低下しており、どちらも長い景気拡大期の末期にあたり、この時期、FRBのインフレ目標2%レベルを越えるインフレは起きていない。
繰り返すが、以上の結論は米国に関するものである。大陸欧州では、需要は回復からはほど遠い状況である。日本では失業率は低いが、景気は低い水準にある。
本稿は、2015年4月22日にwww.VoxEU.orgにて掲載されたものを、VoxEUの許可を得て、翻訳、転載したものです。


