国家間には根強い格差がある。本稿では経済史をひもとき、国家間の深刻な所得格差の仕組みを説明したい。貧困国と中所得国に新技術の普及を促す政策を通じて格差を縮小できる。このような政策は国家間に存在する所得格差の縮小にも役立つだろう。
国家間の所得格差は200年前、比較的小さかった。Maddison(2004)(注1)が西側諸国と呼んだ国々―欧州各国とWestern offshootsと呼ばれる米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド―はそれ以外の国より平均で90% 豊かだった。2000年までに所得格差は750% に拡大した。長期的な経済成長に関する研究のほとんどが現在の所得格差を、遺伝的資質、文化の違い、気候、制度などあらかじめ決定されている要因で説明しようとしている (Spolaore and Wacziarg 2009; Ashraf and Galor 2013; Acemoglu et al. 2005; Guiso, Sapienza and Zingales 2003等) 。このような研究の多くは、提示された既定の要因に対して現在の1人当たり所得の回帰分析を行い、高い相関係数を見出している。しかし、こうした分析は国家間に深刻な所得格差をもたらしている仕組みや分岐の時期についてはあまり参考にならない。
最近の研究
われわれは最近の論文(Comin and Mestieri 2013)で以下の問題を取り上げた:
- 長期的な経済成長の主な理由は何か?
- 国によって成長の原動力が異なるのはなぜか?
以上の問題について、論文中のデータで示したように各国の技術の直接指標の変化は所得を増やす原動力になっているのか調査した。
ある国において技術による生産性向上への寄与は二分できる。1つ目は使用される技術の範囲、2つ目は技術が導入されるまでの時間差に関係する。新しい技術は生産性を向上させるため、新しい技術がその国に到達するスピードが加速すれば全体的な生産性も向上する。また、生産性は新技術の普及率にも影響を受ける。その国で使用される新技術が(所得比で)多いほど、新技術によってもたらされる生産性向上の恩恵を享受できる労働者や資本が増える。つまり、技術の普及率(あるいは技術の普及の度合い)が上昇すれば生産性も向上する。
Comin and Hobijn (2010) は各国の普及曲線の形状は似ているが、垂直、水平方向に変位していることを示す(図 1)。この規則性は曲線の相対的な位置が2つの媒介変数で示されることを意味している。水平方向の移動値からその国に技術が導入された時期がわかる。垂直方向の移動値からは技術が完全に普及した時点の普及率がわかる。
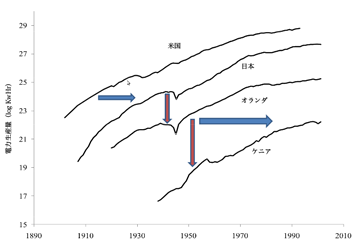
[ 図を拡大 ]
技術普及の歴史的国際比較(CHAT)データ(Comin and Hobijn 2009)を使用し、過去200年間に発明された25の重要な技術に関し、132カ国の(非バランス)サンプルにおける技術普及の度合いと速度を特定した。次に推計値を使って普及を示す2つの指標のギャップについて国際比較を行った。その結果2つの新しい実証結果を得られた:
- 過去200年間に技術が普及するまでの時間差は国家間で縮小している(図2)。
つまり、技術の普及までの時間差は、富裕国(技術導入が早い国)と比較して貧困国(技術導入が遅い国)の方が大幅に縮小している。
- 第2に、過去200年間に貧困国と富裕国の間で技術の普及率の差が拡がり、技術普及の速度の差も拡大している(図3)。
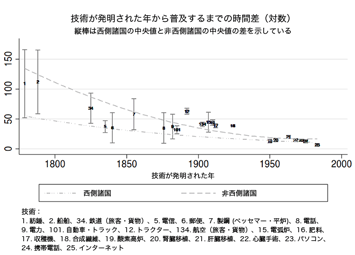
[ 図を拡大 ]
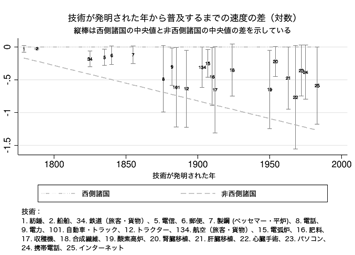
[ 図を拡大 ]
技術の原動力を明らかにした後、それが所得を押し上げる原動力につながるかどうか国際比較を行う。具体的には代表的な2つの国(「先進国」と「途上国」)の所得を押し上げる原動力のシミュレーションを行う。データで明らかになった技術普及の原動力を投入したモデルは、過去2世紀のデータに見られる各国の所得増加のパターンと類似のパターンが見られた。特に先進国では現代の長期的な生産性の上昇率(2%)に到達するのに約1世紀を要したのに対し、途上国では少なくともその倍の時間を要した。その結果、このモデルは富裕国と途上国の間で3.2倍の所得格差を生み出したが、これは過去2世紀の間、実際に観察された4倍の所得格差の約80%に相当する(表1)。
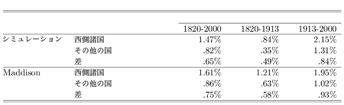
[ 図を拡大 ]
作用している力をよりよく理解するため、技術の普及率と普及の速度を順番に遮断した。この結果、2つのことがわかった:
- 技術の普及までにかかる時間が国によって大きく異なっていることが、19世紀に見られた西側諸国とその他の国との所得格差の大半の理由である。
- 20世紀に「大いなる分岐」(The Great Divergence)が続いたのは西側諸国とその他の国との技術普及率(普及の度合い)の相違による。
このモデルを用いることにより、1820年頃の富裕国と途上国の間の所得格差、また世界の所得分布の下位4分の1の各国、10分の1の各国、そして各大陸で観察された経済成長の原動力を有効に再現できた(注2)。つまり、技術普及の原動力が過去2世紀の間に起こった「大いなる分岐」の本質だったことを示している。
結論
われわれの論文は、技術が普及するまでの時間差と速度の原動力が一体何であるか、特に立場をとるものではない。しかしながら、貧困国と中所得国への新技術の普及を促す政策によって国家間に存在する所得格差の縮小に大きな効果があることを示唆している。
本稿は、2013年5月28日にwww.VoxEU.orgにて掲載されたものを、VoxEUの許可を得て、翻訳、転載したものです。



