| 解説者 | 長岡 貞男 (プログラムディレクター・ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0095 |
| ダウンロード/関連リンク |
現在、職務発明制度の改革が議論されており、特許法35条が大幅に改正される見通しとなっている。企業にとって、職務上の発明を奨励してイノベーションを進め、競争力を強化することは重要な経営課題である。発明者へのインセンティブ制度によって、社員の発明意欲を高めたいという思いは、どの企業にも共通するが、効果的なインセンティブ制度作りは容易ではない。というのも、リスク負担や動機づけ、プロジェクト選択への影響など、さまざまな要素を考慮に入れる必要があるためだ。これを踏まえ、長岡貞男ファカルティフェローらは、企業における人事考課と知財戦略を一体運用することが、真に発明を促進するようなインセンティブ制度の構築に不可欠であると主張する。効率的なインセンティブ設計をめぐる創意工夫で各社が競争することを通じて、イノベーション創出の可能性拡大につながることが期待される。
――どのような問題意識から、この論文を執筆されたのでしょうか。
問題意識としては3つあります。第1に、日本の特許法(35条)は職務発明について、企業は特許の「通常実施権」を持つ一方、発明者の従業員から特許を受ける権利や特許権を承継する場合には、「相当の支払い」をすると定めています。しかし、企業の発明者は発明のために雇用されるようになっている実情に合わなくなっている場合が多いこと。また、「相当の対価」は事後的に請求できるため、多数の訴訟が生じているという問題が生じていることです。
実は、この35条は大正時代にできた条文を踏まえているので、時代に合うように改正されより多様な制度設計が可能となる見通しです。そうであれば、企業はこれまで以上に、どのようなイノベーション促進制度が望ましいのかということを、主体的に、そして真剣に考える必要があるはずです。
第2に、学術的な見地からみても、発明インセンティブ設計は難しい問題でさまざまな研究が積み重ねられてきました。経済学や経営学などで理論的な観点から研究されてきましたし、動機という人間の心理に深く関わる問題であることから、社会心理学などの分野でも取り組まれてきました。そうした学術的な議論をまとめて、今後のインセンティブ設計の参考としたいと思ったことです。
第3に、私どものチームはRIETIで発明者サーベイという調査研究プロジェクトを行っており、ちょうど2回目のサーベイを終えたところで、日米欧の比較研究の視点からも分析してみたいと考えていました。日本の発明者の処遇については、誤解されていることも少なくないので、日本のインセンティブ制度の実情について国際比較の観点から示したいと思います。本研究はファカルティフェローの大湾秀雄教授(東京大学社会科学研究所)及び大阪工業大学の大西宏一郎講師の3名で行いました。
企業活動の現実と合わない現行の日本の発明処遇法制度
――職務上の発明をめぐる日本の処遇制度は欧米に比べて遅れている印象がありますが、実際はどうなのでしょうか。
議論を整理するうえで、まず、歴史的な経緯を概観してみましょう。
現行の日本の特許法35条は、職務上発明に対し発明者の社員が特許権を持ち、社員が所属する企業は無償の通常実施権を持つと規定しています。これは19世紀の米国の判例法のショップライト法理に対応しています。大正時代にできた条文を基にしているのですから、研究開発のために専門に雇われた研究者を想定しているわけではありません。むしろ、工場などで働いている人が生産などの職務に加えて発明もしたというような場合を想定したと考えられます。
しかし、20世紀になると、企業は研究開発を自らの投資負担で大規模に進めるようになり、研究開発のために専門の社員を雇うようになります。このような企業投資やその組織的な努力の重要性を反映して、職務上の発明は企業に帰属するという考え方が登場します。米国そして欧州の多くの国の職務発明の処遇制度は、実際の企業活動とも整合的なこうした考え方を踏まえています。
一方で、日本の現在の法制度はこの点で、時代の動きに遅れをとっています。発明者が研究のために雇用されているという実態と無関係に発明者が保有する特許権を企業に移転する際に支払うことが定められている「発明の相当の対価」によって、発明者を処遇することを強制しています。欧米の多くの国では、職務上の発明は企業に帰属するとした上で、どのようなインセンティブ制度や処遇の仕方が研究者の発明精神を刺激して、優れたイノベーションの可能性を引き出すかに知恵を絞っているのに比べると、日本企業が発明者との訴訟に多くの経営資源を費しているのは残念な状況です。
――現行法でも職務発明の権利を社員から企業に移す際は相当の対価を支払うと定めていますが、それでは不十分ですか。
権利の事後的な移転に「相当な対価」を支払う方式が強制されている現状では、合理的なインセンティブ設計の自由を大きく制約します。発明者より企業が負担した方がよいリスクを発明者が負担することとなったり、企業の事業化投資への誘因の確保に問題があり得ます。
具体的なインセンティブ設計のあり方を含めて、企業がもっと自由に職務発明を推進し、その一方で社員との訴訟リスクも減らすことができるように、改革が進められるのが望ましいと思います。
――現行法の改正で職務発明の法人帰属が日本でも原則となれば、大きな前進となるわけですね。
大学等を除いて、研究開発に加えて事業化投資も行う法人の場合、法人帰属が原則になれば、「発明の相当な対価」で処遇するという法的制約がなくなり、企業はインセンティブ設計に正面から向き合うことになります。また、訴訟リスクは大きく低下します。但し、帰属ルールは本来イノベーションの推進の観点で当事者が選択すべきで、常に法人帰属がいいわけではありません。
発明の動機は「お金」ではなく問題解決のため
――職務上の発明は、実際にはどんな人が、どのような動機で行っているのでしょうか。
まず、発明者はどんな職務についているかですが、日米欧とも大半が研究所に勤める研究者です。日本の研究者の89%は研究開発関連の職場におり、米国(79%)、ドイツ(78%)も研究開発職場の比率が高いのです。ものづくりの現場にいる従業員が多くの発明をしているということではありません。
それでは、どのような動機から発明をしたかですが、圧倒的に多いのが「現実的な問題の解決のため」とか「技術的な可能性の追求」のような内発的な動機です。内発的というとちょっと硬い表現ですが、外部からの刺激や強制によるのではなく、内側から沸き上がってくる研究者魂の発露のようなものです。図1に示すように、内発的な動機に比べると、「金銭的報酬」、つまり、お金のためという動機は自営業の発明者でもそれほど強くありません。ちなみに外発的な動機(外部からの刺激や強制)とは、アメ(たとえば金銭的報酬)とムチ(たとえば降格や雇用関係の解消)を指します。
――お金より問題解決が最大の動機という傾向はどの国でもあてはまるのでしょうか。
内発的な動機が発明の最大の原動力というのは、どの国にも共通します。日米独のデータを取って比較したところ、いずれの国も、「現実の問題を解決したい」という動機が最重要であることが最も多く、「金銭的報酬」という動機はかなり少ないとの結果が出ました。強いて米国で特徴的な点があるとすれば、社会的な名声をあげることが発明の動機になるという傾向が見られる点です。米国では労働市場における流動性が高いために、次の職場で厚遇されるために発明実績は効果的という考え方があるためと思われます。
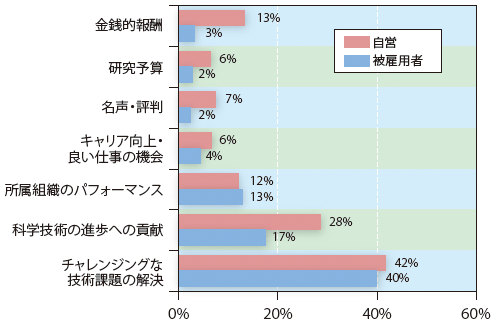
N=5097(被雇用者),114(自営業者) [原図はDPの図4]
インセンティブ制度の設計には細心の注意と工夫が不可欠
――発明を奨励するために、具体的にどのようなインセンティブ制度を設計すればよいのでしょうか。
効果的なインセンティブ制度を設けるためにどのような点を考慮すべきかについて、理論面を踏まえて説明しましょう。効果的なインセンティブ制度の構築に、重要であるとされている第1の仕組みはモニタリング(監視)です。しかし、発明の場合には、情報の非対称性の問題が非常に大きいので、なかなか難しいです。
情報の非対称性というのは、研究者を監督する立場の上司には、そもそも研究者が潜在的にどのような研究プロジェクトに取り組む可能性があり、またそれぞれがどのようなコストと便益を持っているのかの把握が困難であるという点です。優れた研究成果を期待する上で、まず重要なのは、どのような研究プロジェクトを選択するかということなのですが、プロジェクトの選択の仕方について最も詳しい情報を持っているのは、研究者自身なのです。
では、成功報酬という「ニンジン」を用意することで、研究者の意欲を刺激するというのはどうでしょうか。お金が発明の最大の原動力ではないとはいえ、やる気を出させる上では報奨金は効果があるように思えます。しかし、報奨金は特定のプロジェクトを与件とすれば努力を引き出すうえでプラスの効果があるとしても、その一方で研究プロジェクトの選択を歪めるマイナス効果を生む恐れもあるのです。
Lambert(1986)( 注1 )の研究は、企業が研究者にプロジェクトを実施させる際の興味深い結果を示しています。たとえば、金銭的報酬はリスク回避型の研究者に、成功する確率が五分五分になるような難しい研究テーマを避けて、安全で成功率が9割程度は見込めるが、画期的な成果は望めないというようなテーマを選ばせる傾向があるのです。成功報酬のような促進材料を用意したつもりが、かえって研究者の意欲をほどほどの水準に落ち着かせてしまい、より優れた成果が見込めるかもしれないハイレベルの研究に挑む意欲を失わせてしまう危険性があります。
――なるほど、インセンティブ制度の設計は複雑で、一筋縄ではいかない感じがしますね。
私が科学技術振興機構(JST)からの支援で行っている「イノベーションの科学的源泉」についての研究プロジェクトで、革新的な研究をした研究者を対象にヒアリング調査をしたのですが、発明という成果にたどりついた研究のなかには、正規の研究プロジェクトではなく、いわばヤミ研究とでもいうべきケースから発明が生まれた場合も少なくないことが分かりました。また意図せざる研究プロジェクトから画期的な成果が出るというのは、インセンティブ設計の面白さとともに、難しさを示すものです。
成果が出るかどうか不確実な難しい研究テーマに研究者があえて挑戦するような環境を整えるうえで、それ以外のリスクはできるだけ企業が背負うことが大事になります。プロジェクトの選択・実施と、事業経営上のリスクを分離して、研究者には発明にたどり着く可能性を最大限に引き出すようなインセンティブの設計をすべきなのです。
――となると、研究者の雇用という点で考えると、雇用期間も重要なポイントになるのでしょうか。
そうです。長期的な雇用が、イノベーションを追求するうえで、実は良い結果を持っている面も強いです。日本では終身雇用制度が揺らぐなかで、長期的な雇用制度そのものについても競争力の向上にはつながらないと否定的に捉える傾向が強まっています。でも、10年といったような比較的長期間で評価されるなら、若い研究者が最初の何年かはリスクをとって難しい研究にトライすることも可能になるはずです。
米国の研究では、研究プロジェクトに数年という期限をつけてプロジェクトに資金を提供する方式よりも、研究者そのものに資金を提供して5年程度の比較的長期間に自由に研究させる方式の方が、より優れた研究成果につながるとの分析結果も出ています。
――インセンティブの一種として実績報奨制度を採用する事例が日本でも増えていますね。
この論文の分析期間である2000年代に、日本企業は実績報奨制度など職務発明に関する規定を盛んに導入しました。2000年代前半に実績報奨制度の導入や改訂が日本で進んだ背景には、研究開発の重要性への認識が高まったという側面もあるかも知れませんが、2003年のオリンパスの職務発明事件に対する最高裁判決で特許法35条が任意規定ではなく、強行規定であるということが確定したほか、中村修二氏(2014年にノーべル賞を受賞)による青色発光ダイオードの発明における対価請求訴訟で高額な判決が出たことが挙げられます。
つまり、こうした企業にとって外生的な変化によって、実績報奨制度が2000年代に入って一気に導入されたので、制度導入に伴って研究プロジェクトの選択がどう変わったのかを検証することができるのです。
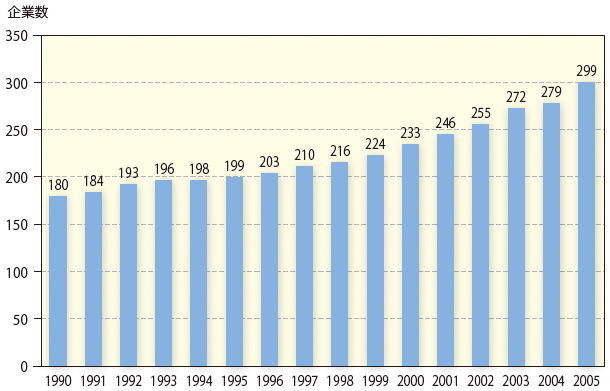
――報奨制度の採用事例の増加は、研究成果などにどんな影響を与えていますか。
この論文では、日本の発明者のライフサイクルのデータ、つまりパネルデータを分析に使用しました。2007年に実施した第1回発明者サーベイの個票データを基に、知的財産研究所のIIPパテントデータベースから各発明者の全期間にわたる特許出願データを収集しています。所属する企業や研究者の学歴などの属性、発明の内容などを個別に識別し、網羅しています。
分析の結果は、実績報奨制度の導入や上限金額の引き上げなどの制度変更は、発明者の発明の質を大きくはありませんが平均的に引き上げることがわかりました。
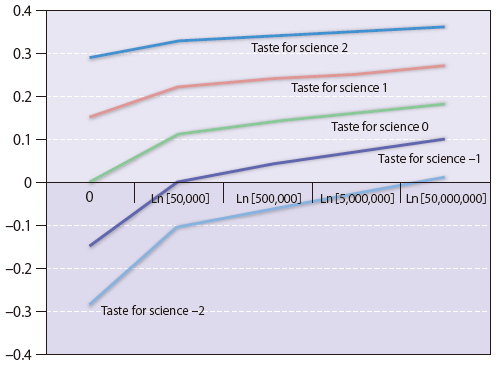
しかし、プロジェクトの選択に着目して詳しく見ると、実績報奨の上限金額が高くなるほど、発明者の科学論文の引用が減少する可能性があることがわかりました。つまり、お金がもらえる場合は、長期的に革新的な成果が期待できるかもしれない半面、短期的に結果が出にくい科学的な基礎研究は敬遠されやすく、短期的な成果が見込める実用的な研究に集中しかねないのです。
また、どの研究者も報奨金の額の影響を等しく受けるというわけではありません。科学をベースとした研究への志向が強い研究者の場合は研究の成果がもともと高く、研究成果に基づく報奨金の多寡は、研究のモチベーションの高さとは特段に関係しているわけではなく、報奨金制度にそれほど大きな影響を受けないことがわかりました。
――昇進・昇給などの報奨制度の研究成果に与える影響はどうでしょうか。
分析結果からは昇進や昇給などは発明者の研究開発意欲を誘発する重要な役割を果たしていることがうかがえます。この点は、次のように考えることができます。インセンティブを与える方式には、先ほど述べた「成果報酬」(絶対評価に基づく)と、Lazear and Rosen(1981)( 注2 )が唱えた「rank-order tournament(相対的な評価、平たく言えば昇格や昇給など)」があります。インセンティブという点では成果報酬でも相対評価(rank-order tournament)でも同じですが、前者は所属企業の業績など発明者が制御できない要因にも依存してしまうのに対し、後者は発明者が制御できる要因で決まるので、研究者は不必要なリスクを負わなくてすむ利点があります。
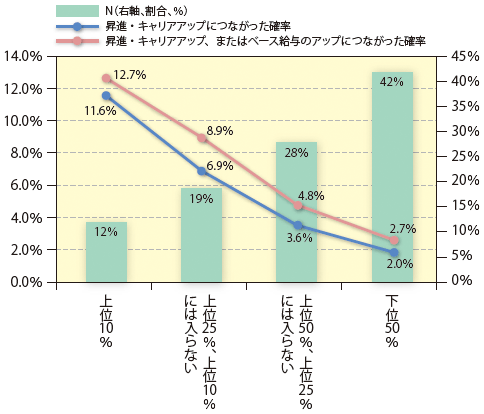
発明の推進には企業の人事考課と知財戦略の一体化が必要
――本論文の政策的な含意についてご説明ください。
特許法35条が改正されることで、職務発明の特許は法人帰属となることが可能となりそうです。その結果企業は、どのようなインセンティブ制度を設計するかという点では高い自由度を得ることになります。
今後のひとつの課題は、現在の日本企業は人事考課と報奨制度をまだ別個に運用していることを改めることです。知的財産権をどのように戦略的に拡大・拡充していくかは、どのようなインセンティブ制度、すなわち報奨金や昇進・昇給などの仕組みを構築するかということと、密接につながっています。ですから、知財戦略と人事考課・管理を一体的に運用させねばなりません。
効果的な制度設計が法律による一律の規定では実現しないように、インセンティブ制度の設計はリスク負担、動機づけ、適切なプロジェクト選択など多様な要素を組み合わせることが求められます。特許法の35条の改正によって、発明を促す望ましい制度作りの進展が期待されるわけですが、それにはイノベーションを促すインセンティブ設計で、企業間で創意工夫の競争が進むことが前提となります。
それから、企業にとってはメリットが薄くても(私的な利益が小さくても)、社会全体では大きなメリットが享受できる(社会的なスピルオーバー効果が大きい)場合に、どう対応するかは政府のイノベーション政策において大事な問題です。そのような発明の創出を促すには、政府による支援が重要です。この点は、RIETIにおける塚田尚稔氏(現政策研究大学院大学准教授)との共著論文「 研究開発のスピルオーバー、リスクと公的支援のターゲット 」(Discussion Paper Series 11-J-044)でも取り上げています。
――今後の研究成果計画について聞かせてください。
長期的なインセンティブとして昇進・昇給は大事です。米国の場合、日本や欧州に比べて報酬金制度よりも、昇進・昇給の方が多く使われています。ではなぜ、米国と日欧では昇進・昇給制度の活用・普及という点で差があるのか、その原因は何かをこれから分析したいと思います。
米国で昇進・昇給が盛んな背景として、労働市場の流動性が高い可能性が考えられます。日本では年功制度を背景に流動性が低いのに対し、米国では職能性を重視した雇用体系となっています。これは発明者との関連でどう捉えたらよいのか、国際比較の視点から研究を進めるつもりです。
解説者紹介
1996年 一橋大学商学部付属産業経営研究所教授、1997年 一橋大学イノベーション研究センター教授、2004-2008年 同センター長。この他、産業構造審議会臨時委員、OECDの貿易と競争政策ワーキンググループの事務局、WIPOの事務局長アドバイザー、公正取引委員会競争政策研究センター主任客員研究員などを務める。
主な著作物:『経済制度の生成と設計』(東京大学出版会・2006年3月・鈴村興太郎・花崎正晴と共編著)、『知的財産制度とイノベーション』(東京大学出版会・2003年6月・後藤晃と共編著)ほか


