| 解説者 | 小林 庸平 (コンサルティングフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0070 |
| ダウンロード/関連リンク |
日本経済の活性化には、企業の研究開発(R&D)投資が活発に行われることが不可欠だ。なぜなら、企業のR&D投資により生まれる便益は、投資を行った企業内にとどまらず広く社会に波及していくからだ。そのため、政策的に投資の拡大を支援していく事の重要性が、経済学的にも指摘されている。
それでは、現在、R&D投資促進のために採られている減税制度は、政策としてどのくらい有効なのだろうか?そうした問題意識の下、経済産業省の行政官でもある小林CFは、RIETI「法人課税制度の政策評価」研究プロジェクトの中で個別の中小企業のデータを用いてR&D減税の効果に関する定量的な分析を行った。
プロペンシティ・スコア・マッチング(PSM)の手法を使って、減税を適用される企業とそうでない企業を比べる際の偏りを取り除いて比較を行ったところ、減税政策は中小企業のR&D投資を2倍以上に増大させる効果を持つことが示された。今後、時系列変化や、適切な水準についての視点など、より精緻な政策評価実現にむけた研究の深化が期待される。
――まず、今回の研究に取り組まれたきっかけについて教えてください。
この論文は、RIETIの「法人課税制度の政策評価」研究プロジェクト(プロジェクトリーダー:楡井誠FF(一橋大学))の一環として書きましたが、このプロジェクトには2つの特徴があります。
第1に、行政側の問題意識がプロジェクトの発端であったという点です。2年ほど前に経済産業省の企業行動課と中小企業庁の財務課という省内で税制を担当する部署の中で、租税特別措置法などの企業に関する税制の政策評価をきちんと行う必要があるという機運が盛りあがりました。
なぜならば、当時も、導入した税制の政策評価が色々な手法で行われていましたが、その枠組みは必ずしも確立してはいないというのが実情だったからです。たとえば投資減税の制度を利用したことによって、企業のR&D(研究開発)投資や雇用が増えたというような分析結果はあります。しかし、それが本当に税の効果によるものなのか、それとも、R&D投資や雇用増加に積極的な企業が減税を利用しただけなのか、はっきりしない部分があるのです。また、投資減税にR&D投資を増加させる効果があったとしても、社会的に望ましい投資水準がどの程度なのかを判断するための評価軸が必要ですが、行政の現場でそうした分析手法を精緻に検討していくことは難しいのが現状です。このような問題意識に基づいて、2009年11月からプロジェクトが行われました。
このプロジェクトのもう1つの特徴は、この論文でとりあげたように、ミクロデータを使って、特定の税制が導入されたことにより個々の企業の行動がどのように変わったのかを分析するとともに、プロジェクトリーダーでもある楡井FFが、マクロの面から社会厚生を評価する分析を行う(Investment Risk, Pareto Distribution, and the Effects of Tax(投資リスク、パレート分布および租税の効果)/RIETI 11-E-015)というように、アカデミックな知見に基づきマクロ・ミクロ両面から分析を行っていることです。
――元々、企業税制に関心があったのですか?
私は現在、経済産業省の任期付き職員として産業構造課で業務にあたっていますが、前職の民間のシンクタンクで税制に関する調査に携わっていました。そこでの関心と知見があったため、本務とは別にRIETIのCFとしてプロジェクトに参加しました。
R&Dの経済学的な位置づけについては、理論的・実証的な分析により、1980年代からその重要性が指摘されてきました。なぜなら、企業がR&Dを行うと、その成果は企業内に留まらずに、知識や知見という形で社会に広く波及します。つまり、R&D投資によって企業側が受け取る利益は、社会全体が受け取る利益(=便益)より小さくなるわけです。結果、企業の最適行動としてR&D投資の水準は社会全体にとって望ましい水準より低くなるのです。こうしたことから、企業のR&D投資を政策的に促進することは重要な意味を持つことになります。
日本企業のR&D投資は、全体としては国際的に高い水準にあります。しかし、企業の規模による差異が非常に大きく、中小企業のR&D投資は低い水準に抑えられています。一方、米国ではR&D支出は企業規模とそれほど関係なく活発に行われており、図1のように1つのグラフにすると日本と対照的な姿になります。
日本の全要素生産性(TFP)の分析でも、大企業のTFP成長率は1990年代に低下したものの、その後回復基調であるのに対し、中小企業は回復に遅れをとっています。中小企業のR&D投資の少なさが日本の生産性改善の足かせになっている可能性を深尾京司FF(一橋大学)らが指摘されていますが、そういった点からも、現在の税制が中小企業のR&D投資の促進に効果的なものになっているのかどうかを検証したいと思っていました。
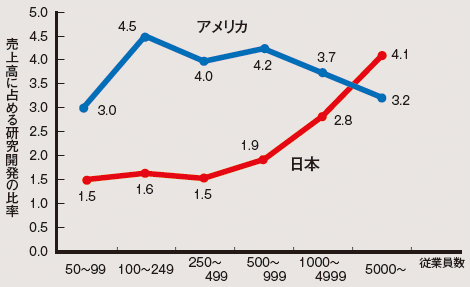
希少な中小企業のR&D投資についての定量分析
――同様の先行研究は多いのでしょうか。
日本では、産業別やセミマクロ別の分析はそれなりになされていますが、企業レベルのデータを使った分析はこれまであまり行われてきませでした。2003年に古賀款久教授が書かれた論文は先駆的なもので、企業レベルのデータを使って、日本のR&D減税の効果を推定していますが、同様の論文は国内では数本だと思います。また、そうした論文も、基本的にはR&Dの大宗を占める大企業を対象としたものですので、今回の研究は、中小企業のR&D投資についての定量的な分析としては、私の知る限り初めてではないかと思います。なお、海外では、マクロ・ミクロ両面から多様な研究がなされており、R&D減税は企業のイノベーション活動の活性化やR&D投資の増加におおむね効果があるという結論が出ています。
――R&D減税の制度と、分析に使用したデータについて教えてください。
日本の中小企業向けのR&D減税は1967年にスタートしたもので、大きく分けて3つのタイプがあります。基本は「総額型」といって、企業の支出した試験研究費の一定比率を法人税額から控除(現行12%)します。これに加えて条件に適合すれば「増加型」と「高水準型」のどちらかの適用を受けることができます。前者は過去一定期間の試験研究費の平均を上回る分について、後者は同じく売上高の一定割合を超える分について、それぞれ一定比率を税額から控除するというものです。
分析に使用したデータは中小企業庁が毎年行っている「中小企業実態基本調査」の平成21(2009)年度の個票です。中小企業約11万社を対象とする調査で、企業の概要や、財務状況、取引の状況、金融機関との関係のほか、平成20年度調査からはR&D減税の利用の有無が質問項目に入りました。このことにより、今回の分析が実現したといえます。
比較時のバイアスを除去
――分析の手法について教えてください。
冒頭に申し上げましたように、政策効果の測定は簡単ではありません。中小企業向けのR&D減税の効果を測る際、減税を受けた企業のR&D支出と、そうでない企業のR&D支出を単純に比べてみても、減税があったからR&D投資をしたのか、R&D投資をしている企業が減税を利用したのかという因果関係、つまり卵と鶏の関係がわかりません。製造業・非製造業といった業種の違い、規模の大小、経営や資産の状況など、さまざま要因が影響するため、単純比較ではバイアスが生まれるからです。これを除去するために考案されたのが、プロペンシティ・スコア・マッチング(PSM)という方法です。もともと疫学調査などで使われていた方法論で、10年ほど前から経済学、とくに政策評価の分野で利用されるようになってきました。
具体的にいいますとR&D減税を使ったある企業Xに対し、R&D減税を使っていない企業の中から規模、業種、非正規雇用の比率、資本構造その他の要因を考慮して、特徴がよく似た企業X'を取り出し、両者のR&D支出を比べます。さまざま企業特性を1つ1つ比較することは非常に煩雑ですので、プロペンシティ・スコアという1つの値に変換します。こうすることで特性が近い企業を簡単に選び出すことができるようになります。特性が似通った企業Xと企業X'のR&D支出の差が政策効果になります。
因果関係を識別するための手法として、PSMの有効性についてはノーベル経済学賞を受賞したヘックマン教授や市村英彦FF(東京大学)らの研究によって定量的にも示されています。PSMは応用範囲の広い分析手法であるため、失業給付、教育訓練、補助金支出といったさまざまな政策の有効性を検証するために使われています。今回はこの方法を日本の中小企業のR&D減税の政策効果に応用したわけです。
――スコアをマッチングするときに3種類の方法を使っているようですがこれはどうしてでしょう。
少し専門的になりますが、簡単に説明しますと、「K-ニアレスト・ネイバー」ではスコアがもっとも近いK個、たとえば5個のものとマッチングさせます。「カリパー」はある一定の範囲に入る対象のものを比較する方法です。また「カーネル」はスコアが近いものほどウェイトが高くなるような関数を使って加重平均を計算し比較する方法です。マッチングの方法は複数提案されていますが、決定版といえる手法はありませんので、複数の方法で分析することによって、分析結果が頑健であるかどうかを確認することができます。
――調査サンプルをプロビット推定してスコアを計算しているのですね。
そうです。ここでわかったことを紹介しますと、就業者数の多い企業や、売上高経常利益率の高い企業は税制を利用する確率が高くなっています。一方、女性就業者比率が高い企業、また負債依存比率が高い企業は税制利用の確率が低くなっています。また企業の組織形態別を調べてみたのですが、有限会社、また立地別では東北地方の企業がそれぞれ低い確率となっています。
――分析の結果どのようなことがわかりましたか
表1は全サンプルの推定結果を示したものです。第1行の「なし」は適用企業と非適用企業を単純比較したもので、3列目は税制適用企業と非適用企業のR&D支出を比率で比較したものになります。結果は、222%となっています。これは、税制非適用企業と比較して、税制適用企業は、R&D投資が222%多いことを意味しています。しかし、先ほどから申し上げているように、これはバイアスがかかった数値です。しかしPSMでバイアスを取り除いたあとの数値は「カーネル」(第2行)で118%、「K-ニアレスト・ネイバー」(第3行)で124%、「カリパー」(第4行)で143%となっています。つまりR&D減税を利用した中小企業は、R&D支出を2倍以上に増やしていることが分かります。また推定値についてですが、誤差の範囲は0.16~0.22と狭く(第4列目)、検定値(第5列目)も7前後と、どのマッチング方法をとっても有意な数値といえます。当初想像していたよりもきれいな結果が得られました。

分析結果の第一印象は、R&D減税の控除比率は総額型で12%ですから、減税の効果は思っていたよりも大きいと感じました。同様の手法を用いた台湾の先行研究では、中小企業に対する減税によりR&D支出が90%増えるという結果が出ています。数字自体はそれを少し上回っていますが、水準としてそれほど大きな違いはないように見えます。
しかしこの研究の過程で関係者にヒアリングを行った結果では、「中小企業の実感として減税はあまりR&D投資には影響を与えないのではないか」あるいは「"減税があるから投資をする"というよりも"投資したついでに減税を使うのが一般的"ではないか」といった意見も多く耳にしました。こうした事前の感触と比べると意外な感じも持ちました。今回の分析結果が出た背景としては、税制が1年限りではなく中長期的に行われていることにより下支え効果を持っているため、R&D減税の適用を受けている企業が制度を利用していく社内体制を整えているのではないかとも思えます。こうした点については、引き続き検討していきたいと考えています。
また、大阪工業大学の大西宏一郎先生と九州大学大学院の永田晃也准教授の先行論文では、総額型のR&D減税は大企業のR&D投資を増やさないという結果が出ています。今回の研究ではデータの限界もあり減税の種類別分析まではしていません。先行論文は大企業のみを対象としているので、こうした違いが出てくる理由についても、今後研究していく必要があるのではないかと思っています。
流動性制約ある企業に有効
――製造業・非製造業、規模別、流動性制約の有無により差異がありますか。
製造業と非製造業とを比較すると非製造業のほうが減税によるR&D投資拡大の効果が大きいようです。一方、従業員数51人以上を大企業、50人以下を小企業とした規模別分析では、規模の大小によって政策効果はそれほど変わりませんでした。
一方、流動性制約の有無で比較すると(表2)、流動性制約のない企業に対する減税はR&D投資を35~66%(一部の推定値は有意ではない)しか増やさないのに対し、流動性制約に直面している企業への減税は、R&D投資を140~147%増やすという大きな効果を生み出していることがわかりました。
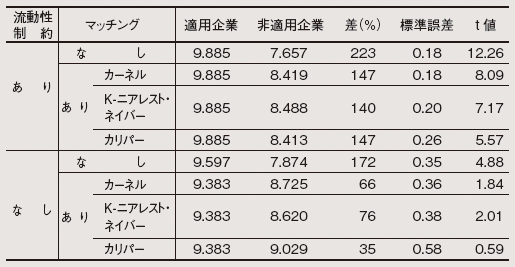
サンプルとして使用した「中小企業実態基本調査」では金融機関などから借り入れをする際に経営者が債務保証をしていたり、第三者の保証や担保を求められたりしているかどうかを尋ねています。この研究ではこれに当たる企業を流動性制約のある企業と見ています。つまり外部から資金を調達しにくい企業にとっては税による補填はかなり有効であるということがいえるのではないでしょうか。
――最後に今後の課題や研究方向についてお聞かせください。
まず時系列的な視点を導入することで、もっと厳密な分析をすることができると感じています。今回の研究では、平成21年度という一時点のデータのみを使用して分析を行いましたが、複数年度の調査結果を使ってパネルデータを整備すれば個別企業のデータを時系列で追うことができますので、税制の効果についてより厳密な分析が可能になると思います。
また、中小企業に対するR&D減税は政策として有効であったとして、利用率が低いという問題があります。「中小企業実態基本調査」によればR&D減税を申請した企業の割合は0.26%程度にとどまっています。多くの中小企業がR&D減税を利用しないのは、使う必要がないからのか、使う必要はあるけれどもできないのか、つまり税制が使いにくいのかなど、阻害要因をよく検討する必要があります。税制の潜在的な効果を高めるためにもこうした点を研究する必要があると思っています。たとえば、創業期などで利益が出ていない企業は、税金を納めていませんので減税の恩恵は受けられません。したがって、今後は、そうした企業への支援のあり方をどうすべきか、または効果の違いをどう見るかについても研究する必要があるのではないかと思います。
最後に今回の研究では減税によって企業の行動がどう変わるかという点について焦点をあてて分析を行いました。しかし、社会的に望ましいR&D投資の水準を達成するために、どういった税制が望ましいか、という規範的な視点からの分析は行っていません。社会的厚生(ウェルフェア)を最大化するために望ましい課税水準はどのくらいか、というマクロ的な研究と合わせてミクロ面での研究を深化させていくことにより、より豊かな政策的インプリケーションが得られるのではないかと感じています。
解説者紹介
2006年 一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。2006年-2010年 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)の勤務を経て、現在、経済産業省経済産業政策局産業構造課課長補佐。2010年より経済産業研究所CF。主な著作は「地域環境とソーシャル・キャピタルの形成」(経済政策ジャーナル・2009年)など。


