| 解説者 | 元橋 一之 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0049 |
| ダウンロード/関連リンク |
日本のIT(情報技術)産業では、ハードウェアは競争力があるものの、ソフトウェアは生産性が低く競争力に欠けると指摘されている。ソフトウェア産業の生産性向上のカギを握るのはイノベーションだが、1990年代後半以降のソフトウェア特許に関する制度改革の動きがソフトウェアイノベーションに与える影響はいかなるものであろうか?
本論文で元橋一之FFは、IIP((財)知的財産研究所)パテントデータベースと経済産業省の企業活動基本調査、特定サービス産業実態調査のソフトウェア産業のデータを用いて検証を行った。その結果、ソフトウェア企業の特許申請数は90年代から徐々に増加傾向にあり、ソフトウェア特許が認められるようになったことによって特許出願企業の増加がみられた。また、ソフトウェア企業が日本特有のソフトウェア産業の重層的な下請け構造から脱却することに寄与していることが確認された。重層的な下請け構造は、日本のソフトウェア産業全体の生産性を引き下げる原因となっているため、特許制度改革がもたらした効果は有用であると言える。
ソフトウェアの特許改革と下請け構造からの脱皮の関係を研究
――ソフトウェアの特許に関する改革と、ソフトウェアのイノベーションとの関係を研究された動機は何でしょうか。
これまでIT産業に関する生産性の実証分析を手がけてきました。日本のIT産業を考えるときには、イノベーションと生産性の関係が非常に重要で、とりわけソフトウェア産業でこの関係が注目されています。日本はハードウェアの分野では中国・韓国に追い上げられているとはいえ、まだ一定の競争力を維持していますが、ソフトウェア産業では米国と比較して生産性が低く競争力に欠けると言われています。これをいかにして向上させるかが、今後の日本のIT産業を考えるカギになります。
日本のソフトウェア産業の特徴は重層的な下請け構造を持っていることです。元請け企業が大規模なソフトウェアの発注を受け、それの一部の開発を請け負う下請け企業が何重にも存在する構造となっています。こうした構造ができたのは、ユーザー側の事情に基づく面が大きいと思います。たとえば、銀行が勘定系のシステムをつくろうとすると、伝票の種類や仕事の流れなど細かいところまで自分達の今の仕事のやり方に合わせたカスタムメードのソフトを「つくり込む」ことをソフトウェア企業に求めるので、システムの規模は非常に大きくなります。そこで元請けは受注したシステムをモジュールごとに分けて下請けに発注し、その下請けがさらに中小ソフトウェアハウスに発注するという構造になります。
これに対し米国では、ユーザーの多くは会計や顧客管理など特定の機能に絞って開発された出来合いのパッケージソフトを購入し、組み合わせて使用しています。ソフトウェアには、個別の取引先から受注生産する受注ソフトと、大量販売を目的とする汎用のパッケージソフト、ユーザーが自分のニーズに合わせて自ら開発する自社開発ソフト(たとえば半導体メーカーが半導体設計のために自前のソフトをつくるなど)の3種類に分けられます。これらについてソフトウェア投資の内訳を見てみると、日本の場合は受注ソフトがおよそ7割と大きな部分を占めています。一方米国では受注ソフトの割合は3割程度であり、パッケージソフトが大半を占めています。米国では、このようにして各種アプリケーションやOSなどの分野にそれぞれ強いソフトウェア企業が育ち、その結果、ソフトウェア産業の生産性が高くなっています。
日本でも、最近はオフショア開発といって、中国やインドの企業にソフトウェアの開発を発注することがあるようです。しかし日本国内では依然として重層的な下請け構造が主体になっています。このような構造は効率が悪く、生産性を下げる要因になっていると指摘されています。ソフトウェア産業を活性化するためには、下請け構造から脱却して独立系になる企業が増えていくことが重要だといえます。これによって業界全体の生産性が上がり、さらにマクロレベルの生産性向上にもつながるわけです。そのために政策的にどうすればよいかが課題になってきます。
中小のソフトウェア企業が独自の開発能力をもち、下請け構造から脱却するためには、ソフトウェアに関する知的財産についての取り扱いが影響してくると考えられます。そもそも90年代後半まではソフトウェア単体の特許は認められておらず、ハードウェアと一体になった場合だけに認められていました。それが1997年の改革でフロッピーディスクなどの媒体に入ったソフトウェアが特許として認められるようになり、2000年にはインターネット上でのやりとりなど媒体に入っていないものまで範囲が広がりました。さらに2003年には特許法の改正によって、ソフトウェアが正式に特許の対象になりました。このような政策によって、良い技術を持った企業が特許を出願できるようになり、イノベーションが加速され、ソフトウェア企業の独立性が後押しされたのではないかと考えられます。こうした流れがソフトウェア産業にどのような影響を与えているかを調べようというのが、今回の研究の動機です。
特許データと産業実態調査のデータなどで分析
――今回の研究にはどのようなデータを使用されたのでしょうか。
特許は出願から18ヶ月後に特許庁によって公表されます。これら個別の特許の情報がデータベース化され研究者用に公開されているIIPパテントデータベース(http://www.iip.or.jp)、経済産業省の企業活動基本調査、それに同省の特定サービス産業実態調査のソフトウェア産業に関するデータの3種類を使用しました。特定サービス産業実態調査は支店、工場など事業所ごとになっているので、これらを企業ごとに分類し直し、IIPパテントデータベースの出願人リストや企業活動基本調査のデータと組み合わせました。
1997年にソフトウェア単体での特許出願が認められるようになる前にも、ソフトウェア技術はハードウェアと一体になっていれば特許として認められたので、ハードウェアも手がけている大手IT企業はソフトウェアに関する特許を出願することが出来ました。したがって、ソフトウェアの特許に関する改革の影響を直接受けるのは、ソフトウェアだけを手がけている企業ということになります。今回の研究は、ソフトウェアの特許が出願できるようになったことで、ソフトウェア産業のイノベーションが促進されたのかどうかを調べるのが目的ですので、これらの企業を抽出しなければいけません。そこで企業の分野別売上高を見て、コンピューターなどハードウェアの売り上げが小さい、ソフトウェアの専業企業を抽出しました。こうして得た550社のサンプルをもとに分析しました。
脱下請けを促した特許制度改革
――分析の結果はどうなりましたでしょうか。
まず、ソフトウェアの特許に関する改革がソフトウェア企業の特許出願の増加につながっているかどうかを指数化しました。ある企業の、ある年における出願特許数が前年より増えている場合をプラス1、前年と同じなら0、減っていればマイナス1とします。この企業ごとの指数を合計した企業数で割ったものが図1に示されています。
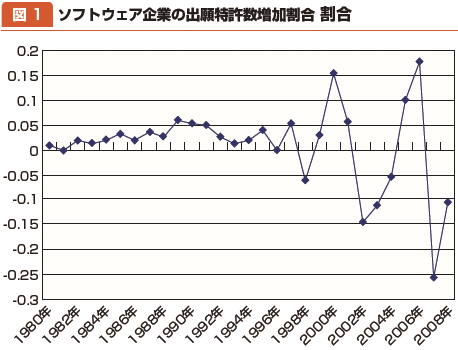
なお、ひとつの特許に複数のイノベーションが含まれることがあるので、ここではイノベーションの数を示す請求項(claim)の総数を使用しています。
図1からは、1997年の制度改正のタイミングで出願数を増加させた企業が増え、2000年には再び大幅に増加したことがわかります。ただし、ソフトウェアの特許出願は景気に左右されやすい面があり、2000年はITバブルでソフトウェア需要が盛り上がったことを割り引いて考える必要があります。2003年の制度改正は形式的には重要ですが、実質的には2000年ですべてのソフトウェア特許が可能になっており、傾向としては、ソフトウェア特許に関する制度改正が特許出願数の増加に繋がっていると見てよいと思います。
次に、ソフトウェア企業が下請け構造から脱却する要因について分析しました。下請け以外のソフトウェアの売り上げ比率(以下、「脱下請け比率」)に、何が強く関係しているかを回帰分析、具体的には固定効果モデルによって推計しました。分析の対象としては、1)特許出願数(対数比率)、2)企業規模を表す従業員数、3)研究開発要員の従業員数に占める比率、4)システムエンジニアの従業員数に占める比率、5)プログラマーの従業員数に占める比率の5つを使いました。これらについて、①全サンプルと、②最初に特許を出した年が95年までの場合(=比較的以前から特許を出願しているグループ)、③96年以降の場合(=最近特許を出願し始めたグループ)の3つのケースに分けて推計した結果が表1です。
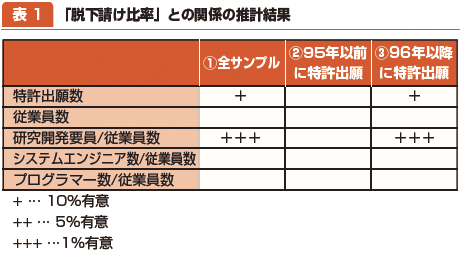
この結果から、①と③について、特許出願数が「脱下請け比率」と顕著な関係があることがわかります。また、同じ場合について、研究開発要員の従業員数に占める比率が「脱下請け比率」に関係していることが読み取れます。一方②について、特許出願数や研究開発要員の従業員数に占める比率が「脱下請け比率」にそれほど影響しないという結果になったのは、ソフトウェアの特許に関する制度改革以前から特許を出願していた企業にとって、制度改革の影響は大きくなかったことを示唆しています。
特許の出願は、企業の下請け構造からの脱却にポジティブな関連性を有しています。特に、特許制度の改革でソフトウェア単体での特許出願が認められるようになってから特許を出願しはじめた企業について、下請けからの脱却に大きな影響をおよぼしているのです。また、人員の面で研究開発に力を注いでいる企業は、下請けからの脱却につながりやすいということもいえます。
結論として、特許制度の改革によってソフトウェア単体でも特許を出願できるようになったことが、日本のソフトウェア産業の生産性を低下させている重層的な下請け構造からの脱却にとって良い影響をもたらしたといえるでしょう。
――ソフトウェア産業の生産性向上のためには、どのような政策が必要でしょうか。
今回の研究の結論から、ソフトウェア特許がイノベーションを促進すると考えられます。また、ソフトウェア企業におけるイノベーションと業界の下請構造の改革には、特許権を強化するプロパテント政策を進めていくことが有効であるということを示唆していると思います。プロパテント政策の方向としては、すでに損害賠償金の引き上げや侵害があった際の被告の挙証責任を軽減する措置などがとられていますが、このような特許権者の権利を強く安定的なものにする措置は、一般的に技術系のベンチャー企業にとっては有利に働くと考えられます。
今後の課題は「特許の藪」問題の研究
――今後の研究課題は何でしょうか。
日本では、知的財産の保護を強化するために、2003年に知的財産基本法が施行され、首相をトップとする知的財産戦略本部が内閣府に設置されました。日本は特許をベースにイノベーションを推進していくというプロパテントの方向へ大きく梶を切ったわけです。
しかし、プロパテントの効果については十分な分析が行われていません。「強い特許」は特許を取得した側にとっては良いことに違いありませんが、特許を使用する側にとっては、ライセンス使用料や手続きなどのコスト負担の問題が指摘されています。
また、特許は万能ではありません。そのことを示すものとして「特許の藪(やぶ)」という言葉があります。これは、ある分野で多くの特許が取得されている場合、それらがあたかも藪のように錯綜していて、新たにその分野に進出したり独自の事業を展開しようとする企業(人)は、まるで藪のなかを進むように、特許が取得されていない「すき間」を探していかなければならないということを示しています。特許の権利を強くすることは、この藪の「棘(とげ)」を大きくして、さらに藪に入りずらくすることになりかねません。そうなると、新規分野への参入や事業展開の意欲を持った企業(人)にとっての妨げになり、新たなイノベーションが起きにくくなってしまいます。
大手企業の場合は、こうした問題にクロスライセンスで対応しています。これは、企業Aが持っている特許群(ある事柄に関するまとまった特許)を、企業Bが使用するのを認める代わりに、企業Bの持つ特許群を企業Aが使用できるように認めてもらうということです。多くの場合は無償で、お互いに自由に特許を使えるようにします。いわば、藪への出入りを自由にするようなもので、これによって「特許の藪」の問題をある程度解決できます。しかし、中小企業の場合は、通常、取得している特許の数が大手企業とは比較にならないほど少ないので、こうした方法はとることができません。規模は小さくても技術的に優れた企業が、新たに事業を展開する際に「特許の藪」が壁になる可能性があるわけです。
米国では、インターネット検索のグーグル社が短期間で急成長したように、イノベーションのダイナミクスによって新たな企業が伸びています。日本でも同様に、イノベーションによって若い企業を伸ばしていく必要があります。その際に「特許の藪」が妨げになるようであれば、たとえば、小規模な企業に対しては特許侵害に関する賠償などを軽くするなどの方策も考えなければならないでしょう。
「強い特許」あるいは「特許の藪」が、中小企業の新規分野への参入や新たな事業展開にとって障壁になっているのかどうかはまだ検証されていません。特許制度は、権利保護による発明に対するインセンティブ効果とその活用による技術スピルオーバー効果の両面のメリットがあります。この両者のバランスを考えた制度設計を行っていくことが必要となりますが、特に「特許の藪」の問題が大きいといわれているソフトウェアの分野でこの問題について考えていきたいと考えています。
解説者紹介
1986年4月通商産業省(現経済産業省)入省。同省通商情報広報官や調査統計部統括グループ長を歴任。RIETIでは2000年客員研究員、2002年から上席研究員を務める。研究テーマは生産性の国際比較やイノベーションシステム論など幅広い。主な著作物は『ITイノベーションの実証分析』(東洋経済新報社,2005年)、『Productivity in Asia』(Edward Elgar Publishing, 2007 年, 共著)など。


