| 解説者 | 藤本 隆宏 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0012 |
| ダウンロード/関連リンク |
中国などへの工場移転が増え、日本の製造業の衰退が懸念されている。果たして日本にはどのような産業が残るべきなのか。藤本隆宏RIETIファカルティフェローは、産業競争力論の基盤である比較優位論と、設計論をベースにした「開かれたもの造り論」を接合し、もの造り現場の観点から「設計立地の比較優位論」を提起した。設計の比較優位が生じるメカニズムを検証し、国内には日本の組織能力と相性の良い「インテグラル型」(擦り合わせ型)の製品を残すべきだと提言している。
日本に残るべき産業は何か
――研究の背景には、どのような問題意識があったのですか。
日本では近年、中国などへの工場移転が相次ぎ、2000年前後には日本から製造業がなくなってしまうとまで言われていましたが、私は当時から疑問を感じていました。毎週のように工場をみていますが、自動車はじめ日本の多くの現場は高い組織能力を持っています。中国脅威論や製造業空洞化論は、現場観察を欠いた過剰反応に見えたのです。
しかし、グローバル競争の時代、すべての製造現場が日本に残れるわけでもない。では、どんな現場や産業が日本に残り、何が海外に出て行くのか。適材適所の産業構造を実現するには、まず産業競争力は何によって決まるのかを再考する必要があると考えたのです。
――そうした問題については、比較優位説から答えるのが一般的ですが。
貿易論における従来の比較優位説では、一国の一産業の競争優位を説明するロジックとして、要素生産性の相対的水準、あるいは生産要素に関する産業特性と地域特性の適合度を重視します。リカードが喝破したこの説は、現在でも重要な命題です。
一方、近年の日本の産業ビジョンでは、比較優位の視点が意外に希薄だったように見えます。確かに貿易財は競争優位性、非貿易財は所得弾力性を基本に据えるという大枠はありましたし、「日本は資本・知識が豊富な先進国になったのだから、資本集約的な工業製品や知識集約的な高付加価値財を作るべきだ」といった大まかな比較優位の発想はありました。しかし、製造業各業種の相対的評価など、個別具体論になると、産業ビジョンは「将来の日本にあってほしい産業、あるべき産業」を熱心に語るものの、それが日本に残れる産業なのかどうか冷徹に問うこと、つまり個々の財に関する競争優位性を、アジアや欧米との競争も念頭に入れ厳しめに検討するという点では、詰めが甘かったのではないでしょうか。
――なぜ、冷徹な分析が不足していたのでしょう。
その一因は、他ならぬ貿易立国論にあったと推測しています。明治維新以来、日本は加工貿易を追求し、1980年代には食料・原料・燃料を輸入して工業製品を輸出する加工貿易(垂直貿易)体制をほぼ実現しました。しかしこの間に、「工業製品は何でも生産し、何でも輸出しよう」という総花的な加工貿易論、つまりフルセット工業化の思想が、産業界や政策担当者に浸透したように見えます。「工業製品のうち何を輸出して何を輸入するのか」という水平貿易や産業内貿易を前提にした精密な比較優位論はあまり追究されませんでした。
しかし80年代後半以降、円高、バブル崩壊による長期不況、アジアの工業経済の台頭、海外直接投資の拡大などから局面が変わりました。日本の貿易構造は「食料・原料・燃料を輸入し、なおかつ工業製品も大量に輸入しつつ、貿易黒字を稼ぐだけの工業製品を輸出する」といういわば垂直貿易と水平貿易の混合形態に移行しました。さらに同一産業分類内で輸出と輸入が同時に起こる産業内貿易も拡大しました。例えば同じ自動車用鋼板でも、ドアの外板は日本が韓国に輸出し、内板は韓国が日本に輸出するといった極めて微細な分類水準での産業内貿易が生じています。
さらに20世紀末になると、日本の産業界は行き過ぎかとも思える規模で生産拠点を中国などに移し始めましたが、概してそこには「日本の現場はどの分野で残れるのか」を見極める冷静な競争優位分析が欠けていたように思えます。「日本が比較優位を持つ財は何なのか」という貿易論の古典的な問いかけに、我々は改めて正面から向き合わねばなりません。
従来の比較優位論は説明力不足
――比較優位論で答えは出せるのでしようか。
実は従来から、標準的な比較優位論では、水平貿易や産業内貿易といった現実の貿易現象、つまり生産関数が似通った製品群の双方向貿易をうまく説明できないと言われてきました。そこで、貿易の現状に対する比較優位説の説明力を高めるべく、「設計立地の比較優位」という概念を提起しました。これは、設計論をベースにした「開かれたもの造り論」と、比較優位の古典的な枠組を融合させ、既存の貿易論・産業論を補完しようという試みです。
――「開かれたもの造り論」とは、どんな概念ですか。
ここでいう「もの造り」は、単に「工場で物を作る」ことではありません。「設計情報をもの、つまり有形・無形の媒体に造りこむこと」です。具体的には、(1)開発(顧客にとって価値のある設計情報を創造する)、(2)購買(媒体を確保する)、(3)生産(媒体に転写する)、(4)販売(顧客に発信する)――というプロセスの総体を指します。言い換えれば、顧客へ向かう「設計情報の良い流れ」を作ることであり、それは製造業の枠組を超えてサービス業をも包摂する概念です。ものに囚われないもの造り発想がその基本です。
――設計現場の立地は、どのように決まるのでしょう。
設計現場の立地決定の一因は設計情報の特性です。この情報の2大源流は市場と技術ですから、(1)市場立地(市場情報が固着的ならその発生源に立地)、(2)技術立地(技術情報が固着的ならその発生源である研究開発集積に立地)、(3)組織能力立地(ある特性を持つ設計情報の処理に適した組織能力が偏在する場所に立地)、――という3パターンが考えられます。このうち(3)を重視するのですが、いずれにせよ、「開かれたもの造り論」の観点では設計現場の立地選択が生産現場の立地選択に先行すると考えるのが自然ですから、貿易論や産業論において設計立地に基づく比較優位を考えることは意味があると思われます。
――伝統的な貿易論は、設計立地がどのように決まると考えているのでしょうか。
伝統的な貿易論は、製品は既に設計済みとして、もっぱら生産立地の決定要因を議論してきました。設計論に立脚する「開かれたもの造り」の視点は看過されてきたといわざるを得ません。この点、バーノンらは1960 年代、「プロダクト・ライフサイクル・モデル」の貿易論で、製品は、まずそれが開発された場所で生産されるという重要な命題を示しました。しかし、設計がどこで行われるかという問いに対しては、米国が製品開発力で圧倒的な力を持っていたこともあり、「当然、米国である」という暗黙の了解にとどまったようです。
その後、クルーグマンらが提唱した「新しい貿易論」は、製品の差異化(製品設計による競争)と規模の経済(量産による平均費用の逓減)をモデルに取り込むことにより、複数の国が同種の製品を互いに輸出し合う産業内貿易をうまく説明しました。ある製品の生産が最初に始まった場所が、規模の経済により累積的に強化され、その製品の輸出拠点になるという考え方です。
――では、なぜ、ある国で、ある特定製品の生産が始まるのでしょうか。
「新しい貿易論」では「それは偶然だ」としています。しかし、「開かれたもの造り論」の観点からすれば、企業はその製品を設計した場所で最初の生産を始めると考えるのが、設計情報の流れからいっても自然です。つまり、新しい貿易論が予想するように、最初の生産拠点が自己増殖的に競争優位を確立するなら、その生産立地を決める要因として、設計立地の競争優位を論じることが重要になります。従って、産業内貿易や水平貿易を論ずる場合、まずもって設計の立地優位を分析すべきではないかと考えます。
組織能力とアーキテクチャの相性
――設計の比較優位は何に影響されるのでしょうか。
もの造り組織能力と製品・工程アーキテクチャの間の「相性」(フィット)が影響すると考えています。まず、何らかの歴史的な経緯によって、ある国の企業あるいは現場に、ある特定のタイプの組織能力が偏在しているとしましょう。すると、設計過程において、その特定の組織能力をより多く活用するタイプの製品や工程が、その組織能力が偏在する国で設計されることが有利になります。例えば設計要素間で多くの調整が必要な「インテグラル型アーキテクチャ」の製品・工程は、設計者間の相互調整を得意とする「統合型もの造りの組織能力」と相性が良いと予想されます。つまり、「国に偏在する組織能力」と各製品のアーキテクチャとの「相性」が、国ごと、製品ごとの産業競争力に少なからぬ影響を与えると考えられます。これが、設計立地に関する「アーキテクチャの比較優位論」が立てる基本的な予想です。
――「擦り合わせアーキテクチャ仮説」とは、どのようなものですか。
「設計の比較優位論」を戦後日本の貿易財に当てはめたのが、私がかねて提起してきた「擦り合わせアーキテクチャ仮説」です。これは、主として戦後日本の歴史的経緯により、日本の貿易財生産企業には「統合型もの造り」の組織能力が偏在する傾向があり、このためにそれと相性の良い「インテグラル型」(擦り合わせ型)の製品を輸出する傾向があるという仮説です。無論、組織能力の構築が大前提で、「日本人なら自動的に擦り合わせが得意だ」などという短絡的な話ではありません。個々の事例ごとに現場・現物の確認が必須です。
――この仮説は実証されているのでしょうか。
検証は容易ではありません。アーキテクチャのインテグラル度とモジュラー度を測定するには、製品ごとに機能、部品、工程の相互関係を洗い出す必要があるからです。試行錯誤によって事例分析や統計分析を積み重ねていくしかありません。
例えば東京大学の私の研究グループは、簡便法を用いて、経済産業省と共同で製品別のアンケート調査を実施しました。アーキテクチャの測定指標として、企業の製品担当者に(1)部品設計が製品に特殊的か、(2)接続部分が社内専用規格か、(3)設計パラメーターの相互調整を要するか――など12の特性について各製品の「インテグラル度」に対する主観的な評価を聞き、5段階評価で回答を得ました。次に、それらの合成変数としてアーキテクチャのモジュラー度(その逆はインテグラル度)を製品ごとに推定しました。
次に国際競争力の指標として同じアンケート調査で輸出比率を聞き、これを前述のアーキテクチャ変数と、従来の貿易分析で多用される労働集約度(労働分配率)で説明する回帰分析を試みました。この結果、労働集約度が高いほど国際競争力が高い傾向が示唆されました。これは仮説と整合的です(詳細は、大鹿・藤本RIETIディスカッション・ペーパー 『製品アーキテクチャ論と国際貿易論の実証分析』 をご覧ください)。
事例分析としては、自動車用鋼板、例えばドアの外板に使う溶融亜鉛メッキ鋼板と、内板に使う通常の冷延鋼板について、機能要素と工程要素の関連をマトリックス形式で分析しました(下表)。すると、日本が韓国に輸出している溶融亜鉛メッキ鋼板の工程アーキテクチャのインテグラル度が、韓国から輸入している冷延鋼板より顕著に高いことがわかりました。
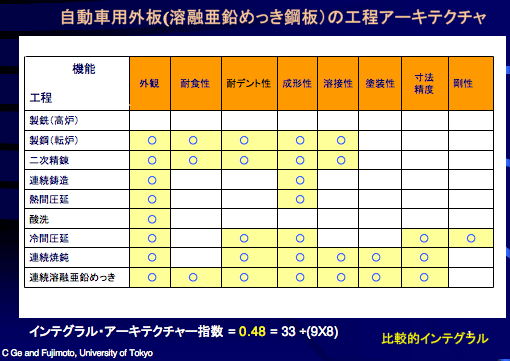
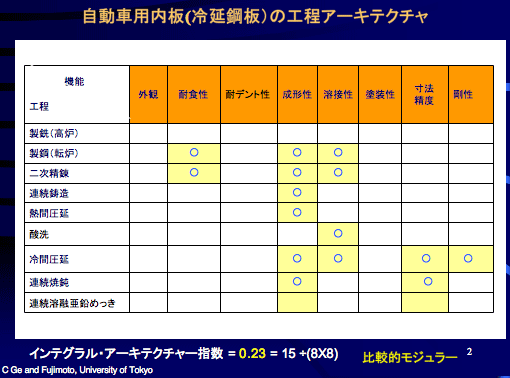
フロントランナーの支援が重要
――日本の産業政策および企業経営への本研究のインプリケーションは、どのようなものでしょうか。
第1に、現時点で競争優位性を持っている分野で負けないように努力しなければなりません。政策担当者は日本に残れない産業を残そうとする護送船団型の政策を捨てる一方で、能力構築レースで先頭を走る企業が、もっと速く走れるように官の力で条件を整備する「フロントランナー支援政策」を採用すべきです。第2に、日本企業は、比較優位を持つ現場を、長期的な競争力の見極めなしに安易に海外に移さないことです。2000年前後に多くの企業が中国に現場を移しましたが、その中には日本に残れたものもかなりあったと思います。第3には、企業や現場はあらゆる面で能力構築に取り組む必要があります。短期的には現在の強みに集中すべきですが、長期的には苦手な領域でも力をつけていかねばなりません。
――今後、どのような研究に取り組みますか。
本研究は、まだまだ探索的な段階です。膨大な労力がかかるので実行は容易ではありませんが、より緻密な調査によって産業分類と貿易統計のリンクを目指します。また、組織能力の賦存度が国によってどう異なるのか、国際的な比較研究にも取り組みたいですね。
解説者紹介
東京大学大学院経済学研究科教授、東京大学ものづくり経営研究センター所長。ハーバード大学ビジネススクール上席研究員。1979年東京大学経済学部卒業後、同年三菱総合研究所入所。89年ハーバード大学ビジネススクールPh.D取得。ハーバード大学研究員、東京大学経済学部助教授等を経て現職。2002年よりRIETIファカルティフェロー。その間にも、リヨン大学客員教授、INSEAD客員研究員も務める。主な論文は、"Architecture-Based Comparative Advantage," EIER4(1):55-112(2007)。


