日本版スチュワードシップ・コードの原則3は、「機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである」としている。機関投資家が当該企業の状況を的確に把握した結果、何が生じるのだろうか。ここでは、投資家によるモニタリングの促進という観点から、株主総会での議決権行使に着目する。2010年度以降、株主総会における議決権行使結果の開示が義務付けられるようになった。そこで我々は、東証一部に上場する3月期決算の企業(除く金融業)について、2011年6月から2014年6月にかけて開催された株主総会における取締役選任議案(約4万2000件、うち4000件が経営者選任議案)に対する議決権行使結果を収集し、計量分析を行った。
まず最初の論点は、日本企業に対する議決権行使が国際的に見てどのような特徴を持つかである。図1は、我々が収集したサンプルと、米国の議決権行使を分析したCai, Garner, and Walkling (2009)、世界各国の議決権行使を分析したIliev, Lins, Miller, and Roth (2015)の取締役選任議案への賛成率の平均値を比較したものである。
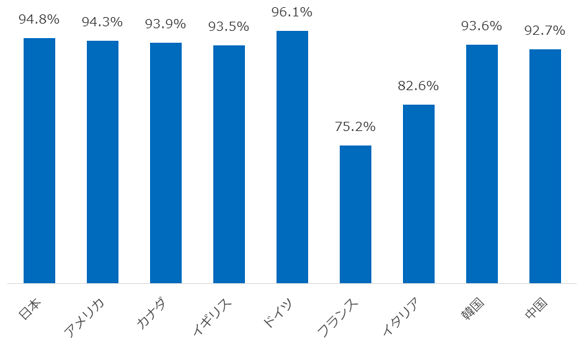
日本企業の取締役選任議案への賛成率の平均値は94.8%、標準偏差は5.3%である。経営者選任議案に限ってみても、平均値は93.9%、標準偏差は5.2%と大きな変化はない。基本的には賛成票が投じられ、反対票が投じられるのは稀であることがわかる。もっとも、日本の賛成率が例外的に高いわけではない。米国での賛成率の平均値は94.3%、標準偏差は7.7%である。また、その他の43カ国での賛成率の平均値は92.3%、標準偏差は18.2%であり、主要国のみを取り上げてみても、賛成率が90%を下回るのはフランスとイタリアのみである。このことから、基本的には賛成票が投じられるという傾向は日本に限ったことではなく、全世界で確認される現象といえる(注1)。
では、現状の議決権行使からはどのような特徴が読み取れるのだろうか。株主はパフォーマンスの低い企業に対してシステマティックに反対票を投じているのであろうか。この点を明らかにするために、取締役選任議案に経営行動に対する株主の総括的評価が示されると仮定して、同議案に対する賛成率を企業業績(ROE)に回帰するシンプルな計量分析を行った(注2)。ここで着目するのは、賛成率と企業業績の関係と、その関係が機関投資家持株比率の高い企業で強まるか(感応度が上昇するか)である(注3)。
経営者選任議案を対象とした分析結果によれば、第1に、ROEの1%の低下は、賛成率の0.18%の低下をもたらす。一見すると、企業業績は選任議案に対してほとんど影響を与えないように見えるが、推計期間のROEの平均値、標準偏差はともに約6%であるから、ROEの1標準偏差の低下は賛成率を約1%低下させることになる。賛成率の標準偏差が約5%であることを考慮すれば、ROEの1標準偏差の低下はその2割程度を説明し、実質的な経済規模を持つと見ることができる。
第2に、さらに重要なことは、機関投資家持株比率が高い企業で、この業績と賛成率の関係が強まる点である。分析結果は図2に要約されているが、機関投資家持株比率(平均値23.8%、標準偏差は15.6%)が0%、15%、30%、45%の企業では、ROEが12%の場合に、経営者選任議案の賛成率がそれぞれ95.9%、95.3%、94.6%、93.9%となる一方、最終赤字(ROEが0%)に陥った場合には、賛成率がそれぞれ94.8%、93.6%、92.3%、91.0%となる。同様の傾向は、企業業績をEBITDA、株価リターン、自己資本配当率に代えても、産業調整済みの値にしても確認される(注4)。このことは、現状でも機関投資家保有比率の高い企業ほど、適切なモニタリングの圧力が働いていることを示しており、今後、日本版スチュワードシップ・コードが定着することで、この傾向は強まると推測される。
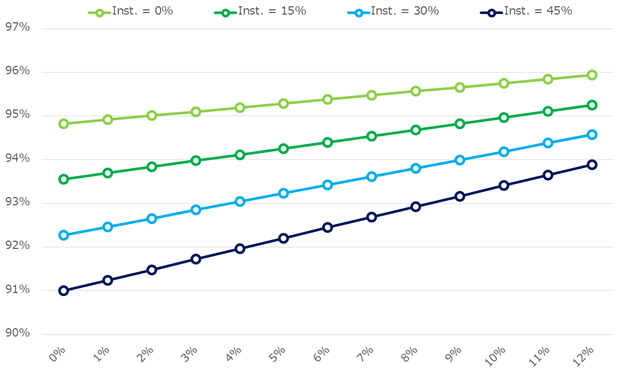
一般に、経営の規律付けのメカニズムは、発言(Voice)と退出(Exit)からなり、発言の典型例としては、アクティビズムが注目される。日本でも、村上ファンドやスティルパートナーズに代表されるアクティビズムの件数は、2006-07年に増加し、社会的にも大きな注目を集めた。しかし、その試みの多くは失敗し、急速に退潮した。この点に注目して、日本を対象とした多くの研究は、米・英のみならず、大陸欧州に比べてアクティビズムが少なく、特に、経営政策の変更などをもたらす影響力が極端に弱いことを強調してきた(注5)。また、こうした事実は、機関投資家による保有が急速に上昇したにもかかわらず、日本では、株主によるモニタリングの圧力が弱いという見方の根拠ともなっている。
しかし、議決権が企業業績を考慮して行使され、機関投資家保有比率が高い企業ほどその程度が強まるという以上の推計結果は、機関投資家が、議決権行使を通じて企業経営を規律付け始めたという見方を強く支持する。ヘッジファンドなどのアクティビストが、株主提案などを通じて企業経営を直接規律付ける経路ではなく、内外の機関投資家が、パフォーマンスの低い企業の経営者選任議案に対して反対票を投じ、その無視できない高い反対率が、企業の内部者(従業員など)の圧力を介して、経営政策の変更や経営者交代の促進をもたらす経路が機能し始めたとみることができる。我々の別の分析では、機関投資家の保有比率の水準が、企業の投資行動、財務選択、配当政策に対して実質的な影響力を持つことが明らかとされている。明示的なアクティビズムが低調な中で、機関投資家による株式保有がこうした実質的な影響力を持つのは、退出による圧力と並んで、上述の議決権行使による経路があるためであろう。



