国債相場が乱高下している。10年物国債金利は0.4%台半ばまで下がった後、一時0.7%台まで急騰し、その後も不安定な動きが続いている。国債バブル崩壊の声も一部には聞かれる状況である。ただし、短期的な変動はともかくとして、中長期でみれば国債相場の大幅な崩れはないとの見方がマーケットでは支配的なようである。
また、相場が下落(金利が上昇)したとはいっても、10年物国債金利は0.6%台で推移しており(6月25日現在)、ゼロに限りなく近い水準が続いていることに変わりはない。以下では、国債相場の先行きを予想するという手に負えない話題からやや距離をおき、国債金利がゼロの近傍で推移することを前提に、その状況下での金融政策の効果について考えてみる。
1999年以降の金融政策
まず最近の金融政策についておさらいするところから始めよう。1999年2月、日銀はコールレート翌日物(一晩の資金貸借に適用される金利)をゼロに限りなく近づけることを決定した。いわゆるゼロ金利政策である。その後、金利をゼロに近づけること自体を目標とするのではなく、通貨量を増やすことを目標と位置付け(量的緩和政策)、十分な通貨量を供給する結果として翌日物金利ゼロを維持するというスタイルへと変更し現在に至っている。
金利をゼロにする政策には2つの要素がある。ひとつは当然のことながらコール翌日物金利という超短期の金利をゼロにすることである。しかし足元の超短期金利をゼロにすることがこの政策の全てではない。もうひとつの重要な要素は超短期金利のゼロ水準をしばらくの間継続すると日銀が宣言し市場に対して約束してきたことである。具体的には「消費者物価上昇率が安定的にゼロを上回るまで」この政策を継続すると約束している。日銀によればこの約束の意図は超短期金利低下の効果を中長期の金利にまで波及させることにある。
翌日物金利をゼロにすることといい、そのゼロ水準をしばらく維持すると約束することといい、99年以降の日銀の政策は金融政策の常識から大きく逸脱しているようにみえるかもしれない。しかし実は99年以降の政策は伝統的な日銀の政策運営スタイルの延長線上にある。
日銀を始めとする先進各国の中央銀行が伝統的に採用してきた政策運営スタイルは、コール翌日物金利やフェデラルファンドレートなど超短期の金利を操作するところに特徴がある。しかし超短期の金利を上下させてみてもそれ自体が企業や家計の投資・消費行動に及ぼす効果は非常に限られている。長期の金利を変えないことには効果はない。そのため各国の中央銀行は、超短期の金利を変更する際に、更なる変更が将来行われるという予想を市場参加者の間で醸成させ、それによって長期金利に影響を及ぼすという非常に巧みな手法を用いている。例えば、日銀がコール翌日物金利を下げると、近い将来、第2弾、第3弾の引下げがあるだろうという予想が醸成される。そうするとその予想を織り込んで長期金利が低下し、それが投資・消費行動を刺激する。これが先進各国の伝統的な政策運営スタイルである。
ところが1999年以降の日本では超短期金利が下限ゼロにぶつかったため、先行き更なる金利引下げがあるという予想が成立しなくなってしまった。そこで日銀は超短期金利を追加的に引き下げる代わりにゼロの水準を常識的に考えられるよりも長めの期間継続すると約束することにより長期金利の低下を促すことを考えた。この約束は、将来の(たぶんかなり遠い将来の)超短期金利についての市場の予想値がゼロでないことに目をつけ、それを下げると約束している、つまり将来の超短期金利の引き下げ余地を「前借り」していると解釈できる。
明日の金利を下げると約束するのが伝統的なスタイルとすれば99年以降の政策は明後日または明々後日の金利を下げると約束することに相当する。その意味で99年以降の政策は、手法の細部は異なるものの、基本的には日銀を始めとする中央銀行が慣れ親しんできた伝統的手法の延長線上にあるといえる。
短期ゼロと長期ゼロの違い
では99年以降の金融政策は有効だったのだろうか。1999年のゼロ金利政策導入以降、国債金利は基本的には低下トレンドにある。6月下旬以降やや風向きに変化が見られるものの大きく見れば低下トレンドにあり、超短期金利のゼロ水準を中長期の金利に波及させるという日銀の目論見は実現されたといえる。しかしそれにもかかわらず、経済には一向に回復の兆しがなくデフレが止まらない。これは大きな見込み違いである。
もっと大きな誤算は国債金利がゼロに限りなく近くなってしまったということである。国債金利がゼロに近いということは超短期金利がかなりの長い期間にわたってゼロ水準を続けると市場が予想しそれが織り込まれているということである。その予想が既に定着してしまった以上、超短期金利ゼロの継続期間に関する市場の予想に働きかけるという99年以降の手法はもはや使えない。その意味で日銀は「前借り」さえ許されない状況に追い込まれている。
ケインズは(超短期金利ではなく)長期金利が下限にぶつかる状況を「流動性の罠」とよび金融政策運営が難しくなると警鐘を鳴らした。伝統的手法の部分的な手直しでは対処できない難しさに日銀が直面するのは実はこれからなのである。
国債価格は政府の通信簿
ここまでの理解を整理しておこう。まず国債価格(国債金利)の決定式として
(国債市場価格×発行枚数)/物価=現在から将来にわたる財政余剰の予想流列の割引現在価値《A式》
を考える。この式の意味は企業を政府に喩えるとわかりやすい。企業の株式時価総額は企業収益の流列の割引現在価値に等しい、あるいは、そうなるように株価が決まると言われている。この原理を政府に当てはめると、国債時価総額が財政余剰(プライマリーサープラス)の流列の割引現在価値に等しくなるように国債価格が決まる。これがA式の意味である。株価が企業の通信簿であるとすればそれと同じ意味で国債価格は政府の通信簿なのである。
A式の右辺を変動させる要因としては2つある。第1は財政余剰に関する予想の変化である。第2は割引率の変化である。例えば人々が経済成長率の低下を予想すると割引率が低下する。そうすると将来の財政余剰の流列が不変であったとしても式の右辺は大きくなる。
財政余剰や経済成長率の予想が変わり右辺が変化するとそれに応じて左辺が動かなければならない。この左辺の調整を担うのが金融政策である。
例として人々が財政黒字の拡大を予想するケースを考えよう。財政黒字の拡大予想が広まるとA式の右辺は大きくなる。このとき両辺をバランスさせるには国債市場価格の上昇か物価の下落(デフレ)が必要である。別な言い方をすると、財政黒字の拡大予想が広まる中でデフレを回避するには国債市場価格の上昇が不可欠である。この国債価格の上昇は金融緩和、すなわち中央銀行が超短期金利を引き下げ、それによって将来も超短期金利が下がるという予想が広まることにより実現される。
別な例として今度は人々が経済成長率の低下を予想するケースを考えてみよう。経済成長率の低下予想が広まると割引率が低下する。このときには将来の財政余剰の流列が不変であったとしてもA式の右辺は増加する。つまり、経済成長率の低下によって株式など民間発行の証券の収益率が低下するため相対的に政府債務の魅力が高まるということである。このときにも前の例と同じく中央銀行の金融緩和は国債市場価格の上昇を通じてデフレを防ぐ効果がある。
この2つの例からわかるように、金融政策の要諦は、様々なショック(経済成長率などに関する人々の予想の変化)を国債市場価格の変化で吸収することにより物価への影響を遮断することである。先進各国の中央銀行が伝統的に長期金利への働きかけを重視してきたという事実はこれと平仄があっている。また99年以降の日銀の政策も長期金利への働きかけに重点が置かれているという点で同種の政策とみることができる。
しかし国債金利がゼロまで低下してしまうとこの原理が働かなくなる。国債価格が上限のところで釘付けになっているため右辺を上昇させるショックを国債市場価格の上昇によって吸収することがもはや不可能になるからである。このときには右辺の上昇は専ら物価の下落(デフレ)で吸収しなければならない。これが「流動性の罠」の怖さである。
米国の国債価格支持政策の教訓
国債金利ゼロの経済ではこの理論予測どおりのことが本当に起きるのだろうか。この理論予測はA式に基づくものであり、A式自体は単純な裁定式である。株価が企業収益の予想で決まることを否定するのが難しいのと同じ程度にA式の成立を否定することは難しい。
それに加えて、中央銀行が国債市場価格の制御を放棄したときに何が起こるかについては既に有名な実験が行われている。米国で1942―50年に採用された「国債価格支持政策」がそれである。
国債金利ゼロが続くということは国債価格が一定の値で固定されるということであり、これは一種の国債価格支持政策である。もちろん、米国の国債価格支持政策は財政面の理由(戦費調達に伴い国債が大量に発行される中で国債価格が下落するのを回避する)から意図的に国債価格を固定させようとしたものであるのに対して日本の国債価格支持政策は仕方なしの消極的な選択であり、その点で異なっている。しかし国債価格を一定値で固定するという点では両者は同一であり、40年代の米国の経験から学ぶべき点は多いはずである。
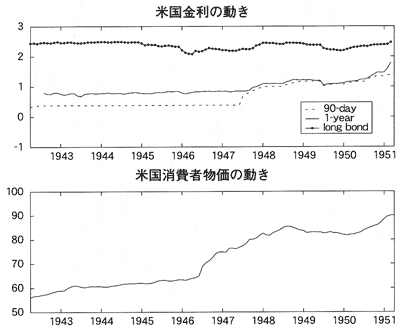
米国の経験を振り返ってみよう。図はこの時期の米国の金利と消費者物価の動きを示している。金利の動きをみると、満期90日の財務省証券の金利が1942年以降3/8パーセントの水準で固定されているのがわかる。他の満期の財務省証券については90日物ほどはっきりと読み取れないが、設定された目標値の周辺で安定的に推移しているのがわかる。一方、この時期の消費者物価はダイナミックな変動を示している。消費者物価は1946年から1948年にかけて激しく上昇した後、1948年には下落に転じ、1950年初まで下落を続けた。そしてその後1951年にかけて再び上昇している。
消費者物価の複雑な変動はなぜ生じたのだろうか。プリンストン大学のウッドフォード教授は最近の研究でこの時期の消費者物価の複雑な動きは財政余剰(あるいはその逆の財政赤字)に関する人々の予想の変化によって説明できると主張している。
まず1946―48年のインフレは戦時下での財政赤字の拡大予想を反映したものとみることができる。財政赤字の拡大予想が拡がるにつれて人々は国債を持ちたがらなくなる。このとき本来であれば国債が売られ国債市場価格が下落する(金利が上昇)ところであるが、中央銀行が国債の市場価格を力ずくで固定する政策を採用しているため国債市場価格は低下せず国債の売り圧力は収まらない。A式が教えるように、国債の売り圧力を解消するには、物価が上昇し、それに伴って国債の実質価格が下落することが不可欠なのである。
次に1948―50年のデフレについては、戦争の終結とともに米国の財政赤字が急速に縮小し財政黒字に転じるなかで進行したという事実が重要である。財政の好転に伴って将来の財政余剰の改善予想が広まった結果デフレが生じたと解釈できる。また、1951年にかけてのインフレ再燃の背後には朝鮮戦争の勃発がある。新たな戦争の勃発に伴い再び財政負担が高まるとの予想が発生し、それがインフレ圧力として作用したとみることができる。
ここから得られる重要なレッスンは、1940年代の国債価格支持政策は中央銀行の手足を縛ってしまったということである。中央銀行が国債市場価格を裁量的にコントロールできる状況であれば、インフレ圧力に対しては国債市場価格を低下させ(金利引上げ)、デフレ圧力に対しては国債市場価格を上昇させる(金利引下げ)ことにより物価への影響を遮断できる。A式でみたように、これが金融政策の原理である。しかし国債価格を予め定められた水準に維持するよう中央銀行が要請されている場合には、ショックに対応して裁量的に国債価格を変化させることができず、その分、物価の変動が大きくなってしまうのである。
財政の役割
米国の国債価格支持政策は1951年3月に財務省と連邦準備制度の間で「アコード」が成立することをもって終了する。アコード成立の背景には、物価変動の原因が国債価格支持政策にあるとの認識がポリシーメーカーの間で持たれるようになったことがあると言われている。米国の国債価格支持政策は、当局がその気になれば終了させることが可能な政策であり、その意味ではまだ扱いやすい。それに比べると日本の国債価格支持政策(国債金利ゼロ)は中止しようにもできないという点で数段難しい問題を抱えている。
国債金利ゼロの経済でデフレを回避するにはどうすればよいだろうか。A式は2つの方法があり得ることを我々に教えてくれる。第1は財政余剰の削減である。デフレは銀行券や国債など公的債務に対する需要が強いことの反映である。財政状況が厳しいとはいっても民間経済に比べればまだless badな状況であると人々が認識しているために資金が公的債務に流れていると考えられる。この流れを止めるには財政状況を民間経済並みのレベルまで悪化させそれによって右辺を小さくするというのがひとつの方法である。
ただし、2人の学生の出来に差がありすぎて通信簿の評点がアンバランスになっているときに出来のよい学生(政府)に「あまり勉強するな」と忠告するというのは誉められた解決策ではない。当然のことながら、出来の悪い学生(民間)に「もっと勉強しろ」と発破をかけるのが理想的な対処である。つまり民間経済の成長を回復させるのが最善の方法である。経済成長率が回復するという予想を人々の間で醸成させることができれば割引率の上昇を通じて右辺が小さくなりデフレ圧力を消すことができる。政府や日銀に求められているのは日本経済復活の道筋をはっきりと国民の前に示すことである。

