イベント概要
議事概要
開会挨拶
高橋 千秋 (経済産業大臣政務官)
水産物は、日本人の食生活・食文化において欠かせないものであるが、水産物の安定供給を担うべき我が国の水産業は、現在非常に厳しい状況にある。水産業の経済状況は、同じ一次産業である農業と比較して、より深刻であり、また高齢化が著しい。このため、水産業をどのように生き残らせていくかは、産業政策としても重要である他、資源を守るという持続可能性という意味でも重要である。
本セミナーは、RIETIにおける「水産業における資源管理制度に関する経済分析研究会」の2年に渡る活動成果を発表し、政策的な議論を喚起することが目的と聞いている。私の出身は三重県で水産業の盛んな地域であり、大学は農学部の出身であることから、個人的にも今回議論される内容に非常に関心を持っている。本日の議論により、学術的な分析に基づいた示唆が得られることを期待している。セミナーの開催に尽力された関係団体・学会に感謝を申し上げたい。
基調講演
水産業の危機と再生策
小松 正之 (政策研究大学院大学教授)
日本の水産業は、漁獲量の減少・資源の悪化・経営の悪化など、負のスパイラルに陥っている。このような状態に陥った根本的な原因は、既存の法制度が漁業者による水産資源の乱獲を防止できる仕組みになっていない点にある。
現在の漁業法は、戦後民主化が進む中で中小資本漁業の育成を目的として制定されたものであり、資源の科学的管理の概念に立脚したものではない。従って、各漁業がそれぞれ、どれだけ、水産資源を漁獲すべきかの計画が全くない。沿岸漁業と中小資本漁業をそれぞれ明確に区分しつつ、かつ同一資源を漁獲するものについての総合的管理の概念や、養殖業と漁業並びに遊漁と漁業の一体的管理の概念などが欠如している。政府は高度経済成長期から現在まで、所得の格差是正を名目に根本的な漁業制度改正を伴う資源悪化の解決を先送りにしてきた。
日本の水産業の再生策としては、厳格な科学的根拠に基づいた最大持続生産量の設定と、個別漁獲枠制度の導入が推奨される。諸外国との漁業条件の違いについては、グループ割当の導入や1人当たり漁獲枠の小量の上限設定などによって柔軟に対処することが可能である。それを後押しする法改正も重要である。
水産資源は国民の共有財産である。漁獲を行う権利は引き続き漁業者が持つとしても、水産資源の管理には国民が関与していく必要がある。その一方で、行政庁や科学者にはわかりやすい情報提供責任が求められる。
排出量取引制度について
柏原 恭子 (経済産業省産業技術環境局環境経済企画調査官)
地球温暖化問題において、CO2 排出削減のために経済的手法をいかに活用するかという議論が活発になされている。経済的手法の主なものは排出権取引制度と環境税だ。
排出権取引制度とは、排出枠に価格をつけて、排出削減に対する経済的なインセンティブを与えるという制度である。現在、国内で導入に向けた議論が行われているのは、排出主体に排出量に関する上限を設定し、その目標達成のために排出枠の取引を認める、キャップ&トレード方式の排出量取引制度である。
キャップ&トレード方式の排出権取引制度を導入する際に問題となるのは、削減義務を課す対象の設定と、排出上限の設定方法である。EUでは、初期配分方法として、過去の実績に基づいて配分するグランドファザリング方式を用いてきた。この方式の欠点は、過去に削減努力をしてこなかった事業者ほど多くの枠をもらえることに対する不公平性や非効率性、また、新規参入者の枠をどのように設定するかといった課題が挙げられる。より公平性を目指した無償配分方法として、ベンチマーク方式があり、また、有償のオークション方式はもっとも公平・効率的とされるが、事業者にとっての負担が大きいため、世界全体で導入しない限り国際競争力への悪影響や炭素リーケージの問題が生じる。
排出枠の取引市場についてみると、実際の取引量に占める実需の割合は1割程度という分析もある。投機的な行動を抑制しつつ、実際の削減にどのようにつなげていけるかが課題となっている。
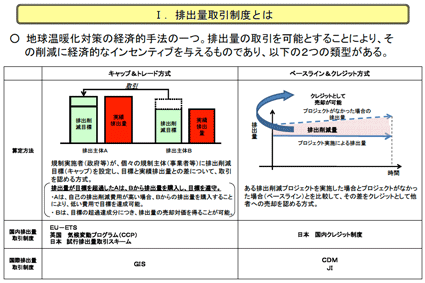
[ 図を拡大 ]
研究成果報告セッション
水産業界の歴史:国内における政策と産業の変遷
黒倉 壽 (東京大学大学院農学生命科学研究科教授)
本発表では、議論の前提として水産の制度史および技術史を概観し、現在の制度がどのような歴史的過程で成り立ち、機能してきたのかを確認する。
制度史についてみると、大宝律令において水産資源が共有財として位置づけられている。その流れの中で、江戸時代になると沿岸漁業に関する地域社会の権利が認められた。明治維新の際、政府は海面の官有宣言を行ったが、さまざまな混乱の末に1年後には取り消した。これにより、従来の慣行漁業権はそのまま認められ、現在まで続いている。
技術史については、江戸時代に畿内の進んだ技術が日本各地に広まった。明治以降になると編綱機開発による定置網の登場など大幅な技術進化を遂げた。しかし、技術の進展に伴って漁民同士の抗争が激化し、多くの事件が発生した。このような抗争は、外延的に漁業が拡大することによって最小限に抑えられた。
しかしながら、1972年のローマクラブの「成長の限界」に象徴されるように、漁業の外延的拡大にも限界が訪れた。そのため、漁業の内部的調整の中で利益をあげる方策が必要とされている。
コメントおよび質問
Q(山下東子教授(明海大学))
黒倉教授の発表は、1)現代の政策は過去の政策の反復である、2)現代の諸問題は過去の政策の失敗から生じている、3)過去には予想もしなかったことが現代には起こっている、という3点に集約されるのではないか。加えて制度や漁業勢力の変遷が資源量の変動と相互に影響を及ぼすと思われるが、なぜ資源には言及されなかったのか。
A(黒倉教授)
漁業管理に必要なのは、精緻な資源解析モデルではなく漁業者を管理するための方策であるので、今回は資源については言及しなかった。
日本における水産エコ・ラべリングの発展可能性:インターネットサーベイによる需要分析
森田 玉雪 (山梨県立大学国際政策学部准教授)
水産エコラベルとは、適切に管理された漁場から得られた魚に対する認証を与えるものである。水産物に限らず、日本では海外に比べてエコラベルの普及率が低い。その原因を探るため、日常的に食品を購入している消費者を対象とするインターネットサーベイ(「お魚の購入に関するアンケート」)を行った。
アンケートの結果、消費者が購入時に重視する点としては「鮮度」や「安全性」が挙げられた。一方で、「環境配慮」や「トレーサビリティ」に関して「わからない」という回答が多いことから、これらに関する関心は高くない、もしくは購買行動と結び付けられていない、といえる(図2)。
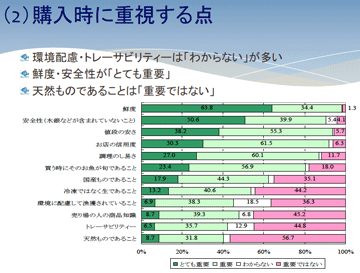
[ 図を拡大 ]
資源量(食用魚の存在量)に関する情報と認識の変化について、回答者にζ:一般的な情報、α:ζ+国際機関による情報、β:ζ+科学雑誌の情報、の3種類のうちのいずれか1つを読んでもらうことにより、情報の前後で回答者の認識に変化が生じるか否かを調査した。いずれの情報を読んだ人も、情報を読むことにより認識が変化したが、このことは、消費者の現在持っている情報量が少ないことを示している。
また、エコラベルに対する追加の支払い意思額(WTP: willingness to pay)は、情報αを読んだ人が最も高いという結果となった。情報αに対する評価は、「興味深い」あるいは「信用できる」で、そうした情報が消費者のWTPを押し上げる効果が高いとみられる。
水産エコラベル普及の要件としては、1)水産資源の減少についての消費者の認識が高まるように、消費者が資源量に関する情報に触れる機会を増やすこと、2)消費者に伝える情報の内容は、「興味深い」「信用できる」ものであること、3)1)~2)の前提として、ラベル不信を解決し得るような制度設計をすること、が挙げられる。
コメントおよび質問
Q(山下教授)
日本では蓄積の無い分野の新規開拓であり、貴重な研究であると評価する。(1)なぜ回答者から団塊の世代を除いたのか、(2)天然物ラベルは魚の保護を意味するのに対し、養殖物ラベルは環境汚染をしていないことを意味しており、両者の意味合いが異なることが回答とその分析上問題になるのではないか、という点を問いたい。
A(森田准教授)
インターネットサーベイでは、登録者の分布の問題から団塊の世代を入れることが困難であるため、やむなく除外している。天然物と養殖物でラベルの意味合いが異なるのは確かであるが、本研究では養殖物に貼るラベルの条件を、餌となる小魚の過剰漁獲をしないことや抗生物質を周囲に拡散させないことなどを通じた「海洋資源・環境保護」として、天然物と統一している。
ITQの効率性と漁船規模の選択-実験経済学的アプローチ-
東田 啓作 (関西学院大学経済学部教授)
ITQとは、まず総漁獲枠を設定し、それを個々の漁業者に配分し、漁業者にその割当を取引する権利を認めた制度である。ITQの導入によって、理論的には、よりコストの低い漁業者に漁獲割り当てが集まるとともに、効果的な資源管理の効果が期待されている。本研究では特にITQ導入下で効率的な市場取引が実現するか、また漁船の規模が合理的に選択されるかを実験経済学の手法によって検証した。
各被験者は、始めに大きい漁船か小さい漁船かを選択する。大小それぞれの漁船には、漁獲量に応じた費用、利益が設定されている。次に、被験者に適当な初期配分を与え、パソコン上で3分間自由に漁獲枠を売買してもらう。このような過程を10回繰り返した。
実験の結果、実際の取引価格は理論値に近づいていくが、その過程には一定の時間を要することが明らかとなった。また、過去の平均取引価格が理論価格と比べて高いほど、規模の小さな漁船を選択する可能性が高かったことから、漁船規模の選択は合理的に行われることがわかった。さらに、初期時点の取引価格は、その後の取引価格や漁船の選択に影響を与えることも示された。
コメントおよび質問
Q(有薗眞琴氏(元山口県水産研究センター所長))
今後、我が国がITQ制度の導入を検討する上で、示唆に富んだ研究である。質問としては、(1)均衡価格に到達する時間を短縮する技術的対策はあるか、(2)現実的にはTACや漁船数は徐々に変化していくと考えるのが妥当であるが、その場合でもITQは機能するか、を問いたい。
A(東田教授)
均衡までの時間短縮には、漁獲枠を資産として認識されないように、リースを導入するということが考えられる。また、徐々に変化する場合でも単年ごとに当研究で明らかにしたメカニズムが機能すると考えられる。
日本の漁業における費用削減の可能性
馬奈木 俊介 (RIETIファカルティフェロー/東北大学大学院環境科学研究科准教授)
本研究では、日本の漁業を地域・漁業種類・魚種によって細かく分類し、その効率性の分析を行った。分析の結果、TAC(総漁獲可能量)対象の魚種全体でも魚種ごとでも、漁業の効率性は0.11~0.14程度となった。これは、投入量の9割近くが無駄になっているということを意味する。デンマークやその他の国々の漁業の効率性は、総じて0.7程度であるとの分析結果からも日本の現状を捉えることができる。すなわち、現在の日本の漁業者数は過大であり、10分の1程度にまで減らすことが可能であると結論できる。またこの結果は、漁業関連の予算を4000億円程度削減できることを意味している。
以上の分析結果は、日本漁業のポテンシャルの大きさを示している。したがって、多少の導入コストをかけてでも、市場メカニズムを用いた適切な管理を導入することの意味は大きい。ITQ導入にかかるコストとして3億円から30億円までの試算がされているが、毎年4000億円の削減効果と比較すれば問題ではない。
コメントおよび質問
Q(有薗氏)
本研究は、ITQが大きな費用削減効果を生むことを示し、こうした解析手法による計画立案と実行が必要であることを提唱している点で先導的なレポートである。質問としては、(1)分析期間中に国連海洋法条約の発効等、資源アクセス環境の変化があったと思われるが、その影響は如何か、(2)資源に関する情報を入れることでモデルの信頼性を増すことができないか、を問いたい。
A(馬奈木准教授)
コスト削減の数値は2004年のセンサスに基づく試算であるので、さまざまな政策があった後のデータを使用している。資源状態については、2004年よりも資源状態が悪化しているとすると、本研究の結果はさらに厳しく更に大きい削減効果となる。すなわち、本研究の結果は非常に保守的な結果であり、現実はより悪い可能性がある。
パネルディスカッション
最新のITQ導入例の評価について-ペルー共和国
原田 厚 (日本水産株式会社海洋事業推進室室長)
ペルーでは、昨年2009年にITQ制度が導入された。現地の経済新聞(El Comercio Peru 2009年8月24日)によると、ITQ制度導入の評価を下すのは時期尚早かもしれないと留保しつつ、漁期開始の集中漁獲が減少したこと、操業隻数の平準化、水揚鮮度の向上、製品歩留りの向上、水揚げ魚価の上昇など当初期待された成果が確認されたと指摘している。これにより国際的な魚粉価格の高騰につながり、日本の魚粉買付量は減少傾向となっている。日本近海でまだ利用可能な資源としてサンマ資源があるが、200海里外では台湾、ロシア、韓国、中国がサンマ漁業を行っている。資源状態の良好なうちに日本漁船がサンマ資源から十分な収益を上げられる構造を作る必要がある。漁業・加工・養殖・流通・販売を組合わせたサプライチェーン協働のビジネスモデルを作り上げることが重要であると考える。
ITQの検証-ニュージーランド
大西 学 (立命館大学衣笠総合研究機構ポストドクトラルフェロー)
ニュージーランド(NZ)では、日本と同様に水産資源保護と水産業健全化の2つの課題に直面し、その解決方策としてITQが導入された。2009年時点でその管理対象魚種は96魚種にも及んでいる。
ITQが導入された結果、多くの水域・魚種で生産可能フロンティアは向上し、生産性が改善していた。一方、超過漁獲には罰金が主要な措置となっており、TACの変更は入札によって選定された民間業者の調査結果を考慮していることがうかがえた。また、漁獲枠は上位10社で約8割を保持しているものの、新規参入が不可能というわけではないことがわかった。
日本にITQを導入する上で考慮すべき点について
勝川 俊雄 (三重大学生物資源学部准教授)
ITQは、日本漁業の管理には適さないという議論がある。しかし、ITQの本質は、経済的な無駄と資源へのダメージを生じさせる先取り競争の抑制のための漁獲権分配と、その後の権利の流動性をどう確保するかという点にあり、細かい運用方法は国によって柔軟に変化させることができる。たとえば、漁業で高利益を出しているノルウェーでは漁業者の権利が強いため漁獲枠は漁船に付属しており、漁業者以外が漁獲枠の取引に参加することはできない。そのため、経済効率面での効果は劣るけれども、社会的な面を重視した制度になっている。一方で、アイスランドやニュージーランドでは漁獲枠の取引の自由度がより高く、経済効率を重視した制度といえる。
日本でも先取り競争が問題となっており、個別枠の導入は避けられない。ただし、その先の経済効率と地域の雇用などのバランスについては議論していく必要がある。
日本に適合する管理手法を
大橋 貴則 (水産庁漁政部企画課動向分析班課長補佐)
ペルーやNZでは、漁業は外貨獲得産業という位置づけであるため、効率性の追求が重要視されている。日本の場合も、漁業の産業としての位置づけをどうするかによってITQ導入などの管理方針が変わってくる。日本漁業の管理を考える上で参考になる国はアメリカである。NZやアイスランドは北緯がかなり高度で日本とは地理的位置が異なるが、日本とアメリカは共に南北に長く、多くの魚種を漁獲対象としている。アメリカでは地域ごとに管理目標を定めており、地域ごとに独自のITQを導入している。たとえば、一部の地域では枠の保有率や取引に制限を課しているが、これは、資源に対しては過剰な漁船隻数で効率性の点では劣っていても、社会経済的な観点からみるとその地域にとってはそれが望ましいという判断によるものである。日本でも地域ごとに漁業の特性は異なるので、地域ごとに管理目標を定めた上で、その後の手段を検討する。ITQを導入するのであれば日本に適合する管理手法を議論しておく必要がある。
地域の多様性に応じる必要性
八木 信行 (東京大学大学院農学生命科学研究科特任准教授)
現在の経済学は効率性という指標を多用する。これは効率性が数字で表しやすいことに起因する。しかし、世の中には効率性以外にも公平性、平等、安定などのような価値判断基準も存在する。漁業は産業としてだけではなく社会生活のような側面も持っているため、効率性という指標のみで議論することには問題がある。
また、日本へのITQ導入について議論があるが、全ての漁業にITQを導入することには反対である。日本では地域ごとにさまざまな自主的な取り組みがなされており、ITQを導入している地域もあれば、オリンピック方式を採用しているところもある。そのような地域ごとの多様性を認めることが重要である。
漁業が直面する課題は魚価上昇と資源回復の2つである。この2つを達成するのに、ITQは1つのオプションでしかない。その他にも、たとえばサクラエビのプール制などのように、多様な選択肢を検討すべき。ただし、資源の回復を考える場合には、干潟や藻場の減少などの外部性を考慮した議論をする必要がある。

