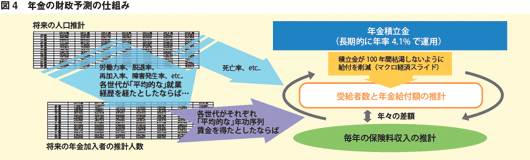イベント概要
議事概要
日本の労働市場が直面する問題は複雑だ。労働市場の構造的な問題が、未曾有の経済危機という循環的な局面で顕在化する中、危機後の雇用システムや労働市場の「かたち」の検討が求められている。雇用・労働システムを再構築して創造と活力を取り戻すために必要なことは何か。RIETIでは、2010年4月13日に政策シンポジウム「雇用・労働システムの再構築:創造と活力溢れる日本を目指して」を開催(東海大学交友会館)、学界、企業、労働、民間シンクタンクの有識者を招いて、雇用情勢の現状や雇用の出口戦略、雇用・労働システムの再構築について議論した。
総論「雇用・労働システムの再構築:雇用危機と労働市場の二極化への対応を中心に」
鶴 光太郎 (RIETI上席研究員)
シンポジウムの問題意識
現在の危機的な雇用問題を、どのようにして危機モードから平時モードに戻すのか。これまでの短期的な視点からの雇用政策を評価し、今後の「出口戦略」を考える必要がある。
一方、中長期的な視点から、労使ともにインセンティブを高めあえるような雇用・労働システムに再構築する必要もある。労働市場の二極化がいわれているが、よりマクロの視点から効率的な労働再配分を行い、人口減少・高齢化問題の克服、産業政策・成長戦略を両立するような雇用創出を目指すことが必要ではないか。
さらに、グローバル競争激化の中での空洞化の問題への対応や、イノベーションを促進させる働き方を労使でどう確保していくかなど、政府として包括的な雇用戦略を考えていかなくてはいけない。
短期的な視点:雇用情勢の現状と評価、出口戦略
2001年~2003年頃の雇用調整期(景気低迷期)と比べ、今回は労働時間・賃金と特に非正規労働者による雇用調整が大きいという特徴がある。一方、正規労働者については、希望退職の募集や解雇は前回ほど行われておらず、調整は比較的少なかった。これは雇用調整助成金の影響によるものと考えられる(図1)。
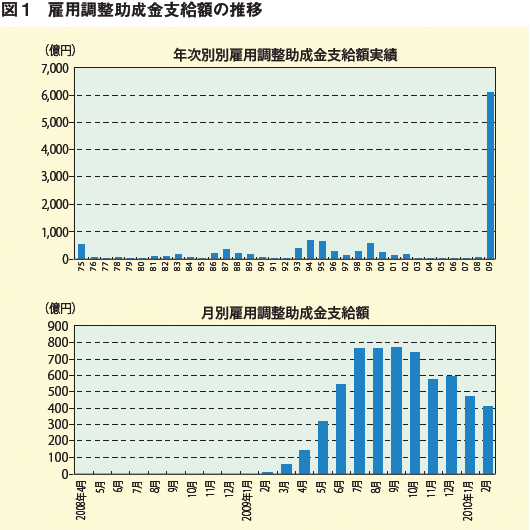
雇用調整助成金の支給規模は、第一次オイルショック時や90年代の金融危機後でも年間600億円前後だったが、2009年度は6,536億円と大幅に拡大された。ただ、こうした政策は持続可能とは考えづらいことから、新たな出口戦略を視野に入れる必要がある。
中長期的な再構築:企業と労働者の視点から
企業は非正規労働者の問題を十分に内部化しているのだろうか。確かに有期雇用は不確実な経済のバッファーとして企業を支えるが、有期雇用を多用することによって生産性が下がる可能性を企業自身が見過ごしていないか。労働コストの低い有期雇用は、国全体の人的資本を劣化させ、企業の利益にも跳ね返ってくるというリスクがある。ヨーロッパでの実証分析では、有期雇用から正規雇用への転換の可能性が高い企業ほど生産性は高くなるという結果がでている。
非正規の問題をどう考えていくか。RIETIが行っている「派遣労働者の生活と求職行動に関するアンケート調査」 (2009年1月以降、3回実施)によると、非正規労働者の幸福度は雇用契約期間が長ければ長いほど高くなる傾向にある。また、単身の非正規労働者の幸福度は低く、結婚などによって家族を持つことは固定費の削減などのリスクシェア効果もあり、幸福度を上げることがわかった。
登録型派遣で働く労働者に登録型派遣の原則禁止について尋ねると、反対する人が賛成する人を大きく上回るという結果を示した(図2)。また、常用型への転換よりも、登録型派遣を続けたいと希望する労働者の方が多いなど、多様な志向に応じたきめ細かな対応をする必要があることに留意するべきだ。
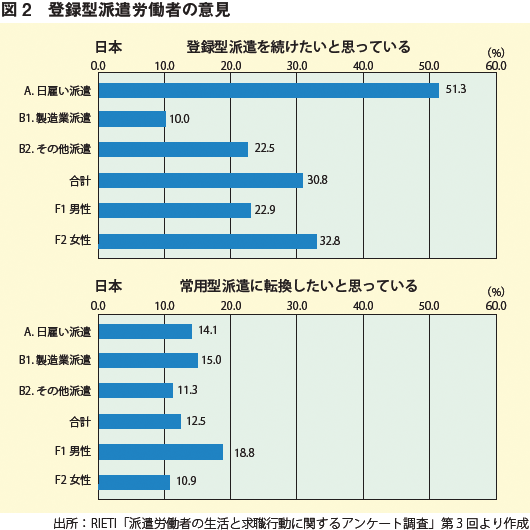
分断された二極化から連続的な制度へ
正規労働と非正規労働の極端な二極化の間を埋めるにはどうすればよいのか。1つの方法は、中間的な雇用形態として原則5年や10年までの有期雇用契約を認めることだ。その一方で、期間の定めのない正規雇用についても、「何でもやれる社員」と捉えるのではなく、勤務地や職種を限定するケースを許容するなど多様性を確保するべきだ。
さらに、雇い止めに関する労使の認識ギャップを縮め、同時に有期雇用期間に比例した処遇や、雇い止めによるトラブルを金銭解決する仕組みの導入を検討することも重要だ。加えて、非正規労働者の意見を反映させるためのメンバーシップ化も行う必要がある。
かつては企業に恩恵を施すことで、それが最終的に家計へも行き渡った。企業を通じた所得の再分配機能が低下したことで、政府には、より直接的な分配機能が求められていることが十分に認識されるべきだ。
報告
報告1「包括的高齢者パネルデータの必要性:労働政策の実証による評価を例として」
市村 英彦 (RIETIファカルティフェロー/東京大学大学院経済学研究科教授)
世界が注目する日本の高齢化
高齢化問題について、15~64歳人口と65歳以上の人口比である従属人口比率でみてみると、高齢化は日本だけでなくアジアおよび欧米諸国で急速に進んでおり、世界共通の問題であることがわかる。
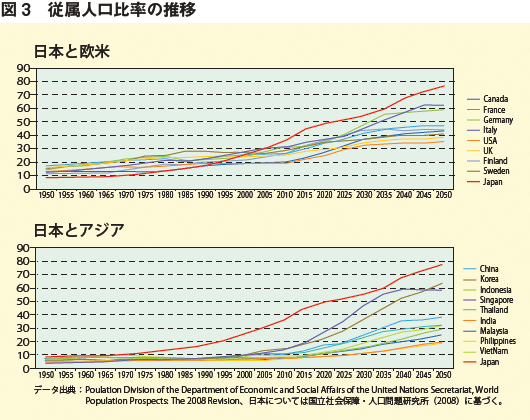
その中でも、日本の高齢化は多くの点で注目を集めている。第1に、他の欧米諸国と比べ、日本の男性高齢者は労働参加率が高い。第2に、アジア諸国の労働者の年齢構成は日本に近づいてきており、日本はアジアのベンチマーク・ケースとして扱われている。第3に、欧米では障害者保険の利用率が近年増加しているが、日本は低率にとどまっている。
高齢者パネルデータの構築
高齢化社会への対応という点では、欧米各国、メキシコ、韓国など多くの国では、今後さらに高齢化が進行することを見越して、すでに高齢者データの整備が進められてきた。たとえば、アメリカでは1994年にHRS(Health and RetirementStudy)が始められ、HRSのデータを活用した研究は1400本を超える。米政府の社会保障改革はHRSの裏付けが必要とされているが、日本では高齢者の実態を把握するデータが整備されてこなかった。
こうした中、RIETIは2005年に「社会保障問題の包括的解決をめざして:高齢化の新しい経済学」プロジェクトを立ち上げて、50~75歳の方を対象とする「くらしと健康の調査」 (JSTAR/ Japanese Study ofAgeing and Retirement)を開始した。
JSTARは、2005年のパイロット調査を経て調査方法の改善がなされ、現在までに2007年と2009年の2回の調査が行われた。また、調査対象都市については、RIETIが実施する2地点に加え、高山憲之教授(一橋大学)の特別推進研究「世代間問題の経済分析」などの他の研究機関に同じ手法で調査実施していただいたデータと合体分析することにより、第2回調査では第1回の5地点に2地点を追加した合計7地点をカバーしている。調査項目は各国の調査と比較可能な形で設計している。具体的には、本人や配偶者の就業状態・医療介護サービスの利用状況だけでなく、記憶力・認知力のテスト、基本生活力の把握などで、さらにJSTARの特徴として栄養調査の項目を加え、幅広い内容となっている。回収率は、第1回が60%、第2回が74%であり、世界の標準を維持している。
現実と政策議論の乖離
これまではJSTARのような包括的調査による実態把握がないため、社会保障政策などさまざまな政策を具体化する際に行われる議論は、本当に必要なサービスが何かではなく、財政面に特化されることになる。また、財政面を検討する場合にも、データに基づかない非現実的な想定のもとで議論が進められがちだ。
たとえば現在の年金財政予測では、人々の多様性は捨象され、現時点で観察される平均的な職歴、所得、障害発生確率などを仮定された「平均的個人」が想定されている(図4)。しかしJSTARのデータからも明らかなように、現実にはさまざまなタイプの家計や個人が存在するため、平均的な姿が代表的な姿とはいえない。また、現在20歳の人が、今後、今の21歳以上の平均的個人と同じの人生経路を歩むと想定する定常性は満たされない事が多い。世代内と世代間の多様性を考慮した分析が必要だ。また、政策が変更されると人々の将来の行動も変わる。国内外で多くの研究があるが、たとえば樋口他(2006)は支給開始年齢の引き上げが高齢者の労働供給に正の影響を与えてきたことを示している。このような効果は年金財政予測に反映されていない。
さらには、疑似パネルには問題があることを示す研究もあり、パネルデータの重要性は高まっている。
これまで、政策立案プロセスにおける想定や政策そのものの誤りを正す仕組みは無く、なされる政策を後付けで正当化する分析ばかりが強調される傾向があるのではないか。
開かれた政策の議論を
日本でも世界標準の包括的なパネルデータの整備を進め、個人や家計レベルでの多様性を持つ行動モデルの推定を行い、その結果を基にした政策を吟味する必要がある。
社会保障政策が多くの人々の暮らしに直結していることを考えると、重要な政策は、省庁内で数人の学者と行政官のみで政策を議論するのではなく、できるだけ開かれた形で、データを共有しながら議論を進めるべきだ。たとえば、公募により3つ程度の専門家グループを組織し、必要なデータを供与して分析を依頼することも一案ではないか。
また、米国ではHRSに限った論文だけでも1400本を超えているという現実がある。現状改善には、パネルデータ構築とともに、きちんとした分析を支える政府内外の人々の教育も重要だ。
報告2「日本の労働と生産性、経済成長」
深尾 京司 (RIETIファカルティフェロー/一橋大学経済研究所教授)
経済成長の源泉と労働の関係
RIETIは一橋大学のグローバルCOEプログラムと協力して、日本の経済成長と産業構造変化を分析するための基礎資料である、日本産業生産性データベース(JIP/ Japan Industrial Productivity Database)の改訂と更新を進めている。
1970年から2006年までのデータ整備を完了しているので、長いスパンでの分析ができるとともに、EUやハーバード大などとの連携により国際比較も可能となっている。
日本の人口1人当たり実質GDP成長率は1990年を境に、1975-1990年比で4%から1%まで下落し、その状態が2006年までの16年間続いている。
1人当たりGDP成長率を4つの要因(全要素生産性(TFP)、資本労働比率、労働の質、1人当たり労働時間の投入(マンアワー))に分解することにより、成長の源泉がどこにあるのかを明確にすることができる(図5)。1番大きなGDP成長率の低下要因は全要素生産性の低下にある。しかし、GDPの成長は労働と関係する部分も少なくない。特に、人口1人当たり労働時間の投入が以前と比べて低下したことはGDP成長率を減少させる大きな原因となってきた。
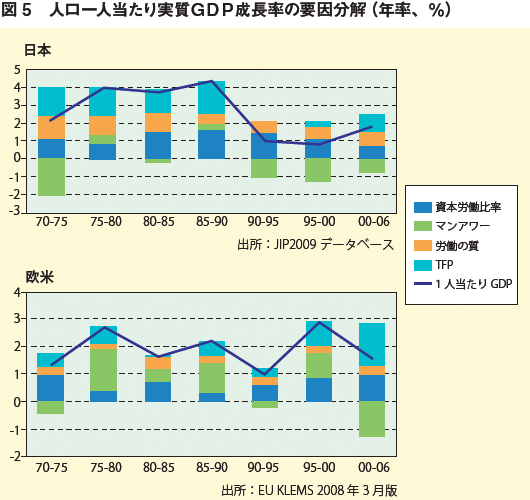
アメリカでは、95年以降に情報通信革命が起きて2006年まで高い成長率が続いたが、その最大の源泉は全要素生産性の成長。日本では、資本労働比率と労働の質が労働生産性(全要素生産性・資本労働比率・労働の質で構成される)の上昇に寄与してきたといえる。
しかし、労働生産性の上昇率自体に日米で大きな差があるわけではない。90年以降の日米の1人当たりGDP成長率の差は、むしろ人口1人当たり労働時間の日米差と実質為替レートの円安化で説明される部分が大きい。
非正規雇用による労働コスト削減と生産性の損失
人口1人当たり労働時間の投入が減った要因としては、第1に、人口1人当たりの就業者数の低下が挙げられる。2000年代以降、高齢化や不況を背景に女性の労働参加率が低下したことや、団塊世代も労働力から退出したことが影響している。日本の人口1人当たり就業者数は最近では大幅な減少傾向にあり、年率0.4%ずつ減っている。第2は、雇用者の平均労働時間の減少が挙げられ、改正労働基準法の影響のほか、非正規労働者の雇用増も大きな要因と考えられる。
また、パート労働者の増加は、労働コストを大幅に削減する一方で労働の質を下落させる要因として働いていることがわかった。工業統計調査と賃金構造基本調査個票データをマッチングして正規労働者とパート労働者の生産性の格差を測ると、この格差は賃金率の格差よりも大きい。つまり、企業は雇用の柔軟性を手に入れるためにプレミアムを支払っている可能性が高い。
生産性の上昇のために
日本は中長期的な経済成長の源泉をどこに求めるべきか。GDP成長率を上昇させるためには人口当たり労働時間や労働の質の向上に加えて、全要素生産性を上昇させることも必要だ。
まずは、市場の新陳代謝機能を高める必要がある。日本は、生産性の高い企業の拡大・新規参入や、生産性の低い企業の退出や工場が閉鎖することで経済全体の生産性が上昇するという、マーケット淘汰のメカニズムによる効果が非常に小さい。また、日本の中で相対的に生産性の高い独立系多国籍企業は雇用を減らし、比較的生産性の低い子会社に雇用を移していることも、日本の低い新陳代謝機能をもたらしている可能性がある。
もう1点指摘できることは、日本のIT投資の低さである。たとえば、日本企業の多くは組織改編や労働者の教育を回避する代わりに、カスタムソフトウェアを導入する傾向が強い。このことが日本において情報通信技術を導入することの効果を弱めて(情報通信技術の導入を割高にして)、全要素生産性の上昇を妨げている可能性もあるのではないか。
報告3「経済のグローバル化と国内雇用」
戸堂 康之 (RIETIファカルティフェロー/東京大学大学院新領域創成科学研究科国際協力学専攻准教授)
日本経済の現状とグローバル化がもたらす可能性
現在の日本経済は、十分な創造と活力に欠けた状態といわざるを得ない。GDPの伸びは低く、この成長率が今後10年間続くとすれば、1人当たりGDPは他の欧米・アジア諸国に逆転されたり、差が拡大したりしてしまう可能性がある。
日本経済の停滞の原因は、グローバル化の遅れにある。輸出や対外直接投資の対GDP比が低いというだけでなく、国内雇用における大卒以上の外国人比率や海外居住者比率も先進諸国との差が大きく、雇用のグローバル化も進んでいない。
多くの実証研究は、企業のグローバル化が生産性を拡大するという結果を示している。たとえば、輸出による生産性の上昇は平均2%、海外直接投資は2%上昇、海外での研究開発活動では3%の上昇などの分析結果がでている。
内需産業の保護は所得の再配分にしかならない。真の内需拡大策というのは、グローバル化を世界各国で進めて生産性を上昇させ、互いの国内所得の増加や技術伝播によって内需と外需双方を拡大させる好循環を生み出すことにある。
グローバル化は国内雇用を縮小するのか
グローバル化により、国内雇用が縮小する可能性があるとの懸念がある。確かに、対外直接投資や海外業務委託の増加は短期的な雇用を減少させるかもしれないが、長期的にはグローバル化は生産性を上昇させる。生産水準が拡大することによって雇用が増える可能性もある。実際にどちらの効果が大きいのかを証的に検証し、データから政策インプリケーションを引き出す必要がある。
RIETIでは、「工業統計表」や「企業活動基本調査」またはJIPデータベースを活用して多くの研究者が分析を活発に行ってきた。たとえば、1991年時点で海外に製造子会社を有する日本企業の雇用成長率を分析した研究によると、短期的には雇用が減少するが、5~6年経つと雇用が増加する(RIETIDP 03-J-019 )。また、日本企業の初めての海外投資を扱った研究では、投資した年には生産性が増加して生産量が増え、雇用量は投資した年には変化しないが、1年後以降に増加することが示されている(RIETI DP 07-E-006 )。
たしかに、こうした企業レベルの分析では、特定企業が海外投資による生産性向上で雇用を増やしたとしても、国内の競争激化の末、競争に負けた企業が雇用を減らすことも考えられる。しかし、産業レベルのデータを使った海外業務委託と国内雇用量の分析においても、海外業務委託が全体の雇用量に対して明らかにマイナスの影響があるという研究結果は存在しない。
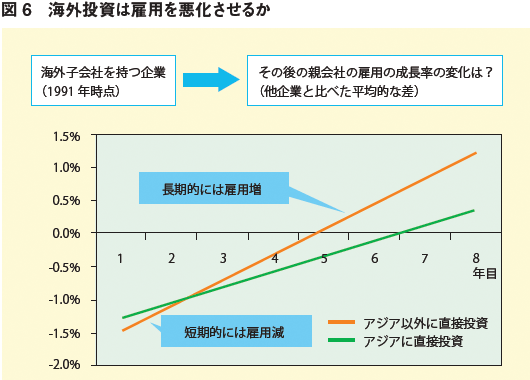
また、輸出の増加によって輸出産業の雇用が増えるだけでなく、輸出産業に部品やサービスを供給している産業についても、産業連関効果を通じて雇用が増えることを示した研究もある(RIETI DP 10-J-029 )。つまり海外直接投資や海外業務委託が最終的に雇用を減らすという分析結果は無く、むしろ長期的にはグローバル化によって国内雇用が増加するという結果が目立つ。
一方、グローバル化は高度人材への需要シフトをもたらす点に注意する必要がある。
実際、海外業務委託によって国内の大卒雇用は増加するが、高卒では逆に雇用が減少するという分析結果もある(Ahn, Fukao and Ito 2007)。
日本経済再生の鍵(政策提言)
企業のグローバル化によって高度人材への労働需要のシフトが起こる可能性はあるが、雇用が必ずしも悪化するわけではない。日本経済再生のためには、人材そのものを高度化しつつ、経済のグローバル化を促進することが望ましい。
さらに、日本では生産性が高く、潜在的にはグローバル化できるはずなのに海外進出も輸出もしていない、私が「臥龍企業」と呼ぶところの企業が多いことが最近の研究で明らかにされてきた(RIETI DP 08-J-046 )。このような「臥龍企業」は2000社にもおよぶと推定される(図7)。こうした企業を活かす政策が検討されるべきだ。
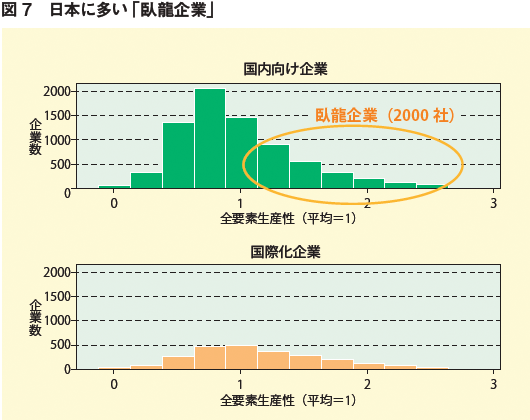
また、グローバル化への足がかりとして外国人熟練労働者の雇用を促進する政策や、頭脳流出を抑えるために研究部門を備えた対日投資を誘致する政策についても、実証的な効果の分析を行った上で検討されるべきだ。また、日本の大学がグローバル化から取り残されていることも強調しておきたい。人材の高度化のためには、外国人教員や留学生の増加、講義の英語化など大学もグローバル化する必要がある。
パネルディスカッション
いま求められる日本の雇用戦略
樋口 美雄 (慶應義塾大学商学部教授・商学部長)
日本の労働市場が抱えている問題は、二極化や貧困問題、長時間労働、少子高齢化、グローバル化などが複雑に絡み合っており、個別の雇用対策では乗り切れない。
これまでの雇用政策は、他の政策との整合性が欠けていたり、効果が相対立することも多かった。たとえば、1986年の男女雇用機会均等法の成立を受けて、政府は女性の雇用促進を投げかけた。しかし、同時期に配偶者特別控除制度が設けられた。この制度は、専業主婦または一定所得以下であるならば2倍の控除を受けられるというもので、働かないほうが得になる制度といえる。つまり同じ時期に、一方では女性の就業にアクセルを踏みながら、もう一方ではブレーキを踏むという政策が行われていた。
今後は、政府全体として、雇用という視点から現状を認識して将来のビジョンを描いた上で、さらに省庁の枠を超えた政策パッケージ、つまり「雇用戦略」を立てることが必要である。各政策の整合性を高めるためにも、政労使が一体となって合意を作り、実現可能性を考慮し、具体的な目標数値を設定してPDCAサイクルを働かせる仕組みを作らなければならない。
では、具体的に雇用戦略を考えるために留意すべき労働市場の現状はどうなっているのか。まず、足元では女性の雇用者数は堅調である一方、リーマンショック以降の2008年9月以降は従来の景気後退期にあっては守られてきた男性の雇用者数が減少している(図8)。この背景には、男性を比較的多く雇用していた建設業と製造業の大幅な雇用者数の減少、女性の就業が多い医療・福祉分野の成長という産業構造の転換がある(表1)。勤労世帯の平均世帯所得は減少しており、保育サービスなどの女性の就労支援を求める動きが強まっている。さらに非正規雇用の拡大も目覚しい。
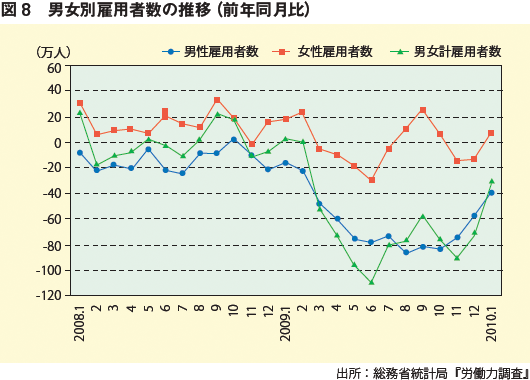
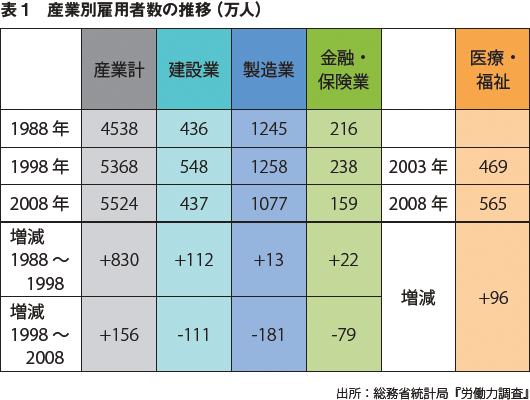
正規労働者に限定すると、長時間労働が引き続き問題となっている。ワークシェアリングは正社員の中でのみ行われ、非正規労働者は蚊帳の外に置かれてしまっている。正規労働者の雇用を残業時間の削減によって維持する結果、給与は下がり、非正規労働者は雇用調整の対象になっている。
今後は、雇用機会の量を拡大するだけでなく、労働の質も同時に向上させる必要がある。そのために、1)供給サイドのインセンティブに着目した就業意欲刺激策、2)新たな産業における雇用創出、3)その需給を仲介する効果的な就労支援、4)能力を発揮できるセーフティネット作りを雇用戦略として議論するべきだ。
雇用・労働システムの再構築
荻野 勝彦 (トヨタ自動車人事部担当部長)
人事労務に携わる立場から最近の雇用政策に対する認識や、望ましい雇用慣行のあり方について述べたい。
企業人事の立場からすると、労働市場の大半の問題は景気の良し悪しによるものであって、構造的な問題と思われるものも景気回復によって解決することが多々あるのではないか。たしかに構造的な問題もあるが、それをあまり強調して政策論を展開するのは危険だと感じる。
最近の日本の雇用政策は本末転倒ではないか。労働需要が不足しているのに、供給側を中心とした政策に疑問を感じる。「ある産業が成長すると人手が足りなくなり、労働条件が上がって労働者が自発的にその分野へ移っていく」というのが正常な順番だ。最低賃金の議論においても、まずは生産性を上げることで賃金や最低賃金が上がる、あるいは景気回復による人手不足で最低賃金が上がるというのが正常な手順である。先行させて最低賃金を上げ、生産性向上投資を支援するという方法は確実に上手くいかないだろう。
また、新卒者を長い時間をかけて育成する日本的雇用慣行は、それなりに体系的に整備され、社会にも定着している優れたシステムだ。たしかに問題もあるが、欧米のシステムを真似るよりも、日本独特の雇用慣行を今後の雇用システムの基軸に据えて競争力の源泉とする方が賢明ではないか。
1995年に日経連が提示した自社型ポートフォリオでは、長期継続雇用を重視することが強調されており、これ自体は優れた発想だったが、意図どおりには実現していない。長期蓄積能力活用型でもスローキャリアな働き方はあまり実現せず、高度専門能力活用型も当初の期待ほどは発達しなかった。そのため、雇用柔軟型が定型的な業務に固定されがちとなり、高度専門能力活用型や長期蓄積能力活用型へのキャリアパスが途切れていることに最大の問題がある(図9)。
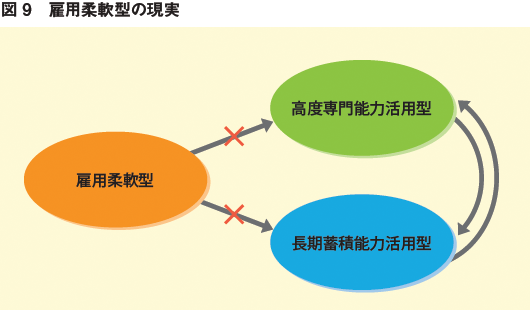
キャリアが途切れる最大の問題点は、有期契約労働者の勤続が伸びにくい構造にある。企業は景気変動に対応するため、有期契約の実務的本質である雇い止めの可能性を担保したい。すると、「解雇権濫用法理の類推適用」などを回避するために「更新2回、期間3年」などでの予防的な雇い止めが必要になる。これによって有期契約者は短期勤続になり、OJTなどの能力開発が行われにくく、低技能な業務に固定されがちになる。具体的な方策としては、有期契約労働の更新回数の多少・継続期間の長短に関わらず、契約満了をもって当然に終了することを明確にすることが考えられる。企業は予防的な雇い止めが不要になり、労働者は勤務期間が延び、能力開発が進むなど利点が大きい。雇用契約を明確化させるとともに多様化させ、キャリアの「飛び石」(表2)を設定することを提案する。
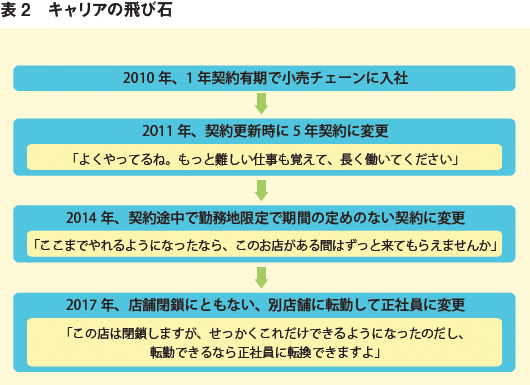
雇用・労働をめぐる現状と課題
長谷川 裕子 (連合参与/中央労働委員会委員・全国労働委員会労働者側委員連絡協議会事務局長)
労働組合の視点から昨今の雇用対策への評価、雇用政策の方向性について述べる。
バブル崩壊後の氷河期に就職できなかった若者への対策が終わらないうちに、新たに就職できない新卒世代が誕生してしまった。このダブルの氷河期世代への対応が新たな課題となっている。
まず、雇用対策の評価について、今回の深刻な雇用情勢の下、雇用調整助成金の拡充に対して労使で取り組み、実際に正規労働者の雇用を維持できたと評価している。ただし、生活保障と訓練をセットにした第2のセーフティネットを今後も拡充するべきだ。ワンストップサービスのような労働行政の取り組みも必要である。
労働者派遣法の見直しに携わり、派遣会社を育成することの必要性を感じた。派遣会社が能力開発を自発的に行うようなビジネスモデルの確立が求められる。雇用創出を図る上で、産業政策と労働政策と教育政策を経産・厚労・文科の3省庁が連携して行い、わが国の教育のあり方に職業訓練という視点を取り入れるべきだ。
今後の雇用システムのあり方について、連合は雇用の原則は期間の定めのない直接雇用であるべきと考える。雇用の多様化や流動化の結果に何が起こったのか、政労使はしっかりと認識するべきだ。雇用の多様化を進めるのならば、均等均衡処遇を担保する必要がある。
これからは男性も女性も高齢者も働く時代である。保育所、学童保育、介護などのように男女が働ける社会の支援基盤を整備する必要がある。
雇用・労働システムの再構築の視点
水町 勇一郎 (東京大学社会科学研究所教授)
雇用・労働システムの再構築と雇用戦略のあり方について、特にヨーロッパでの雇用戦略と労働法の関係を見ながら、労働法制のあり方をどう考えるかという問題提起をしたい。
第1に、どのような成長戦略・競争戦略をとるかということと労働法制のあり方は密接に関っている。競争戦略には、高付加価値を生み出そうとする上向きの競争戦略と、コスト削減に徹する下向きの競争戦略と、そして両者を組み合わせた競争戦略を考えることができる。たとえばヨーロッパでは、1990年代後半から2000年代にかけて上向きの競争戦略がとられ、労働法制の改革の大きな3つの柱として、1)性、民族や年齢、障害、さらにはパートタイム労働者、有期契約、派遣労働者といった雇用形態による差別を原則禁止する雇用差別禁止法制、2)高水準の最低賃金の設定、3)失業者に継続的な職業訓練を行って社会復帰や高生産性部門への転換を図るというアクティベーション政策がとられている。
1)と2)で労働者の地位と質を底上げし、高コストの結果、生き残れなかった部門の労働者を3)によりフォローするという戦略。実際にはヨーロッパの高失業の問題は未だ克服されてはいないが、日本も国家としてどのような戦略をとるのかを明らかにすべきで、その戦略に沿った労働法制を考えていくのが第1の課題となる。
第2に、どのような雇用システムをとるのかということ。長期雇用と短期雇用の二極併存を保つシステムと、正社員と非正社員を相対化して全体で流動性や柔軟性を確保するシステムのどちらを選択するのか。前者を選択するならば、正規雇用に対しては厳格な解雇規制を維持しつつ有期雇用の利用規制は緩やかにするという、現行法制に近い形になるだろう。後者を選択するならば、雇用保障についても正規と非正規の間の差別禁止原則を適用し、有期派遣労働の利用に対しては入り口規制をかけつつ正規雇用に対する解雇規制を柔軟にすることが検討されることになる。ただし、雇用システムの選択をする上で重要なポイントが2つある。1つは、この選択は国が一方的に課すものではないということ。企業の業種、実態ごとにいわゆる雇用のポートフォリオは多様である。多様な選択を可能にする法制度設計が必要だ。もう1つは、法制度設計の際に、制度自体を中立的にして、業種や企業の実態に応じた選択を可能にするシステムにするべきである。
第3に、どのように労働問題を規制し統合していくのか。世界的には分権化と同時に集権化が起こっている。多様化している社会の中では、集権的に上で決めて下に従えということができなくなってくる。その中で、一番現場に近い企業・事業場レベルでの当事者の声、特に非正規の声を反映した形で公正かつ効率的なルールを作っていくことが重要であるが、国家レベルで全体の方向性を統合することも必要だ。国家、産業や地域、企業・事業場が統合された重層的な社会的ガバナンスの基盤を構築し、労使対話の基盤を作ることが不可欠である。
雇用・労働システムの再構築~女性就労支援の視点から~
矢島 洋子 (三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 経済・社会政策部主任研究員/中央大学大学院戦略経営研究科客員教授)
女性就労の支援施策の観点から雇用システムの課題を整理したい。
子供を持つ女性の働き方に対する希望と現実の間には大きな隔たりがある。女性が希望しているような家でできる仕事や短時間勤務、フルタイムだが残業のない仕事などがこれまでの日本社会にはあまりなかった。ワークライフバランス(WLB)施策とは、今まで日本になかった仕事や多様な働き方を作るともいえるのではないか。
これまでに女性就労支援策の効果があらわれなかった原因は、複数の施策がかみ合わなかったことにある。90年代以降、保育所の整備や企業の両立支援策が進んできたが、長時間労働という基本的な働き方が維持されていたために、これらの制度が十分利用されなかった。1980年以降、M字の底は上がってきているが、その中身は子どもを持っている人が働けるようになっているのではなく、未婚者の割合が増えていることによるもので、これまでの両立支援施策の効果が出ていないことがわかっている。ただ、ここ数年、WLB施策の広がりなどから、特に都市部の大企業では女性就労を取り巻く状況は好転したという印象を持っている。しかし今度は、大都市圏の保育所の待機児童の問題や、女性の半数以上が両立支援策を利用しにくい非正社員になってしまっている状況により、WLBや両立支援施策の効果が限定的になるなどの課題が顕在化している。保育や企業の両立支援、WLBという施策がかみ合ってくことが重要である。景気低迷や男性の継続就業の不安定化を背景に、女性も働かなければ家計が成り立たないという潜在的な女性の就労ニーズが高まっていることからも対策が急がれるべきだ。
いまだにWLBの取り組みを、子育て女性の両立支援策に限定するという企業の誤解が解消されていないようだ。男性の働き方も変えていくことで、基本的な働き方を見直していくところに手をつけなければ、今後も施策の効果は限定的になるだろう。
中小企業や地方では、WLBは難しいという声があるが、会社の規模や地域に関わらず、雇用の維持自体が困難な企業ではWLB以前の問題が大きいということであり、生産性の高い新規産業の創出も急がれる。また、労働者の賃金水準が低ければ、短時間勤務などの選択は厳しくなる。社会全体の産業政策によって雇用創出を行ったり、時間当たり労働の生産性を労働者側からも向上させることも、女性の就労支援につながると考える。
ディスカッション
労使の信頼関係は変化しているのか
樋口:以前の日本では、企業が栄えれば労働者も栄えるという感覚が強かった。しかし2000年代以降、企業の利益が労働者に還元されないと指摘されることが多い。非正規労働者の比率が増える中で、労使の信頼関係は変わってきているという印象がある。
荻野:1990年あたりから株主の利益を大切にする、モノをいう株主が機能することがコーポレートガバナンスであるという風潮が非常に強くなってきた。たとえば、教育訓練は短期的には株主価値を高めないため、労働者が自己責任で行うことが株主重視であるという極論まであり、労使の信頼関係への影響は否定できない。ただ、内部留保の分配の問題もあるが、安定したコミュニケーションのある労使であれば大きく信頼関係が損なわれることはなかったのではないか。
長谷川:株主重視が背景にあるため、企業の利益が上がっていても労働者への分配が非常に低いことはあった。また、正規労働者と非正規労働者の労労間の問題も起きた。職場の中に33%も非正規労働者がいる現実に対して、労使が手当てなどを十分対処しなかったことは労使双方の反省すべき点だ。
均等均衡処遇のあり方
荻野:いわれのない処遇の差別は禁止されるべきだ。しかし、欧米でいわれるような企業の枠を超えた社会横断的な同一労働同一賃金や均等処遇は、日本の雇用慣行の中ではなじみにくいと考える。大陸欧州では職種別の労組があり、中央団体交渉で賃金が決まるが、日本では賃金に加えて賞与にも企業ごとの業績などが反映されるため、同一職種に従事していても企業が違えば賃金・賞与が異なることは当然と受け止められていて、日本と欧米では一般労働者の業績に対するコミットメントがかなり異なっている。日本では社会的な同一労働同一賃金よりも、企業内の同一価値労働同一賃金がなじむだろう。
長谷川:今回の改正派遣法が成立すると、強行規定ではないが、派遣先労働者との均衡処遇が適用される。その点では均衡処遇については1歩前進したといえる。連合も同一価値労働同一賃金があるべき姿と考えるが、産業別や地域別の均衡処遇をどうやって行うのかについては、まだ議論が整理されていない。当面は企業の中での均等処遇を労使交渉の中で話し合うべきという考え方は荻野氏と同じだ。
水町:ヨーロッパでは同じ場所で働いていれば雇用者が違うとしても同じように取り扱うという場所の単位を原則としている。日本でも場所という概念を取り入れて複雑な労使関係に対応することも必要だ。客観的な理由のない差別を禁止するという時の客観的な理由として、職能給システムの下で前提が異なる時に、違いに合わせたバランスを取る「均衡」という視点も取り入れるべきだ。
矢島:女性割合の高い職種として保育や介護などがあることを考えると、職種別の最低賃金や同一価値労働同一賃金の考え方は女性の就労を支える意味で重要と思われる。WLBの推進では、育児介護休業法の改正により、2010年6月末から短時間勤務の導入が企業に義務付けられる。こうした動きの中で、働き方の多様化に即した賃金制度のあり方が、企業の制度運用における大きな課題になっている。企業は1人当たりの生産性ではなく、時間当たりの生産性によって評価・処遇することが求められている。
質疑応答
1 雇用戦略における地方自治体の役割をどう考えるべきか。
樋口:1970年代のヨーロッパでも、地方のニーズをいかにして雇用戦略に織り込むかが重要視されるようになってきた。たとえば、WLBを推進する施策も、平均的な通勤時間が異なるという地域特性の違いを考慮する必要がある。コミュニティの中でいかにリーダーを育成するのかも重要な議論だ。
2 経産省・厚労省・文科省は、具体的にどのようにして連携するべきなのか。
長谷川:各大臣の顔がよくみえる時なので、この時期にこそ三省が一緒になってラウンドテーブルで政策を立てるべきだ。
3 高齢者の雇用機会をどのようにして創出していくのか。
荻野:高齢者には多様性があり、働き方や仕事の内容についてさまざまな配慮が必要である。また、人的資本投資を行うよりも既存の技能を活かす方が好ましい労動力でもある。賃金などの労働条件については柔軟性が必要だし、若年雇用に悪影響を与えないというキャリアの意識改革も必要かもしれない。
4 短時間正社員が企業で上手くいかない理由は何か。
荻野:コスト構造からも、仕事の内容からも時間当たり生産性という概念になじまない労働も存在する。1日6時間働くのと比べて、8時間働くこと、必要であれば残業や休日出勤ができることには特別の価値があることも多い。正社員との時間割計算での均等にこだわると確実にうまくいかない。格差を受け入れて均衡の考え方を取り入れた方が上手くいくのではないか。
5 地域の実情に応じた労働基準を設定する際に、どのような観点からのガバナンス設計を行うべきか。
水町:樋口先生のご指摘のように、コミュニティでのリーダー作りという観点は非常に重要だ。アメリカの労働力投資委員会は、地域のリーダーや労使が参加して、多様なニーズの運用を決めている。
6 企業にWLB推進のモチベーションを与えるのは何か。
矢島:メンタルヘルスの問題が大きいために、企業のWLBへのモチベーションは非常に高いと感じている。