過去15年間、米国において技術革新が大きく進展したことが最近の研究で明らかになりつつある1。このことは、1980年代後半から1990年代末までの特許申請・取得の急増に如実に現れている。この増加のペースは、政府あるいは民間の研究開発費の増加を大きく上回るものであった。図1は技術分野ごとの米国での特許の増加を示したものである。アメリカの特許のかなりの部分は外国の発明者に対して認可されている中、国内発明者による特許の割合では、特に特許申請が最も増加している技術分野で増えている。近年の特許の急増は、アメリカの研究開発の生産性が向上したのではなく、アメリカ人が発明に対して特許を申請する傾向を強めたためである可能性もあるが、Kortum and Lerner [1998, 2000, 2003] の最近の特許関連データによる研究は、前者の説明がより整合的であることを強く支持している。もしこの結論が正しければ、一般に観測されている米国の全要素生産性(TFP)の最近の成長を説明する要因の1つとして、これを挙げることができる2。
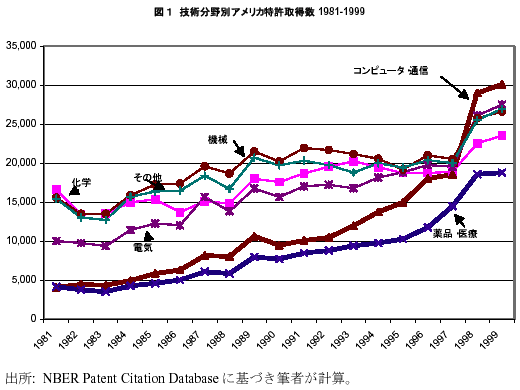
図1 技術分野別アメリカ特許取得数
なぜアメリカの研究開発生産性は向上したのか
しかし、仮にアメリカの研究開発の生産性が向上したとして、なぜ向上したのかという疑問が残る3。私は最近書いた論文において、この原因の1つの可能性として、米国に本拠を持つ学術研究機関からのノリッジ・スピルオーバー(知識伝播)の増大の重要性を調査している4。本論文は、本質的には図2に示したような現象を説明しようと試みたものである。この図は、アメリカ国内の特許による科学学術雑誌の論文の引用が1980年代半ばから1990年代後半にかけて急激に増加したことを示している5。米国の特許法では、すべての特許申請者は「参考技術の適切な引用」を提出しなければならない。つまり、発明者は自分の発明の基礎となった既存の発明や発見を明確にしなければならないのである。アメリカの特許保護を受けようとする人たちは慣行として既存の特許を引用してきた。しかし、最近、アメリカを拠点とする技術開発者の間で、大学の学術研究者による科学論文を引用するケースが増えつつある。アメリカの特許制度の下では、参考にした重要な発明や発見を引用として明記しない場合に明確な罰則が課される一方、余計な引用を記載することにもコストがある。Jaffe, Fogarty, and Banks [1998]などの最近のアメリカの経済学者による研究は特許の引用のかなりの部分が知識伝播を反映していることを示している。
1980年代半ばから1990年代末にかけて、米国特許商標局によるアメリカ人への特許認可が2倍以上増加、実質研究開発費がほぼ40%増加、世界の科学論文の数が13%増加という中、特許の学術論文引用はなんと13倍以上も増加している6。国立科学基金(National Science Foundation )などのアメリカの科学政策機関の関係者の多くは、広い意味で、学術科学と産業技術がかつてよりも近づいてきていることの現れとして、この現象を非常に興味を持って見ている。これは、公的資金による学術研究から企業の技術革新への知識伝播がかつてよりも増えてきていることを意味しているといえるかもしれない7。これが、1990年代アメリカの技術革新の波に重要な貢献をしたのかもしれない。
こうした最近のトレンドを肯定的に捉える見方は、Evenson and Kislev [1976]やそれに触発されたAdams [1990] や Kortum [1997]らの最近の理論研究の影響を受けている。これら一般モデルの中では、応用研究はある特定の分野内でのサーチ過程であり、いずれは開発の余地がなくなってしまうものとして捉えられている。しかし、基礎科学は、応用研究者に新たなサーチ分野を開き、生産性と応用研究努力を少なくとも一時的には向上させる。この理論的見地に立てば、アメリカにおける民間の研究開発支出の急増、急激な増加を見せた特許取得、全要素生産性成長の加速を示す数々の証拠、さらに急激なアメリカの特許による学術論文引用の増加は、すべて学術研究による新たな開発機会への反応として捉えることができる。こうしてみると、他の先進国が大学の科学研究と産業界の技術革新の緊密な連携を意識的に促し、米国モデルを意識的に模倣しようとていることは驚くに値しない。
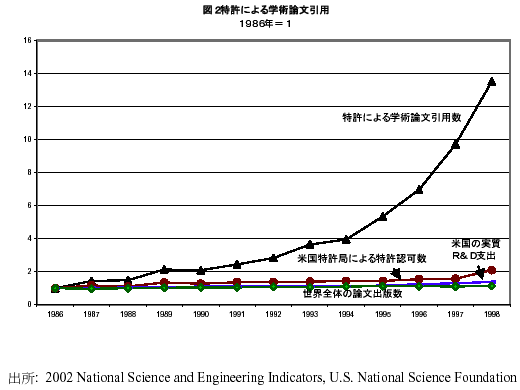
図2 特許による学術論文引用
最近のトレンドを説明する4つの仮説
しかし、学術科学から企業の研究開発への知識伝播の強化は、図2に示したような変化をもたらしたいくつかの要因の1つにすぎない。さらに、そうした知識伝播が強化されたとしても、これはいくつかの異なる要因で起きたものであり、その要因ごとに政策的なインプリケーションも異なってくる。最近の文献をざっと読み、少し考えるだけで、現在のトレンドを説明する少なくとも4つの代替仮説を思いつくことができる。
第1の仮説は、「科学の有用性の向上」仮説である。最近の科学論文には、産業界の研究開発にすぐ応用できるような発見が多く含まれおり、それが多くの科学分野で妥当しているために知識伝播が大きくなったという仮説である。この仮説によれば、学術から産業への知識伝播の増加は、主に大学での科学研究の性質が変化したことによる、ということになる8。
第2の仮説は、「研究開発方法の変化」仮説である。これは、企業の開発者が新技術の開発手法を変えたという仮説である。新しい研究開発手法は、最新の技術ばかりではないにしろ、とにかく学術論文に非常に頼っているために、最近のさまざまな技術分野の特許が学術論文を引用する傾向を強めていると考えることができる。ところで、最近の特許による学術論文引用のこうした増加は、学術科学による発見によって生まれた新たな「開発機会」への企業の反応を強く反映している。強調すべき点は、引用を増加させた原因が、企業の研究開発の方向と性質を基礎科学によって提供される新しい開発機会を探る方向に変化させた開発者側にあることである。第1の仮説と同様に学術研究からの知識伝播が時間を通じて増加したことを説明するが、そのメカニズムが異なる。
第3は、「開発内容の構成変化」仮説である。これは、ある分野の技術は学術研究と、ある期間、非常に強い関係を持っていた。あるいは同様に、ある学術分野が常に企業の特許に頻繁に引用されていたと考える仮説である。この仮説によれば、頻繁に引用する分野での特許申請が特に増加したから全体での引用が増加したように見えるということになる。同様に、学術論文の増加が、歴史的に企業の研究開発と密接に関係している分野に偏っていたから引用が増加したように見えると考えることもできる。つまり、個々の技術分野や学術分野では科学と技術の関係そのものに変化はほとんどなく、むしろ特許と論文の分野の分布が変化したために、見た目、全体の引用が増加したと考えるのがこの仮説である。この仮説を少し変形したものとしては、大学による特許取得の急激な増加があったという仮説も考えられる。この場合には、開発者の構成の変化が特許による学術論文引用の増加に寄与したことになる。
頻繁に学術論文を引用する特許技術分野や頻繁に引用される学術分野に引用の増加が強く偏っていることは、それ自体、一連の基礎研究により生まれた「開発機会」への企業開発者と学術研究者たちの反応を反映しているかもしれない。確かに、こうした特許分野と科学分野の複合体の成長は、学術と産業の相互作用が実際に成長したことを仮定する「開発手法の変化」仮説や「科学の有用性向上」仮説の証拠ともとれる可能性もある。「構成変化」仮説が強調するのは、新しい開発機会があったとして、それが非常に限られた分野内のものであり、開発手法変化や科学の有用性の向上と整合的な幅広い分野での変化が観察されないという点である。
第4の仮説は、「弁護士主導」仮説である。特許引用の変化はすべて引用慣行の変化によるものであるという仮説である。特許審査官に印象づけたいという願望、あるいは訴訟の恐れなどのさまざまな戦略的理由から、特許専門弁護士は顧客に学術論文の引用を増やすことを勧めてきた。学術論文の電子検索の利用が増え、引用の手間がかからなくなったことも、さらに引用の増加に寄与している。この仮説は、極端な場合には、学術と技術の間の関係の変化について特許データはなにも語っていないことを意味する。
これらの仮説は、互いに排除しあうものではないが、特許による論文引用の適切な解釈の仕方について異なるインプリケーションを持っている。図2が本当に意味するところ、それが最近のアメリカの技術革新の波にどう関係したか(あるいは関係しなかったか)、適切な政策対応はなにかを理解するために、グラフに示されたトレンドに対するこれらの仮説の相対的寄与度を検出することが必要である。
狭い分野に限られた学界からの知識伝播の増加
筆者の最近の論文 Branstetter [2003][PDF:720KB]は、共通の実証フレームワークの中でこれらの仮説の相対的な重要性を検定している。この論文では、データの全体的なトレンドの大部分が「構成変化」仮説と「開発手法変化」仮説で説明できることが分かっている。驚くべきことに、特許による論文引用の増加は「バイオネクサス」すなわち生物科学関連の科学技術分野に偏っている。この分野での特許取得、論文出版は時とともに増加しており、この技術分野で活躍する技術者の数もかなり増加している。バイオネクサス以外でも学術論文への引用が増加しており、その時系列の相対的増加の度合いも小さくはないのだが、バイオネクサスと比べるとまだまだ少ない。元データを見ると、1990年代半ばに「弁護士主導」による劇的な引用増加があったこともわかる。しかし、この法律的誘因による増加をコントロールしても、構成変化と開発手法変化が相対的に重要であったという結論は質的には変わらない。これらの結論はこの分野の最近の文献と整合的である。この論文の主旨は、学界からの知識伝播の増加は、アメリカの特許統計に見られるような技術革新の波に有意に寄与したが、その効果のほとんどが狭い科学技術分野に限られていた、ということである。
これらの事柄は日本にどう関係するのだろうか。後述のとおり、この研究は最近の日本企業における研究開発の発展に非常に関係している可能性がある。1990年代がアメリカの技術革新のルネッサンスだった一方で、ある測定法によれば、1990年代の日本の技術革新は比較的スローダウンしていた。中村吉明氏と私は最近出版した論文でこのスローダウンの研究をしている9。もちろん日本の経済学者も同様な問題について最近研究している10。
1990年代を通して、アメリカに比べて日本の民間部門の研究開発支出はあまり増加していない。研究開発の生産性を研究開発支出(ドル)あたりの特許数で計ってみると、日本の主要企業の技術開発の生産性の成長が1980年代に比べて1990年代に低下していたこともわかる。さらに主要な技術分野での日本企業による米国特許取得数が、1990年代にアメリカのライバル企業に追い越されていたこともわかる。図3に示されているとおり、たとえば情報関連技術において、日本企業がアメリカで取得した特許数は、1990年代初めまではアメリカ企業の取得した数とほぼ同じであった。しかしその後、アメリカ企業による特許取得数が急成長し、1990年代末のアメリカと日本の情報技術産業の「パテントギャップ」は、1980年代初めよりも拡大している。図4は生物科学関連の特許にもともとあった大きな差が1990年代を通してさらに拡大していたことを示している。
この傾向は、産業界のリーダーたちあるいは市場専門家の間の、少なくとも経済的に重要な分野で日本企業の研究開発努力があまり生産的な結果を挙げていないという懸念と符合している。日本政府は日本の研究開発の生産性を向上させるために研究開発体制の改革を模索してきた。この改革の鍵の1つは、大学の学術研究者と企業の研究所の連携強化である。もちろん、これは大学と産業の強い連携がアメリカの技術ルネッサンスに重要な役割を果たしていたという認識に基づいている。
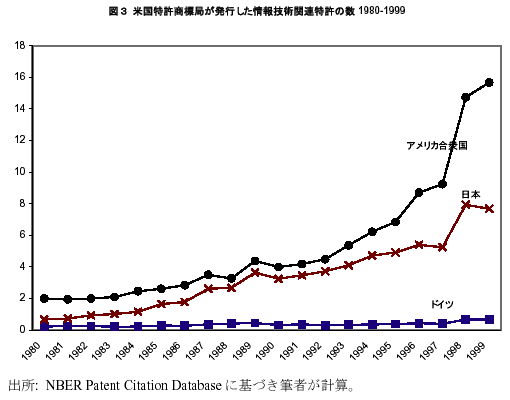
図3 米国特許商標局が発行した情報技術関連特許の数
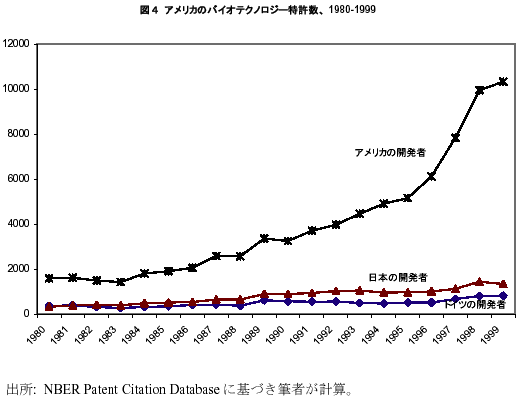
図4 アメリカのバイオテクノロジー特許数
日本の「産学連携」の効果にも過度な期待は疑問である
しかし、先述の特許引用データによる私の分析は産学連携をもう少し注意深く見る必要があることを示唆している。Branstetter [2003]の結果は、大学での研究からの知識伝播の強化が、アメリカの「バイオネクサス」で見られたような特許数の増加と、特許数/研究開発費比率の増加に寄与したことをおおむね支持している。しかし、その一方で、「ITネクサス」で特許による論文引用があまり見られなかったことは、大学科学からの知識伝播は、アメリカの情報技術分野における技術革新の波に対してはせいぜい補助的な役割を果たしたにとどまっていたことを示している。さらに、アメリカのデータを用いた私の以前の研究では、大学の保有している特許の正式な形でのライセンシングが大学から企業への知識の流れにおいて二次的な役割しか果たしていないことが示されている。これらの結論が正しいとしたら、日本で熱心に推進されている「産学連携」の効果について、もう少し期待を現実的にする必要があることになる。日本の大学の技術ライセンス事務所(TLO)の設立、正式な形での企業への技術ライセンスの促進は、日本企業の技術革新に少なくとも短期的にはそれほど大きな効果をもたらさないかもしれない。個人的には、大学研究者と企業研究者の間の伝統的な障壁を取り払って生産的な相互作用、産学連携的活動を促進しようとする日本政府、企業、大学の努力を支持している。しかし、産学連携はせいぜいアメリカの技術革新を部分的に後押しした程度にとどまっている上に、その効果は非常に限られた範囲の技術分野にしか見られなかった。アメリカでそれほど大きい効果のなかった産学連携が日本だけで大きい効果をもたらすと考えるのはあまり現実的ではないかもしれない。
もちろん、これらの仮説は最近の日本のデータの傾向を注意深く調べることで検証されなければならない。幸いに、ほとんどの主要企業が重要な発明のほとんどについて、日本だけではなくアメリカでも特許を出願している。アメリカの法律のもとでの特許申請は「参考技術の適切な引用」が要求されている。したがって、日本企業のアメリカ特許に含まれている引用の傾向を統計的に分析することで、日本企業が新技術の開発に際して、どれだけ大学の学術研究を利用するようになったかを調べることができる。これらの引用リストから、引用された学術論文を特定化することができ、そこから執筆者とその所属研究機関を知ることができる。このようにして、特許による論文引用を用いて、日本企業全般の学術研究への依存度だけではなく、どの大学、どの分野が日本企業の技術革新に貢献したかを調べることもできる11。
この数カ月の間に、ハイテク産業で活動する数百の日本企業のこのようなデータを用いて、日本企業の研究開発と大学の連携の変化を調べることを予定している。また、私自身の統計的分析の結果を適切に解釈できるよう、日本の産学連携について、日本の経済学者やその他の専門家により蓄積された相当な量の研究を学ぶ予定である。これらの企業レベルのデータによる分析が日本の技術革新体制の理解の進化に貢献すると考えている。


