| 解説者 | 清田 耕造 (ファカルティフェロー)/長谷川 誠 (ミシガン大学) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0088 |
| ダウンロード/関連リンク |
グローバル化の進展により外国への直接投資は益々増加し多国籍企業化も進んでいる。そうした中で、企業が獲得した利益を、より多く日本に還流させるにはどうしたらよいのだろうか。
日本の国際法人税制は、以前は米国に倣って海外で稼得した所得に対しても日本の法人税を課すという「全世界所得課税方式」を採用していたが、海外子会社に蓄積された利益の日本への送還を促す目的で、2009年に「国外所得免除方式」に一部移行した。国内のみならず海外からの関心も高い今回の制度変更の影響について、清田耕造FFと長谷川誠助教授は、経済産業省の海外事業活動基本調査と企業活動基本調査の個票データを使い、実証的に検証した。
――法人所得の国際課税制度を研究された動機は何でしょうか。
清田: 国際課税の制度は主に2つにわけられます。1つは日本が2009年まで採用していた「全世界所得課税方式」で、この方式ですと、日本企業が海外で獲得した所得を、国内に引き戻した時点で日本の法人税が課されます。たとえば、日本企業の子会社がシンガポールにあったとします。この子会社が稼いだ100ドルを日本の親会社に送る場合、日本の法人税率が40%だとすると、40ドルが課税されることになります。しかし、その前にシンガポールの法人税(税率は15%)として15ドルをシンガポールで払っているのでその分が免除され、残りの25ドルの税金を日本で支払うという方式です。もう1つは「国外所得免除方式」で、この制度ですと海外で獲得した所得には自国の法人税は課されません。先ほどのケースですと、シンガポールで15ドル支払っていれば、日本で追加的に課税されることはなくなります。
米国で日本の政策変更に高い注目
長谷川: 日本は2008年5月に、当時の甘利明経済産業大臣が全世界所得課税方式から国外所得免除方式への移行についての本格的な議論を開始するように指示しました。これを受けて経済産業省内に国際租税小委員会が設置され、同年8月に中間リポートが出されました。そして翌2009年3月に、日本国内の法人が海外の子会社から受け取る配当について、一定の条件のもとで非課税とする内容の法案が可決されたことにより、2009年4月から日本の法人所得に関する国際課税制度の部分的な国外所得免税方式への移行が正式に決定しました。
清田: 企業から見れば、海外で事業展開している子会社がその国で税金を支払えば、日本では課税されなくなるので、海外子会社から日本の親会社への配当などの送金のコストが減ることになります。前出の中間リポートでは、2006年度までに日本の海外子会社がため込んでいた内部留保は17兆円に上ると推定されています。これだけの資金をどうすれば日本に還流できるか。日本での追加的な課税がなくなれば、企業は資金を親会社に戻しやすくなる、と考えられたのです。
長谷川: このような政策変更がされている時、私は米国のミシガン大学で財政学を学んでいました。米国は全世界所得課税方式を採っていて、日本は元々その制度を取り入れていました。実は、米国でも国外所得免除方式に移行しようという動きはあって、10年以上議論が続いていました。しかし、政治的な理由などから実現しませんでした。そこに日本が米国に先駆けて移行を実行したということで、米国の財政学者や政策担当者は日本で何が起こっているのか、非常に注目していました。2008年当時、経済協力開発機構(OECD)に加盟していた経済大国といわれる国々の中で、全世界所得課税方式を採用していたのは、主に米日英の3カ国ぐらいで、その後、英国も国外所得免除方式に移行しています。米国としては、取り残されたような感覚もあったかと思います。
国際的な資金の動きは国の間の税率の差に左右されやすい面があります。全世界所得課税方式のもとでは、低税率の国から税率の高い国に資金を送ると、税のコストが発生します。留学中の指導教員の1人であるジム・ハインズ教授が国際課税の専門家であったこともあって、2009年の制度移行が企業の国際的な資金移動に与えた影響を研究しようと思い立ちました。
3つの仮説を立てて分析
――分析の方法について教えて下さい。
長谷川: 分析にあたっては、海外子会社のデータとして経済産業省の海外事業活動基本調査(2007年-2009年)の個票を使いました。日本の親会社については同省の企業活動基本調査(2007年-2009年)を使用しました。この研究には配当の送金額があることが欠かせないので、この金額があるデータを選びました。この2つのデータを使うことで、日本の親会社・海外子会社の財務情報、海外子会社から日本の親会社への送金額と、日本の親会社が海外子会社から受け取った金額がわかります。他の統計にはこうしたデータがありません。
清田: 今回の研究では、全世界所得課税方式からの制度変更の効果について、(1)海外子会社の親会社への配当送金は増加したのか、(2)制度変更により海外子会社の配当送金は子会社が立地する国の税率(法人税率や源泉税率)により反応するようになったか、という2つの疑問に注目しました。この疑問への答えを導き出すために、3つの仮説を立てて定量的に検証しています。具体的には、海外子会社から日本の親会社への配当送金のパターンがどのように変わったのかを、制度変更以外の影響を取り除いて制度変更との関連性の強さを分析するため、回帰分析に制度変更のダミー変数を含め、制度変更前後の比較(before-and-after comparison)を行いました。
1番目の仮説は、「国外所得免除方式の導入は、現地法人からの配当送金を促す効果があったのか」で、外国の税率の変化など、日本の制度変更以外に配当送金に影響しそうな要因を取り除いた上で、今回の制度変更によって日本企業の海外子会社の親会社への平均的な配当の増加額を見ようというものです。
長谷川: 2番目の仮説として、「今回の制度変更によって、海外子会社が配当を送金するのにあたって、現地の法人税率に対する反応は変わったのか」を立てました。これは、今回の制度変更によって、法人税率の低い国に立地する子会社からの配当がより増加することが考えられたからです。制度変更によって、海外子会社は現地で税金を納めれば、日本で追加的に納税しなくても済むようになりました。そうなると、多国籍企業の中には、さまざまな税率の国に立地する海外子会社がある中で、税率の低い国に立地する子会社にいったん所得を移し、その上で、その子会社から日本に送金することによって、税金のコストを低く抑える、という行動が活発化することが想定されたからです。また先に述べたように、全世界所得課税方式のもとでは、低税率国の子会社からの配当送金にかかる税のコストが大きかった分、配当が国内で非課税となることでそのような子会社がより強く制度変更に反応して配当を増加させると考えました。
清田: 3番目の仮説は「海外子会社からの配当は、配当への源泉税率に、より敏感になる」です。国外所得免除方式になると、日本での追加的な税金は払わなくてもよくなります。配当にかかるコストは現地での税率によることになり、法人税率だけではなく、その国から日本への配当送金にかかる源泉税の負担がどれだけ重いかに、より敏感にならざるを得ないと考えられます。
――分析の結果はいかがでしたか。
長谷川: 回帰分析ではまず平均的な子会社の配当送金を見ているのですが、第1の仮説で考えたように、今回の制度変更によって、日本企業の海外子会社の親会社に対する配当送金が平均的に増加するという結果は得られませんでした。これは、そもそも親会社に配当を送金している海外子会社が全体の3割程度しかなく、それ以外は配当を送金していないので、平均的な子会社に注目すると、制度変更の影響が見えにくくなってしまうからだと考えられます。
清田: 2番目の仮説についても、法人税率の低い国に立地する子会社がより配当を増加させるというような行動は見られませんでした。これについては、使用したデータが2007年-2009年のもので、制度変更後1年目しか見ていないという制約があると考えられます。企業が税負担に対して戦略を変えるのには、もう少し長い時間がかかるのかもしれません。また、もしかすると、制度変更に伴う脱税や過度の節税に対する取り締まりの強化を企業側が懸念したことも、影響しているのかもしれません。
また、3番目の仮説に対しても、制度変更によって海外子会社が立地する国の配当への源泉税率をより配慮するようになるといった、現地の源泉税率と配当との強い関連性は見られませんでした。これは、配当に対する源泉税率が、日本と投資先の国との間の租税条約で決まっていることが多く、税率のばらつきが小さいためと考えられます。
内部留保が十分な企業は配当送金を増やした
――配当送金をしている海外子会社は限定的なのですね。
清田: 企業の海外子会社が親会社に配当を送金するかどうかは、そもそも子会社に内部留保が蓄積されているかどうかによるのではないかと考えました。この考えから、内部留保が蓄積されている海外子会社について分析すると、制度変更への反応が確認できました。つまり、1番目の仮説が支持されたわけです。
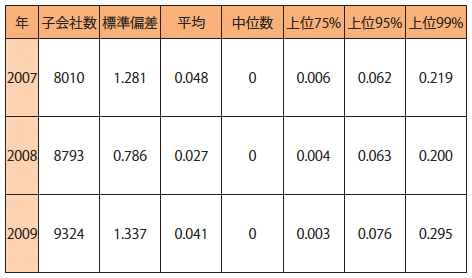
さらに、制度変更以前の配当が大きい子会社ほど、制度変更への反応が強く、配当送金の増加量が大きいことがわかりました。
長谷川: ただし、内部留保残高の大きさを考慮しても、2番目と3番目の仮説は支持されませんでした。これは先に述べた理由に加えて、企業が配当にかかる税金の負担を最少に抑えることについて、それほど熱心ではないことの表れなのかもしれません。
米国からの配当送金が急増
――制度の移行後、米国の子会社から日本の親会社への配当送金が急増したと指摘されていますが。
長谷川: 米国に立地する日本企業の子会社から親会社への送金が制度変更以後に急増したことは、今回の分析に使用したデータの個票からではなく、経済産業省が公表している、国ごとの日本への配当送金の集計金額によるものです。それによりますと、米国からの送金が2009年に急増しています。米国は法人税率が高く40%に上っています。その中で制度変更後に米国からの配当送金が急増したということは、2番目の仮説を立てた時に考えた、税率の低い国からの配当送金が増えるのではないか、という考えと相反します。
清田: 企業の海外子会社から親会社への配当送金を考える場合には、その企業が現地で稼いだ資金から、現地に再投資する機会がどれだけあるかを考慮する必要があります。今回の日本の制度変更は、2008年9月に起きたリーマン・ショックの直後にあたりました。このため、米国経済の低迷によって、日本企業の米国における子会社は現地での再投資の機会が減ったため、親会社への配当送金に回すという判断がなされた可能性があります。
長谷川: また、米国との租税条約によって配当への源泉税が一部免税されていることが影響しているのかもしれません。
制度変更で一定の効果はあった
――以上の分析結果から、どのような政策インプリケーションが得られるのでしょうか。
清田: 1番目の仮説で考えた、「国外所得免除方式への制度変更によって、海外子会社から親会社への配当送金が増えるのではないか」ということについては、平均的な企業について分析すると、増えていませんでした。これは、もともと親会社に配当を送金していなかった海外子会社が、国外所得免除方式への制度変更によって新たに配当の送金を始めるということはなかった、ということを示しています。ただ、内部留保を十分積み上げていた海外子会社が、親会社への配当の送金を増やしたことは確認されました。このことは、海外子会社に蓄積された利益を日本に戻すという、今回の制度変更の目指した効果はあったのではないかと考えられます。
長谷川: 一方、税率の低い国から日本への配当送金が増えるのではないか、との仮説に対しては、低税率国から日本への配当送金が増えたという結果は出ませんでした。この政策変更にあたっては、低税率国の子会社へと所得を移転させることで節税を図る租税回避行動に拍車がかかることが心配されていました。しかし、今回の分析結果は、2009年にはそのような過度の節税を目的にした行動は見られなかったということを示唆しています。
ただ、ここで注意が必要なのは、今回の研究の対象が制度変更後一年目の反応である点です。制度の変更に対して、企業側の経営戦略の中で、配当送金に関する対応を変更するかどうかを決めるのには、もう少し時間がかかるかもしれないということです。また、もう1つ注意しなければならないのは、税率の低い国に立地する子会社に対しては経過措置が適用されており、配当免税を申請できるようになるタイミングが、少し遅くなっている可能性があるということです。
こうしたことに加えて、日本企業の税に対する意識が他の国の多国籍企業と比べて異なるのではないかということも考えられます。日本の企業文化の中で、税金というものは、きちんと払うものであるという考え方が根付いているのかもしれません。それに対して、欧米の多国籍企業は、税を管理するべきコストの一部としてとらえる意識が強いと聞いています。このような企業文化の違いが配当送金という行動にも反映されていることもあるかもしれないという面も考慮する必要があるでしょう。
清田: このような研究ができたということは、海外から親会社に対する配当の送金と、親会社が海外子会社から受け取った配当額の記入されたデータがあるから可能になったことです。ですから、こうしたデータを今後もぜひ継続して整備してほしいと思います。
長谷川: 細かいことのようですが、今回の分析で使用したデータの個票には、配当送金のところが空欄になっているものが多かったようです。この場合は欠損値として扱わざるを得ません。今、述べられたように今後も継続してデータを整備していただく中で、たとえば、配当送金がない場合は「ゼロ」と記入してください、というような注意書きを添えてもらうと、無配当の子会社をより正確に把握できるようになると思います。
より長い期間での分析が課題
――今後の研究課題は何でしょうか。
清田: 今回の研究では、さまざまな面で十分考慮できなかったところがあります。たとえば、米国からの配当送金が2009年に急増した要因として考えられることとして述べましたが、現地での投資機会が多いのか少ないのかは配当送金に影響することです。今後はこのような要因も含めて分析して、より精緻な分析にしていきたいと思います。
長谷川: 今回の研究はデータの対象期間は2007年-2009年の3年間でしたが、今後は2010年以降のデータも加えて、より長い期間で、制度変更の効果を見たいと考えています。
解説者紹介
2002年慶應義塾大学大学院経済学研究科博士(経済学)取得。2001年-2003年横浜国立大学経営学部専任講師。2003年-2007年横浜国立大学経営学部助教授。2007年-2013年横浜国立大学大学院国際社会科学研究科・経営学部准教授を経て、現在、慶應義塾大学産業研究所教授。
主な著作物:"A Many-cone World?"
Journal of International Economics
, 86(2): 345-354, 2012.

長谷川 誠
2013年米国ミシガン大学経済学博士課程修了(経済学博士号取得)。現在、政策研究大学院大学助教授。主な著作物:"The Eff ect of Public Disclosure on Reported Taxable Income: Evidence from Individuals and Corporations in Japan," (with Jeff rey Hoopes, Ryo Ishida, and Joel Slemrod), forthcoming, National Tax Journal .


