| 解説者 | 植村 修一 (上席研究員) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0081 |
| ダウンロード/関連リンク |
世界的な金融危機の発生を受けて、各国政府・国際機関の間で、マクロプルーデンス政策に対する関心が高まり、その体制整備が進められている。マクロプルーデンス政策とは、広く金融システム全体に潜むリスクに着目して、それに対処することにより、金融システムの安定を図ろうとする考え方で、挙げられている政策手段の1つに、信用規制がある。日本は1980年代後半からのバブルの生成と崩壊の過程で、不動産業向け融資の総量規制を実施した。総量規制は、信用規制の一種であるが、当時はあくまでも土地対策として採られた措置であった。この規制導入当時に担当省庁である大蔵省(当時)で実務に携わり、深い知見を持つ植村SFが、マクロプルーデンスの視点から規制の検証を行うことにより、将来へのインプリケーションを導き出した。
リスクを金融システム全体でとらえる
――まず始めに、マクロプルーデンス政策とはどのようなものなのでしょうか。
マクロプルーデンス政策には統一された定義がなく、いろいろな観点があるのが現状です。ただ、共通の理解として、リスクの所在を特定の銀行など1つ1つの金融機関としてではなく、金融システム全体としてとらえるということがあります。2011年の20カ国財務相・中央銀行総裁会議に向け、国際通貨基金(IMF)と国際決済銀行(BIS)、新設の金融安定理事会(FSB)は共同で、マクロプルーデンス政策に関するレポートを公表しました。レポートでは、この政策の必要性が述べられ、マクロで物事を考えていくスタンスが改めて確認されました。
具体的な政策の例としては、たとえば米国の住宅バブルに続いて欧州でも住宅バブルがはじけたわけですが、こうした不動産バブルに対して、いくらの価格の物件に対して、いくらまでローンを借りることができるかを規制するローン・トゥ・バリュー(LTV)や、年収に対してローンをいくらまで借りることができるかを規制する債務所得比率(DTI)の規制のように、クレジットそのものの規制があります。また、金融機関のバランスシートに関して、自己資本比率規制の上げ下げや、流動性比率の規制もあります。さらに、金融のインフラ面では決済制度やディスクロージャーの改善も含まれます。
――マクロプルーデンス政策と不動産業向け融資の総量規制の問題を取り上げようとした動機は何でしょうか。
2008年のリーマン・ショックに端を発した米国のサブプライム問題から最近の欧州金融危機に至る一連の危機はまだ終わっていません。このグローバルな金融危機の中で起きていることは、日本がこれまでに経験してきたこと、つまりバブルの生成から崩壊に至り、その後、「失われた10年」といわれたのが15年になり、やがて20年にもなって閉塞感に覆われた状況になっていることと同じではないかと考えています。
日本がバブルで経験したことからは、バブルにどう対応すればいいのかという教訓が導き出せます。それは、マクロ経済政策においてバブルには早めに対応しなければいけないということです。バブルが起きている最中には、今起きていることがバブルであるということには気づきにくい。気づかないと対応が遅くなります。したがって、早く対応しなければいけません。
一方、プルーデンス政策については、これまで、どちらかというと個別の金融機関の健全性が重視されてきました。しかし、それだけを見ていたのでは、知らず知らずのうちに問題をため込んで、いつか大変な事態になる可能性もあります。そこで、システミックリスクへの対応をしなければいけない。これがマクロプルーデンス政策の観点です。どういう政策を打てばいいのか、については、今後、バーゼル銀行監督委員会による国際的に業務を展開する銀行の新たな自己資本や流動性に対する規制であるバーゼルⅢが実施に移されます。また、アイデアとしては、クレジットが過度に膨らむのを防ぐ信用規制もありますが、これは、よく考えてみれば、日本がバブルの生成から崩壊の過程で導入した不動産業向け融資の総量規制に似ています。そこで、一度当時に立ち戻って、この規制を今日的視点から見直して、将来へのインプリケーションを引き出してみたいと思ったのが動機です。
欧米で進むマクロプルーデンス政策の体制づくり
――欧米諸国などでは、どのような体制がとられているのでしょうか。
米国では、監督機関がバラバラであったことが問題になりました。銀行に関して全国的には連邦準備理事会(FRB)や通貨監督庁(OCC)があり、各州の銀行は州ごとに監督当局があります。それとは別に証券業は証券取引委員会(SEC)が監督するというように、金融機関の中でも監督機関が分かれています。そこで、こうした機関を覆う大きな傘をつくろうということになって、金融安定監督評議会(FSOC)が設置されました。このFSOCがマクロプルーデンス政策の状況について議会に報告する体制をつくりました。これは法的に定められたもので、事務局は財務省の中に設けられました。まだ発足したばかりであり、今後の動きを見ていかなければなりません。
英国では中央銀行であるイングランド銀行(BOE)がマネタリーポリシーを担い、英国金融サービス機構(Financial Services Authority: FSA)が金融機関を監督していますが、この2機関に財務省を加えた3者の間の連携がうまくいかないことが、住宅金融会社のノーザン・ロックの破たんを招くことになりました。この反省から、中央銀行に監督機能を集約させる方向で動いています。
欧州でも大きな傘をつくることで合意しています。欧州システミックリスク理事会(ESRB)というマクロプルーデンスに責任を持つ機関が設立され、ミクロプルーデンスを担う欧州銀行監督機構(EBA)、欧州証券市場監督機構(ESMA)、欧州保険年金監督機構(EIOPA)とともに欧州金融監督者制度を構成することになりました。ただ、欧州中央銀行(ECB)のもとに銀行監督を一元化することを柱とする欧州銀行同盟という構想が浮上しており、そのもとにどういう銀行が入るのか、議論が行われている最中です。いずれにしてもECBがプルーデンス政策面でも重要な役割を担うことになります。
地価は下がったがバランスシートは傷む
――不動産業向け融資の総量規制の導入には、どのような背景があったのでしょうか。
1980年代後半から不動産バブルが発生して、主に東京の地価が高騰しました。この背景には、東京がやがて世界の金融センターになるとの期待があり、そうなればオフィス需要が高まるとの思惑から商業地の地価が高騰していきました。1987~88年には大阪や名古屋に地価高騰が波及し、さらに地方の各都市にもおよんでいきました。サラリーマンが首都圏で家を建てることができないという状況になり、「持てる者」と「持たざる者」との間の不公平への不満が高まったため、土地監視区域制度の強化など、いろいろな対策がとられましたが、地価高騰は収まりませんでした。こうして1990年3月に公示された同年1月1日時点の地価に示された前年1989年の上昇率で不動産バブルは決定的になりました。そこで、最後の手段として不動産業向け融資に対して、強力な信用規制が導入されたのです。
――不動産業向け融資の総量規制はどのような結果をもたらしましたか。
これがきっかけになって、土地バブルは崩壊しました。土地の価格はずっと下がり、資産デフレのきっかけになりました。商業地の公示地価の前年比上昇率を見ると、東京圏が1987年に6割を超す上昇を見せ、89年には大阪圏が5割近く、名古屋圏も2割を超す上昇を示していました。全国平均では、86年から90年まで2桁の上昇が続きました。それが91年から一転して全国平均でマイナスとなり、その後下落が続きます(図表1)。全国銀行の貸出残高を見ますと、不動産業向け貸出は87年に3割を超す伸びを示し、90年まで2桁の増加が続きましたが、91年以降は1桁の伸びに落ち着きました(図表2)。地価の高騰に歯止めをかけるという目的は達成し、家を建てるということがサラリーマンの手の届くところになるということは実現しました。しかし、そうした目的を上回る地価の下落が続いたことで、土地を保有している会社や、そうした会社に貸している銀行のバランスシートが傷むことになりました。
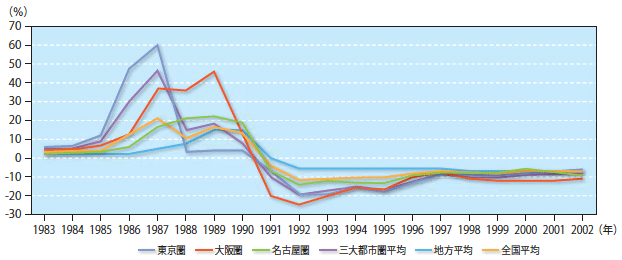
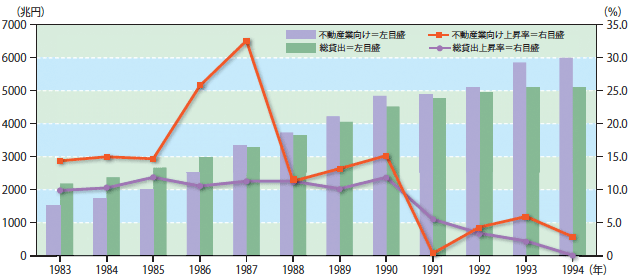
その一方で、こうした資産デフレの原因を、すべて不動産業向け融資の総量規制に帰すと考えることは早計だと思います。不動産バブルが生成したと考えられる1989年は、同年5月の公定歩合引き上げ以降、強力な金融引き締めが行われ、その後地価税も導入されるなど、ある時点から地価を引き下げる政策が一気にとられたのです。
――不動産業向け融資の総量規制について、どのような評価ができますか。
不動産業向け融資の総量規制は、あくまで土地関連の政策として導入されました。地価高騰の背景には、不動産業向け融資が大量になされているという事実がありましたので、1990年の時点では、不動産業向け融資の総量規制を導入しないという選択はありえなかったと思います。総量規制という政策は、土地対策という軸から評価して見れば、地価の高騰をストップさせ、地価を下げるのに寄与したことは明確でしょう。
また、金融政策が不動産バブルを生んだとされますが、1980年代後半は一般物価が落ち着いていました。国際協調の面からも、「日本はもっと低金利にしてくれ」といわれており、金融引き締めには動きづらかったのです。こうした中で、1989年5月以降の金融引き締めは不動産業向け融資の総量規制とタイミングが一致しており、不動産バブル崩壊には効果がありました。
債権問題が起こる、という思慮が必要だったわけです。また、当時は、とにかく「土地の値段を下げろ」という声が大きく、不動産業向け融資の総量規制を解除するのも大変でした。解除に対しては「まだ早い」の大合唱でした。この背景には、土地の価格は上がるけれども下がることはない、という神話があったのです。
1989~90年には、地価の上昇が地方都市にまでおよんでいましたので、それに先行した首都圏の地価高騰の時期である1987~88年が重要な時期だったと考えられます。一般物価が落ち着きを見せていたこの時期に不動産業向け貸出をペースダウンさせることができれば、金融引き締めのときには不動産向け融資の規制は解除していくという方法で「山をならして谷を浅くする」ことができ、資産デフレ問題に対し、より望ましい結果が引き出せた可能性があります。
しかしながら、ミクロプルーデンス政策では、こうした発想は出てきません。なぜなら、土地の値段が上がっている段階では、不良債権はなくなりますので、個別の銀行にとっては問題ないことになります。したがって、何か対策をとらなければならないという認識は出てこないからです。これに対して、マクロプルーデンスの視点から見れば、地価の上昇に伴ってリスクがため込まれているのではないか、という疑いが生じます。当時は、この発想が欠けていたわけです。
また、別の視点として、1980年代には「規制は悪である」という発想が広がっていました。銀行を監督する当局は、当時、預金金利の自由化や銀行店舗の立地の自由化などによって銀行間の競争を促し、利用者の利便を図るとともに銀行業務の効率性を向上させようとしていました。当時の環境では、自由化と逆に、何かに歯止めをかけるという規制は、導入しにくかったのです。不動産業向け融資の総量規制も世論に押されてやむにやまれず導入したというところがあって、結果的に地価の上昇に対して早めに導入することにはならなかったのです。
不明確な政策当局間の連携
――日本におけるマクロプルーデンス政策の体制はどのようになっているのでしょうか。
日本はバブルの生成と崩壊を経験しました。これを踏まえて金融庁に金融機関の監督を一元化しました。金融庁の設置法には金融の円滑化や安定化を図るとあり、システミックリスクを予防するというマクロプルーデンス政策の役割は、法制度上は金融庁にあります。一方で、日銀もマクロプルーデンス政策の発想を持っています。したがって、両機関がマクロ政策を議論して問題意識を共有し、連携して政策を打ち出していくことが望ましいと考えられます。現段階でも、両機関の関連部局は日常的に情報交換を行っているようですが、残念ながら、その協力の実態は外部には明らかになっていません。マクロプルーデンス政策では、個別の問題が起きる前に早めに手を打っていかなければなりません。この点がやや不明瞭になっています。
米国ではFSOCの事務局は財務省に置かれるなど、財務省が包括的な役割を果たしています。他方、日本には、マクロプルーデンス政策に関係する機関として、財務省、金融庁、日銀、預金保険機構などがありますが、これらを包括するものがないのです。
マクロプルーデンス政策については、一般物価を考慮しながら、不動産価格の動向など、同時に起きている別のことに、マネタリーポリシーとしてどう対応するかも問題になります。日銀の白川方明前総裁や西村清彦前副総裁は、「一般物価だけでなく、ほかの面も見ていかなければならない」という趣旨の発言をしています。国際的には、「バブルが発生することは仕方のないことで、バブルがはじけたときにどう対応するかが重要だ」とするFEDビューと、「一般物価だけでなく、事前の金融政策が重要である」というBISビューがあり、リーマン・ショックや米欧の住宅バブルの崩壊などから、FEDビューの旗色は悪くなっています。両者の発言はBISビューに近いものですが、こうした認識が日銀だけでなく、金融に関係する部門に共有されているのかは疑問です。
――マクロプルーデンス政策を進める上での課題は何でしょうか。
欧米ではマクロプルーデンス政策の体制をつくった上で、国民への説明責任を果たすために報告が行われる体制が組まれています。しかし、日本では、日銀が年2回レポートを発行しているだけで、国全体として統一した見解を示すものがありません。国民から見ると、金融システムに問題があるのか、ないのか、あるとすればどうするのか、といったことがきちんと議論されているのかも見えないというのが実情です。こうした体制はバブルが発生した1980年代後半と変わっていないのではないでしょうか。金融危機は必ず繰り返されるものです。現在も続いているグローバル危機は、過去にバブルの生成と崩壊を経験した日本にとっても、対岸の火事ではないのです。欧米の危機を教訓に、日本に欠けているものは何かを真剣に考えるべきでしょう。
――今後の研究についてお聞かせください。
金融危機は必ず繰り返されると言いましたが、なぜ繰り返されるのか、について、過去の事例のサーベイに基づいて検証したいと思っています。そこから、いずれ日本でも起こるものとして、将来の金融危機にどのように備え、対処すべきか、というインプリケーションが導き出せると考えます。
解説者紹介
1979年東京大学法学部卒業後、日本銀行入行。営業局、ロンドン駐在、大蔵省銀行局総務課長補佐(出向)、調査統計局企画調査課長、同経済調査課長、大分支店長などを経て、2004年より2年間RIETI上席研究員(出向)。日本銀行へ帰任後、金融機構局参事役、同審議役を経て2011年日本銀行退職。2012年より現職。主な著書に『リスク、不確実性、そして想定外』(日本経済新聞出版社・2012年)、『リレーションシップバンキングと地域金融』(日本経済新聞出版社・2007年/筒井義郎との共編)、『地域情報化と金融』丸太一・国領二郎・公文俊平編「地域情報化認識と設計」補論1(NTT出版社・2006年)


