| 解説者 | 大西 宏一郎 (大阪工業大学)/長岡 貞男 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0080 |
| ダウンロード/関連リンク |
新たな技術・製品開発の担い手として、大学院の博士課程で高度な教育を受け、高い能力を身につけた「博士(課程博士)」の活躍が期待される。しかし、現状は、高学歴人材に対する産業界のニーズは決して高くない。一方で、日本企業の中には、博士号を持たずに入社し、職場での研究活動をベースに学位を取得する「論文博士」が多数存在する。それでは、この2種類の博士は、企業内でどれだけの発明を生み出しているのだろうか。それぞれの発明生産性に差異はあるのだろうか。こうした疑問に答えるべく、大西宏一郎・大阪工業大学講師と長岡貞男PD/FF(一橋大学イノベーション研究センター教授)は、客観的なデータを用いて企業で働く博士のライフサイクル発明生産性を分析した。
――まず、今回の研究に取り組まれた問題意識について教えてください。
大西: 経済を成長させるには、優れた技術や製品を開発する必要があります。資源小国である日本において、特に技術・製品開発は生命線であり、それを担う人材への社会的な期待は非常に大きいといえるでしょう。そうした高度な能力を持つ人材を代表するのが博士、つまり博士号の取得者です。
ところが大学院に進み博士号を取得した人材が産業界から引く手あまたかといえば、決してそうではありません。博士号の取得者に対して「タコツボ志向で視野が狭い」「プライドが高く指示を聞かないから使いにくい」といった印象を抱き、彼らを採用することに消極的な企業も少なくないのです。
長岡: 文部科学省は1990年代に、産業界で活躍する博士が将来的に増えていくと予測して、博士号取得者の増加を政策的に後押ししました。ところが実際には、そうした高学歴人材に対して産業界からニーズは高まらず求人はあまり増えませんでした。結果として博士号は取ったものの、それにふさわしい就職先が見つからないというケースが多発しています。これが、いわゆる「ポスト・ドクター(ポスドク)」「オーバードクター」問題で、状況はかなり深刻です。この問題は、日本に限らず世界各国で顕在化しています。企業になかなか入れないので、博士号取得者は大学や公的な研究機関で働こうとしますが、その場合も常勤研究職には就けず、非常勤職員として雇用されるケースが多いのです。
大西: 高度な教育を受け、高い能力を身につけた人材の活用が進まないのは、教育を受けた個人のみならず日本社会全体にとっても大きな損失です。
それでは、実際のところ、博士号取得者を敬遠する産業界の声は的を射ているのでしょうか。つまり、博士号取得者は企業に入っても、さほど活躍していないのでしょうか。それとも、一旦企業内に入れば、期待に応えるだけの実績を上げているのでしょうか。
こうした問題は、感覚的に議論しても意味がありません。データから明らかにして、産業・教育政策や企業経営に資するべきです。私たちはこのような問題意識から、企業で働く博士のライフサイクル発明生産性、つまり生涯的な発明生産性を客観的なデータから分析することにしました。
企業内には2種類の博士、「課程博士」と「論文博士」
――ときどき「論文博士」という言葉を耳にします。これは通常の「博士」とは違うのでしょうか。
長岡: 日本での博士号の取得方法には2通りあります。大学院の博士課程に進んで博士号を取得するのが第1の方法です。これを「課程博士」と呼びます。もう1つの方法が、大学の学部を卒業したり大学院の修士課程を修了したりした後に企業に就職し、職場での研究活動をベースとして博士号を取得するケースです。つまり社会人になってから博士になる仕組みで、日本ではこれを「論文博士」と呼びます。欧米では、ドクター(博士)と言えば課程博士が当たり前で、それ以外のケースは稀です。逆に欧米と違って日本では論文博士が多く、博士号取得者の実に半分程度が論文博士なのです。
――なぜ日本だけで論文博士というシステムが普及・定着したのでしょう。
長岡: 色々な要因が考えられますが、1つには日本の産業界がフレキシブルだからではないでしょうか。欧米の企業は大学院で博士号を取得した人材を中心に研究職を採用します。これが固定的なやり方になっていますが、日本の企業は博士号の未取得者を採用し、その人材を企業内で育てて優れた研究者に磨き上げる傾向があります。博士号を取得していない社内の研究者に博士論文の執筆を奨励したり、国内留学させたりする企業もたくさんあるのです。このような企業側の努力もあって、非常に優れた業績を上げている論文博士がたくさんいます。
たとえば血液中のコレステロール値を低下させる薬物「スタチン」の発見者として国際的に著名でノーベル賞候補にもなっておられる生化学者の遠藤章先生はもともと学部卒です。また関節リュウマチへの特効薬として世界各国で承認された国産初の抗体医薬品「アクテムラ」を開発された大杉義征先生は修士課程修了です。
初めて論文博士に着目、学歴による研究開始時期の違いを考慮して分析
――本研究の革新性は、どのような点にあるのでしょうか。
大西: 課程博士、論文博士を含めた学歴と発明生産性の関係を、15~30年程度の比較的長期のデータを使って明らかにしている点です。論文博士の生産性に着目した研究は国内外を通じて初めてだと思います。論文博士というシステムがない海外で、それに着目した研究がないのは当然ですが、国内でも論文博士に視点を当てた研究はありませんでした。
課程博士は大学院の博士課程に進み、そこで博士号を取得してから企業に入ります。ですから企業で研究職として活動を始める時期は、学部卒や修士修了の人より遅くなります。本研究では、こうした学歴による研究開始時期の違いを考慮してライフサイクル発明生産性を分析しました。
長岡: 基礎データとして「RIETI発明者サーベイ」の情報を使用しました。このサーベイは、RIETIが「日本企業の研究開発の構造的特徴と今後の課題」研究プロジェクトの一貫として実施したものです。2007年の1月から6月にかけて日本の研究開発を担っている発明者を対象に、その発明と、それをもたらした研究開発プロジェクトについて調査し、5300件近くの回答を得ました。質の高い特許を中心に調査し、日本、米国、欧州特許庁(EPO)のすべてに出願された経済協力開発機構(OECD)の3極特許を主な調査対象としました。それまで日本で実施されてきたイノベーション関連の調査には、科学技術政策研究所の全国イノベーション・サーベイ(2004)、特許庁の知的財産活動調査(2003年から毎年)、企業活動基本調査などがありますが、いずれも企業ベースの調査です。これに対してRIETI発明者サーベイは発明者本人にアンケート調査し、研究開発の過程や発明者のプロファイルについて、詳細な情報を得ています。
更に本研究で整備し利用したデータはパネルデータ、つまり時系列データとクロスセクションデータを合わせたものです。このデータを用いることで、本研究では企業で働く博士の発明生産性の時系列的な変化をとらえることができました。また博士の学歴や勤務場所、所属企業の属性など、さまざまなコントロール変数を使った分析も可能になりました。なお本研究では発明者名の名寄せの都合から、1つの企業に長期間にわたって勤務している約1,700人の発明者を選び出して分析対象としました。
大西: 発明生産性を測る指標として、特許出願件数という客観的なデータを用いました。特許出願件数から博士の生産性を分析した研究は、過去にもいくつか存在します。総じて博士の生産性が高いという結果が出ていますが、それらの研究の多くは課程博士の研究開始時期が遅いことを考慮していないため、その発明生産性を過大評価する可能性がありました。私たちが把握している範囲では、研究開始時期の遅れを考慮した研究も1つだけありますが、その研究では博士の生産性の高さは統計的に有意ではないとの結果が出ています。つまり博士の発明生産性について、過去の研究の分析結果は一致していなかったわけです。本研究では研究開始時期の遅れを考慮したうえで、数値によって明確な結論を出そうとしました。
分析結果を述べる前に、今回分析に用いた発明者の生涯での特許出願件数とその被引用件数を、件数別に対数変換して見たのが図表1と図表2ですが、おおよそ正規分布する傾向にあることがわかります。これは一部の人の生産性が非常に高く、大部分の人はゼロに近い近辺に分布していることを表しています。このような傾向は、社内の研究者や大学研究者の生産性を分析した先行研究で頻繁に観察されるものです。つまり、社内の研究者でも、個人間でその生産性に大きな差があることを示しています。生産性の差を決める要因は、企業の出願傾向や職場環境、研究に従事した期間など色々あります。我々の問題意識は、そのような要因をコントロールしても、依然として学歴で説明できる部分が残るのかというところにあります。
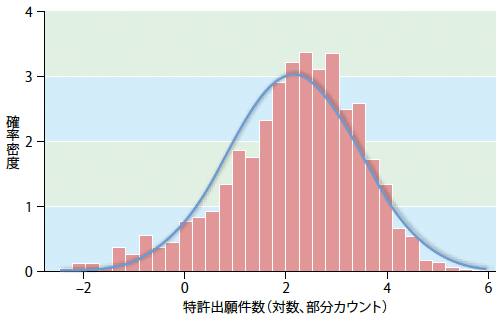
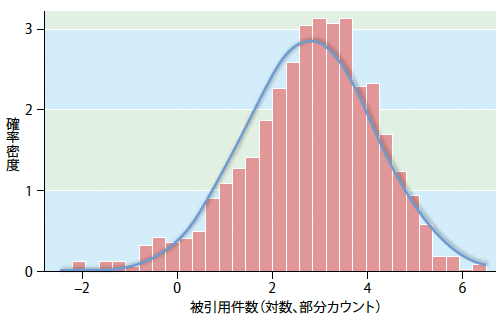
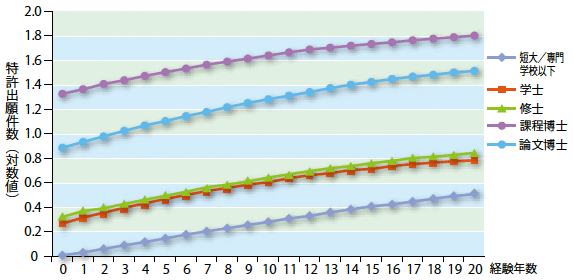
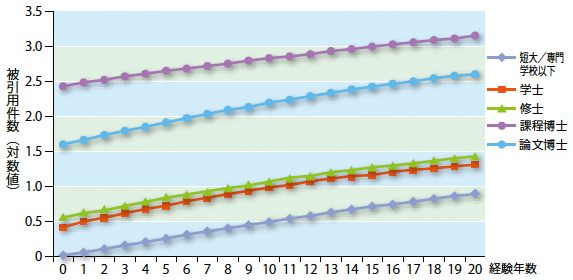
両博士とも発明生産性は高水準
――分析の結果、どのような知見が得られましたか。
大西: まず、課程博士のライフサイクル発明生産性、つまり生涯的な発明生産性が高いとの知見が得られました。課程博士は大学院の博士課程に進み、そこで博士号を取得してから企業に入ります。したがって発明開始時期が遅れるわけですが、その点を考慮しても特許出願件数、被引用件数の両面で課程博士の生産性は統計的に有意に高く、ライフサイクル全体で修士課程修了者より約63%高いことがわかりました。こうした差は企業間の違い(固定効果)、その特許出願性向や規模の時系列的な変化、職場環境の違い、従事している研究プロジェクトの性格、研究分野間の違いなどに加えて個人のモチベーション、性別、観察できない個人の能力差をコントロールしても依然として残ります。
次に、課程博士の発明生産性は論文博士より38%程度高いことがわかりました。ただし、その差は統計的に有意ではなく、課程博士と論文博士は同程度の生産性を持つといえます。これは本研究によって初めて得られた知見です。
さらに、①課程博士は企業に入った直後から高い発明生産性を示し、その高い生産性は長期にわたり持続する、②論文博士は企業に入ってから発明生産性が大きく上昇する傾向がある――ことがわかりました。こうした傾向があることは従来から予測されていましたが、本研究で統計的に実証できました。
――政策的なインプリケーションはいかかですか。
大西: 本研究で、論文博士の発明生産性が課程博士と同程度に高いことがわかりました。つまり論文博士は、研究者として企業に大きく貢献しているといえます。また、論文博士の取得は、研究能力を表すシグナリングとしての役割や、研究に対するモチベーションの維持に役立っていることも考えられます。論文博士については、「企業から寄付を受けた大学が、その見返りに企業内の研究者に博士号を与えているだけでないか」といった見方があり、その増加を抑えて課程博士の育成に力を入れるべきだとの声も出ていますが、本研究から得られた知見から考えれば、論文博士を政策的に減らすことは合理的ではありません。
課程博士のライフサイクル発明生産性の高さが実証されたことにも、大きな政策的インプリケーションがあります。企業の研究能力を高めるには、より積極的に課程博士を活用すべきであることが示唆されたわけですから、政策的には課程博士の育成が重要ということになります。ポスドク問題が深刻化しているのは事実ですが、だからといってその育成を怠ってはならないでしょう。
課程博士の採用は企業に有益、論文博士の育成も得策
――企業経営に資する知見もありますか。
大西: 課程博士は論文博士と違い、企業が資金と時間をかけて育成する必要がありません。にもかかわらず課程博士の発明生産性は入社直後から高く、しかもそれが長期にわたって持続するのですから、発明開始時期の遅れを考慮しても、企業にとっては「お買い得」です。企業は「使いにくい」などといわず、課程博士の採用に前向きに取り組み、その能力を経営改善に生かしていくべきではないでしょうか。
長岡: 論文博士の育成・支援も大切です。企業などの中には、技術情報の流出を懸念し、研究者に「学術論文を執筆してはいけない」と指示するケースがあるようです。論文の発表を認める企業でも、勤務時間中の執筆を禁止することがあると聞きます。しかし、それでは研究者の自己研鑚の機会が減り、長期的に見れば企業にとってマイナスとなる恐れがあります。
――金利動向にはどの程度注意すべきでしょうか。
大西: 教育の効果を測る研究はたくさんありますが、教育効果の過大評価につながる学歴と能力の相関性を完全に排除するのは困難です。今回の研究では博士の出身大学の偏差値などを変数に用いたり、パネルデータを用いて固定効果推計を試みていますが、それでは十分ではありません。また、今回の研究では課程博士の発明生産性が高いことがわかりましたが、それは特許を出願した人、言い換えれば企業に入って活躍している人だけを分析対象にしたためかもしれません。もともと企業に採用されていない課程博士が、新たに採用されたとしても同様の生産性を発揮できるとは言い切れないのです。
さらに、企業における研究者の役割は研究だけではありません。研究職として入社しても、やがて管理職になって研究活動から離れる人がたくさんいます。特に日本では、優秀な研究者ほど管理職になる傾向があるのです。つまり企業は研究者にマネジメント能力も求めているわけで、それが課程博士の採用に消極的な理由の1つになっている可能性があります。今後は、こうした問題点を踏まえ、一段と踏み込んだ研究に取り組みたいと考えています。
長岡: このほか、産業界と大学をはじめとする教育界のミスマッチにも着目しています。産業界が研究職として採用したい人材と、大学が研究者として育成したり雇用したりする人材では、質がかなり違います。たとえば日米とも国策としてバイオテクノロジーの研究を推進し、この分野で多くの博士号取得者が誕生しましたが、雇用先側を見ると、肝心のバイオ産業の成長は限定的で、博士号を持つ人材の受け入れ先は限られています。このため日米とも多くのオーバードクターが出ているのが実情です。これはミスマッチの典型であり、このような問題をいかにして少なくしていくか、そのために産学連携で何ができるかは重要な政策課題となっています。この問題についても、研究する必要があると感じています。
解説者紹介
東京大学工学部卒業。1980年マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院よりM.S(.経営学)、1990年マサチューセッツ工科大学経済学部よりPh.D.(経済学)。1975年通商産業省入省後、1986年世界銀行へ出向。1992年成蹊大学経済学部教授。1996年一橋大学商学部付属産業経営研究所教授。1997年より一橋大学イノベーション研究センター教授、2008年からは同センター長兼任。この間、産業構造審議会の臨時委員、OECDの貿易と競争政策ワーキンググループの事務局、WIPOの事務局長アドバイザー、公正取引委員会競争政策研究センター主任客員研究員などを務める。

大西 宏一郎
横浜市立大学商学部卒業。2007年一橋大学大学院経済学研究科博士課程修了、2005年財団法人知的財産研究所研究員、2006年文部科学省科学技術政策研究所研究員を経て、2009年現職。


