| 解説者 | 深尾 光洋 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0079 |
| ダウンロード/関連リンク |
日本の財政赤字の水準が看過できない状況にあることは、疑うべくも無い。財政破たんを回避し、健全化するための方途はどこにあるのだろうか。
RIETIの「社会保障・税財政」プログラムの深尾光洋PD/FFは、今回のDPで特にバブル崩壊後の日本経済をマクロ的な観点からとらえ、日本の長期的な潜在成長率の低下、長期化するデフレの実態、政府債務と利払い負担などの現状を概観した。分析の結果は、財政に対する信頼性を取り戻すためには、少なくとも消費税で20%程度に相当する50兆円程度の歳出削減ないし増税が必要であることを示している。また、財政再建の有効な方途と考えられている「デフレからの脱却」について、10年前と比べて政府債務が巨額になってしまっている現状では、政府の利払い負担を急増させることで政府信用を悪化させるリスクがあると指摘する。
――まず、今回の論文執筆にあたっての問題意識をお聞かせください。
ヨーロッパのソブリン危機を見ても分かるように、財政危機は国の経済に非常に大きな悪影響を与えます。たとえば財政危機に陥ったギリシャは国債の金利が非常に上がっています。その一方で、日本では今のところ金利は上がっていません。日本政府の総債務の対GDP比率は233%と、ギリシャの166%(2011年末現在IMF見通し=以下同)を大きく上回っています。また負債から金融資産を差し引いた政府の純債務で見てみても日本は131%に達しており、ギリシャの153%に近づきつつあります。こうした厳しい状況の下で日本の金利がなぜ安定しているのか。ヨーロッパ周辺国の財政危機の構造と、日本の財政問題の構造のどこに違いがあるか。日本の金利が今後上昇していくシナリオが考えられるのか。こういった点をしっかり整理してみる必要があると考えました。
欧州の中で財政危機に見舞われた国を見ると、ギリシャやポルトガルは中進国の水準ですが、アイルランド、さらにスペインとなると先進国に近づいてきます。そういった国でも財政危機が起きるということは日本もしっかり考えておかなければなりません。他方で、欧州のユーロ圏の国々は独自の金融政策を持っていません。そうした日本とは異なる条件も含めて考察をする必要があると考えます。
――論文の全体の流れや構成について紹介してください。
景気の現状、成長力、財政収支の見通し、財政赤字削減に伴う落とし穴あるいは財政破たんのシナリオという順序で分析を進めていま。
こうした構成となったのは日本の財政の維持可能性のシミュレーションについて分かりやすく提示したいという考えが基本にあります。まず日本の財政がどの程度深刻なのかという点を見なければなりません。また野田内閣で消費税が現行の5%から10%に引き上げられることが決まりました。税率が倍になるのですから、大規模な増税といえますが、それでどの程度赤字を削減できるのか。そして増税によって日本の財政再建を安定軌道に乗せられるのか否かの相場観をしっかり見る必要があると思います。
こうした分析を行うためには、前提条件として日本の今後の潜在成長率を推計する必要があります。また当然のことながらなぜ日本の過去の成長率がここまで下がってきているのかの議論もしなければなりません。日本の生産性の上昇は、米国に比べ非常に低いのか、あるいは少子高齢化といった人口動態の変化を考慮すると相応なのか、なども検討する必要があります。将来の潜在成長率が推計できれば、それを前提として、今回の増税案がどの程度評価できるのかが分かりますし、逆に将来の財政の維持のためにはどの程度の増税が必要かも分かります。その上でリスクや落とし穴の分析も可能となるというわけです。
また「日銀がお札を刷れば物価が上がる」といった主張をよく耳にします。確かに金融政策として量的緩和はある程度有効だったことは事実ですが、それがどのようなときに有効で、どのようなときには意味がなくなるか。最近イングランド銀行のキング総裁も米FRB(連邦準備制度)のバーナンキ議長も量的緩和の限界について少しずつ言及をし始めるようになりました。その点についても、補論という形ですが議論をしています。
日本経済の不運と逸機
――90年以降のマクロ経済の動きについて、どのように分析しておられますか。
鉱工業生産指数を見ると景気が相当回復してくると、マイナスショックを受けて逆戻りしたことがこの間に4回はあります。94年の超円高、97年の金融危機、2008年のリーマン・ショック、2011年の東日本大震災です。
日本経済を振り返るとバブル崩壊はある程度仕方ないという実感がします。「山高ければ谷深し」です。80年代にあれだけ金融緩和を継続したのは、日銀に対する外部からの圧力もありましたし、日銀自身の判断の甘さもあったと思います。バブルをいったん作ってしまった以上落ち込むのは当たり前で、いわば自業自得といえるかもしれません。しかし90年代初頭の超円高については、「運の悪さ」によるものである可能性があります。あの時期に1ドル=80円を一時突破するような円高になった要因は、国際収支や金利についてどう分析してもなかなか合理的な説明がつきません。
事実、市場の勢いともいうべき90年代初頭の円高はそののちに是正されましたが、97年の金融危機のあとで、日本はデフレに突入してしまいました。不運といえば2008年のリーマン・ショックもそうです。97年は一面自業自得ともいえますが、リーマン・ショックは「とばっちり」という側面が強い。しかもその影響力は金融危機のときよりも大きく、経済の落ち込みも非常に深刻なものになりました。さらにその回復の途中で2011年の東日本大震災と原発災害が起こりました。
不運は不運として日本経済はチャンスも逃しています。それは小泉内閣の末期です。この時期にやはり消費税を上げておくべきだったと思います。2003~04年の円安誘導と量的緩和、そののちの中国や欧米の景気の拡大で鉱工業生産指数もバブル期をしのぐ水準にありました。ここで消費税を5%前後引き上げておけば、財政赤字の累積も少なくなるので、そのあとの処理はしやすかったと思います。この時代は財政赤字も順調に減っており、いわゆる上げ潮論で何とかなるという考え方が強かったわけですが、私は甘かったのではないかと考えます。年金や医療、介護保険のどれをとっても、特に後期高齢者向けの支出が増えてくるわけで、必死に抑え込みを図っても財政負担は大きくなるのは確実です。景気回復、特に円安だったあの局面は好機でした。
――潜在成長率について詳しいシミュレーションを行っていますが、結果はいかがでしたか。
潜在成長率の推計は長く手掛けているテーマです。経済企画庁(当時)時代から始まり、日銀の企画調査課長時代、またその後在籍した日本経済研究センターでも推計を続けていました。今回も同様の手法を用いて、慶応大の学生とともに一夏を使って算出しました。数字自体は内閣府や日銀が公表しているものと非常に近いものです。
推計の結果、2010年の潜在成長率は0.5%となりました。米国の潜在成長率は2.5%程度といわれていますが、米国の労働力人口(15~64歳)のトレンドの増加率はヒスパニック系の流入なども含めて年間1%程度あります。一方日本の場合は団塊の世代の大量退職などがあって多少上下はするのですが、平均すると年間マイナス1%くらいになります。潜在成長率は資本、労働力、生産性で構成されますが、その1つである労働力を比べると日米を比べると2ポイントくらいの差がありますので、0.5%という数字が米国に比べて見劣りするということもないと思います。
――将来の財政バランスの予測においては、どのような条件設定をされましたか。
GDP成長率はIMF見通しにおいて日本が潜在GDPの水準に達すると予測される2014年以降、先ほどお話しした潜在成長率年0.5%で推移、労働力人口の減少が加速する2031年からはゼロを見込んでいます。また、GDPデフレータ・インフレ率は14年にデフレを脱却し、以後はゼロインフレを見込んでいます。また消費者物価上昇率は、過去のGDPデフレータと消費者物価の上昇率格差の平均を考慮して1%弱を見込んでいます。重要な点は政府債務の平均金利で、デフレ脱却に伴い2011年の年1.1%から徐々に上昇して2016年に年1.5%に達しその後は横ばいで推移することを想定しています。
これらを含め前提は8つありますが、弱点から申し上げましょう。まず増税による景気の悪化をきちんとは見込んではいません。つまり増税をする場合に増収分の一部を景気刺激に充てることを想定し、それがうまくいった場合を想定しています。景気刺激を全く行わない場合、また景気刺激策がうまくいかなかった場合は景気が悪化して税収自体が落ち込んでしまいますが、それは想定していません。これはかなり楽観的な前提といえます。
もう1つは政府支出の対GDP比率について、利払い以外は横ばいを見込んでいます。これも非常に楽観的な見通しといえます。これを実行するには社会保障で全面的な所得テストを実施する、つまり一定以上の高所得者には年齢を問わず年金は支払わない、医療でも自己負担を求めるといった措置を導入して、社会保障費の伸びを強力に抑制する必要があります。もう少し具体的にいうと、たとえば年金については現在65歳の受給開始年齢をさらに数年間引き上げると同時に一定以上の所得がある受給者の給付を削減する、医療については高所得者の医療費は高額になる場合を除き全額自己負担にするなど、現状を大きく変更するような措置を導入するようなことが前提となります。
シミュレーションではこれらの前提のもとで景気回復時に段階的な増税を行うことを想定しています。その際には景気刺激策を実施しながらうまく軟着陸させていくというのが考え方の基本になっています。
金利上昇で一層の増税必要に
――予測の結果についてご説明ください。
上述のように、前提としてはかなり楽観的な内容を含んでいますが、結果としては2014年4月に2%引き上げ、15年10月に3%引き上げという現行の消費税増税方針では全く財政再建は図れず、プライマリーバランス(PB)を実現するためには、25%まで消費税を引き上げないといけないということが分かりました。
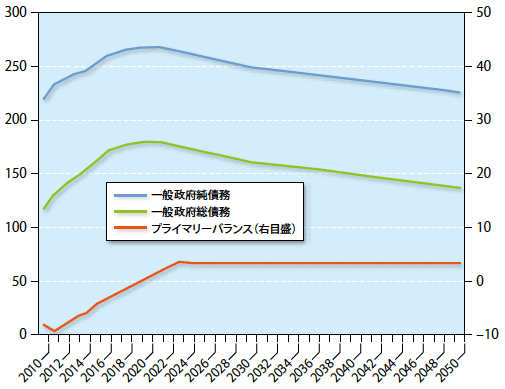
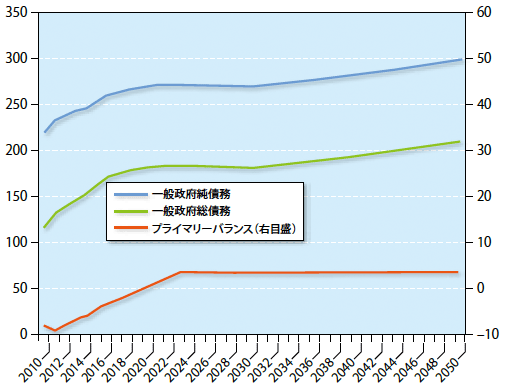
プライマリーバランスの赤字は2017年に4.1%と12年の9.2%から約5ポイント改善します。ですがこれでは政府債務GDP比率はどんどん上昇していきます。2022年に政府純債務が200%を、2024年には政府総債務が300%を超え、財政の維持が難しくなります。消費税を25%まで引き上げるシナリオ(2014~23年の10年間毎年2ポイントずつ増税を実施)ですと、2020年に政府の純債務の対GDP比が180%でピークをうち、その後低下に転じます。ただこの場合確かにプライマリーバランスは2024年以降3.4%の黒字となりますが、利払い負担が重いため、政府債務の対GDP比率の低下は極めてスローペースでしか進みません。
一方で、消費税を高率にすると、たとえば欧州諸国でもあるのですが、領収書やインボイスを残さないで現金取引するといった脱税行為が増えます。また例外品目を作ったり、軽減税率を導入したりする国も多いのですが、これをやると予定した税収が得られなくなります。先日も欧州の経済学者と情報交換する機会があったのですが、すでに高めの消費税を導入した経験者の助言として、「補助金は出しても良いが絶対に例外品目を設けてはいけない」と強調していたことが印象的でした。
財政再建の方法としては、消費税だけに頼る必要はないわけです。消費税率自体は段階的に20%以上まで引き上げる。他方で、未納問題が深刻な自営業者の定額の国民年金保険料の廃止や、厚生年金負担のうちの基礎年金給付部分(労使合計で約6%分)のカットによる正規雇用の負担削減等が考えられます。また炭素税を導入して段階的に引き上げると同時に、その税収の一部を使った法人税減税、省エネ投資や家庭の断熱工事に対する大規模な補助金の導入も有効だと思います。
――金利動向にはどの程度注意すべきでしょうか。
たとえば政府が支払う金利が2016年から21年まで毎年0.2ポイントずつ上昇し、2.5%にまで達したと仮定してシミュレーションしてみましたが、利払い負担の対GDP比が膨らんでしまい、プライマリーバランスの黒字分ではまかないきれなくなります。論文の中で式を示しましたが、政府純債務の対GDP比が1.4倍に達した現在の時点で金利が2ポイント上がった場合を想定すると、対GDP比で2.8%のプライマリーバランスの改善が必要になるという関係になります(1.4×2=2.8)。これは消費税5%引き上げで達成できると予想される税収の増加(対GDP比)2.5%を上回ってしまいます。
2000年ころは政府純債務のGDP比率は60~70%といったところですので、金利上昇が利払いに与える効果も小さく、デフレからの脱却を主張することも容易でした。しかし、その後、政府債務がどんどん巨額になっている関係で、金利上昇が財政に与えるリスクが大きくなっています。現在、財政がとりあえず維持可能であるのはゼロ金利が定着しているからです。日本のほか米国、英国、スイスなども事情は同様です。日本では「インフレ率3%を目指そう」という主張が見られます。少し考えてみますと、数年後には政府純債務はもっと膨らんで200%に近づきますので、金利が上昇した場合の利払い負担も大きく膨らみます。財政再建の道筋を明確に示しながら行わないと、デフレからの脱却自体が財政破たんのきっかけにもなりかねません。
――どうすれば財政破たんを回避できるのでしょうか。
今後、デフレから脱却して物価が上がり始める局面がやってきます。そのとき金融政策は緩和気味に維持して、すかさず増税を実施して景気の過熱を防ぐ。この増税によって財政赤字の拡大を防ぎ、財政再建につなげていくことが可能となります。これは非常に難しい作業になると思われます。飛行機にたとえると日本経済はいま失速しかけているわけですが、高度を落としながら一層スピードをつけて、機体を持ち上げていくという難度の高い操縦が必要となります。
ではどのようにしてインフレ局面になるか、もちろんすぐにではないのですが、国民が政府に対する信用をなくす時点がポイントとなります。現在日本の家計部門の純金融資産(金融資産マイナス負債)の多くは高齢者が保有しています。70歳以上が全体の4割、60歳台、50歳台がおなじく各3割を保有していると推計されています。これらの人々が直接的ないし間接的に巨額の国債を含む大部分の円資産を保有しているわけですが、政府の信用に疑念が生ずると、徐々に預金や国債から株式、不動産、または外貨に資産を移していくでしょう。バブル的な株高や不動産高による景気回復が見られるかもしれません。同時に高齢化の進展もあって経常収支は赤字になっていく。ですから円安となって輸出も増加します。このときにインフレ率が上昇し始めます。ここが増税のチャンスとなります。
ただしそのときに政府債務が巨額になっていると利払い負担増大のために赤字解消に必要な増税の幅が大きくなり、政治の安定が保てるか否かが問題となります。増税において負担を求められるのはやはり現役世代が中心となります。もちろん消費税は高齢者にも負担は発生しますが、彼らは社会保障でそれを取り戻すことが可能な年代です。そうなると高齢者が保有する金融資産の価値を維持するために、現役世代に重い税を課すのは公正かという議論も起きかねません。その時点で仮に政府が増税に踏み出せないとなると、破たんシナリオに突き進むことになります。つまりインフレが進み始めた時点でゼロ金利局面は終わりを告げる。これに伴って政府の利払いが急激に膨らみ、国債価格は暴落します。論文の冒頭で日本政府が戦中から戦後にかけて、ハイパーインフレを通じて財政再建を実現した経緯について考察をしていますが、インフレによって国債の実質価値を大幅に低下させることで「財政を健全化する」ことは確かに可能です。これはデフォルト(債務不履行)ではありませんが、実質的には財政破たんと同じことになります。
解説者紹介
1974年京都大学工学部卒業。1981年ミシガン大学経済学博士号取得。1974年4月日本銀行入行。1983年8月経済企画庁調査局、1991年経済協力開発機構(OECD)シニアエコノミスト、1997年慶應義塾大学商学部教授(現職)、2005年から2010年まで日本経済研究センター理事長を兼任、2011年より経済産業研究所プログラムディレクターを兼任。近著に「財政破綻は回避できるか」日本経済新聞出版社、2012年、「国際金融論講義」日本経済新聞出版社、2010年


