| 解説者 | 佐藤 清隆 (横浜国立大学経済学部教授)/清水 順子 (学習院大学経済学部教授) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0075 |
| ダウンロード/関連リンク |
2008年のリーマンショック以降、円高トレンドが続く日本円に対して、対ドル為替レートを観察するだけでなく、貿易相手国として重要性を増しているアジア各国の通貨を含んだ実効ベースで日々の為替変動を注視するニーズが高まってきている。こうした中、RIETI「国際マクロプログラム」(プログラムディレクター:伊藤隆敏PD/FF)の「通貨バスケットに関する研究プロジェクト」は、産業別名目実効為替レートに続き、2012年7月、産業別実質実効為替レートを公開した。このデータは、研究、政策立案、企業活動など幅広い分野での活用が期待されるが、さらに実際のデータ作成に携わっている清水教授、佐藤教授らが公表データの基となるアジア各国の産業別物価指数と貿易シェアなどの膨大な原データを使って行った解析により、電気機器産業の実質実効為替レートが他産業に比べて円安(=価格競争力が大きい)となっている要因など、政策含意に富む結果が明らかになった。
産業別・日次ベースでの円の名目・実質実効為替レートを計算
――産業別の実効為替レートを研究された動機は何でしょうか。
清水:私たちが所属するRIETI「国際マクロプログラム」(プログラムディレクター:伊藤隆敏PD/FF)」の「通貨バスケットに関する研究プロジェクト」(プロジェクトリーダー:小川英治FF)は、その前身である2005年の「アジアの最適為替制度プロジェクト」での研究の一環としてアジア通貨単位(AMU)のデータベースを構築し、RIETIのウェブサイトで公表しています(http://www.rieti.go.jp/users/amu/index.html)。通常、新聞やテレビなどで報道されている為替レートとは円の対ドルレートですが、これに対して、AMUはアジア各国の通貨に対して円がどのように動いているのかを表す指標になっています。そこからさらに一歩進んで、日本経済や日本企業にとってより役立つ為替指標をつくろうと考え、作成・公開したものが産業別の実効為替レートです。
円の実効為替レートとは、日本と貿易相手国の2国間の為替レートを貿易相手国のシェアに応じて加重平均した値であり、日本の対外競争力を測る指標として用いられます。この実効為替レートのデータは、各国の中央銀行や国際決済銀行(BIS)によって公表されています。特にBISのデータは包括的で、多数の国々の実効為替レートのデータを公表しています。日銀はBISのデータを採用していますが、これらのデータは月次であるため、急激に為替レートが変動しても、その翌月にならないと、実効ベースでどれだけ変動したのかがわからないという欠点があります。また、国全体の貿易ウエイトで計算しているため、産業別の競争力まではわかりません。
一方、米連邦準備理事会(FRB)や英国中央銀行(BOE)は日次ベースで自国通貨の実効為替レートを公表しています。円についても日次ベースで実効為替レートを公表すれば、多くの人にとって有益な情報となりますが、それが産業別であれば更に価値があるだろうと考えました。
佐藤:2008年にリーマンショックが発生してから、円だけがすべての通貨に対して増価しました。しかも、欧州諸国の財政危機が一段と深刻化するにつれて円レートは一段と増価し、2011年10月末には1ドル=75円32銭の戦後最高値を記録するほど円高が進行しました。こうした中で、日本の輸出企業が円高により深刻な打撃を受けているという報道が多く見られます。
確かに、日本企業全体として円高の影響を受けているのは間違いありません。しかし、円高の影響は産業によって異なる可能性があります。たとえば、日本の代表的な輸出産業である自動車とエレクトロニクスを考えてみましょう。自動車の場合は、欧米諸国など先進国への輸出に加えて、近年ではアジア諸国などに進出して生産拠点を構築しています。これら生産拠点は現地での販売を基本としており、日本からはエンジンなどの基幹部品が輸出されています。これに対してエレクトロニクスの場合は、アジア域内の工程間分業の進展により部品・中間財の域内取引が活発に行われていて、最終的な輸出先は欧米諸国になっています。こうした生産・販売構造の違いにより、日本企業が直面している実効為替レートは産業ごとに異なるのではないかと考えました。また、急速に円高が進んだ場合、月次データの公表を待っていては、企業が直面する為替レートをタイムリーに把握することができません。より速報性のあるデータ公表がよいと考え、日次ベースの実効為替レートを公開することにしました。名目と実質の両方の実効為替レートを産業別かつ日次データとして公開していますので、幅広い分野の研究に役立つのではないかと思います。
清水:産業別の名目実効為替レートについては、既に昨年6月からRIETIで公表を始めています。また、物価データを用いて実質化した実質実効為替レートについては本年7月からの公表となっています。
苦労した各国物価データの収集
――実際にはどのような作業をされたのでしょうか。
佐藤:まず、名目実効為替レートを産業別に計算する作業にとりかかりましたが、その際に日本国内で広く使われている産業分類に従って、繊維、化学、金属・金属製品、一般機械、電気・電子機器、輸送用機器、精密機器、その他製品の8つの分類を採用しました。そして、産業ごとに貿易相手国のウエイトを計算してそれら貿易相手国の通貨に対する為替レートを加重平均し、名目実効為替レートを計算しました。
次に産業別の実質実効為替レートを計算する作業を開始しましたが、まず物価データの入手に関して大きな困難に直面しました。産業別の実質実効為替レートを計算するためには、対象国すべてに共通の産業分類に従って物価データ(できる限り生産者物価指数)を入手する必要があります。
円ドルレートであれば、日本も米国も同じ産業分類で生産者物価は比較的容易に手に入ります。しかし、日本にとって今や最大の貿易相手は米国ではなくてアジアです。アジア諸国では先進国ほど統計面の整備が進んでいないことが多くあり、共通の産業分類で生産者物価指数を入手することができるのか、どこから入手することが可能なのか、最初はわかりませんでした。日本の主要貿易相手国と考えられる国の統計資料や政府・統計局のホームページをくまなくチェックし、必要なデータを探し当てるのに膨大な時間を費やしました。最終的に、各国共通の新たな産業分類に基づいてデータ収集と貿易ウエイトの計算を行い、円の実質実効為替レートを完成するのに1年近くかかりました。この作業の難しさが、産業別の実質実効為替レートが他の機関で公表されていない理由でしょう。
産業別の違いが大きい実質実効為替レート
――産業別の実質実効為替レートを計算して、どのようなことがわかりましたか。
佐藤:実質実効為替レートを計算した結果、産業ごとに為替レートの動きにかなりの違いが見られることがわかりました。ここ数年の円の名目為替レートは全ての通貨に対して増価傾向にありますが、産業別にみると、実質実効ベースで為替レートが大きく増価している産業もあれば、他の産業ほど増価せずにかなり円安の水準にとどまっている産業もあることが確認されました。BISなどが公表している実質実効為替レートはあくまで全産業の平均値ですので、こうした産業別の動向の違いは確認することができません。
図1において、日本の代表的な輸出産業である、電気機器、輸送用機器、一般機械の3つの産業の実質実効為替レートを見てみましょう。2005年を基準として、同年以降のデータを日次で計算していますが、3つの産業のなかでは、平均値(All:黒い実線)と比べて輸送用機器(Transport)がかなり円高の水準にあり、それに対して電気機器(Electric)は逆に平均値よりかなり円安の水準にあります。一方、一般機械(General)はほぼ平均値に近い水準で推移しています。
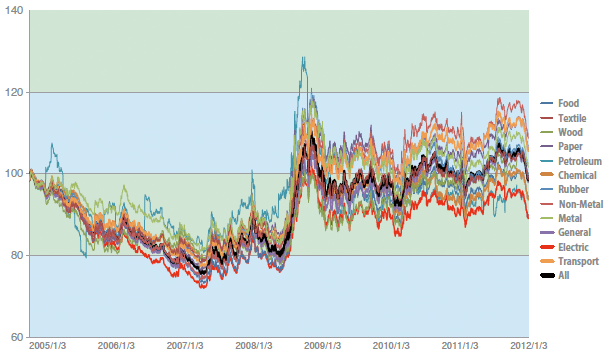
実質実効為替レートは、その産業の価格競争力をある程度反映していると考えられます。図1のデータを文字通り解釈すれば、輸送用機器(その代表的産業である自動車産業)は実質実効為替レートがかなり円高の水準にあり、同産業は円高の影響を受けて価格競争力が低下していることになります。一方、電気機器の場合は実質実効為替レートがかなり円安の水準にありますので、名目為替レートが円高に振れていても、他の産業と比べてかなりの程度価格競争力を維持していると解釈できます。しかし、電気機器産業の輸出企業は本当に実質実効ベースで測った価格競争力の高さを享受しているのでしょうか。実は上記のような解釈は実態を正しく把握していない可能性があります。
そこで、実質実効為替レートの変動を引き起こしている要因を調べるためにシミュレーション分析を行いました。具体的には、実質実効為替レートを自国の生産者価格、貿易相手国の生産者価格の加重平均、そして名目実効為替レートに分解し、どの要因が実質実効為替レートの変動を説明できるかを調べました。分析の結果、日本の電気機器産業の実質実効為替レートの変動は、同産業の生産者価格の低下によってもたらされていることがわかりました。これは他の産業には見られない、電気機器産業固有の特徴です。電気機器産業は非常に価格競争の激しい業界で、欧米企業との競争だけでなく、アジアでは韓国や台湾の企業とも激しい競争を行っています。同産業に属する日本企業は、貿易相手国と比べて自らの生産者価格を引き下げる努力をしており、その結果として実質実効為替レートが他の産業と比較して円安の水準にあると解釈できます。
清水:こうした分析結果は、最近の日本の電気機器メーカーの決算が赤字になっているという事実とも整合的です。
佐藤:電気機器産業の場合、輸出市場で厳しい競争を行っているだけではありません。日本国内の販売においても海外メーカーと競争しています。たとえば自動車産業の場合も日本国内に輸入車が入ってきていますが、日本国内で海外メーカーと激しい価格競争を行っているわけではありません。これに対して電気機器産業の場合は、海外の競争相手と輸出先でも競わなければならず、国内販売でも厳しい競争を勝ち抜かなければなりません。こうした国内市場での価格競争が、電気機器産業の生産者物価を引き下げているとも考えられます。
清水:実質実効為替レートの計算を通じて、産業間の円高進行度の違いを比較検討することができるようになりました。この結果を踏まえて、たとえば緊急円高対策をどの業種に重点的に行うか、などの重要な政策課題に反映することができると考えます。
――名目実効為替レートと為替レートの関係ではどのようなことがわかりましたか。
清水:名目実効為替レートは日本の貿易ウエイトによって各々の対円レートを加重平均した値ですので、計算上は日本の米国に対する貿易ウエイトの分だけ、名目実効為替レートは円ドルレートと連動することになります。しかし、実際に両者の関係を分析してみたところ、米国との貿易ウエイト以上に円ドルレートと連動していることが確認されました。実際の名目実効為替レートの動きは9割以上、円ドルレートと連動しています。
これは、米国以外の貿易相手国、特に日本の最大の貿易相手となっているアジア諸国の大半が、自国通貨を米ドルと連動させる為替政策をとっているためです。
産業別実効為替レートによる実証分析例:株価と為替レートの関係
――株価と為替レートの関係は産業別で差があるのでしょうか。
清水:一般的に円ドル為替レートが円高になれば日経平均株価が下がるといわれています。この関係が産業別にどのようになっているかについて、東京証券取引所の産業別の株価指数とRIETIの産業別の名目実効為替レートを用いて検証しました。その結果、一部の産業を除いて、産業別の名目実効為替レートが円高に振れると、産業別の株価指数は下がるという、負の相関があり、更にその強さは産業ごとに異なることが確認されました。この負の相関は、2008年のリーマンショック以降大きくなっています。
ここで、なぜ株価と為替レートの負の相関関係の強さが産業ごとに異なるのかを考えてみました。円レートが株価に影響をおよぼすルートには以下の2つがあると考えられます。第1に、ドル建てで輸出していた場合、為替レートが円高になると輸出企業が実際に受け取る円の収入が減ってしまいます。第2のルートは、海外現地法人の利益送金です。近年、海外進出により現地生産を行う企業が増えています。こうした日本企業の海外現地法人が、海外で稼いだ利益を日本に送金する際にも、円高の影響を受けます。特に、最近の日本の経常収支は貿易収支の黒字よりも所得収支の黒字の占める割合の方が大きくなっています。海外に生産を移転している割合の大きい産業ほど、利益送金の際に円高の負の影響を大きく受けると考えられます。そこで、産業ごとの海外現地生産比率と、円高が株価に与える影響の大きさ(産業別株価指数の為替感応度)をプロットしてみますと(図2)、海外現地生産比率の高い産業ほど、円高が株価に与える負の影響が大きくなるという関係が明らかになりました。
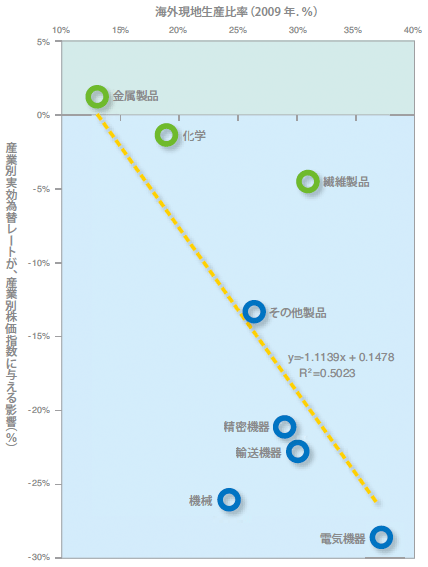
日本企業はプラザ合意以降、円高対策として積極的に海外現地生産を進めてきました。その結果、海外現地生産の割合が高くなりましたが、海外現地法人の利益もまた為替リスクにさらされているということがこの関係に表れているわけです。
産業別実質実効為替レートのデータをさらに拡張
――今後の研究課題は何でしょうか。
佐藤:今回は、日本の産業別実質実効為替レートを作成しました。同様の手法で、アジア諸国や米国、欧州諸国の産業別実質実効為替レートを作成したいと考えています。すでに中国や韓国の産業別実質実効為替レートの作成に取り組み始めたところです。次の仕事として、日中韓の産業別実質実効為替レートを比較し、その分析結果を論文にまとめていきたいと思います。
たとえば、中国は米国に対して巨額の貿易黒字を計上しており、米中間の貿易摩擦は深刻です。中国人民元の対ドル名目為替レートの水準がしばしば問題とされ、人民元レートをドルに対して切り上げるべきだと米国側は強く主張しています。私たちが中国人民元の実質実効為替レートを産業別に計算し、中国最大の輸出産業である電気機器の実質実効為替レートを公表することによって、中国の電気機器産業の国際的な価格競争力を検証することができるようになります。米中間の貿易関係を考える上で参考になるはずです。
また、韓国ウォンの名目為替レートは2008年9月のリーマンショック以降、大幅に減価しました。この大幅なウォン安によって韓国企業は日本企業が太刀打ちできないほどの価格競争力を得たと考えられますが、産業別の実質実効為替レートを計算することで、韓国企業の価格競争力を分析することも可能になります。
日中韓の3カ国のあとは、他のアジア諸国や米国、欧州諸国についても産業別実質実効為替レートの計算を進めていく予定です。こうして得られた実効為替レートのデータや検証結果は、日本だけでなく海外でも活用して頂き、企業の経営戦略や政策立案などに幅広く役立ててもらいたいと考えています。
解説者紹介

佐藤 清隆
横浜国立大学経済学部卒業。2001年経済学博士(東京大学)。2001年(財)国際東アジア研究センター上級研究員。2002年横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料センター助教授、2007年同センター准教授を経て現職。主な論文:"New Estimates of the Equilibrium Exchange Rate: The Case for the Chinese Renminbi," The World Economy, 35(4), 2012, pp.419-443 (with Junko SHIMIZU, Nagendra SHRESTHA and Zhaoyong ZHANG), "The Choice of an Invoicing Currency by Globally Operating Firms: A Firm-Level Analysis of Japanese Exporters," International Journal of Finance and Economics, forthcoming (with Takatoshi ITO, Satoshi KOIBUCHI and Junko SHIMIZU).

清水 順子
一橋大学経済学部卒業。Chase Manhattan銀行(東京)、日本興業銀行(London、本店)、Bankof America Int'l (London), Morgan Stanley(東京)等に勤務した後、1999年一橋大学大学院商学研究科入学。2004年一橋大学大学院商学研究科博士課程修了,博士(商学)取得。同年4月から一橋大学大学院商学研究科助手。その後、明海大学経済学部准教授、専修大学商学部准教授を経て、2012年4月より現職。主な著書:『東アジア通貨バスケットの経済分析』(共編著)(東洋経済新報社・2007年8月)、「グローバルインバランス、東アジア通貨間乖離と国際協調の必要性―AMUによる分析等」(共著)(『経済政策分析のフロンティア第3巻グローバル化と国際経済戦略』藤田昌久・若杉隆平(編著))(日本評論社・2011年8月)。

