| 解説者 | 宇南山 卓 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0064 |
| ダウンロード/関連リンク |
少子・高齢化の21世紀の日本社会において、経済成長のエンジンとしてプロダクト・イノベーションの重要性が増している。しかし、その影響を計測する方法は必ずしも確立しているわけではない。現在、生産性の尺度としては全要素生産性(TFP)が広く使われているが、このTFPには、計測に使われる投入量が統計上の制約から正確には把握できないことや、需要側の要因をとらえることが難しいといった弱点がある。こうした問題意識の下、宇南山FFらの研究グループは、「プロダクト・イノベーション」の重要性について、日本経済の産業構造変化や、個別のプロダクト・イノベーション事例など、多面的な研究分析を行い、イノベーションを後押しする政策を提言している。
――どのような問題意識から、この論文を執筆されたのでしょうか。
今回の論文は、私が所属するRIETI「少子高齢化のもとでの経済成長」研究プロジェクト(プロジェクトリーダー:吉川洋RC/FF(東京大学))の主要な研究成果を包括するものです。少子高齢化を巡ってはいろいろな問題がありますが、人口が減るということに注目しますと、何らかの形で生産性を上げないと経済成長ができないことになります。これまでは全要素生産性(TFP)を引き上げることが経済成長の源泉であると議論されてきました。しかし、プロジェクトリーダーである吉川FFの問題意識として、経済成長はTFPだけでは捉えられないだろう、という考えがあります。
また、プロダクト・イノベーションによる新しい製品やサービスの誕生が経済成長の主要な源泉になるということは、既存研究でも認識されていますが、その計測方法は確立されていません。そこで、私たちのプロジェクトでは、プロダクト・イノベーションの影響について、個別商品の開発事例などさまざまな角度から研究を行ってきました。
TFP では計れないイノベーション
――なぜプロダクト・イノベーションはTFPでは計測できないのですか。
理由は2つあります。1つは統計の問題です。TFPは、どれぐらいインプットがあったか、それに対して、どれぐらいアウトプットがあったかの差を、事後的に計るものです。しかし、統計の制約上、インプットを正確に計測することはできません。どれだけの資本が投入されたか、その資本がフル稼働しているかどうかは、統計上で正確に計ることは不可能です。まして、労働者に至っては、目まぐるしく働いている時もあれば、暇な時もあります。統計上こうした違いを捉えることはできません。
稼働率が上がる状態というのは、見かけ上、少ないインプットで多いアウトプットが生まれれば観察されます。たとえば、iPadが誕生して、それまでノートパソコンをつくっていた人がiPadもつくることになり、工場の稼働率が上がるとします。するとTFPが上昇したことになります。しかし、実際にはトヨタ自動車のカンバン方式のような生産プロセスにイノベーションがあったのではなく、単に売れる新製品が誕生して稼働率が上がっただけのことです。言い換えれば、TFPは需要の尺度となっていることになりますので、それを生産性の向上とみなすべきではないのです。より一般に、プロダクト・イノベーションが起きていれば、多くの場合で需要要因によってTFPが上昇します。TFPの結果としての上昇だけを捉え、経済成長の根本的な源泉とみなしてしまっては、経済成長の規定要因を正しく捉えることができないのです。
2つ目は、因果関係の解釈の問題です。稼働率が常に100%であると仮定すると、その場合はTFPが技術進歩の尺度になります。しかし、技術進歩というものは研究開発(R&D)投資によって達成されるものですが、そもそもR&D投資をするという動機は需要の動向に規定されているのです。
たとえば薄型テレビのケースでは、消費者が薄型テレビを欲しいということは生産者にも分かっていました。しかし、薄型テレビの誕生には多額のR&D投資による技術革新が必要でした。最終的には薄型テレビの需要が確実にあることが確認されてR&D投資が実行され、生産プロセスが革新されて薄型テレビが生み出されました。このケースでは、生産技術の革新によって成長が達成されたことは間違いありません。しかし、そもそもR&D投資をしたことの動機は、皆が欲しいものを的確に把握できたことに原点があります。その意味では、生産性の上昇ではなく、需要の把握そのものが成長の源泉なのです。
以上のことから、TFPは、2つの意味で後付けの説明になる可能性があることが分かります。多くのケースで、成長を規定しているのは需要の動向である、ということです。生産が伸びた時、TFPは必ず上昇しますが、実は成長の根源的な決定要因は需要要因であり、新製品の誕生であるといえます。
サービス産業の停滞が日本の低迷の原因
――戦後日本経済の産業構造の変化をスカイライン分析で検証されていますが、日米欧との比較結果はいかがでしたか。
産業構造の変化に着目したのは、どんどん新製品が生み出されていけば、産業構造が変化していくだろう、と考えたからです。いわば、新製品が誕生していることの状況証拠が産業構造の変化だといえます。ある産業が伸びて、ある産業は没落していく。それは新製品誕生の結果であります。
日米欧の産業構造の変化を比較して分かったことは、日本経済が成長していた時期は、10年程度のスパンで見ると、産業構造がどんどん変化していました。しかし、成長が滞った時は産業構造も変化しなくなっています。
日米欧の産業構造の変化を比較してみると、問題はより明確になります。過去20年間、多くの先進国はサービス産業を中心として成長を達成してきました。たとえば、日本と同じ「ものづくりの国」というイメージのあるドイツでも、現在ではサービス産業が経済成長をけん引しています。その意味では、日本が経済成長に出遅れた原因はサービス産業にありそうです。我々は、日本はサービス産業のプロダクト・イノベーションが弱いのではないかと考えています。
薄型テレビ市場を開拓したプラズマ
――プロダクト・イノベーションの事例研究として、まず薄型テレビを取り上げられていますが、そこで分かったことは何でしょうか。
この例では、直接にプロダクト・イノベーションの過程を検証しました。そこで分かったことは、薄型テレビ市場では、プラズマテレビが先行したという事実の重要性です。
テレビの生産にかかわる人々の間では、大型で薄型のテレビの需要があることと、その中では液晶テレビが将来有望であることは、かなり以前から広く知られていました。にもかかわらず、大型で薄型のテレビを最初に実現したのはプラズマでした。
しかし、液晶テレビはすぐにプラズマにキャッチアップできました。その背景には、プラズマの大型薄型テレビが出てからすぐに行われた、薄型液晶テレビ向けのR&D投資があったのです。液晶テレビは20年前から小型のテレビとして存在していましたが、各社ともに大型化を実現するための大規模なR&D投資には踏み切れていませんでした。プラズマテレビが大型薄型テレビの市場を開拓したことで、大型投資が決断できたのだと思います。
このことは、投資を決断するにはどのような情報が必要であるかを示唆しています。よく「ニーズを知る」ことが新製品誕生のカギであるといわれ、そこからR&Dが実行されると考えられています。しかし、実際には、「○○を欲しいと思っている人達がいるようだ」といった程度の漠然とした情報では、企業は巨額のR&D投資には踏み込めないのです。どの程度の価格で、どれぐらいが売れるかといった具体的な市場規模が明らかになることで、巨額のR&D投資が実現し、プロダクト・イノベーショが起きるのです。
薄型テレビの場合、プロダクト・イノベーションを起こせた理由は、プラズマという、パイオニアがいたからです。プラズマを手がけるメーカーには薄型テレビに参入した固有の要因がありました。もともとプラズマは大型の表示装置として存在しており、相対的にそれほど巨額のR&D投資をしなくても済みました。また、プラズマテレビに最初に参入したメーカーはブラウン管テレビをつくっていないメーカーであり、リスクをとってでも市場に参入せざるを得ない状況でした。しかし、そうしたプラズマテレビという実験台があったからこそ、王道といえる「液晶の」薄型テレビが誕生することができたわけです。
規制緩和も有力なイノベーションの源泉
――事例研究としてドリンク剤も取り上げられていますね。
ドリンク剤の場合は、大型液晶テレビの開発と異なり、新しい効能を持った新製品が開発されたという意味でのプロダクト・イノベーションが起きたわけではありません。ここでは、販売経路そのものがイノベーションを起こす契機になりうることを示したのです。どんなによい製品でも、買う場所が限られていると売れません。この事例では、医薬品という安全上の理由で市場が制約されている商品に注目して、その規制が緩和されたことで、どれぐらい市場が拡大したかを計測しました。
具体的には、ドリンク剤の一部が「医薬品のうち、特に安全上問題のないもの」を販売の規制がない医薬部外品に移すという規制緩和の対象となり、コンビニエンスストアなどでも売れるようになった事例です。この規制緩和の結果、ドリンク剤を販売する店舗が急激に増え、それだけで、売り上げが爆発的に伸びました。このことは、販売経路を増やすことがイノベーションになり得ることを示しています。
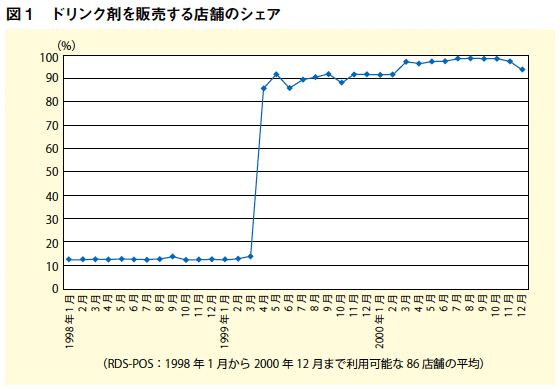
政府がイノベーションを起こそうと思っても、できることは限られていますが、規制緩和はイノベーションの起爆剤になり得えるわけです。しかも、規制を取り払うことは政府の一存でできるのです。不必要な規制を撤廃すること、すなわち適切な規制緩和は有力なイノベーションの源泉になるのです。
イノベーション起こすITの中間投入
――IT(情報技術)産業と経済成長について、中間投入の効果に着目されていますが、それはなぜでしょうか。
IT産業は、現在進行形で多くのプロダクト・イノベーションが行われており、日本経済の将来を考える上でも更なる発展が期待される分野です。このITセクターの成長が経済全体の成長にどのような影響を与えているかは一考の価値があります。
もちろん、直接的な影響としては、IT産業自体が新製品であり、IT産業自体の生産が伸びるという効果はあります。しかし、それだけであるならば、自動車や電機などの他産業にも同じようにあるわけで、IT産業の場合は、それだけではないだろう、という問題意識がありました。
IT産業の成長がほかの産業の生産性を引き上げる効果がある、と皆が信じています。IT革命によって経済全体の生産性も上昇する、という仮説についてはそれを支持する研究もたくさんあります。しかし、具体的にどの産業の生産性を向上させたのかを検証してみると、どうも結論がはっきりしません。確かにパソコンを利用し、Eメールをやりとりしたりすることで生産性が上がるというイメージはあります。ただ、パソコンなどのIT機器を多く投入した産業が必ずしも生産性を上げたということは確認できていません。現在では、「ITも使い方次第で生産性を引き上げる効果が変わってくる」というのが一応の結論になっています。
それに対し、我々はIT機器の投入量、すなわちIT投資の大きさだけでは、IT産業の影響が計測できないのではないかと考えました。そこで、別のアプローチとして中間投入に注目したのです。トヨタ自動車のハイブリッド車「プリウス」について考えてみましょう。プリウスを生産するには、部品として使われている半導体や演算装置などが欠かせません。しかし、産業別の投入を見る時には、これらの「部品」は付加価値としての投入には表れてきません。そのために、労働や資本だけに注目すると、プリウスに多くの半導体が使われていることを見逃してしまいます。いまや、自動車産業はIT関連産業としての側面を持っているのではないでしょうか。通常のガソリン車とプリウスを比べた場合、生産現場のコンピューターは一緒です。どこが違うかというと、中間投入に違いが表れています。
プリウスが売れたのは、消費者の需要に応えるプロダクト・イノベーションだったからと考えられます。しかも、高度なIT技術なしにプリウスの誕生はあり得なかったという意味では、IT産業の波及影響といえます。
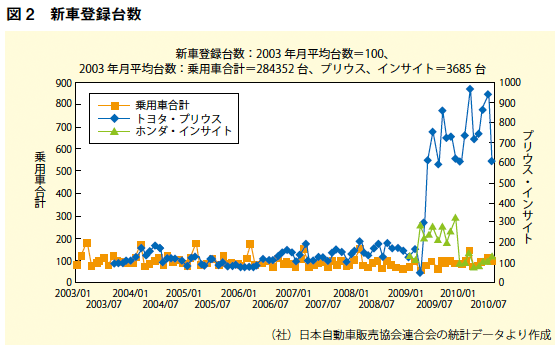
ITが部品としてどんな産業に投入されたのか、その結果、変わった産業はないだろうか、という問題意識で調べた時、まさにそうして変わった産業ではプロダクト・イノベーションが起きており、成長産業になっていました。言い換えれば、IT技術には部品という経路を通じてイノベーションを起こす力があるのではないでしょうか。
IT 革命が生んだ新製品
――具体的には、中間投入の効果はどのような産業に表れていますか。
テレビ、カメラ、電話機は、一般にプロダクト・イノベーションの典型として認識されています。その背景にはIT産業による中間投入も伸びていることが、間接的ではありますが、分かってきました。薄型テレビやデジタルカメラ、携帯電話などは、生産工程の効率化でイノベーションを起こした製品ではなく、半導体を大量に使うことで需要を掘り起こした製品です。昔のカメラには半導体はほとんど使われていなかったのが、現在のデジタルカメラは「半導体の固まり」といってよいほど、たくさん使われています。ゲーム機などの玩具についても同様のことがいえます。
プロダクト・イノベーションが起きると、TFPが上昇して成長が達成されますが、そのプロダクト・イノベーションを引き起こす要因を増やしたのがIT革命ではないでしょうか。言い換えれば、プロダクト・イノベーションを引き起こすプロセスそのものの革新がIT革命だったのだと考えます。
ボリューム・ゾーンの開拓を
――こうした検証を通じて得た政策インプリケーションは何でしょうか。
経済成長のためにはTFPの上昇が必要だということに議論の余地はありません。その上で、TFPが技術革新の尺度であるという世界観に立っていれば、新たな技術をどんどん生み出して経済成長を達成しなければならないという、いわゆるハードコアな技術進歩至上主義に陥りがちです。
しかし、今回の研究によって、プロダクト・イノベーションは狭い意味での技術革新だけで引き起こされるわけではないことが分かりました。ドリンク剤の例のような販売経路の革新のように、新たな需要を生み出すことで達成できるのです。
新製品と人々のニーズを考える時、吉川FFは「ボリューム・ゾーン」を重視することを提唱されています。ボリューム・ゾーンとは、アジアなど成長地域の中所得の人たちをターゲットとした市場を指します。この人たちの需要を捉えられれば、必ずしも先進的な技術がなくても製品は売れ、経済成長は達成できるのです。
そうしたことから、政策面では、新規の需要を獲得すること、あるいは新規の市場を開拓することを可能にするような政策が求められます。その際には、薄型テレビの例で見たように、新たな市場に参入する際の不確実性を下げることが重要です。特に、ニーズがあることは分かっているが、リスクが大きすぎる先進的な事例に対して支援することが効果的だと考えられます。また、ボリューム・ゾーンへの参入には、カントリーリスクを含めた市場へのアクセスを支援するような政策が望まれます。
IT中間投入の検証を拡大
――今後の研究課題は何ですか。
IT産業の中間投入の効果の検証をもう少し広げてみたいと考えています。IT産業の中間投入を多くした関連産業の幅を広げられないかということです。イメージとしては、太陽光発電などのニューエナジーがあります。天気による発電量の変動を細かく制御することを可能にしたといった点で、まさしくITなくしては実現できなかった革新だからです。
解説者紹介
1997年東京大学経済学部経済学科卒業。同大学大学院経済学研究科博士課程修了、博士号(経済学)取得。慶応大学総合政策学部専任講師、京都大学経済研究所講師を経て、2006年より現職。
主な著作は、"The Engel Curve for Alcoholand the Rank of Demand Systems," Journalof Applied Econometrics, vol. 21. pp.1019-1038. (2006) など。


