財政事情が厳しさを増す折、政策当局には、より客観的に有効な政策を立案する必要性が問われている。政策の決定方法も大きく変化し、これまで以上に論理的に説明責任を果たす必要もある。こうした時代の要請に応えていくためには、経済政策を担う経済産業省としても、経済動向をより精緻に分析する必要性があるとの問題意識のもと、福山光博CFと及川景太CFらは、最近の国内外における主要なマクロ計量モデルの潮流や、その体系の理論的整理を行うとともに、新たに「MEAD-RIETIモデル(MRM)」を構築した。
MRMは四半期経済データを基本に、短期の各種リスクや政策効果の定量的な評価を目的にしたハイブリッド型のマクロ計量モデルである。今回のDPをもとに、より透明性の高い政策立案への議論が重ねられていくことが期待される。
政策決定プロセスの変化に対応したツールが必要
――本研究に取り組んだ背景には、どんな問題意識があったのでしょうか。
福山:まず指摘したいのは、経済政策の決定過程が以前と比べて大きく変化しているという認識です。これは、特に、私自身が、内閣府に出向していた時代の経験に起因するものです。
特に転換点となったのは、2001年に経済財政諮問会議が設置されたことです。同会議では、関係閣僚の他、産業界や学界からもメンバーに加わり、国民の目に明らかなオープンな場で政策の優劣について議論が交わされ、総理の判断で政策が決定されるというスタイルが定着しました。私は、2004年から2年間、内閣府に出向し、経済分析・見通しを担当しておりましたが、この会議で政策についての議論と決定が進むのを間近に見ながら、政策決定のスタイルが以前と大きく変わっていることを実感しました。この会議は現在では存在しませんが、透明な政策決定というあり方そのものは、今後も続いていくと考えられます。
このような透明な政策決定プロセスでは、政策の立案に、より説得力が求められることになります。そうした中で、研究の蓄積が進んだマクロ計量モデルが、政策の議論に供されるようになってきました。たとえたとえば、経済財政諮問会議においては、「構造改革と経済財政の中期展望」(いわゆる「改革と展望」)と題する中期の経済ビジョンが検討されるようになりましたが、その際、内閣府の「経済財政モデル」のシミュレーション結果が活用されるようになりました。また、金融政策についても、日本銀行は、2000年に入って「経済・物価情勢の展望」(いわゆる「展望レポート」)を公表し、経済の先行きを見通しながら政策を決定していますが、ここでもマクロ計量モデルを用いたシミュレーションが活用されております。このような、計量モデルを活用した政策の立案は、我が国だけでなく、海外でも潮流となりつつあります。
さらに、より直接的な動機として、私は、2008年から10年までの2年間、経済産業省で、経済産業政策局調査課というマクロ経済分析や政策立案を行う部署に配属されたことがあげられます。この2年の間に、我が国経済は、いわゆるリーマン・ショックと深い景気後退を経験し、政府は累次の経済対策を講じてきました。このような難しい時期に、さまざまな形で分析・政策立案に関わる中で、経済産業省も、経済官庁の一角として、経済モデルもひとつのツールとして活用しながら、世の中に対して、より納得感のある政策のあり方を示せるようにすべきだと考えたのが、こうしたDPをまとめたきっかけです。
及川:私も福山CFと同時期に調査課に在籍していました。大学で経済学を専攻していたこともあり、担当業務のひとつとして、ある程度の経済理論に関する素養が要求されるマクロ計量モデルを用いた分析がありました。担当した当初は、内閣府経済社会総合研究所の「短期日本経済マクロ計量モデル」や、その他研究機関の公表する同種のマクロ計量モデルを使って分析を行っておりましたが、他機関の計量モデルへの理解が不十分な面もあり、要求されるさまざまな政策的「問い」に対して、十分な説明責任を自分自身が果たせていないと感じていました。また、近年は財政が逼迫していますから、国民が望んでおり、経済対策を含む、一定の効果が期待される政策であっても、全てを実施することはできません。限られた財源を有効に使うためには、費用対効果を考えて、優先順位を論理的に決めていく必要があります。そのためのツールを作りたいと考えたのが、MEAD-RIETIモデル(以下、MRMと略)を構築したきっかけです。
今、事業仕分けが話題になっていますが、政策決定の過程をオープンにして、広く国民に向けて説明責任を果たす事が求められていると感じています。今後は経済政策についても、同様の観点で今まで以上に有効かつ費用対効果の高いものを選別していく必要があります。
福山:経済産業省の前身である旧通商産業省は、主に個別の産業に介入するミクロの産業政策を担ってきました。右肩上がりで成長する時代には、ミクロの分野に配分するリソースは潤沢でした。しかしながら、財政情勢が厳しい今日では、経済全体を見渡しながら、限られたリソースを、効率よく活用していかなければなりません。その際、マクロ計量モデルを用いたシミュレーション結果も、望ましい政策を判断するひとつの材料となり得ます。
ここで指摘しておきたいのは、計量モデルはひとつのツールであって、これで全てが解決されるというわけではないことです。また、MRMの分析のスコープは短期の経済分析に限られます。しかしながら、このような留保はありますが、MRMが、ひとつの判断材料として、政策立案に貢献することができればと期待しています。
研究と政策立案の架け橋を目指して
――このDPにはどのような特徴がありますか。
福山:米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発し、2008年9月に米大手投資銀行が破綻したことで世界的な金融危機が深刻化しました。この影響を受けて、日本経済も大きな困難に直面しました。経済のグローバル化が進んだ現代は、危機もすぐに連鎖していきます。こうした中、海外の経済動向を含めた各種のリスクや政策効果の分析を行いつつ、将来の経済の姿を想定しながら政策運営を行っていく必要が、これまで以上に高まっています。解決すべき課題をより精緻に把握し、必要な対策を立てるには、このようなマクロ計量モデルは有用でしょうし、できる限り広く政策当局の担当者に、活用して欲しいと考えています。
このような観点から、このDPは、研究者向けのものではなく、経済学の基礎知識があれば枠組みを理解できるように、できるだけ分かりやすくまとめることを意図しました。構築したモデルを「MEAD-RIETIモデル」(※MEADは経済産業省経済産業政策局調査課の略称)と名づけたのは、このモデルが、政策を担う経産省とアカデミックな研究を行うRIETIをつなぐ役割を果たればと思ったためです。DPをまとめる上では、RIETIの研究者の方々からも貴重なコメントを頂きました。
及川:私もやはり、研究と政策の架け橋ということを意識しました。重視したのは研究としての独自性というより、「政策立案に使えるきっちりしたサーベイ」であることです。この目的を踏まえ、このDPには通常の研究論文と比べてかなり多くの注釈を入れました。本文は25ページまでですが、その後5ページ分は参考文献、続く31ページから94ページ(最終ページ)までは補論となっています。本文の倍以上を補論に割いたのは、本文中に登場するマクロ計量モデルをひとつずつ取り出して解説をしたためです。
例えば、潜在GDP(GDPP)の推計手法、就業者数や失業者数、消費者物価指数や経常収支の定義や対ドル為替レートの定式化など、経済政策を考える上で欠かせない要素について、その算出方法の数式などをまとめています。
また、国内外の主要機関が採用しているマクロ計量モデルや、そこで使われている関数についても詳細な解説を加えました。具体的には、内閣府が採用している短期日本経済マクロ経済モデル、日本銀行が採用しているハイブリッド型日本経済モデル(Q-JEM)、米国連邦準備理事会が採用している設備投資関数、イングランド銀行が採用しているMacroeconomic Model(MM)、カナダ銀行が採用しているMUSE(Models of U.S. Economy)、欧州中央銀行が採用しているAWM(Area Wide Model)の設備投資関数、国際通貨基金が採用している投資関数などについてです。
各種リスクや政策効果を定量的に評価できるハイブリッド型マクロ計量モデル
――分析の結果、どんなことが分かったのでしょうか。
福山:各国の政府機関・中央銀行や国際機関では、経済政策の運営に当たって、マクロ計量モデルが経済の見通しや各種リスク・政策効果の評価に活用されてきました。70年代まで活用されてきたマクロ計量モデルは、伝統的なケインジアン型の枠組みに従ったものでしたが、その構築・活用の状況は近年、変化しています。
しかしながら、70年代のルーカスによる批判は、新しいタイプのマクロ計量モデルの発展を促すことになりました。すなわち、従来のマクロ計量モデルが前提とする経済変数の関係は、現在の政策が将来についての人々の期待に影響を与えることにより変わり得るとし、過去のデータに基づいた行動を仮定した計量モデルによる分析を批判したルーカスの主張は、期待形成や各経済主体のミクロ的基礎付けのあるマクロ計量モデルについての研究が進む契機となったのです。この「ルーカス批判」以降、たとえば、中央銀行においては、経済主体の動学的最適化行動に基づくDSGE(Dynamic Stochastic General Equilibrium)モデルの活用が進む一方、変数選択の自由度が高く、短期的には均衡との乖離を許容しつつも長期的には均衡関係に向けて収束していくとするエラーコレクション型推計式を利用することで、理論と実証のバランスを重視したハイブリッド型モデルも多く開発されるようになりました。
私たちのDPでは、まずは、こうしたマクロ計量モデルの研究・活用のトレンドを整理した上で、自らのモデルとしてコンパクトなハイブリッド型モデルを採用しております。
及川:今回、私たちが構築したMRMも、国内外の主要マクロ計量モデルと同じく、これまでの経済理論やマクロ計量モデルの発展を踏まえたものです。分析の結果、この点を明らかにしています。MRMの基本構造と、家計部門、企業部門、雇用・賃金・物価の決定について、他のモデルにも触れつつ、その考え方を説明しました。
その上でMRMを使って、海外経済の変動や為替、特にドル・円レートのネガティブなショックが日本経済に与える影響についてシミュレーションを行いました。また、MRMの動学的な特徴を見るための比較対象として、主要変数からなる簡単なVARモデル(ベクトル自己回帰モデル)を構築し、両モデルのインパルス応答の比較を行ったところ、ショックがもたらす経済全体へのインパクトの程度とその期間に関して大きな違いは認められませんでした。解釈が難しい面もありますが、ある程度モデル作成者の恣意性から中立的なVARモデルの動学特性と、我々の作成した種々の経済理論に基づくMRMの動学特性に大きな違いがないとことから、ディスカッション・ペーパーの中でも書いている「経済理論との整合性と実際のデータとのフィットを重視したハイブリッド型モデル」の構築には成功したと言えると思います。
今回の研究の具体的な成果のひとつは、当初の目的通り短期的な経済対策の効果を理論整合的に検討するための材料を提供できたことだと思います。また、多くのマクロ計量モデルでは公共投資の乗数効果の規模が主眼となっており、乗数表の公表が主たる成果物となっていますが、MRMの論文では、日本銀行のQ-JEMのそれと同様、インパルス応答のシミュレーション結果を紹介することで、外生的な経済状況の変化がもたらす時間を通じた変化を明確に示しました。この結果を見ると、海外GDPに対するネガティブなショックと比較して、為替レートの円高ショックの方が、日本経済に対し、より長期的な影響を与えていることが示されています(図1、図2)。この結果は、海外GDPの減少が直接的に外需に与える影響よりも、為替レート変動を通じた相対価格の変化による外需に与える影響の方が長期間に渡ることを示唆しており、短期的な国内経済への影響という視点に立てば、円高がもたらすネガティブな効果は大きいと言えるでしょう。このように、時間を通じた経済変動を主たる成果物としたことは、MRMのリスクシナリオを明らかにするという問題意識とも絡むひとつの特徴と言えると思います。
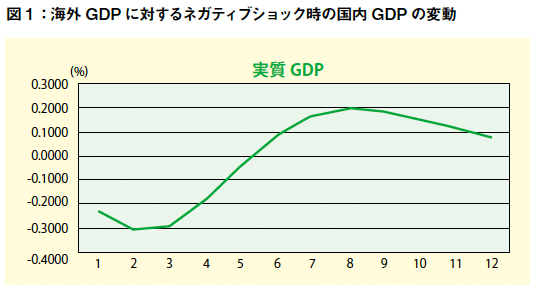
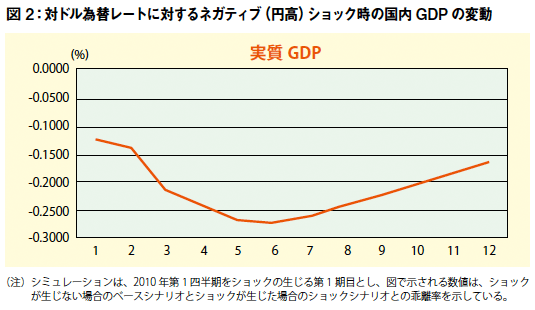
今後の課題は米国以外の海外要因をどう取り込むか
――今後の研究課題は何でしょうか。
福山:主な課題は2つ挙げられます。ひとつは、企業部門についてさらに分析と改善が必要であることです。設備投資は消費と並ぶ重要な需要項目であり、また企業部門と金融部門の関係の分析も、昨今の金融危機に照らし合わせると重要だと思います。
もうひとつは、海外要因をより精緻に見ていくことです。ここ数年の日本経済は、海外発のショックの影響に左右されてきました。経済的な相互依存が深まる中、海外におけるショックや為替レートの変動の影響を正確に把握しながら政策運営を行っていく必要は従来以上に増しています。ところが、これまでのマクロモデルでは、海外部門は米国経済や円ドル相場を基礎にしたものが多いのです。近年は中国を始めとしたアジア経済が急成長を遂げており、日本経済におけるその影響が増しています。また、存在感を増しているユーロなど米ドル以外の為替レートの変動が日本経済に与える影響についても、より詳細に把握する必要があるでしょう。
及川:私はMRMに、内生的成長理論を盛り込んで、ある程度中長期に対応するモデルに発展させたいと考えています。現在のMRMではマクロの生産性(TFP)をモデル外で決まる外生変数としていますが、実際には、教育や研究開発など生産性を向上させる「投資」行動が経済主体によって内生的に決定されると考えられます。
短期的な経済動向の分析に特化するのであれば、そのような投資行動の変化による生産性変動は無視してよく内生化するメリットはあまりありませんが、中長期となれば話は変わります。また、生産性は経済産業研究所の重要な研究テーマのひとつでもあります。こうした課題を今後掘り下げて行きたいと考えています。



