| 解説者 | 土居 丈朗 (慶應義塾大学経済学部教授) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0059 |
| ダウンロード/関連リンク |
日本の法人税は国際的に見て負担が重いので、引き下げるべきだという議論がよく聞かれる。ところで、法人税とはいったい誰が負担しているのだろうか。もし、税率が引き下げられたならば、その恩恵は誰が受けるのだろうか。こうした素朴で、かつ興味深い問いに対して、土居丈朗教授は今回の論文「法人税の帰着に関する動学的分析-簡素なモデルによる分析-」で、動学的な分析手法モデルを用いながら具体的な回答を試みている。
経済学の理論では、法人税率の上げ下げは労働者の負担が変化することにつながる。負担が変化するスピードは、労働分配率などによって異なるため、法人税の税率や労働分配率の議論を行う際には、「法人税を負担しているのは誰なのか」ということを、きちんと認識することが必要だと土居教授は強調する。
法人税を負担しているのは誰か?
――どのような問題意識から、この論文を執筆されたのでしょうか。
法人税の帰着とは、法人税は誰が負担しているのかということです。「法人税」という名称からのイメージで、一般の方々の中には「法人税を負担しているのは、企業そのものだ」と考えている方が少なくないと思いますが、経済学の見方では、税金を経済的に負担するのは生身の人間だけになります。企業などの法人は、生身の人間のように存在しているわけではなく、従業員や経営者、株主、債権者、顧客などといった、法人に関係するステークホルダーが集まったもの、別のいい方をすれば、そのような人々との契約の束です。したがって、法人税は、そうした生身の人間であるステークホルダーの中の誰かが負担していることになります。
この法人税の帰着は、経済学では、1960年代にハーバーガー教授らが分析の枠組みを提示して以降、長い間にわたって議論が行なわれています。しかしながら、ノーベル経済学賞を受賞した経済学者のジョセフ・E・スティグリッツ教授が、公共経済学に関する著書の中で、「企業は法人税を負担していないという点では、経済学者間では意見が一致しているが、このことは経済学者以外の人々にはよく理解されていない」旨の指摘をしているように、経済学者の常識と世間の常識が、本件に関しては一致していないのが現状です。
グローバル化が進む中、日本企業の国際競争力の観点から法人税を引き下げるべきだという指摘があります。しかし、消費税の引き上げをめぐる議論が増える中で法人税の引き下げを行うことは、「消費者冷遇、企業厚遇」と受け止められるため、実現するのは政治的に難しいのではないかといわれています。これも、経済学者以外の人々にとっては、法人税の引き下げは企業に恩恵を与えるものだという印象が強いことが原因ではないでしょうか。
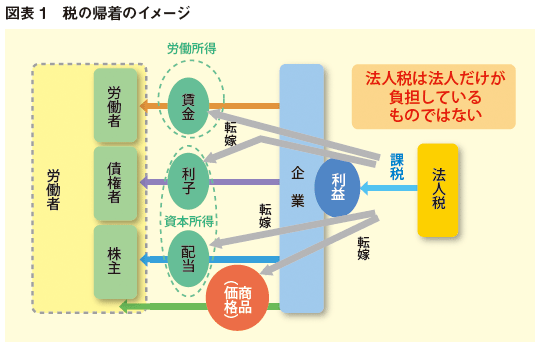
しかし先述のように、実際には、法人税を負担するのは企業ではありません。したがって、法人税引き下げの恩恵を受けるのは、経営者や株主だけでなく、労働者や顧客(=消費者)である可能性もあります。そうした内容について学術的に考え、モデルをつかって数値的に示すことは、今後の日本の税制を考える上で有益だと考えました。
――タイトルにある"動学的な分析"というのは、どのような分析方法なのでしょうか。
まず、経済学で言う「動学」とは、現在から将来にかけての異時点間の分析という意味です。法人税は、従業員や経営者、株主、債権者、消費者などが負担しているとして、それをどのように分析するのか、ということになりますが、関係者が多いということは、色々な側面を考慮して分析の枠組みを作らなければなりません。
株主を例にとって見ましょう。株主が法人税をどれくらい負担するのかを考えるにあたって、いつの時点のことを論じているのかを整理してみます。株主が法人税を負担するのは現在かもしれませんが、株主が株を保有するのは将来の経営の成果、正確にはキャッシュフローの増加を期待して保有しているという面があります。現在の株式保有者は、将来という時点も考えて株主になっているのです。そうなると、株主は将来上がる利益にかかる法人税も負担することになります。
今度は資金繰りという観点から考えてみましょう。もし、ある企業が1億円の資金が必要だとすると、その調達法は2つあります。ひとつは、銀行から借り入れたり社債を発行したりして調達するもので、この場合は支払利息が費用として課税対象利益から差し引かれるので、法人税の支払い額はその分だけ少なくなります。従って、法人税の支払いに伴って、負債に関して節税効果が発生することになります。もうひとつの調達法は、株式を発行するものです。この場合は株主に配当を支払うことになりますが、配当というのは税引後利益から支払われるものなので、現行税制では節税効果が発生する余地はありません。こうしてみると、法人税の帰着以前の問題として、社債の方が株式よりも企業にとっての負担が少ないということになります。実は、企業金融論の世界では、法人税が企業の資金繰りに影響を及ぼしている事が昔からいわれています。
このように、法人税の負担はというのは、「今日」というような限られた視点から捉えようとしても、それは今日の法人税の負担という一断面に過ぎないため、十分な分析はできません。ちょうど、スナップショット1枚だけでは、時間の経過を加えた全体像が見えてこないのと同じです。法人税の負担状況というのは、時間とともに変化していきます。ですので、今日、明日、そして来年...という具合に将来の企業活動を見渡した中で、どのような経営を選択し、その結果としてどれだけの負担が誰に及ぶかという問題の立て方をしなければなりません。そうすることで、現実的な企業行動に即した形で、法人税負担の分析を行うことが可能になります。
言い換えますと、現在から将来の時間軸を置いて、それに沿って法人税の負担の行方を考えるということになります。今年、来年、再来年といった時間の経過にともなって、法人税の負担が誰にどのように及ぶのかを分析する、というのが動学的な分析のイメージです。
現在から将来の時間軸で税負担の行方を考える
――動学的な分析の手法を使った先行研究は多いのでしょうか。
動学的な分析そのものは、1970年代から動学理論や経済成長理論をベースにした分析の枠組みとして使われている手法で、今回の論文もそうした枠組みを活用したものです。ただ、法人税の帰着に関するこれまでの研究は、ある初期状態から税の仕組みを動かした変化を見る場合、一定の期間が経過したのちに「定常状態」といわれる安定した状態について分析していました。つまり、最初(現在)と最後(変化の後将来たどり着く安定した状態:定常状態)の比較に重点を置いたものだったのです。映画の撮影に使うフィルムにたとえると、初期段階のひとコマと最終段階のひとコマだけがあるようなものです。今回のように最初と最終段階の間をどのように移行していったのかがわかるコマの数々、専門用語で「移行過程」と呼ばれる途中段階を示し、分析を行ったような先行研究は非常に少ないと思います。
たとえば法人税の税率を変えた場合に、ステークホルダーそれぞれへの影響がどのようになるのかといった議論をきちんとするためには、今回の研究のように、捕捉の度合いが高く厳密な動学的分析がより有効でしょう。
ただし、動学的分析手法にもデメリットがあります。それは、最近、盛んに議論されている、国際化のもたらした影響を扱うのが難しくなるという点です。
企業の国際的な資金調達や資本移動が激しくなる中で、ある国で法人税を下げるとその国における資本収益率が上昇するので、外国からの資本流入が起こります。つまり、ある国の法人税率の引き下げが法人税率を変えていない他の国に影響するわけです。こうした影響について、特に欧米税の専門家の関心が高まっていて、法人税についても国際的な経済の影響を加味する形での分析が進んでいます。ところが、国際間の資本移動や貿易など国際化のもたらす影響に着目すると、動学的な議論は複雑になりすぎて解けなくなります。そこで、今回の研究では、国際的な影響についての分析は一時棚上げにして、閉鎖経済を前提に動学的な手法で分析を行いました。
代表的な個人・企業を想定した分析モデルを使用
――分析には、どのようなモデルを使われたのですか。
モデルの登場人物は、家計と企業になります。家計といっても多数存在するわけですが、議論の単純化のために、多数存在する家計を代表する「代表的家計」というものを設定します。代表的家計は無限期間生きて、毎期、労働・消費・貯蓄をします。また、自分の労働供給、労働時間をどのくらいにするかを決めることができます。そして予算の制約がある中で、最も自分の満足度を高めることができる労働・消費・貯蓄の組み合わせを選択します。
一方、企業も同様に代表的企業を想定します。今回は閉鎖経済を前提にしていますので、個人の貯蓄額がそのまま企業の資本投下に回されるという前提のもとで、企業は税引き後利益の最大化を目指します。以上が議論の準備となります。
代表的な家計・企業は、いずれも異時点間で満足度や利潤を最大化するのです。その結果、企業が作ったものが消費されることで、財市場での均衡がはかられます。その他に、家計のストックベースの貯蓄額が企業の資本投入量と一致する資本市場の均衡と、家計の労働供給と企業側の労働需要が一致するなどの条件があり、そうした均衡が同時に達成されるという状態が、現在から将来に向けてつづきます。分析に使ったデータは四半期データですので、4期経過すると、1年経過したことを意味します。この現在から将来までの毎期毎期の状態を、映画フィルムの1コマのようなものとして、それを連続して眺めることにより、法人税の負担が将来に向けてどのように変わっていくのかを見ることができる仕組みを作ったといえます。
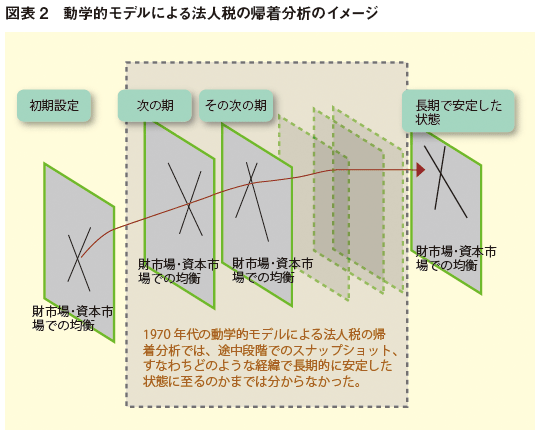
――個人の負担については、どのように計測されましたか。
個人は、顧客である消費者として法人税を負担しているというように考えることもできますが、所得を得るばかりで消費を全くしない人も、消費をしているのに全く所得を得ていない人もいない、つまり、消費者も所得という糧がなければ税の負担をすることはできないのです。こうしたことから、今回の論文の特徴として、どのような形で所得を得ているのかによって税の負担を捉えています。企業と関係する個人所得は大きく労働所得と資本所得に分けられます。労働者といっても、貯蓄や財産を一切もたず労働所得のみに依存するような「完全な労働者」というのはほとんど存在しないでしょう。小額でも貯金があれば、利子所得がありますので、資本家の一員ということになります。そうすると多くの人は、労働所得も資本所得も得ていることになりますので、この理論モデルでは、純粋な労働者、純粋な資本家という区分けはできません。したがって、個人によって労働所得、資本所得から得ている割合は違っても、マクロ経済全体で見たときに、法人税の変化によりどちらの所得の負担がより大きいのかを計っています。
法人税の負担の割合を考える際、労働所得の法人税負担割合(J)は、税負担が1%変化したときに、「労働所得の変化する割合」を、「労働所得の変化割合+資本所得の変化割合の合計」で割ったものです。したがって、資本所得の法人税負担割合=1-Jとなります。
法人税の引き上げの影響は労働所得依存が高いほど大きい
――どのような分析結果が得られましたか。
理論的には、長期的には法人税率の引き上げは労働所得に100%帰着することになります。このことは先行研究で明らかになっていますので、本論文のポイントはそのスピードになります。法人税率を1%相当分(0.3ポイント)引き上げた際、最初の第1期(四半期)では法人税率の負担は翌期には6.2%が労働所得に帰着し、93.8%は資本所得に帰着します。4期目(四半期)には、20%以下が労働所得、80%以上が資本所得に帰着するのです。そして最終的には100%が労働所得に帰着します。(図表3)このスピードは、労働分配率などのパラメータを変えることにより変化します。
労働分配率を上げる場合、言い換えれば、付加価値のうち、労働者の取り分を増やした場合は、皮肉なことに、法人税の負担はより多く労働者に及ぶことになります。つまり、税率が変わらなくても、労働所得に対する税の負担が増えてしまう結果になります。
また、モデルの上では代表的家計、代表的企業で議論してきましたが、現実には、労働所得の比率がどれくらい高いかは個人によって異なります。法人税率を引き下げた場合は、その恩恵は長期的には労働所得に帰属することになりますが、低所得者ほど、資本所得の比率が低く、労働所得の割合が高くなりますから、法人税軽減の影響もより受けやすいといえます。
こうした結果からみても、法人税の税率や、労働分配率の議論を行う際には、法人税を負担しているのは誰なのかということを、きちんと認識することの重要性が確認できます。
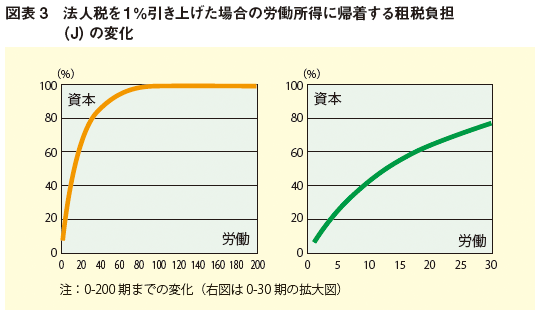
――今後の研究計画などについてお聞かせください。
今回の分析は、法人税の帰着がどのようなルートで及ぶかを論理的に分析することを主眼にしたものでしたので、今後は、前述したような資金調達面を含めた分析をしたいと考えています。
追加的に設備投資を行う場合の資金調達の方法としては、借入金、内部留保、株式発行といった選択肢があります。こうした選択肢を分析に組み込むためには、配当政策の仮定をおく必要があるのですが、配当政策には、定額で配当するものから自社株買いをするといったものまで多岐にわたるなど、かなり複雑なために、今回の分析に含めるのを見送ったという経緯があります。
また、資金調達の手段として借り入れをしすぎると、貸し倒れのリスクが上がるため、資金調達が難しくなったり、金利が引き上げられたりします。こうした金利負担は専門用語で「負債のエージェンシーコスト」と呼ばれるのですが、その分だけ資本所得が減ることになります。法人税率が上がると、負債の節税効果が上がるので、より多くの資金調達を借り入れで行い、負債のエージェンシーコストも大きくなります。そうした形を通じて、法人税率引き上げの負担が資本所得に及ぶ可能性もゼロではありません。
こう考えてみると、実は、法人税が長期的には労働所得に100%帰着するということには必ずしもならない可能性が出てくるのです。そして、負債に伴うコストが減少することで、浮いたお金を配当などに回すといったように、企業行動の変化となって現れることも考えられます。こうした点についても研究していきたいと思います。
解説者紹介

土居 丈朗
慶應義塾大学経済学部教授。1999年東京大学経済学研究科博士課程修了(経済学博士)。1998~99年東京大学社会科学研究所助手、2001~02年カリフォルニア大学サンディエゴ校客員研究員、2002~09年慶應義塾大学経済学部准教授等を経て2009年から現職。主な著作は『地方債改革の経済学』日本経済新聞出版社(日経・経済図書文化賞、サントリー学芸賞受賞)、『財政学から見た日本経済』光文社新書、『日本の税をどう見直すか』(編著)日本経済新聞出版社など。

