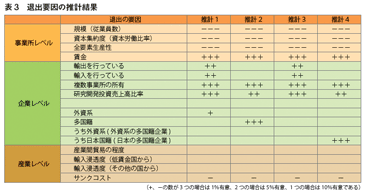| 解説者 | 乾 友彦 (内閣府経済社会総合研究所主任研究官/日本大学経済学部経済学科教授) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0052 |
| ダウンロード/関連リンク |
1990年代以降の日本経済の長期停滞をもたらした原因の1つとして、しばしば、経済のグローバル化が挙げられる。特に企業の海外進出により、生産性の高い優良企業が国外に流出し、国内では生産性の低い企業の割合が高まるという、いわゆる経済の「空洞化」への影響が懸念されている。しかし、外資系を含む国内製造業の17万にのぼる事業所データを使った乾友彦氏らの研究によると、日本におけるマクロの生産性の変化のほとんどは、既存事業所のシェアの変化によるもので、企業の参入・退出の影響は非常に小さく、生産拠点の海外移転は日本の製造業全体の生産性低迷の原因とはいえないことが明らかになった。
日本では輸出の拡大など需要面からグローバル化の役割を議論しがちだが、乾氏は、グローバル化によって企業の生産性をどのように高めていくのか、そのための課題は何かという、供給側の視点に立った分析や政策論議を深める必要があるのではないかと指摘する。
重要な供給サイドの視点
――今回の研究の問題意識からお話いただけますか。
1990年代以降の日本経済の長期停滞をもたらした原因の1つとして、経済のグローバル化が指摘されます。こうしたグローバル化犯人説の背後にあるのは、「生産性の高い優良企業が国外に流出してしまい、国内では生産性の低い企業の割合が高まったのではないか、あるいは、途上国から割安な製品の輸入が増え、競合する国内企業が打撃を受けたのではないか」といった疑念です。しかし、欧米などでは逆に、国内企業がグローバル化に伴う国際競争にさらされることで、企業の市場への参入、あるいは市場からの退出が加速され、国内の生産性が高まるというプラスの効果が確認されている例が少なくありません。では日本の場合、企業の国内市場への参入・退出は、マクロの生産性にどの程度の影響を与えているのでしょうか。また、そうした企業の新陳代謝はどのような要因によって実現しているのでしょうか。こうした疑問に具体的に答えることが今回の研究の目的ですが、同時に、グローバル化の影響を企業の生産性という経済の供給サイドから検討することにより、従来の、やや需要サイドに偏った議論に一石を投じるという狙いもあります。
近年の日本経済は輸出に大きく依存しており、政策論においても「グローバル化をうまく利用する=輸出をさらに拡大する」というように、やや需要サイドに偏った議論になりがちです。しかし欧米の例を見るまでもなく、グローバル化をきっかけに国内企業の生産性をどのように高めていくのか、そのために必要な政策は何か、といった供給サイドの視点に立った分析や議論をもっと深めていくべきだと感じています。
――分析には、どのようなデータを使用されたのですか。
国際経済学の分野では近年、分析単位が産業から企業や事業所へとシフトする動きがあります。同じ国の同じ産業内でも、個々の企業や事業所はさまざまに異なる特徴を持っており、そうした個別の経済主体の違いを考慮に入れることで、より正確な実証分析ができるようになります。また、分析単位が変わることで、前提となる経済理論も変化しており、そうした新しい理論を踏まえた分析も可能になります。今回の研究では、工場レベルの統計である「工業統計表」と企業レベルの統計である「企業活動基本調査」、そして、経済産業研究所(RIETI)が中心になって作成している「日本産業生産性(JIP)データベース」(http://www.rieti.go.jp/jp/database/d05.html)の3つを利用しました。
分析の目的は、1)事業所を参入、退出、存続グループに分けて、それぞれがマクロの生産性にどのような影響をもたらしているか、2)事業所の退出はどのような要因によって決まっているのか、この2点を明らかにすることです。そのため、工業統計表からは、個別事業所の規模を表す従業員数や資本労働比率(労働者1人当たりの資本額)、売上額、全要素生産性(TFP)、賃金などの事業所単位のデータを、企業活動基本調査からは、事業所を保有する企業の単位での輸出入の有無や所有形態、研究開発投資(R&D)などのデータを入手しました。
さらに、海外との貿易が企業の退出に与える影響については、JIPデータベースを使い、貿易相手国を安価な労働集約財を日本に主に輸出しているいわゆる低賃金国と、その他の国という2つのグループに分け、影響の違いを分析しました。また売上額などを実質化する際に必要になるデフレータも同データベースの産業単位のデータを使っています。
平均年齢が高い日本の製造企業
――分析対象の事業所はどのような特徴を持っていますか。
分析対象は、従業員50人以上の製造業の企業の事業所約17万件で、一企業が複数の事業所を持つケースが多いために、企業数にすると約1万4000社になります。表1の上段には事業所単位でとったデータ、下段には企業単位のデータの平均値や最大値、最小値が示してあります。
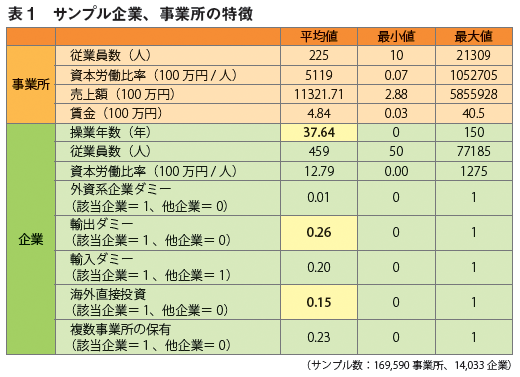
まず、目立った特徴としては、企業の平均年齢が37.64年と、かなり高齢であることです。一方で、輸出をしている企業の割合は26%、海外直接投資を行っている企業の割合は15%にとどまっていることから、日本の企業は比較的高齢であるけれども、グローバル化は必ずしも大きく進んでいないといえます。また、1994年から2005年までの参入・退出確率(表2)を見てみると、サンプルが従業員50人以上と比較的大きな事業所に限られているとはいえ、日本の場合、参入・退出という新陳代謝が非常に少ないことが分かります。企業の平均年齢が比較的高い水準にあることは、このような参入・退出の少なさと関係している可能性があります。
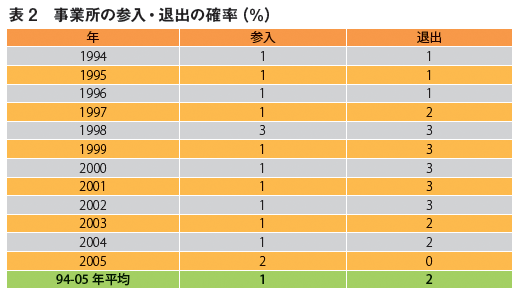
――分析の手法について教えてください。
事業所の参入、退出、存続がマクロの生産性にどのような影響をもたらしているかについては、事業所単位で計算した全要素生産性データ(TFP)を使い分析を行いました。すべての事業所を集計したマクロの生産性の変化を、①各事業所内の生産性の変化、②異なる生産性を有する事業所間のシェアの変化、③事業所の新規参入、④事業所の退出――以上の4つの要因の影響に分解するという手法をとりましたが、このうち②は、たとえば生産性が高い事業所が市場におけるシェアを高めることでマクロの生産性を高めるというようなケースが想定されます。次に、事業所の退出がどのような要因によって決まっているのかを調べました。事業所の退出を説明する変数は、表3に示したように事業所、企業、産業単位のデータに分かれています。1994年から2005年までのデータを使い、事業所が退出した場合を1、それ以外を0と表記し、1、0の動きを以上の説明変数から説明するプロビットモデルという手法を使いました。
参入・退出の生産性改善効果はごくわずか
――まず、マクロの生産性の要因分解についてですが、どのようなことが分かりましたか。
分析結果を表4にまとめました。マクロの生産性の変化を促す4つの要因の寄与率が表示してあります。これによると、事業所間のシェアの変化の効果が飛び抜けて大きく、全体の82%をこの要因が説明しています。次に大きいのが各事業所自身の生産性の変化であり、これが14%を占めます。残りが注目の企業の参入・退出要因で、ここでは退出を多国籍企業とそれ以外の企業に分割表示してありますが、全体を併せても3%程度に過ぎません。このことから、欧米の事業所・企業を対象にした類似の研究結果に比べ、日本の参入・退出がマクロの生産性に与える影響度合いは非常に小さいといえます。これは、先に述べたように、日本の事業所・企業の参入・退出が非常に限定的で、新陳代謝がなかなか進まないことの当然の帰結でもあります。したがって、日本の場合、こうした新陳代謝がどのようにして決まっているのかが次に問われることになります。
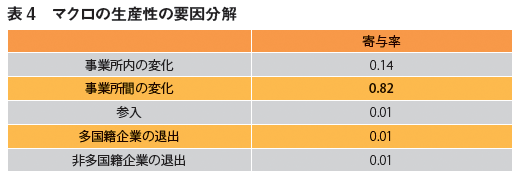
――退出の決定要因はどのようなものでしたか。
表3の左側に、退出に影響を与えると想定される要因が示されています。事業所単位、企業単位、産業単位で、各要因が退出を促す効果を持つ場合は+、逆に退出を抑制する効果を持つ場合は-の符号が記してあります。符号の数は、各要因と退出の因果関係が統計的に見てどの程度強いものなのかを表しており、数が多いほど関係性がより明確であること、空欄の場合は関係性が確認できなかったことを示しています。推計は説明変数の一部を変えながら4パターンについて行いました。
推計の結果、まず、事業所単位の変数については、事業所の規模が大きく、資本労働比率が大きく、生産性が高い事業所ほど退出しにくいという関係が確認できました。これは、欧米を対象にした先行研究と同様の結果です。一方、賃金は高いほど退出しやすくなるという、これも先行研究と同様の結果です。
次に企業単位の変数ですが、事業所を保有する企業が、1)輸出を行っている、2)輸入を行っている、3)複数の事業所を有している、4)研究開発投資売上高比率の水準、という4つの要因に加えて、企業所有形態について①外資系、②多国籍企業、③外資系の多国籍企業、④日本の多国籍企業の4つの要因を考えました。所有形態は互いに重複している部分がありますので、1つずつ説明変数に加えて推計しています。結果を見ると、複数の事業所を持ち、積極的に研究開発投資を行い、多国籍企業であるほど退出しやすいという関係が確認できました。これは、多国籍企業や、複数事業所を持つ企業であれば、事業所が1つだけ、もしくは国内だけで事業を展開する企業に比べれば、事業所の統廃合がより柔軟に行えるからだと考えられます。研究開発投資に関する結果は海外企業を対象にした先行研究とは異なりますが、ここでは研究開発の厚みが、企業の経営戦略の柔軟性を高める効果を持つものと理解することができると思います。
外資系企業は逃げ足が速い(Footloose)という批判がよく聞かれますが、所有形態のうち、外資系であることが退出を促すという関係については、+がひとつだけとなり、統計的に明確な形では裏づけることができませんでした。また、多国籍企業については退出する確率が高い、むしろ日本の企業の場合だけで、外資系企業はそうした関係は見いだせませんでした。残る輸出入の影響については、多国籍企業であることをコントロールすると、輸出入が影響を与えていない結果から、輸出入は、退出に大きな影響を与えていないものと結論づけることができると考えます。
低い輸入浸透度、競争高まらず
――低賃金国からの輸入の影響はいかがでしたか。
中国など東アジアの国々が低価格の製品を日本に輸出しているため、競合する国内企業が打撃を受けているという議論はいまも根強くありますが、表3から分かるように、低賃金国からの輸入の浸透度(輸入/国内総供給)は企業の退出に影響を与えていません。また、低賃金国以外の国からの輸入の浸透度、産業間貿易(工程間分業のように同じ産業内で製品をやり取りする貿易形態)の程度についても、退出への影響は見いだせませんでした。これらの分析結果は、貿易が海外企業との競争を高め、事業所・企業の新陳代謝を高める重要な役割を果たしているとする海外の先行研究と大きく異なります。
日本の場合、こうした要因が退出に大きな影響を持たないのはなぜか。1つの可能性として、現状の輸入浸透度が競争を通じた企業の退出を促すほど十分に高い水準に達していないという点が挙げられます。日本の輸入浸透度は総輸入ベースで9%程度ですが、米国は先行研究によると1992年において28%と、大きな開きがあります。
また、産業レベルの要因として、事業の撤退や縮小を通じても回収できない固定費用であるサンクコスト(埋没費用)を示しました。多額のサンクコストが見込まれる場合、退出は難しくなるため、抑制効果(-の符号)を持っています。
――分析結果から浮き彫りになる政策課題はどのようなものでしょうか。
分析結果や、背後にあると思われる輸入浸透度の現状を踏まえれば、まずは事業所・企業の競争をさらに高め、参入・退出をサポートするような政策が必要なことはいうまでもありません。ただ、今回分析の対象である製造業は規制緩和が相当程度進んでいるため、単に規制緩和を進めるというだけでは十分な政策とはなり得ません。また、これまでの政策は、どちらかといえばベンチャー育成など参入促進に注力されていますが、退出を促さないことには新陳代謝が促進されません。企業の退出により失われる職の安定性をどのように補っていくべきか、どのような職種の方々がどのような被害を受けることになるのか分析し、必要に応じたセーフティーネットを用意することも欠かせません。
――今後の研究課題についてお聞かせください。
必要な政策について考える上でも重要なことですが、やはり、なぜ日本では事業所・企業の参入・退出が国際的に見て低い水準にとどまっているのかという点について、さらに踏み込んだ分析が必要だと感じています。こうした傾向は最近に限ったことではないため、労働慣行など、歴史的・文化的な側面も含めた検討を行う必要性を感じています。そうした点から見れば、日本だけでなく、近隣の東アジア諸国も加えた比較分析が有用になる可能性があります。こうしたことから、今回のような分析に必要なミクロデータの蓄積を東アジア各国にも広げて分析を行い、先行する欧米の研究事例と比較していくことが将来の課題になると考えています。
解説者紹介

乾 友彦
1985年一橋大学経済学部卒業。日本政策投資銀行を経て、2009年より内閣府経済社会総合研究所主任研究官に就任。
主な著作は、「生産性と日本の経済成長―JIPデータベースによる産業・企業レベルの実証分析―」(東京大学出版、2008)(分担執筆)、「日本経済グローバル競争力の再生:ヒト・モノ・カネの歪みの実証分析」(日本経済新聞出版社、2008)(分担執筆)、「日本経済のグローバル化」(東洋経済新報社、1998)(共著)など。