| 解説者 | 中田 大悟 (研究員) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0045 |
| ダウンロード/関連リンク |
人口構造の高齢化と年金財政は、世論の関心を集める問題の1つである。高齢化の主な要因には、少子化と長寿化の2つの要因があるが、少子化に比べて長寿化が年金財政に与えるインパクトについてはこれまで議論がなされてこなかった。そこで、中田大悟Fらは、長寿化を通した人口構造の変化が、マクロ経済と年金財政の安定性にどのような影響を与えるか、という問題についてのシミュレーション分析を行った。
分析の結果、高齢化を見越した人々のライフサイクルの貯蓄行動により、想定されていた運用利回りが得られない可能性があり、これが年金財政の安定性に負の影響をおよぼすという結論が得られた。これは人口構造の高齢化が年金財政に与えるリスクの1つと考えられる。論文では、支給開始年齢のさらなる引き上げが、どの程度これらの影響を緩和できるかについても分析している。また、支給開始年齢に伴う柔軟な高齢者労働市場の構築、介護制度の拡充などの重要性を訴えている。
年金は長寿に対する保険
――どのような問題意識から、この論文を執筆されたのでしょうか。
人口構造の高齢化の要因には、「少子化」と「長寿化」の2つが挙げられます。少子化は出生率の低下として表れ、長寿化は平均寿命の延びとして捉えられます。これまでは少子化問題に人々の注目が偏在していました。その背景には、現在の日本の労働市場における女性の働きにくさ、そして男性のワークライフバランス維持の困難さがあります。このような不条理な面があるからこそ、人々は少子化に関心を寄せ、それが年金に与える影響を危惧してきたのです。
一方で長寿化は、それ自体は喜ばしいことですので、人々がそれほど問題視してこなかったのは当然ともいえます。しかしながら、長寿化の年金財政に対するインパクトは懸念すべき事項です。図1は、人口構造の高齢化の指標として、過去の将来人口推計ごとの65歳以上人口と15~64歳人口の比率を比較したものです。これを見ると、2002年低位推計より合計特殊出生率(TFR)を高く仮定したはずの2006年出生中位死亡中位推計の方が、人口構造がより高齢化していくことが分かります。これは2002年推計時よりも2006年推計の方が、より長寿化が進展すると予測しているためです。2006年人口推計が発表された直後、厚生労働省も暫定的ではありますが、長寿化の進展が年金財政に与える影響の見通し(以下:暫定試算)を発表しました。
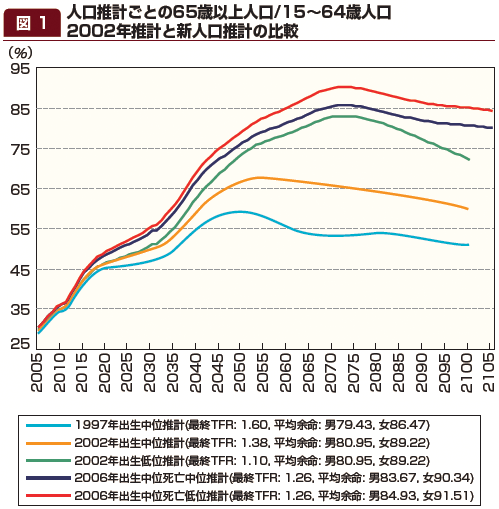
そこで、長寿化が年金財政に与える影響という観点を通じて、私たちが公的年金に本当に期待すべきことは何なのかを問いかけたい、というのがこの論文の目的の1つです。公的年金はさまざまな機能を含んでいますが、第一義的な意義として、予期せぬ長寿に対する保険と考えるべきではないでしょうか。たとえば若くして亡くなった場合、それまで保険料を支払っていたとしても、遺族年金を除けば、加入者自身が公的年金を受給することはできませんが、長生きすれば、自分が支払った保険料以上の金額を年金として受け取ることができます。公的年金は長寿に対するリスクを皆でプールして備える制度なのです。この意味で、損得勘定だけで年金制度を論じるのは問題があります。第2に、公的年金は引退後の消費水準の維持を助ける制度です。特にサラリーマンは引退後に労働所得を失いますが、貯蓄だけで現役時代と大差ない安定的な生活が送れるとは限りません。そこで、公的年金の所得比例年金によるサポートの意味が出てくるわけです。
このように考えると、現行の65歳からの年金支給開始が、今の、そしてこれからの日本人のライフスタイルに本当にフィットしたものであるか検討が必要です。従来通り65歳から絶対支給すべきというのも1つの考え方ではあります。ですが、年金支給開始年齢を引き上げれば当然年金財政に余裕が生まれ、毎月の給付額を増やすことができます。先述したように、日本の長寿化は世界最高水準にあり、現在もなお、進行中なのです。このような状況下で、どのような選択をすべきか、その判断材料を提供するということも本論文の目的となっています。
年金財政推計に豊かなインプリケーションを与える分析手法
――今回の分析手法の特徴を教えて下さい。
政府が実施している推計のうち、人口推計と年金推計は推計期間が特に長く、おおよそ100年間です。厚生労働省の公式推計では、この100年間に、通時的に一定の経済前提を与えて年金財政の推計を行っています。100年後のことを正確に予測することは不可能ですが、100年間不変の賃金上昇率や運用利回りを仮定として与えた推計には、議論の余地があります。
経済学の多種多様なモデルの中で、最も長期間を扱う基礎的モデルが本論文で使用した「世代重複モデル(OLGモデル)」です。人々は将来の人生設計を考えながら生きています。その集積が国全体の経済パフォーマンスになりますが、OLGモデルはそうした人々のライフサイクル行動の帰結を的確に抽出するモデルとして最適です。これを使うことで、経済学的に妥当な前提を年金の財政推計に与えることができるのではないかと考えました。一般的には、OLGモデルを使った年金研究は、そのモデル内だけで完結させる、つまり、モデル内に政府部門を登場させ、その中で年金の拠出と給付のやりとりをさせることで単独で分析を完結させてしまうのが通常です。
一方で、年金研究には年金財政モデル、もしくは年金シミュレーションモデルといわれるモデルも多く利用されています。こちらは、より会計的な計算、年金数理計算の積み重ねで出てくる年金の拠出と給付のバランスを時系列で追う方法で、現実にある年金の細やかで複雑な制度を忠実にそのモデルに織り込むことが可能です。対して、OLGモデルは経済学の基本モデルで、インプリケーションも非常に豊かですが、実際の年金制度が持っている複雑性を反映させにくいという難点があります。これらのモデルは別々の年金推計として利用されてきましたが、両方のモデルを組み合わせることで、年金財政の将来推計をさらに豊かなものにすることが本論文の狙いでもあります。
――既存のモデルとの違いは何でしょうか。
年金財政モデルで最も大規模かつ精巧なものとして、厚生労働省が作成・使用しているものがあります。このモデルは、最近公表されましたが、永らく詳細が不明でした。そこで、それまでの間、日本の財政学や公共経済の研究者の一部のグループが厚生労働省発表の推計を再現するモデルの開発を行ってきたという経緯があります。そうした流れの中で最も新しいモデルに属するのが、私たちが作った「RIETI年金財政モデル(RIETIモデル)」です。このモデルは、厚生労働省が出している推計とそれほど大きな差異のない数値が出るだけでなく、非常にコンパクトで操作性が高いモデルです。
2050年以降の年金財政に懸念すべき影響が生じる可能性
――シミュレーションの結果からはどのようなことが導き出されたのでしょうか。
100年間一定の経済前提を与えた厚生労働省の推計に比べて、OLGモデルから導き出された一般均衡論的に整合性が高い経済前提を与えたときに生じた一番の大きな差は、家計ライフサイクルの行動が運用利回りに与える影響です。「人々がライフサイクルの行動をとる」とは、若い時は貯金を少しずつ積み立てていき、老後、特に退職前後からそれを取り崩して生活していくことです。人口構造が変化すれば、当然ながら金融市場に流れ込んでいく貯蓄の総額も変化します。お金の供給が変化すれば、お金の価格であるところの利子率も変化していきますし、利子率が変化すれば年金の財政にも大きな影響をおよぼすことは容易に想像できます。現行の年金制度は、160兆円以上の莫大な積立金を有し、その積立金を運用することで年金財政の確保を図っています。つまり、積立金の運用次第で年金制度の将来の持続可能性が大きく左右されるのです。
図2では本論文でのOLGモデルによる各人口・支給開始年齢想定別の平均利回りのシミュレーション結果を示しています。2012年~2100年までの期間、厚生労働省の試算ですと、実質運用利回りを通時的に3.1%で一定と仮定しているわけですが、OLGモデルによる推計でも、期間平均でみると、これに近い値であることがわかります。ところがこの期間の利回りの変動を見ると、2050年代まで、厚生労働省の想定より運用利回りが高く得られない可能性があることがわかります。
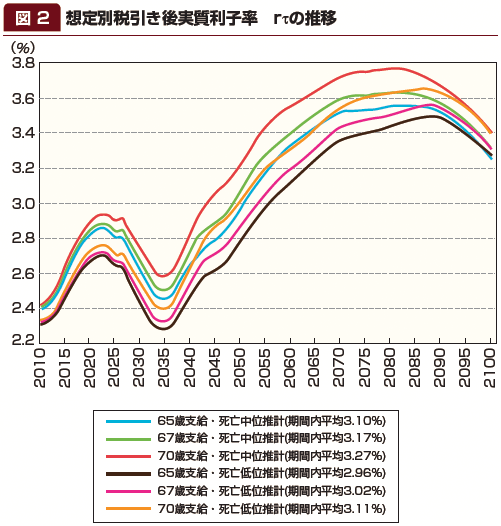
ここで問題になるのは、現行の年金制度の財政方式が、100年間制度を持たせることを規定した有限均衡方式である点です。年金の保険料率を労使折半合わせて18.3%まで引き上げるという現行の引き上げスケジュールに則って保険料を上げていけば、積立金は現在よりさらに積み上がっていきます。今は、給付の約4年分の積立金を有していますが、2050年までかけて年金の積立金を積み上げて運用していき、それを6年分強のレベルにまで引き上げることになります。そして、2050年以降、それを取り崩しながらの残りの半世紀を乗り切っていこうというのが現在の年金制度の前提になっています。
ところが、積立金の利回りが均衡期間の前半50年で予想を下回ると、必要な積立金が積み上げられず、100年間乗り切れると想定していた計算を修正する必要が出てくる可能性があります。これは、先行研究での年金推計の結果からは得られなかったインプリケーションではないでしょうか。こうした点からも、人口構造の高齢化の年金財政に与えるリスクが1つ明らかにされたと思います。
年金財政のマイナスを支給開始年齢の引き上げで補完
――どうすれば、そうしたリスクに対応できますか。
日本の年金制度は、18.3%までにしか保険料を上げないと決定されていますので、年金財政のマイナス要因を吸収しようとすれば方法は2つです。毎月の給付額を減らすか、支給開始年齢の引き上げるかです。給付額については、現行制度において所得代替率は50%を下回ってはいけないとの制約があると考えると、残るは支給開始年齢の引き上げとなります。
年金を「長生きに対する保険」と考えるならば、長寿化に伴って支給開始年齢を引き上げることはごく自然な方法です。表1は、年金支給開始年齢を変えたときの所得代替率の変化を示しています。このような結果は、家計のライフサイクルの行動が運用利回りを通じて年金財政に与える影響を緩和するには、マクロ経済スライドと共に、年金支給開始年齢の引き上げを考えるべきであることを示唆しています。
また本論文では、支給開始年齢の引き上げについて67歳、もしくは70歳を想定しています。これには、現在進行している65歳までの引き上げスケジュールを単純に引き伸ばすことで到達するように仮定しました。日本の予測される高齢化には2ステップあって、団塊世代が引退する時期に一段高齢化が進み、その後団塊ジュニア世代が引退したときにさらに高齢化が進みます。本論文の想定した引き上げスケジュールですと、結果的に団塊ジュニアの支給開始に間に合う形になりますから、それが年金財政の改善に寄与しているわけです。
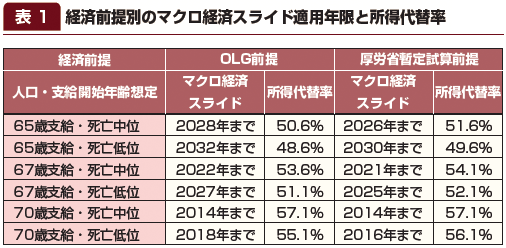
ただし、年金制度の給付水準の指標として一般に使われており、本論文でも採用している所得代替率と呼ばれる数値には注意が必要です。メディアなどの報道では、今後の推計では所得代替率が50%を切るのではないかと、年金の信頼性に疑問符を投げかけていますが、今60%ある所得代替率のもとでも、国民が満足、納得しているかは疑問視される部分でもあります。給付額の決定に不公平感や判りにくさが伴うと、国民の年金に対する信頼は損なわれてしまいます。この意味で、支給額のレベルを所得代替率の水準だけで考えることは、留意しなければならないでしょう。
高齢者の労働市場構築と介護制度充実が必要
――年金支給開始年齢を引き上げた場合の課題は何でしょうか。
中高齢者の関心事は、退職してから年金支給開始までの期間の生活をいかに持続させるかです。統計にもよりますが、平均的な退職年齢は現状では58歳程度となっています。それが67歳、70歳まで引き上がれば、少々の蓄えでは切り抜けられません。国民の納得を得るためには、退職年齢の引き上げや高齢者にフィットした働き方をさらに広めることが重要です。したがって、柔軟な高齢者の労働市場を構築していくための施策を講じながら、極めて早い段階で国民に支給開始年齢の引き上げを周知させる必要があります。
日本の高齢者の就業率は、もともと国際的に高い水準であるものの、低下の傾向がみられます。これは国の政策とは裏腹に、高齢者が働きにくい労働市場になっている可能性が高いことを示唆しています。キーポイントになるのは、介護保険、介護制度をどのように拡充していくかでしょう。60歳代の労働者が共有している問題は、親世代が要介護状態になっている可能性が高いことです。介護を必要とする親を抱えたまま労働市場に出ていくことは困難ですから、そういう人たちが労働市場に参入できるような介護制度の拡充が重要になります。
――今後の研究の方向性について教えて下さい。
年金以外の分野でも、医療保険・介護保険の財政の持続可能性について研究を始めました。また、社会保険料の負担と企業活動についても関心を持っています。今後、社会保障の財源をいかに支えていくかどうかの議論のなかで、家計の負担に関しては多くの議論がなされていますが、あまり分析がされていない企業の負担の仕方についての研究も進めていきます。
解説者紹介
創価大学経済学部卒業。2003年横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(経済学)。2003年横浜国立大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー講師(中核的研究機関研究員)を経て、2005年より現職。主な著作物は、「非正規就業者増大のもとでの厚生年金適用拡大と国民年金の経済的効果」(共著、『季刊社会保障研究』、国立社会保障人口問題研究所、第40巻第2号)、「年金と財政-基礎年金給付の国庫負担水準の影響-」(共著、『季刊家計経済研究』、家計経済研究所、第60号)、「女性活用策と経済成長」(共著、独立行政法人経済産業研究所RIETI政策シンポジウム『女性が活躍できる社会の条件を探る』)など。


