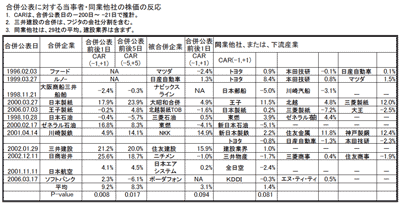| 解説者 | 宮島 英昭 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0007 |
| ダウンロード/関連リンク |
M&Aは二面性(両刃の剣)を持つだけに様々な議論があるが、資源効率化と組織の効率化というプラス効果がマイナス効果を上回っていれば促進すべきであると宮島RIETIファカルティフェローは指摘する。M&Aの実施を通じて、個々の企業の経営効率化のみならず、産業全体の構造調整への貢献が期待できるためだ。一方で、M&Aが株式市場の過大な評価などによって不適切な形で実施されないようにチェックすることも重要だと述べている。
日本におけるM&A増加の要因と形態的特徴
――論文では、日本のM&Aの発生要因と取引面の特徴について分析し、その国際的特徴について考察されていますが、そもそも日本ではいつごろからM&Aが盛んになってきたのでしょうか。
世界では1890年代、1920年代、60年代、80年代、そして90年代と大きく分けて5回のM&Aブームがありました。これに対し、日本では1930年代などにブームが確認できますが、戦後の高度経済成長期には企業が内部成長を重視したほか、メインバンクシステムを通じた自主再建が選好されたり、株式持合いなどの安定株主化が進んだりして、M&Aの件数はあまり増えませんでした。しかし、90年代末から急速に増加しています。
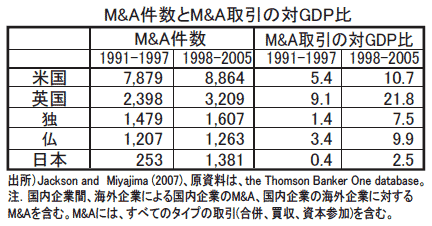
――その背景にはどんな要因があるのでしょうか。
まず、設備・雇用・負債の過剰をもたらす「負の経済ショック」が影響したことが挙げられます。それぞれの産業部門の企業数が多すぎて効率が悪いと考えられるうえに、国際的な競争の激化を背景に規模の経済を追求しようとする動きも出てきました。それが製紙(日本製紙)、鉄鋼(JFE)などでM&Aが登場し始めた理由で、成熟産業ではM&Aを軸に事業再編が行われていったということができます。
一方で、技術革新や規制緩和といった「正の経済ショック」によるM&Aも登場しました。すなわち、成長産業におけるM&Aです。IT関連産業を例にとれば、規制緩和や技術革新を機に新規参入が数多く生じ、その結果、参入企業数が過剰となってしまうと、今度は企業同士が統合して効率化を図ったり、あるいは時間を買う効果を見込んだ企業買収により、競争に勝ち抜けるスピーディーな事業展開を目指したりするといった動きが見られました。世界全体で見れば、1980年代には事業再編をもたらすネガティブな経済ショックによるM&Aが席捲しましたが、その後90年代に入るとポジティブな経済ショックによるM&Aが起きたのです。しかし、日本の場合は、両方のスタイルのM&Aが重なるように起きたというのが特徴です。
インフラ整備でM&Aコスト安に
――日本で90年代に入ってM&Aが急増するきっかけは何だったのでしょうか。
M&Aはいったん増加し始めると自動的に増えていくような作用が働くのですが、急増する契機としては、先ほどの正・負のショックに加えて、M&Aのインフラができてきたことが大きいと考えられます。具体的には連結会計、時価会計といった会計制度のほか、持ち株会社の解禁や株式移転制度(株式交換)の導入などが挙げられますし、独占禁止法の運用明確化など法制度の整備も重要な役割を果たしています。もっとも、こうした法制度の整備ができたからM&Aが増えたというよりは、経済界から実態に合った法制度を求める声が上ったことで、法制度が現実に即して変更されたと考えた方がより適切といえるでしょう。
――M&Aが増えれば、それを支えるインフラ部分に関連するビジネスも育ってきますね。
そうです。投資会社や法律事務所などM&A関連ビジネスの分野にも数多くのノウハウなどが蓄積されるのですから、既存のM&Aで整備されたインフラを活用することができるわけです。社会全体としてみればM&Aにかかるコストを引き下げることが可能になります。
事実、その結果、日本では1999~2006年のM&Aの件数は、金融部門を除くと全体として伸びています。件数そのものは欧米に比べてまだ少ないとはいえ、世界全体ではM&Aの件数が2002年以降にいったん減少傾向に入ったのとは対照的です。
日本的経営風土とM&A
――論文では、M&Aの形態や取引の多様性に目を向け、日本のM&A市場の特性を分析されていますね。
英・米のM&Aは、敵対的買収、公開買い付け、買い手間のコンテストなどのアームレングスな関係によって特徴づけられ、またターゲットを一つの法人格の下に置く合併という形をとる傾向が強い。
それに対して日本のM&Aは、ターゲット企業の法的独立性を維持する買収、部分買収、提携の比重が高く、コーディネーションを基礎とする関係によって特徴づけられる友好的な買収が中心となっています。それは敵対的なM&Aよりも友好的なM&Aの方が、日本の経営環境に適しているからといえるでしょう。
これまで、長期雇用やメインバンクシステム、株式相互持合いなどの日本的経営がM&Aの進展を阻んできたといわれ、そうした「日本的経営」が解体し始めたことがM&Aの増加の一因だと指摘されていました。確かに、メインバンクが担っていた救済の役割が縮小したことが、M&Aを増やす要因ということもできます。しかし、M&Aを実施する際には、日本の風土に合ったスタイル、つまり友好的で、事業再編につながり、そして相手企業の独立性を維持して企業文化を尊重するスタイルでなければM&Aの効果は見込みにくいのです。
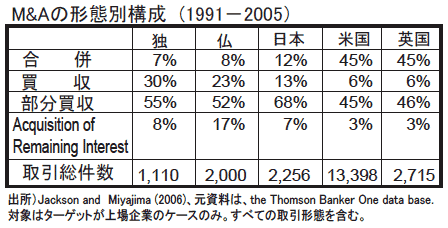
企業価値を向上させるには、自社のノウハウを注入しながら相手企業の効率性を上げることが重要ですが、それには従業員の同意を得ることが欠かせません。M&Aによる企業価値の向上は、M&Aへの従業員の賛成がなければ実現できないのです。
M&Aの効果を短期・長期で評価する
――M&Aの普及に伴い、M&Aの経済的効果があったかどうかの評価が重要になりますね。
M&Aの効果は2つの側面から見ることができます。1つはシナジー効果であり、もう1つは対象企業の経営の規律づけです。シナジー効果という場合も、成長産業におけるM&Aと成熟産業におけるM&Aでは異なります。そもそもM&Aはプラス効果もあれば、マイナス効果もあるという二面性(両刃の剣)を持つことを忘れてはいけません。
プラス効果としては、規模の経済が働いて、製品の納入先や原材料の調達先に対する価格交渉力が増すということが挙げられます。また、全く新規の投資をするよりもM&Aのほうが早く成果を上げることができますし、費用も安くてすみます。M&Aされる側の企業にとっても、相手方からノウハウの移転が期待できるほか、事業の選択と集中を進めて経営効率を改善させることができるという利点があります。
――M&Aの効果は企業ベースだけでなく、産業全体でも議論ができるのでしょうか。
こうしたプラス効果の結果、生産性の低い産業分野が縮小する一方で生産性の高い分野の方が拡大していくなら、経済全体としてみれば資源配分効率が向上することになります。言い換えれば、M&Aは、生産性が低い企業や分野を淘汰・排除するための有効な手段であり、経済全体の構造調整にも貢献できるのです。
――具体的にはどのように効果を測るのでしょうか。
短期的には合併・買収公表後の累積異常収益率、CAR(Cumulative Abnormal Return)という指標を使います。M&Aの発表が株式市場でどのように評価されたかをみるものです。それによると、代表的事例をあげた下の表では少し低いですが、M&Aの対象企業のCARは合併のケースを平均すると近年5%ぐらいを示しています。もっとも、米欧では20~30%、少なくとも国際的には15~20%に達するのですから、日本の5%という数字はあまり高いとはいえません。
――長期的な評価はどうでしょうか。
長期の場合はTFP(全要素生産性)や売上高成長率、ROA(総資産利益率)などの指標を使ったパフォーマンスで判断します。外資が日本企業を買う場合はプラスという効果が出たりしてはいますが、全般的には長期的な効果は必ずしも明確には確認できていません。
様々な理由が考えられますが、ある産業でM&Aが起きたら、その取引先に波及してそれに対応したM&Aが起きるといったように、産業間で玉突きのようにM&Aが生じている事態が考えられます。そうだとすると、必ずしも全てのM&Aで、統合後パフォーマンスが上がるとは言い切れないところがあるでしょう。
不適切なM&Aの恐れ
――論文では、M&Aがもたらすマイナスの側面についても分析されていますね。
米国などでは買い手の経営者が尊大で自信過剰であるとか、コーポレートガバナンスが充分にきかないために、自分が欲しいから高く買うという不合理な形でM&Aが実行されたケースがありました。これなどは「過大なM&A」ということができます。
もう1つの「過大なM&A」の例は、株式市場の過大評価に基づきます。何らかの利用で自社の株式がそのファンダメンタルバリューより高く評価されると、経営者にはそれを利用して他社を買収しようという誘因が作用します。
この場合は先ほどの例と違って経営者は合理的に行動しているのですが、市場自体が不合理だということになります。
――日本ではそうした「過大なM&A」が生じていますか。
全般的に日本ではM&Aが尊大な経営者の意識や、過大に評価された株価によって行われた可能性は低いといえます。しかし、部分的にはハイテク部門や新興株式市場で、「過大なM&A」の例が散見されます。株式市場主導型の例としてはライブドアのケースはその典型でしょう。2004~2005年までは「過大なM&A」が大きな流れになっていたということはありませんが、だからといって安心するわけにはいきません。M&Aの効果を整理すると、資源効率化と組織の効率化というプラス面がマイナス面を上回っているので、M&Aは促進すべきだと私は考えます。しかし、それにはM&Aの中身をしっかりチェックする必要があります。
今後のM&Aの趨勢を読む
――日本では今後、M&Aの件数が増えるでしょうか。
日本のM&Aの水準は時価総額ベースではGDP比で3%程度に過ぎず、世界各国でブーム時にはGDP比10%に達するのに比べるとまだ低いといえます。モノづくりが中心の日本では、M&Aは企業価値を向上させる際の補完的な役割を果たすのにとどまる可能性が強く、世界と同じ水準にまで比率が上昇するのは難しいかもしれません。
一方で、株主持合方式が色濃く残り、パフォーマンスが悪い企業がまだまだ淘汰されずに残っており、景気がよくなってきた2003年以降は企業改革の熱が少し冷めていることを考えると、M&Aは今後も企業の経営改革を促進する力になります。M&Aを通じて、外部の改革案と内部の改革案を競い合って効率の改善につなげるといったコンテストの効果は大きいですから、M&Aの比率が世界並みにならなくても、その役割が上昇する可能性は十分あるといえます。
――政策面からはどのようなことが考えられますか。
まず、国際的な競争を背景に企業がM&Aに踏み切ろうとしているときに、国内のシェアの変化を前提にした従来型の合併審査ではもはや非現実的です。この意味では、公正取引委員会が近年は柔軟な姿勢を打ち出しているのは望ましいといえます。
第二には国内企業のM&Aは奨励しながら、海外企業のM&Aには消極的というダブルスタンダードはもはや許されません。日本企業自身が海外ではM&Aを仕掛けているのですから。
第三に、統合によって生じたレント(超過利潤)が有効に使われるように、適切な内部ガバナンスの機能がより一層重要になります。
解説者紹介
立教大学経済学部卒業、同大学大学院修士課程修了、東京大学大学院経済学研究科博士課程修了、早稲田大学商学博士。東京大学社会科学研究所助手、ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員などを経て、1995年から早稲田大学教授。2002年よりRIETIファカルティフェロー。研究テーマは日本経済論、日本経済史、企業金融、コーポレートガバナンス。主な著作物は、『産業政策と企業統治の経済史:日本経済発展のミクロ分析』(2004)有斐閣、『現代日本経済』(2006)有斐閣(橋本寿朗・長谷川信氏との共著)、Corporate Governance in Japan"(2007)Oxford University Press(共著)他著書論文多数。