| 解説者 | 田中 一弘 (ファカルティフェロー/一橋大学大学院商学研究科) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0002 |
| ダウンロード/関連リンク |
日本企業は「会社は誰のものか」と問われた時、建前としての株主主権とホンネとしての従業員主権との間でジレンマを感じている、と田中助教授は指摘している。法律を整備する際には、そうした主権観や経営者の規律付けの実態を考慮すべきこと、すべてを性悪説で片付けずに、経営者の良心を発揮させやすくする構造を考えることが重要だと述べている。
企業の主権観を明らかに
――まず、企業に対するアンケート調査を実施した狙いをお話し下さい。
このディスカッション・ペーパーの元になったアンケート調査は、RIETIの研究プロジェクト「日本企業のガバナンス:そのブラックボックスを開く」(主査:伊丹敬之一橋大学教授)のメンバーが、質問項目から全員で何度も議論して作成し、実施したものです。
研究プロジェクトのテーマはコーポレート・ガバナンス(企業統治)ですが、これまでのガバナンス論は委員会設置会社、あるいは社外取締役の比率をどうするかなどの構造的メカニズムに議論が集中していました。企業の方などとお話ししていますと、形は作ってみたが、どうもぴんとこないという声が多かったのです。なぜなのかと考えてみると、大事な部分がブラックボックスになってるためで、それを開けてみようと考えたわけです。ブラックボックスになっている部分の1つが「会社は誰のものか」という主権の問題であり、もう1つが経営者の意志決定に何が影響するのかといったプロセス的メカニズム論でした。
主権の問題には、企業は誰のものかという実態論、あるいは誰が持つのがふさわしいかという規範論があります。一方、メカニズム論というのは経営者がどのように規律づけられるかという話です。その中で構造的メカニズム論はたとえば執行役員制を採用した会社のパフォーマンスがどうか、社内の議論が活性化しているかなどを調べるものです。
ただ、構造論だけではどうもしっくり来ないのです。そこで、経営者が実際どのように規律づけられるのか、どういう相互作用が起きるのか、を調べるプロセス的メカニズム論が重要になります。このアンケートは主権論とプロセス的メカニズム論が質問項目の前半部分と後半部分になっています。この論文では主に前半部分を使い、後半部分をぴりっと効かせる形で使っています。
株主・従業員主権を軸に企業を3分類
――この論文での核になるのが「株主派」「従業員派」という概念ですが、これについて説明してください。
株主派、従業員派というのは恣意的に分けたのではなく、判断の基準というのは アンケート調査 [PDF:696KB] の最初の質問にあります。ここで9つの質問をしているのですが、ズバリ会社は誰のものだと思いますか、という質問だけでなく、できるだけ企業のホンネを引き出すために、実務家が日常の中で考えそうなことを質問にして、多面的に評価しました。
具体的には株主を重視する意見を1、従業員を重視する意見を7という両極端として、中立的な立場を4とします。全部で7段階のうち、自分がその数直線のどこに当たると思うかを自己評価してもらうというユニークなものです。
その評点を平均して、3.5未満を株主派、4.5以上を従業員派、3.5-4.5を中間派と位置づけています。ですから、ある企業に御社は従業員派ですねと言っても、いや違いますという答えが返ってくるかもしれません。これはアンケート調査の限界でもあります。
また、アンケートでは、同じ質問について10 年前はどうだったかを現時点で評価してもらっており、どの程度主権観が変化したかをとらえています。このこともユニークな点だと思います。
――3 つに分類した企業グループにはそれぞれどのような特徴があるのでしょうか。
株主派、従業員派に共通しているのは、小規模で利益率が高い企業であるということです。こうした会社が主権観の旗幟を鮮明にしています。従業員派の企業の方がより小粒でピリリとした企業といえるかもしれません。これに対して中間派企業は相対的に規模が大きく、利益率が低いという特徴を持っています。
――株主派は株主への分配が多いというような特徴もあるのですか。
おもしろいことに、株主派が重視するのは第一に株価で、株価上昇を強く意識しますが、増配を重視する傾向は我々が考えるほど強くありません。むしろ、情報開示が優先順位としては高いという結果が出ています。また、理由は明らかではないのですが、これまで株式持ち合いを強化してきたという特徴がでています。
日本企業の主権観にジレンマ
――この概念を中心にアンケート調査で明らかになったことを、いくつかのポイントに絞ってお話し頂けますか。
第1のポイントは、全体として日本企業は株主重視の傾向を強めていると考えられていますが、その動きは斉一的ではない、つまり企業全体がそちらの方向に動いたのではないということです。平均としては確かに株主重視の方向に変化していますが、変化は株主派に顕著に見られるのであって、従業員派はほとんど変化していないのです。従業員を重視する立場の企業は10年前との意識の差が全くないといって良いと思います。全体の中で株主の意向を気にしている企業が株主重視の方に動いているというイメージです。
第2に、全体を引っ張った株主派は、株主が強い会社だということがあります。企業は内発的に株主主権が正しいと考えているというよりも、現実の必要性に迫られて株主重視の立場をとっているようです。外国人株主の比率も相対的に高いですし、また筆頭株主が強い傾向があります。21%が親会社を持っている上場子会社で、社長選任プロセスなどでも親会社の意向を気にしています。市場や機関投資家などの株主に対する配慮とは別の配慮が働いていることに、注意が必要です。従業員派では親会社を持っている比率が17%ありますが、こちらはあまり親会社の意向を気にしていません。
株主派は親会社の圧力を気にしているだけでなく、企業間での株式持ち合いを強めていますし、また外国人株主など機関投資家からの直接的な脅威を強く感じています。ただ、これらの企業は従業員軽視に転じているわけではありません。株主派の従業員に対する意識は、他の項目に比べるとあまり変化していません。株主派でも9割が競争力の源泉は従業員の能力、やる気だと答えています。誤った意思決定をした時にも、従業員の士気に影響すると考えているのです。
第3 に、先に見た株主派だけでなく日本企業全体としてみても、建前は株主主権だが、ホンネは従業員重視だという主権におけるジレンマに悩んでいるという姿が見て取れることです。図に見るように、建前では多くの人が株主重視の回答をしています。しかし、業績が悪化した際に、配当重視か、雇用重視かを尋ねた質問では、配当優先という企業は大きく減ってしまいます。また、経営者が不適格だった場合にも、株主の圧力ではなく、日本的な社内の圧力や合意によって経営者が交代するのがよい、という企業が多いのです。ここにある種のねじれというか、ジレンマが現れていると感じています。
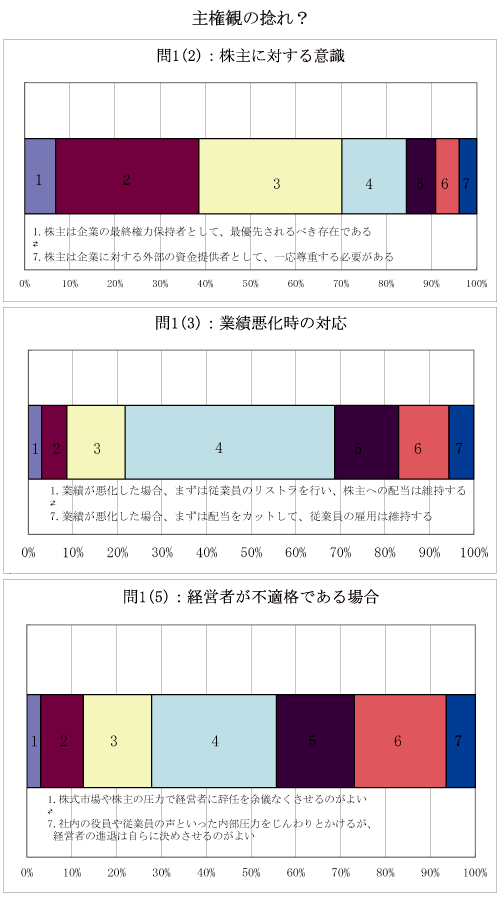
――このアンケート調査を元に「会社は誰のものか」という問いにズバリ答えてください。
ズバリ言えば、ジレンマだと思います。法律的には株主主権であり、多くの日本企業はそれを認めていますが、それだけでは釈然としない感情を抱えているようです。従業員を大事にすることには経済合理性があり、それがなければ会社の経営はうまくいきません。企業人の実感に根ざした違和感がこの中にあると思います。本当に株主重視にしてしまって大丈夫なのか、と考えているのでしょう。
経営者の集まりなどでこの調査の話をさせて頂く機会があるのですが、そのとき株主重視は建前で、ホンネは違うようですね、という話をしますと皆さんどっと笑います。株主主権という建前だけでは不安だということを多くの経営者が感じておられると思います。
主権観を元にしたガバナンス制度を
――これをもとに、どのような政策的提言をお考えですか。
政府の政策は、主権意識やガバナンスのプロセスに立ち入ることは難しいと思います。法律を左右するのは構造です。ただ、アメリカの法律はアメリカのガバナンス構造だけでなく、主権観やプロセスを踏まえ、それに根ざしているのではないでしょうか。ですから、違う主権観やプロセスメカニズムをもった日本にそのまま持ってくるのは危険なのです。
我々としてどのような構造を作るかを考える時に、従業員重視の主権観を持っていることや、アメリカとかイギリスとは違った規律付けのプロセスを持っていることを踏まえて、制度をより現実的なものにしていくことが重要だと思います。
また、法律は経営者の規律付けを目的としていますが、今の構造は経営者というのは放っておくとさぼるか悪さをする、という性悪説を大前提としています。本当にそれだけでよいのでしょうか。それがないといえば嘘になりますが、たいていの経営者は多かれ少なかれ、よい成果を残したい、責任をきちんと果たしたいと思っているはずです。その部分を見落としてはなりません。
このアンケートでプロセスを重視したのはそのためです。経営者は他者の目を気にしながら自己規律を図っていく、そこを見てみたいと思ったのです。経営者性悪説一本槍では無理です。性善説というか、経営者の良心というものを発露させやすい仕組みを考えてみてはどうかと考えています。もちろん、性善説だけではだめなのですが、これまではあまりに性悪説に傾きすぎたきらいがあります。両方が必要なのです。
たとえて言うと、性悪説という近視のレンズの度を強めていくだけでは、視力は改善しないのと同じです。そこに性善説という乱視の度を加えると、急にものが良く見えるようになるのです。今の日本は近視のレンズを分厚くして、ふらふらしているような状態だと思います。適切な乱視の度を入れてやれば、ガバナンスの現実がよりよく見えるようになるのだと思います。最近では海外の学者でも日本企業を深く調査して、同じような結論に到っている文献があります。
次には国際比較も
――今後はどのような方向に研究を進めて行かれますか。
次の段階としては国際比較をしようと考えており、既にデータはとれています。これを日本の調査結果とすりあわせていきたいです。
また、企業が感じているジレンマが日本企業のガバナンスにどのように影響してきたかを探ることも重要なテーマです。一部の企業は組織を変えましたが、その成果があがっていないかもしれません。ホンネと建前の乖離が直近の日本企業の経営にどのような影響を与えたのかに関心を持っています。
また、今後、株主の力が強くなっていけば、企業はそれに対応して手を打つことになるわけですが、株主重視の意識が今後強まっていくのかどうか、にも関心があります。日本はよりアングロ=サクソン的な企業観を持つことになるのでしょうか。
私の感じでは必ずしもそうはならないと思います。ホンネと建前の乖離が限りなく大きくなっていくことは難しいと思います。ホンネが変わることもあるかもしれません。しかし、企業の意識は経済の側面だけで語れることではなく、日本の文化、歴史や人間関係のあり方が深く関わっているものですから、ホンネがそれほど大きく変化していくことはないと思います。ホンネと建前のギャップを埋める動きがどう出てくるかを注視していきたいと思います。
アンケートの概要
本論文の分析対象となったアンケート調査は2005年2月24日に上場・非上場3235 社を対象に郵送調査で実施された。内訳は上場企業が東証1,2部上場の2154社、非上場企業が売上高500億円以上の全906社と400億円以上から無作為抽出した175 社である。回答の最終締め切りは5月13日。回答を得た企業は上場会社232社、非上場会社53社の合計285社で、有効回答率は8.8%だった。本論文は上場企業232社を対象にした集計結果をもとにしている。
プロジェクト「日本のコーポレートガバナンス:そのブラックボックスを開く」のメンバーは筆者の他に、伊丹敬之(一橋大学)、広田真一(早稲田大学)、江川雅子(ハーバード・ビジネス・スクール 日本リサーチセンター)、久武昌人(経済産業研究所)、小幡績(慶應義塾大学)。
解説者紹介
一橋大学商学部卒業。同大学大学院商学研究科博士後期課程修了(博士(商学))。神戸大学大学院経営学研究科助教授を経て、2003年より一橋大学商学研究科助教授。研究テーマは企業統治、経営哲学、経営者論。2005年2月から06年1月までRIETIファカルティフェロー。主な論文に「企業統治:経営者の自己規律を促した日本型企業システム」(工藤・橘川・フック編『現代日本企業1企業体制(上)-内部構造と組織間関係』有斐閣、2005年)など。


