| 解説者 | 浅川 和宏 (ファカルティフェロー/慶応義塾大学大学院経営管理研究科) |
|---|---|
| 発行日/NO. | Research Digest No.0001 |
| ダウンロード/関連リンク |
いま、日本企業に求められるグローバル化戦略として、RIETIファカルティフェローを努める浅川和宏教授は最新の「メタナショナル経営」を提唱している。世界企業に比べ依然として自国の優位性を基調としてグローバル展開している日本企業にとっては、メタナショナル経営の考え方を取り入れることのメリットは大きく、この視点を取り入れることで、これからの日本企業は、グローバル競争上、優位に立つことも可能になると指摘している。
――論文テーマであるメタナショナルとは、どんな経営を指すのですか。
メタナショナル経営は、もともとINSEADのドーズ教授により提示された概念です。自国に優位性がある企業は、その長所を生かしながら海外で事業を展開していくのが一般的です。メタナショナル企業はそれだけに飽き足らず、世界各国で蓄積した経営に関するナレッジ(知識・情報)を有効活用し、グローバルでみて優位性を確保していく経営を行っています。
メタナショナル経営の場合、仮に自国が小さ過ぎたり、事業展開に向いてなかったりしても、海外で得られる経営資源をうまく使うことで、グローバルでは競争上優位に立つことも可能になります。
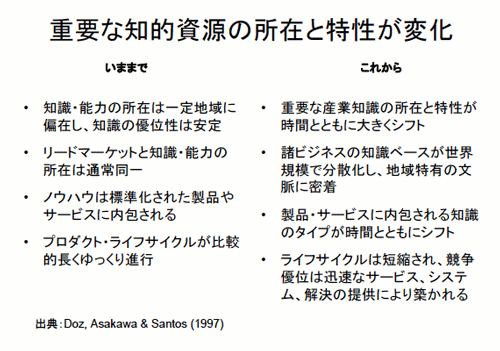
――論文ではメタナショナル経営の特長が最も表れている企業として、いくつか例を挙げていらっしゃいますね。
STマイクロエレクトロニクスが代表的です。イタリアとフランスの企業が合併してできた半導体メーカーです。イタリア、フランスは、半導体産業からみれば、立地条件が良いとはいえません。技術蓄積が乏しく、主要な顧客もいないからです。いわば、「間違った場所に生まれた企業」といえるでしょう。それにもかかわらず、同社は海外企業との提携を進め、米国、日本、台湾などに技術開発拠点を設けることで、世界中の知識、情報をうまく集約し、強い競争力を持つ企業になりました。
携帯電話のノキアも同様です。自国のフィンランドは小国ですが、英国でR&D(研究開発)活動を進め、米国から先端技術、マーケティングのノウハウ、日本からは顧客満足志向のあり方などを積極的に取り入れて、それを結実させて成功しました。
地域ごとのナレッジを吸い上げる
――なぜいま、メタナショナル経営が重要だと考えるのですか。
ワインを例に説明しましょう。かつてはフランスなど欧州がワイン市場の中心で、ノウハウ、技術、知識が豊富にあり、そこに行きさえすれば必要なナレッジは手に入りました。ところが現在、ワインは世界中で作られ、それぞれの国でその土地ならではのノウハウが産み出され、蓄積されています。企業は、いま先進的とみられる場所に拠点を置いたとしても、そこを本拠とするメリットが何年続くのか、判断がつきにくくなっているわけです。
つまり現代は、ある産業のメッカはこの地域だというように、ノウハウが一箇所に集中する状況ではなくなっています。活用できる知識やノウハウがあちこちで育ち、しかも、時間とともにそうした地域は移り続けているのです。
自国市場が強ければ、その優位性に立脚した経営戦略を進めることはもちろん大切ですが、それに安住せず、世界各地で育っている技術、知識も迅速に社内へ取り込んでいかないと、グローバルでの競争上、企業は確固たる地位を築けないことになります。
――メタナショナルという概念は、これまでの経営学でいわれてきた経営戦略とはどう違うのですか。
米国の経営学者、マイケル・ポーター氏は1986年、2つの企業戦略を示しました。1つは、各国の市場ごとに対応するというマルチドメスティック戦略です。国によって競争環境が違うので、それに合わせて対応を変えていくというものです。もう1つは、世界を単一市場とみなすグローバル戦略で、標準化された戦略を各国で展開します。ただ、現在は、どちらの戦略を選んでも、それ一辺倒では通用しなくなっています。自国市場の強みが10年後にはハンディになるかもしれないようなダイナミックな変革が起きている時代です。企業の組織。構造をそもそも静態的な分類に当てはめることが妥当かどうか疑問です。いまは企業が時々の局面に応じてより柔軟に、より迅速に対応することが求められているわけです。ナレッジを核とした戦略に立って、ナレッジの流れを「本社→ローカル」「ローカル→本社」「ローカル→ローカル」と臨機応変に変えていくメタナショナルこそが、いまの時代にふさわしいと考えています。
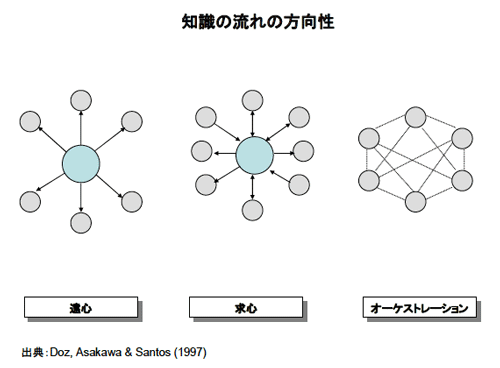
――実際に、日本企業がメタナショナル経営を取り入れる場合に辿るプロセスについて、論文では「ナレッジ・マネジメント・サイクルのグローバル化」とおっしゃっていますが、これはどういうことでしょうか。
3つの段階があります。まず、世界中にアンテナを張り巡らすことです。これは、R&D でもマーケティングの拠点でも構いません。「まさかこんなところに」と思われる場所から、むしろ有益な情報が得られるのです。次に、取り込んだノウハウをいかに社内で伝播させるかです。社内からは「使えるはずがない」などと抵抗がありがちですが、それを乗り越えて、有望なナレッジに育てていくことが必要です。最後に、世界中の拠点で適宜ナレッジを活用します。
この流れがメタナショナルのサイクルです。潜在的なナレッジを発掘し、世界の拠点のネットワークに取り入れていく知識ブローカーたる人材の育成がカギを握っています。
自国本位、自前主義に傾きがちな日本
――日本企業の中で、メタナショナル的企業は少ないと指摘されています。海外と比べて日本企業はメタナショナルを取り入れていないのでしょうか。
事業レベルでは、メタナショナル戦略を生かした事例も既に見られます。論文でも取り上げていますが、たとえば資生堂は、香水文化の乏しい日本から本場フランスの香水市場に進出して、現地の人材、情報を生かして成功を収めました。
しかし、会社全体でみれば、日本企業はポーター氏のいうグローバル戦略をとりがちです。つまり、日本の強さをそのまま海外へ持ち込んで事業を展開しがちです。グローバル企業といえば、もともと日本が強い自動車や家電メーカーの名前が浮かぶのは、その裏返しでしょう。
ただ、この戦略がずっと通用し続けるわけではありません。かつて世界のトップだった日本の半導体産業が低落したのは、自国の強さに安住し、自前の日本人スタッフ中心で研究開発を進めたことと無関係ではありません。これとは対照的に、日本を追い上げた韓国、台湾などの半導体企業は、海外から積極的にナレッジを吸い上げて、それを有効に活用しました。
メタナショナル戦略は、国際競争力が比較的弱いといわれる産業、たとえば医薬品、化学などの日本企業にも、海外企業と伍して競争できる可能性をもたらしてくれます。
――論文の中で、メタナショナル的視点を導入するために日本企業には3つの課題があるとされています。それらは何ですか。
第1に、自国主義の克服、つまり日本のやり方が常にベストであるという自国本位の発想を改めること。第2に、自前主義の克服、つまり何でも自社内でまかなおうとするのではなく、海外からのアウトソーシングも組み合わせること。そして第3に、先進国至上主義の克服、つまり世界中のあらゆる場所から知識・情報を集めて活かすことです。
――さまざまなナレッジのなかでも、R&Dは最も自国本位、自前主義の傾向が表れやすいと論文で指摘されていますが、メタナショナル戦略はR&Dにどう反映されるべきであると考えていますか。
海外でのR&D活動がなかなか展開しない理由として、自国に集中させた方が効率がいい、技術が流出してしまう懸念がある、などの点があげられます。最近は、やや増える兆しがありますが、経済産業省の最近の調査によると、日本企業の海外R&D比率は4.1%にとどまっています。
R&Dのうち、"D"の開発は、本社の技術をもとに現地の市場ニーズに合わせた製品を作ればいいので、比較的成果をあげやすいのですが、"R"の研究は容易ではありません。特に、欧米の先進国で研究を成功させるのは、販売や生産などと比べて、難しさの質が違います。日本から駐在員を派遣し、現地を管理させる方法が必ずしも通用しないからです。
海外で成果をあげ、それを日本でも活用することを目指すなら、現地の著名な研究者をトップに据えて、運営を任せる方法があります。本社からの統制がきつ過ぎると、現地の運営がうまくいかなくなるからです。一方で、海外拠点を自由にさせすぎると、本来の目的から乖離してしまう恐れがあります。そのバランスをとって、ある程度、運営が軌道に乗った段階で、現地と本社の問題意識をすり合わせて、共通の目標をもつようにしていくわけです。
――今回、日本企業の先進国でのR&活動の現状を調査されていますが、評価は如何ですか。
米国特許分析および事例調査の結果、現地ナレッジ獲得に成功している海外R&D拠点の場合、(1)現地拠点の吸収能力、(2)現地との対外的ネットワーク、(3)現地拠点の自律性、(4)本社との適度の連携、(5)本社側の現地ナレッジに対する吸収能力、が伴っていることが明らかになりました。
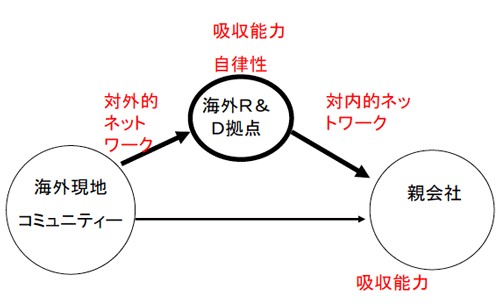
しかしそれらをどれだけ有効活用できているかに関しては、ナレッジを移転・融合し、活用するレベルまで達していない例が多いことがわかりました。海外研究所をスターター、イノベーター、コントリビューターと3つの発展段階に分けると、イノベーターまではいっても、本社の研究に貢献するコントリビューターにはなっていないわけです。
このため、企業によっては海外R&D拠点を閉鎖したり、売却したりするケースがみられるのは、残念なことです。
中長期では、産業政策とも一致
――近年、日本企業は中国、インドなどへ活発に投資しています。現地でのR&D活動のポイントは何ですか。
欧米先進国でのR&D活動が十分に機能しているとはいえないなかで、今度は中国やインドなどの新興国に目を向けているわけです。新興国でR&D拠点を育成するには、まず、「現地の技術水準は常に低い」「人材は欧米よりも常に劣っている」といった偏見を捨てることです。こうした先入観が現地にとけ込む際の障害になっているからです。先進国流のやり方を押しつけず、固定観念を改め、現地の強みを最大限引き出していく姿勢が日本企業にとって重要でしょう。
――最後に、日本のグローバル・イノベーションに向けての示唆として、産業政策の立場から見たメタナショナル経営を論文ではどうとらえていますか。
メタナショナル戦略は、グローバルに展開して価値創造を行う経営ですから、どこの国に立脚するかは問わないことになります。これに対して、産業政策は国内の産業を振興するのが目的です。企業が海外へどんどん進出すると、産業政策上はマイナスになることも考えられます。
ただ、これはあくまで短期的な側面です。中長期でみると、ノキアを生んだフィンランドに海外から携帯電話関連の企業が進出しているように、グローバル化は利点となって跳ね返ってくるのです。国にとっては、企業のイノベーションの環境を整えて、産業集積の厚みを増す政策をとることが、何より重要になるでしょう。
解説者紹介
早稲田大学政治経済学部政治学科卒業後、(株)日本興業銀行勤務。ハーバード大学MBA、INSEAD(欧州経営大学院)Ph.D. 取得。慶應義塾大学大学院経営管理研究科講師、助教授を経て現在同大学大学院教授。その間、マサチューセッツ工科大学客員研究員、米スローン産業研究プログラム・アフィリエート、ウィーン経済大学客員教授等を兼任。主な著作物:『グローバル経営入門』マネジメントテキストシリーズ, 日本経済新聞社, 2003、Organizational tension in international R&D management (Research Policy 30.5.), 2001、他論文多数。


