イベント概要
概要
日本経済は、構造的にデフレ脱却を実現し経済活性化を図ることが急務となっている。その中で、2013年6月14日、アベノミクスの3本目の矢である「成長戦略」が発表された。
これを受け、同月26日に開催されたRIETI政策シンポジウム「『成長戦略』に迫る―第三の矢はどこまで飛ばせるのか?―」では、政策実施責任者として成長戦略策定に携わった経済産業省の石黒憲彦氏から、10年後には1人当たりGNI(国民総所得)を150万円以上拡大するという「成長戦略」の中身に関する詳細な説明がなされるとともに、RIETIの深尾京司PD、読売新聞の野坂雅一氏を交えて、成長戦略の評価と今後の課題について多面的な議論が交わされた。
議事概要
基調講演
石黒 憲彦 (経済産業省 経済産業政策局長)
1. 日本再興戦略の概要
6月19日に発表された経済成長戦略「日本再興戦略」は、経済産業省(以下、経産省)だけが考えたものではなく、多省庁が成長に向けたさまざまな施策を込めてつくり上げたものだという点で、従来の成長戦略とは大きく異なっている。その内容は、日本産業再興プラン、戦略市場創造プラン、国際展開戦略の3つに分けられる。これらを実施することで、澱んでいた人・物・金を動かし、10年間の平均で名目成長率3%、実質成長率2%程度を実現し、結果として名目GNI(国民総生産)を1人当たり150万円以上拡大するという目標が閣議決定されている。
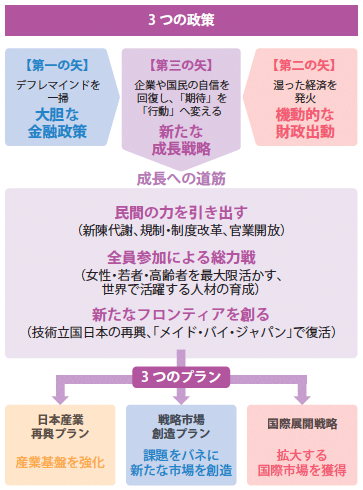
まず、日本産業再興プランは産業基盤を強化するための施策プログラムで、産業の新陳代謝の促進を第1の柱として掲げている。第2の柱は人材力の強化・雇用制度改革で、雇用維持型の労働行政から労働移動支援型への政策転換、女性の活躍推進と待機児童解消加速化プランなどを行っていく。第3の柱は科学技術イノベーションで、総合科学技術会議の司令塔機能強化や府省横断型の研究開発への重点的資源配分などを行う。第4の柱は世界最高水準のIT社会の実現で、ビッグデータの分析・活用促進のための規制緩和や革新的な電子行政サービスを実施する。
第5の柱は立地競争力の強化で、公共施設運営権等の民間開放(PPP(官民連携)・PFIの拡大、コンセッション方式の対象拡大)、環境・エネルギー制約の克服(環境アセスメントの迅速化、電力システム改革、原発の再稼働)、国家戦略特区の実現などの施策を実施する。第6の柱は中小企業・小規模事業者の革新で、個人保証ガイドラインの策定により、中小企業が再チャレンジや創業の際に融資を受けやすくする仕組みなどを考えている。
戦略市場創造プランは、課題を解決しながら戦略的に市場を創っていくものである。第1の柱は健康寿命の延伸で、日本版NIH(米国 国立衛生研究所)の創設、一般医薬品のインターネット販売の原則解禁、医療・介護情報の電子化、医療の国際展開などの施策を進めている。第2の柱はクリーン・経済的なエネルギー需給の実現で、電気事業法を改正し、電力システム改革を着実に実行していく。第3の柱は世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現で、従来は自治体ごとの農業委員会が貸付の審査をしていたところから、都道府県レベルで管理機構をつくって融通することで、株式会社等の農業参入を促進しようとしている。
国際連携の推進に向けては、貿易のFTA比率7割を目指す。また、インフラのパッケージ輸出、トップセールスの展開、中堅・中小企業に対する支援とともに、クールジャパンの推進として、海外の放送枠を買い、日本のコンテンツを提供することも考えている。
2. 緊急構造改革プログラム
日本産業再興プランの1丁目1番地である産業の新陳代謝の促進を実行するため、緊急構造改革プログラムを作成した。これは、過小投資、過剰規制、過当競争の3つのゆがみを是正して、民間投資の拡大、新市場の開拓と公的保険の隣接分野の民間開放、事業再編の促進を行うことで、経済の好循環をつくっていくというものである。
過少投資への対策としては、すでに今年の年頭に10兆円の緊急経済対策を実施している。さらに、医療機器やロボットスーツ、介護ロボットなどは初期市場では値段が高くなるので、リースによって導入の促進を図るための諸制度を整える。また、クリーンエネルギー・ファイナンス制度として、民間事業者が一般の住宅の屋根などを借りる仕組みや、スマートコミュニティーが投資を回収できるまでの期間、産業革新機構等から出資する中長期の融資制度も考えている。
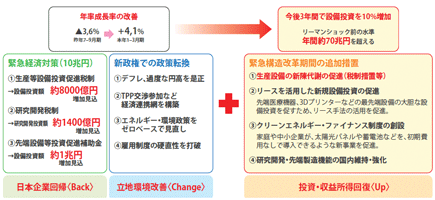
[ 図を拡大 ]
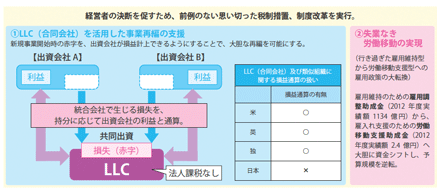
[ 図を拡大 ]
過剰規制の改革については、まず、企業が計画する実証実験が法律に抵触する場合、企業単位で特例を設ける企業版特区の創設を考えている。アメリカでGoogleが行っている自動運転車の走行実験などがその例である。第2に、公的保険の隣接分野にあるグレーゾーンを解消するため、認定制度を創設することである。どこまでならやってもいいか、条件は何かといったことを明確化することで、企業が安心して新事業に取り組めるようにしたいと考えている。
過当競争の解消については、雇用調整助成金の使い方を変え、労働者の側に助成金が行く仕組みをつくろうと考えている。また、LLC(Limited Liability Company/ 合同会社)をつくることも検討している。たとえば、エチレンプラントが過剰な状態で、A社とB社のプラントの1つをつぶすと、損失が発生したときに親会社が損益通算できるという、一種の企業版エンゼル税制のような制度を考えている。
パネルディスカッション
モデレータ:中島 厚志 (RIETI理事長)
報告1
モデレータ:深尾 京司 (RIETIファカルティフェロー・プログラムディレクター / 一橋大学経済研究所 所長・教授)
1. 成長戦略:評価と課題
安倍政権は、前政権と比べると企業活動の活性化を重視しているという点で、方向性は高く評価できる。特に国内回帰や国内立地環境の改善等で国内投資を拡大すること、TPPへの参加を目指すことは重要な選択だった。ただし、総花的で各府省のウィッシュリストのような性格が非常に強く、総需要の不足の解消と潜在成長率の引き上げのために、各府省から出てきた政策がどれほど寄与するのかという道筋が明らかにされていないことには留意する必要があるだろう。
2. 総需要不足と潜在成長率の停滞
日本はリーマンショックのときに-8%という大きなGDPギャップが生じたが、内閣府の推定では直近でも2.3%のGDPギャップがあるという。また、消費者物価も対前年比でまだマイナス成長が続いており、両者の間に非常に強い相関があることは明らかである。したがって、GDPギャップを+2%程度に持っていかないと、消費者物価上昇率2%にはとても及ばない。現在、年間11兆円に達する需要不足がある中、経産省のプランでは民間の設備投資を3年間で7兆円拡大することを目指しているが、供給能力の増大は20兆円程度が見込まれるため、焼け石に水である。
![図4:GDPギャップ[実際のGDP-潜在GDP]とインフレ率の推移 図4:GDPギャップ[実際のGDP-潜在GDP]とインフレ率の推移](/jp/events/13062601/data/figure_4.gif)
日本は過去20年間、平均1%以下の成長しか達成できていない。さらに、今のままでは2020年まで労働供給は毎年0.4%程度減少し、成長率をさらに0.3%程度引き下げる要因になる。また、資本投入のためには、減税だけでなく資本収益率の引き上げが大前提になるだろう。2%成長のためには、TFP(全要素生産性)の上昇を1.2%程度にし、待機児童ゼロ、女性の就業拡大などの施策を着実に実行して、労働投入を-0.3%から+0.2%程度の寄与に持っていく必要がある。
日本のTFPの上昇が90年代以降大幅に停滞している原因として、非製造業にIT革命が起きなかったこと、製造業で新陳代謝が機能せず、中小企業における生産性の上昇が停滞したことが指摘されている。新陳代謝が不全に陥った背景には、大企業の国内工場閉鎖がある。したがって、国内回帰により重点を置いた政策を実施すると同時に、中小企業の研究開発を支援していく視点が重要である。
3. 残された課題
政府は設備投資減税によって法人負担を軽減するとしているが、日本企業は、工場の建物や機械に関しては、低成長の割に着実に資本蓄積を続けてきている。他方で、ICT投資や無形資産投資など、組織変革やOff-JTなどによる成長への寄与は、主要先進国の中で最も小さい。したがって、設備投資よりも、こうした分野を支援すべきではないだろうか。また、今回の成長戦略では、法人税の減税や労働市場の改革(解雇法制)は課題として取り上げられなかった。
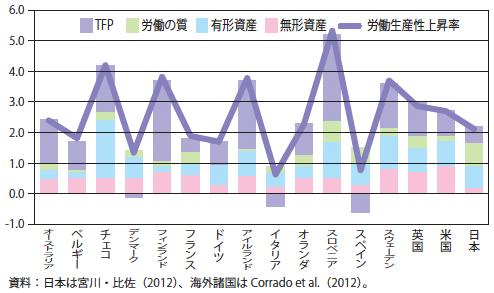
報告2
野坂 雅一 (読売新聞東京本社 論説副委員長)
1. 総合評価
安倍政権が発足して半年、読売新聞としては、成長戦略の方向性は妥当であると評価している。問題は実行力である。この戦略は参議院選挙を目前に控えてまとめられたが、7月の参議院選挙が終わると、その後3年間は国政選挙がなく、選挙をあまり意識せずに政策に集中できる可能性が高い。これをどう活かすかが問われることになるだろう。
これまで民間企業や地方各地は、選挙に絡めて政府にいろいろな要望を出してきたが、今、問われているのは民間の活動である。総理も成長戦略の第2弾の発表のときに、「民間活力の爆発」という表現を使っている。昨今、民間は内部留保を貯めこむばかりで、賃上げやボーナスアップ、雇用の拡大については慎重な態度を取ってきた。こうした従来の発想を変えていく必要がある。
2. 成長戦略の成否を握る課題
今後の課題は、好循環への道筋がまだ不透明なことである。現在、日本の潜在成長率は1%弱といわれており、これを2%に高めていくことはかなりハードルが高い。また、仮に2%まで行ったとしても、企業が潤うだけで家計が潤わなければ、好循環シナリオは進まない。また、成長戦略には3年間で設備投資を1割増、海外のインフラを30兆円獲得、農業の所得倍増など野心的な目標がたくさん盛り込まれているが、従来のパターンで看板倒れに終わってはいけない。KPI(重要業績評価指標)は今回の目玉の1つだと思うが、きちんと成果目標を立てて達成できていないとすれば、何が足りないのか確かめていくことが重要である。
また、今回の戦略の中にも、規制を省く国という意味の「規制省国」、少子高齢化やエネルギーの制約など課題が多いという意味の「課題先進国」、エネルギーの安定供給を目指すという意味の「エネルギー最先進国」などのキャッチフレーズは盛り込まれているが、具体的な取り組みが待ったなしの状況に来ている。特にエネルギーは、原発の再稼働問題がこの夏以降、大きな焦点になるだろう。原子力規制委員会は、審査に少なくとも半年程度かかるというが、電力の安定供給なくして成長戦略はない。
TPPは、成長戦略の成否を象徴するものになるだろう。TPP交渉においては、恐らく農業の新たなる市場開放を要求されるだろうが、それに備えて、農業の競争力をどう強化するのか、成長産業としてどうよみがえらせるのかという課題がある。10月ごろの大筋合意を目指して時間のない中、日本がこの交渉にどう臨み、それと並行して国内のさまざまな対策・政策をどう実行していくかが問われている。
最後に、G8やG20などで、日本は財政再建と経済成長の両立、特に財政健全化を国際公約にしている。成長戦略を打つ中では財政出動をせざるを得ないが、その一方で財政再建をどう図っていくのか。この大きな命題・難題にこれから取り組まなければいけない。いよいよ日本の覚悟が問われることになるだろう。
ディスカッション
年率2%の実質GDP 成長へ至る道筋
中島: 年平均2%程度の実質成長率を実現するには、家計に恩恵を波及させ、好循環シナリオに乗る必要がある。人・物・金を一気に動かすためには、どのようなことをしなければならないのか。
石黒: :アベノミクスは、この半年間で劇的にマクロ経済の環境を変えている。1-3月のGDPが4.1%という極めて高い成長率を出し、個人消費も回復してきている中で、民間の設備投資がマイナス0.3%だったことは、現状の日本の問題を顕著に表していると思う。今、日本の設備は老朽化が進んでおり、設備を一新することで生産性とエネルギー効率の向上が図れるはずだ。その後押しをするべく、この3年間を集中投資期間として、設備投資減税という思い切った税制を用意した。
深尾: 私の報告では、古くなった資本はその分価値が減ったと見なして推計している。分析の結果は、固定資本は生産に比べてそれほど減っていない。むしろ日本が必要としているのは、特に中小企業のR&D、情報通信やソフトウエアへの投資、労働者の訓練・教育などへの投資だと思う。
中島: 企業の収益増を賃金アップに結びつけるためには、どんなことをすればよいのだろうか。
野坂: 民間の賃上げに政府が関与することは難しいので、民間側が発想を変えて、収益を上げたら、その恩恵を従業員にも分配し、それが個人消費の拡大という形で社会に広く回っていくようなことを考えるべきだ。
石黒: 現状では、法人税率の引き下げについて国民的理解を得るのは困難だ。理解を得られるのは、思い切った設備投資を国内でやる企業に対して実効税率を下げることだと思う。また、経産省の分析では、2002年から実質成長率が1%程度ずつあったにもかかわらず、雇用者報酬はほとんど横ばいという状態だ。今、マクロ環境が劇的に円安に振れてきた中で、ポジティブな方向に企業活動が向かってくれることを期待している。他方、失業率がじりじりと下がってきていて、4.1%程度まできている。これが3%台程度になってくると、労働需給に逼迫感が出てきて、賃金が上がってくると思う。
労働市場改革
中島: 労働市場の改革があまり盛り込まれていないという指摘について、どのように考えるか。
石黒: 解雇ルールの見直しに触れられなかったのは踏み込み不足ではないかという議論もあるが、日本の大企業の経営者は現在の雇用慣行に特に違和感を持っていない。一方、厚生労働省は今回、「プロジェクト限定社員」や「地域限定社員」という正社員制度をつくることに踏み切っている。
深尾: 賃金を上げるには、労働力不足の状態をつくり出すしかない。設備投資をリーマンショックの前の水準に戻すだけでは不十分で、もっと短期的に需要の創出を図るべきではないか。また、われわれの実証研究によると、非正規雇用の賃金が低いのは生産性が低いためである。解雇法制と同時に、職業訓練やジョブカードの普及などについても踏み込む必要があると考える。
石黒: 開廃業率を上げる点では、たとえば個人保証を取らない融資を増やすことで、起業・創業のハードルを下げることがポイントになるだろう。また、大企業などで余剰感があるのは中高齢者なので、そこにセカンドキャリアを積んでもらうことが、潜在的な起業予備軍になるだろう。中小企業に関しては、ものづくり補助金などで医療などの分野に転換していただくことを考えている。
国際戦略
中島: TPPは成長戦略の縮図だという話があったが、国際戦略の中心はやはりTPPになるのか。
野坂: 今、日本政府は「メガFTA(自由貿易協定)」で、さまざまなものに挑んでいる。日中韓、RCEP(東アジア地域包括的経済連携)、日EUのFTAなどもあるが、目先の一番のターゲットはTPPである。
石黒: 日本がTPPの交渉参加を表明したことで、中国が日中韓を引き続きやろうといい出している。また、ASEAN+3でやりたいといっていたのをASEAN+6でRCEPを進めようともいい始めている。FTAのカバー率を7割にするという目標は、現状が19%だから非常に野心的な目標だが、TPPの参加表明とともに、今、日中韓、日EUが一斉に動き始めているといえる。
戦略の実行に向けた課題
中島: 今回の成長戦略の中で最優先事項は何か。また、残された課題として何があるだろうか。
野坂: 大変盛りだくさんの戦略なので、優先順位を付けていかなければ総花的に終わってしまう。また、起業・創業も大事だが、もう1つの柱として、第2創業や事業承継をうまくやっていくことを進めてほしい。
深尾: デフレ脱却に向けては、需要不足の解消を第一優先とすべきだ。財政健全化は社会保障の改革を中心に行い、同時に需要が息切れすることがないような政策をぜひ取ってほしい。2番目に重要なのは、潜在成長率を高めることだ。そのためには、TPPを成功させることが非常に重要である。
石黒: 今年の税制改正で事業承継税制の使い勝手が良くなり、親子関係にない人が引き継ぐことも可能になった。また、第2創業の支援に関しては、設備投資減税だけではなく、LLCの仕組み、ベンチャー投資を促進するための税制の仕組みなどの税制の支援措置を満載して、秋の臨時国会で法案を成立させたいと考えている。
質疑応答
Q1: 国際的に見ても高い日本の民間のR&Dが、生産性や設備投資に向かわない理由は何か。
深尾: アメリカではR&Dの売上高比率が最も高いのは中堅の企業であるのに対し、日本では大企業が中心である。恐らく日本の中小企業は、自前でR&Dをしなくても取引先からのスピルオーバーで技術・知識を得ることができていたのだろう。しかし、大企業が海外に生産を移転している中で、今後は政府も中小企業への支援を増やし、自前で技術・知識を蓄積していくという企業風土に変えていく必要があるだろう。
野坂: 通商白書2013(2013年6月公表)に、ドイツの中堅企業が独創的な技術力や商品開発力を強化して、海外マーケットを取って成功している事例が紹介されている。日本にも中堅・中小企業が420万社もあるので、そこがR&Dをしっかりと行い、日本経済を引っ張っていってほしい。
Q2: 今回の投資減税が3年間の期限付きだとすると、3~5年後のラインの更新・増強のときにはまた高い税金を払わなければいけなくなるのではないか。
石黒: 民主党政権の1つの成果として法人税率が5%弱下がっているが、現在は震災復興のための付加税が3年間かかっている。27年度からは基本税率に戻り、法人税負担は5%弱下がることになる。

