人間の営みは時間と場所に規定される。今は過去の歴史と無関係ではないし、此処は世界の動きと無関係ではない。食料・農業政策のあり方を考える際も過去の歴史や世界の動きを踏まえる必要がある。
アダム・スミス、ケインズ、シュンペーターらの経済学の古典が今日でも度々引用されるのは、いくら経済が進化しようとそれが人為による営みである以上時代を超えて通用する原理があるからだろう。農政にも百年を超える歴史があり、柳田國男、石黒忠篤、和田博雄、小倉武一ら農政をリードした偉大な先人達がいる。かれらの主張は今日でも十分通用する。というより、かれらが示した解決策が採用されなかったため、かれらが取り組もうとした食料・農業問題は悪化しながら存続してしまったといったほうがよいだろう。
日米貿易摩擦が80年代に激化してから農産物の自由化は大きな問題となってきた。1993年のWTO(世界貿易機関)設立により農産物貿易に新しい規律ができあがり、現在更なる自由化に向けて交渉中である。ほとんどの産品について関税撤廃を要求される自由貿易協定の締結交渉でも農産物は大きな争点だ。農業のためにWTO交渉でリーダーシップがとれない、自由貿易協定が結べないという非難が農業界に向けられている。世界最大の農産物純輸入国でありながら、農政に対する内外の風当たりは極めて強い。
先人達の農政思想に学ぶ
戦前の日本農業には零細農業構造と過酷な地主制の下にある小作人の解放という課題があった。
水田小作料の物納制の下で地主には収穫物の半分の米が集まった。1900年頃既に寄生化していた地主勢力は、農業の生産性向上ではなく、米の供給を制限することにより米価を引き上げて所得増加を図ろうとした。そのため、彼らは国防強化を口実として食料の自給、米の高関税による輸入の制限が必要であると主張した。(これは今日と似てないだろうか)これに対し、日本民族学の父であり農商務省の法学士第一号でもある柳田國男(1875-1962)は、小作料の物納制を批判するとともに、労働者の家計を考えるのであれば外国米を入れても米価の下がるほうがよい、海外農業と競争できるよう農業の構造改革を行い企業として経営できるだけの規模をもつ2ha以上の農業者を養成すべきであると主張した。柳田は「日本は農国なりとは農業の繁栄する国という意味ならしめよ。困窮する過小農の充満する国といふ意味ならしむるなかれ。」と言う。
柳田とともに新渡部稲造を中心とする「郷土会」に参加した石黒忠篤(1884-1960)は小作人の地位向上に尽力したが、地主勢力の抵抗により小作調停法の制定と小規模の自作農創設維持事業が開始されたにとどまった。農林省の悲願ともいえる小作人の地位向上、自作農創設を農地改革によって実現したのは、第一次吉田内閣で局長から次官を飛び超えて大臣になった和田博雄(1903-1967)である。戦前の農政は強大な政治力を持つ地主勢力に対する抵抗の歴史だった。農地改革には議会の反対が強い中でGHQの力を借りた。しかし、他の戦後改革と違い日本政府から自主的な改革案が出されたのはこれのみだった。後にアメリカは日本の成功を他のアジア諸国に及ぼそうとするが、台湾を除きすべて失敗している。農林省の改革への情熱がなければ「歴史上最も成功した農地改革」(マッカーサー)は実現しなかった。
1942年に制定された食糧管理法は乏しい食料をいかに国民に均等に配分するかという目的で作られた消費者保護の法律であり、1953年まで米価は国際価格よりも安かった。経済復興を図るためには労働費を抑制しなければならない、そのためには労働費の大宗を占める食料費すなわち農産物価格を抑制しなければならなかった。しかし、農産物価格を抑制すれば食料増産ができなくなる。このディレンマを解消する奇跡的な政策が和田農相・経済安定本部長官による農地改革と傾斜生産方式だった。小作人に農地の所有権を与え生産意欲を増大するとともに傾斜生産方式による化学肥料特に硫安の増産により、米価を下げても生産は増加した。
農業基本法の悲しい運命
しかし、農地改革により零細農業構造が固定化してしまった。零細農業構造改善という仕事を受け継いだのが小倉武一(1910~2002)による1961年農業基本法だった。農業基本法は、農業の規模拡大によるコストダウンによって農工間の所得格差是正を図ることを目的とした。所得は売上額(価格×生産量)からコストを引いたものだ。米のように需要、売上額の伸びが期待できない作物でも、コストを下げれば農家所得は向上できるはずだった。
しかし、実際の農政は農家所得の向上のため米価を上げた。コストが高く規模の小さい副業週末農家でも米を生産した方が高い米を買うよりも有利であったため農地を賃貸しようとはしなかった。いったん規模拡大の道に乗せれば、規模拡大はコストを引き下げ支払可能地代を増加させ、更なる規模拡大を生む。しかし、高米価によって農地が貸し出されなかった日本では、規模拡大の好循環に乗ることができなかった。
食管法廃止後も高米価は生産調整という価格維持カルテルによって継続されている。米のわずかな供給増加(減少)が大きな米価下落(上昇)をもたらすため、規模拡大・コストダウン意欲を持たない副業農家にとって生産を多少減らしても価格を高く維持した方が有利である。副業農家が生産を維持することは主業農家の規模拡大を阻害したが、主業農家も副業農家も同等の議決権を行使する農協運営の下で稲作農家の7割を占める副業農家に後押しされた農協・農政は高米価・生産調整政策を堅持した。農業のハンディキャップを補おうとした政策がかえってそのハンディキャップの克服を困難にしたのだ。
高米価は生産意欲を増やし米消費の減少に拍車をかけた。1970年から実施された生産調整は年々拡大し今では水田面積の4割にもなっている。農業資源が収益の良い米に向かい、麦等の生産は減少し自給率が1960年の79%から40%へ低下しても、米余りの中では農地も余っているという認識が定着し、誰も食料安全保障に不可欠な農地資源の減少に危機感を持たなかった。600万haあった農地のうち農地改革で解放した面積(194万ha)を上回る230万haが転用・潰廃で消滅した。今では国民がイモだけ食べて生き長らえる程度の農地しか残っていない。農家が減少しても農地も減少してしまえば規模拡大は進まない。40年かけて0.9haの農場規模が1.2haになっただけだ。
農政の先人達には、農家の貧困克服は零細農業構造の改善によるべきであり農産物価格を上げ消費者家計を圧迫すべきではないとする明確な農政理念があった。しかし、経済原理から外れ高米価政策に転換した農政に、皮肉にも多数の農家は米単作兼業という経済原理に即した対応を行った。高米価、兼業、農地転用という3種の神器により副業米単作農家の所得(792万円)は勤労者政策所得(646万円)を大きく上回るまでになったが、農業の構造改革は失敗し、食料供給の主体となるべき企業的農家の育成は妨げられ、農業は衰退した。農地の貸し手はいるが引き受け手である担い手がいないため農地が耕作放棄される中山間地域農業の荒廃は明日の日本農業全体の姿である。
農本主義者といわれた石黒は言う。「農は国の本なりということは、決して農業の利益のみを主張する思想ではない。所謂農本主義と世間からいわれて居る吾々の思想は、そういう利己的の考えではない。国の本なるが故に農業を貴しとするのである。国の本たらざる農業は一顧の価値もないのである。」石黒のいる国の本たる農業とは国民に食料を供給するという責務を果たす農業であり、食料供給に不可欠の貴重な農地資源を食いつぶす農業ではなかった。「何ゆえに農民は貧なりや」という問いが柳田の農業問題への取組みの基本にあった。しかし、農業が衰退するなかで農家・農村の豊かさが実現するとは夢にも思わなかったのではないか。解放された小作農が新たな地主となり宅地等への転用売却により大きな資産を取得するとともに、農地改革の結果生じた零細農業構造が米価引上げによって一層強固なものとなりその後の農業の発展を阻害するという事態の前で、今日柳田や石黒がいればどのようなメッセージを発するのだろうか。
WTOの成立と世界の農政
ウルグァイ・ラウンド農業合意は、国内支持、国境措置、輸出競争の3つの分野にわたり、1995年から2000年まで次のとおり保護水準を引き下げていくことを約束した。
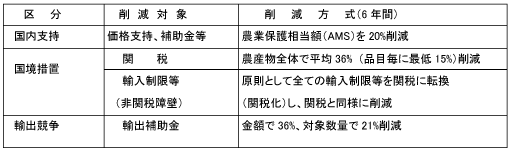
特に、輸入数量制限等関税以外の輸入障壁を関税に置き換える。関税化である。その方法は、過去の輸入量が消費量の5%を超えるときはその輸入量、それに満たないときは消費量の5%(ミニマム・アクセス)を、低税率の関税割当として設定し、それをこえる輸入量については内外価格差を関税として設定する。我が国の米については、関税化の特例措置を採る代償としてミニマム・アクセスは8%とされた。その後関税化したのでミニマム・アクセスは7.2%、関税率は500%相当となっている。
アメリカは農家に対する保証価格と市場価格との差を財政により補填(直接支払い等)することにより、農家所得を維持しながら国際競争力を確保している。EUは可変課徴金等により域内市場価格を国際価格より高く設定する一方、過剰生産分を輸出補助金によって処理していた。しかし、1992年に農政改革を行い穀物の域内支持価格を引き下げ、財政による農家への直接支払いで農家所得の減少を補った。現在の穀物支持価格は小麦シカゴ相場を下回る。EUはアメリカ産小麦に関税ゼロでも輸出補助金なしでも対抗できるのである。我が国も2000年度から中山間地域への直接支払いを導入し、価格政策から直接支払い政策への一歩を進めることとなったが、消費者負担型農政の基本的性格に変わりはない。EUがアメリカと同じ財政負担型農政に転換したにもかかわらず、日本のみ取り残されている。かつてのアメリカ対EU・日本という構図がアメリカ・EU対日本という構図になっている。
OECDが計測する農業保護額では日本はアメリカと同程度、EUの3分の1程度であるにもかかわらず、最も農業保護的な国であるというイメージが内外に定着した感があるのは、関税に依存した消費者負担型農政を続けているためである。
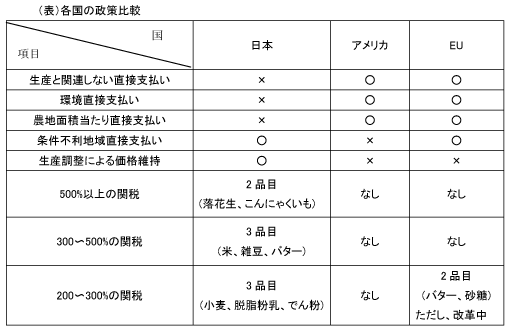
WTO農業枠組み合意(2004年7月)
今次交渉も各国の農業保護を削減し貿易の障害をいかにして取り除いていくのかという見地から交渉されている。本年7月、交渉のフレームワークが合意された。なお、具体的な関税削減率の数値等は今後の交渉に委ねられている。
直接支払いを導入し関税への依存度を低めているアメリカやEUと異なり、直接支払い導入に踏み切らない日本は米、麦、乳製品等の高関税を引き下げられない。枠組み合意では、一定以上の関税は認めないという上限関税率はその役割についてさらに評価されることとなり、事実上先送りされた。関税率の高さで品目をグループ化し高い関税品目には高い削減率を課すという階層方式が採用されたが、一定の重要品目については例外が認められることとなった。
問題は例外が認められる条件である。例外を要求すれば代償を求められる。それがガット・WTOの基本ルールである。今回の合意文書でも “実質的なアクセス改善は全ての品目で達成される”、“実質的なアクセス改善はそれぞれの品目に要求され、関税削減と(低税率の)関税割当によって行われる”、“そのような品目全てについて関税割当の拡大が要求され、その拡大は階層方式の全体的な目的を損なわないように関税削減方式からの乖離具合を考慮して約束される。”と書かれている。普通に読めば、例外を要求すれば通常要求される関税割当の拡大以上の拡大が要求されるということになろう。ウルグァイ・ラウンドで米の特例措置の代償としてミニマム・アクセスが加重されたのと同じだ。
関税か直接支払いか
農業を保護することとどのような手段で保護するかは別の問題である。関税はあくまで手段にすぎず、目的とすべきは農業の発展や国民への食料の安定供給であって関税の維持ではない。目的と手段を混同してはならない。消費者負担による関税と納税者負担による直接支払いは手段の違いである。消費者から負担を求める方が財政当局と折衝するより抵抗が少ないことが関税という手段を採ってきた理由である。しかし、納税者負担による直接支払いは、消費や貿易への歪みをなくし国民経済全体の厚生水準を高め諸外国との貿易摩擦を避けるとともに、受益の対象を真に政策支援が必要な農業や農業者に限定できるというメリットがある。
関税引下げによる価格低下に対しては直接支払いで対抗できる。しかし、内外価格差を残した中で関税割当数量が拡大されれば国内生産縮小という対応しかない。これは農業の生産性向上を阻み食料自給率の低下を招くことになった、生産を縮小しても価格を維持したいという高米価・生産調整政策の繰返しである。この選択は農産物貿易の問題にとどまらず、企業的農業を育成し強い農業を目指すのか、引き続き二兼農家主体の護送船団方式を採るのかという農政全体の選択に他ならない。対外政策と国内政策の間に齟齬があってはならない。関税引下げの特例を求めれば代償として関税割当の大幅な拡大が求められる。食料自給率の向上を考えるのであれば、関税引下げ、関税割当拡大のいずれかを求められる場合は迷わず関税引下げを選ぶべきだ。
真の農政改革を目指して
8月の食料・農業・農村政策審議会の『中間論点整理』は、WTO交渉で本格的な関税引下げが先送りになったので、麦作経営安定資金等畑作物についての不足払い(農家価格と市場価格との差の補てん)の一部を担い手農家に対する直接支払いに移行するものの、米、麦等の農産物関税引下げへの対応としての本格的直接支払いは見送るという内容となった。
麦作経営安定資金は国家貿易によるマークアップが財源であり、また、既存の不足払いを直接支払いにするのも、財務省一般会計の腹が痛むわけではない。一方、本格的直接支払いについては農林水産省が既得権の抵抗に遭い農業予算の大幅な組換えに成功しなければ一般会計に追加負担を要求される。農林水産省は先送りするつもりはなくても、こう考えた財務省の抵抗にあったのかもしれない。しかし、これでは市場価格は下がらず消費者負担型農政に変更はない。関税も下げられない。EUが自らの域内事情から先んじて農政改革を行い、これをもってWTO交渉で関税引下げ、輸出補助金撤廃など積極的な対応を行っているのと対照的だ。
また、米の相対収益性は麦等の農家保証価格の引下げによりますます有利化する。米の過剰圧力は高まり麦等の生産は減少し食料自給率はさらに低下する。食料自給率の向上を旨とする基本計画策定のための審議会(新基本法第15条)が自給率低下の政策を打ち出すとはなんとも皮肉な結果だ。何のための農政改革かという目的に立ち返るべきだろう。
和田は「日本の役所からも農業関係についてはその道の人から相当尊敬される学者―行政官であると同時に立派な学者が出る」よう東畑精一東大教授を所長に迎え1946年農業総合研究所(現農林水産政策研究所)を創設した。通産省が現経済産業研究所を設立したのに先立つこと40年である。しかし政治との関わりが強くなるにつれ、幹部もそのような人材の育成に興味を持たなくなったし(小倉が作った経済研修制度はほとんど廃止状態にある)、若手も経済学に習熟しても評価されない(能力主義が導入されても評価できる人もいない)のでは勉強しなくなる。かくして経済学を理解する人のない経済官庁が出来上がる。食料自給率の向上という目的には農業資源の米への集中を招いている米価の引下げ、本格的直接支払いの導入という根本的な対策が必要なのだ。しかし、それに踏み切れず、経済学の視点からその効果を考えることなく、とにかく何らかの直接支払いを打ち出さないと改革を打ち出した手前格好がつかないと考えたために大目的に反する政策提案になってしまったのだろう。
価格維持のための生産調整を廃止し、米価を需給均衡価格9.5千円程度まで下げ、所得を大きくマイナスにすれば副業農家は耕作を中止する。(畑作物についても全ての価格支持政策は廃止する。)さらに農地を農地として利用するための農業版特別土地保有税を導入し不作付け対応の機会費用を高めれば、農地は貸し出される。一方、一定規模以上の主業農家に耕作面積に応じた直接支払いを交付し、地代支払能力を補強してやれば、農地は主業農家に集まる。農地の集積による規模拡大・生産性の向上により農産物価格をさらに引き下げ、国際価格へ接近させることが可能となる。
このような農政改革を実施してこそ、米の生産調整廃止による米生産の拡大及び米と他作物の相対収益性の是正を通じた他作物の生産拡大による食料自給率の向上、国民・消費者への安価な食料の安定的供給、消費者価格低下による国民負担の軽減、安い原料農産物供給を受けられる食品産業の発展、担い手農家の所得向上、規模の大きい農家ほど農薬・化学肥料の投入を抑制することによる環境にやさしい農業の推進という新基本法の諸目的を達成できる。
農業を保護するかどうかが問題なのではない。関税による価格支持か直接支払いか、いずれの政策を採るかが問題なのだ。先日柳田の著書にはさまれた“農業経済の基本問題”という和田のメモ書きを見つけた。その中で和田は貧農救済のためでも米価を吊り上げるのではなく国債または税金により奨励金(直接支払い)を交付すべきであると書いている。70年の時空を超えて若き日の和田があるべき農政を語りかけてきたように感じた。
関税引下げという外圧が来るまで改革しないというのではなく、衰退の著しい我が国農業自体に内在する問題、特に構造改革が遅れている米問題に対処するため、主業農家に限定した直接支払いを導入するという改革を行わなければ、農業は内から崩壊する。「スピード感をもって農政改革を進める。」という大臣の意思表明はどこに行ったのだろうか。これまでどおりの農政を続け座して農業の衰亡を待つよりは、直接支払いによる構造改革に賭けてはどうだろうか。過去の失敗にも学ばず世界の流れからも取り残される者はいずれ滅ぶしかない。
和田や小倉のような人材は今日のぞむべくもない。しかし、彼らをもってしても農地改革から農政改革という夢はかなわなかった。農政を氏に至る病から救う者は誰なのだろうか。
2004年11月号 『食糧と安全』に掲載


