第2次安倍晋三政権の成立以来、政府による経済団体に対する賃上げ要請が恒例化している。要請の機能は大きく分けて2通りある。1つは日銀がインフレ実現を目指して金融緩和を続けているので、歩調を合わせて名目的な賃上げを求めるというもの。もう1つは雇用の非正規化や利潤の内部留保を通じて実質的な労働分配率が下がっているので、その向上を目指し実質賃上げを求めるものである。
ここでは、要請に意義があるとすれば第1の視点によるもので、第2の視点は根拠薄弱であることを論じたい。
◆◆◆
まず、第2の視点を確認するため、過去20年弱の労働生産性と賃金の関係を振り返り、賃金決定のあり方に実質的な変化が起こっていないことを論証する。
限界生産力(生産要素を1単位投入した際の生産の増加量)で賃金が決まるという標準的な経済理論に従えば、マクロの生産技術が、労働投入の生産への貢献が一定の値であるという「コブ・ダグラス型の生産関数」で表現され、労働市場と財市場が完全競争であれば、賃金は労働生産性に比例する。
労働生産性は労働者が1時間あたりに生み出す価値、時間あたり賃金は労働者が1時間あたりに受け取る給与である。貨幣価値は時間とともに変わるため、価格指数で実質化する必要がある。労働生産性には国内総生産(GDP)デフレーターを用いるのが一般的であるが、賃金は、ほかに消費者物価指数(CPI)で実質化する方法もある。
上記の理論が現実に当てはまるのかどうか、1994~2013年の実質賃金を実質労働生産性で割った値の推移を示した(図参照)。
(生産性に対する賃金の比率)
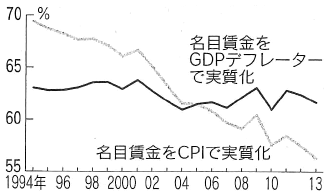
時間あたり賃金をCPIで実質化した場合、「賃金/生産性比率」は大幅に下落している。これは労働生産性が上昇しているにもかかわらず実質賃金が上がっていないことを意味し、経済理論の予測が外れていることを示す。しかしながら賃金をGDPデフレーターで実質化すると、この比率はほぼ安定しており、経済理論の予測が大まかに成立していることを示している。
このように実質化に用いる価格指数によって結果が大きく異なるのは、GDPデフレーターがGDPを構成する財を対象とする一方でCPIは消費財を対象としているからである。GDPには消費のほか、投資、政府消費、純輸出(輸出マイナス輸入)が入り、両者のバスケットの中身は大きく異なる。このうち「輸出マイナス輸入」の価格指数の動き方が、両者のズレを説明することが知られている。
日銀によると輸出物価指数(2010年=100)は1994年1月の136.2から2014年12月には116.6に低下した一方、輸入物価指数は76.0から129.4に上昇した。08年の金融危機後の急激な円高によって円ベースの輸入価格が急落したことを除いては、この20年ほどの日本では輸出価格は下がり輸入価格が上がるという交易条件の悪化が起こった。
輸出品価格の下落と輸入品の上昇によってGDPデフレーターには下降圧力がかかり、輸入品価格上昇によってCPIには上昇圧力がかかる。このため00年代の日本はGDPデフレーターでみると大幅なデフレ、CPIでみると小幅なデフレであった。両者のズレの原因としては、投資財や政府消費財を含むか含まないかという問題もあるが、主因は交易条件の悪化であると指摘されている。
実質賃金が実質労働生産性に比例するとの理論を検証する際に適切なのは、両者の名目値を同じ価格指数で実質化することである。したがってGDPデフレーターで実質化した両者の関係が安定しているということは、標準的な経済理論が日本経済を記述することにほぼ成功していると考えて差し支えないだろう。
◆◆◆
労働生産性が上がった時に賃金が上がるという関係が日本経済全体で観察されるのは、生産性が上がると企業は生産量を増やそうとするが、同時に労働投入も増やすため人手が足りなくなり、賃金が上がるというメカニズムが働くためである。また、労働生産性向上と賃金上昇の間に一定の比例的関係が生まれるのは、コブ・ダグラス型関数が想定する技術的関係が、日本経済全体ではおおまかに成立しているためである。
賃金を実質化するのにCPIではなくてGDPデフレーターを用いるのが適切なのは、食料やエネルギーなどの輸入品の価格が上がったからといって、国内企業の賃金支払い能力が上がるわけではないことからも明らかである。
もっとも、労働者の購買力を測るのはCPIであるため、名目賃金がCPI以上に下がって、労働者の生活水準が下がっているというのは事実である。ただし日本の労働者の購買力低下は、交易条件が悪化して日本人の購買力が下がったことの表れである。国内労働者の購買力低下は問題だが、大切なのは交易条件を改善することである。
昨今の原油価格の下落は交易条件の向上につながる朗報だが、さらなる交易条件の改善のためにはエネルギー政策、製造業の立地政策、通商政策など多岐にわたる政策的対応が求められることになろう。いずれにせよ、問題の所在を取り違えて労働市場にむやみに介入しようとすることは避けなければならない。
筆者のここでの主張は、主として一橋大学のマクロ経済学者が行ってきた主張の繰り返しである。齊藤誠教授は交易条件の悪化による富の国外流出を以前より指摘しており、深尾京司教授は交易条件の悪化が実質賃金に与える影響を数量的に分析している。
国外に目を転じても、米国や英国での労働生産性が上がっても実質賃金が上がらないとの指摘に、ハーバード大学のマーチン・フェルドシュタイン教授やロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)のジョン・ファンリーネン教授らが反論している。彼らもCPIとGDPデフレーターの差に注意を払うことが必要であるとしており、追加的にいくつかの点に注意を払えば、米英でも両者が比例することを見いだしている。
◆◆◆
実質労働生産性が高まれば実質賃金が上がるという安定的な関係を前提にすれば、政府の賃金決定への積極的介入が支持されうるのは、実質賃金を変えない範囲で、物価水準の上昇に見合った名目賃金上昇に対して働き掛けるということであろう。この時に参考にする物価水準は、CPIよりもむしろGDPデフレーターであろう。
一歩進めて、デフレ脱却のために、名目賃金を上昇させコスト増を通じて物価水準を上昇させるという考え方もあるかもしれない。この場合、外生的な賃金上昇がどれだけ価格に転嫁されるのか、ミクロデータを用いた着実な実証研究をもとに議論することが大切である。一橋大や東京大学では、小売店から集めたPOS(販売時点情報管理)データを使った価格決定に関するミクロ的な分析が進められている。賃金と関連する分析にも期待したい。
なお、賃上げ問題を、非正規問題・働き方改革といった構造問題と併せて一体的に議論すべきだとの意見もあるが、これらは実質労働生産性を引き上げようという議論であるといえる。
実質労働生産性と実質賃金の関係が安定的なわけだから、実質労働生産性が伸びれば、実質賃金は結果として伸びる。しかし、政府による賃上げの要請や春闘といった場面では、様々な関係者の利害が鋭く対立する多様な論点を俎上(そじょう)にのせて議論を停滞させるよりも、物価上昇に見合った賃上げをいかに実現するかという一点に集中したほうが、賃上げはスムーズに行われることになろう。
2015年3月6日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


