2008年9月以降の世界的な金融危機に対応するため、欧米各国は中央銀行のバランスシート(資産と負債)を急拡大させる非伝統的金融政策を相次いで導入した。その際、各中央銀行は望ましいインフレ率として「2%」に近い水準を強く意識して効果をあげた。一方、日銀はバランスシートの拡大に踏み込まず、日本は依然としてデフレ脱却のめどが立っていない。
将来のインフレ率に目標を設定するインフレ目標政策は1990年代以来多くの中央銀行が採用してきた。主要国では日銀、欧州中央銀行(ECB)、そして米国の中央銀行にあたる連邦準備制度はインフレ目標政策を公式には採用していない。しかし「目標」ではないものの、望ましいインフレ率について、ECBは「2%以下だが、2%に近い数字」、米連邦準備制度も「1.5%~2%」とほぼ一致した数字を挙げている。日銀は昨年12月に「中長期的な物価安定の理解の明確化」として「消費者物価指数(CPI)の前年比で2%以下のプラス領域にあり、委員の大勢は1%程度を中心と考えている」と示した。
◆◆◆
今回の世界金融危機を経て「インフレ目標政策の限界が見えた」との批判がある。金融危機の原因として、望ましいインフレ水準を掲げる欧米の中央銀行が、安定したCPI上昇率に安心して、金融市場のバブルを抑制できなかった、という論理である。
しかし、この議論は金融政策にあまりにも多くの目的を求めすぎである。伝統的な金融政策の唯一の手段は政策金利である。インフレ目標政策を標榜する中央銀行でも、目的とする変数はインフレ率と需給ギャップ(または失業率)の2つだ。「1つの政策手段で2つの目標」というだけでも、常に2つの目標の間にトレードオフが発生する。それに加えて金融システムの安定のためにも金利を使うと、どの目標も達成できない状況が発生しやすい。金融システム安定化には、他の政策手段も必要だ。
たとえば、金融監督当局がリスクの高まり(銀行信用の急拡大、株価や地価の急上昇)に応じて、銀行の資本規制、貸出担保率規制、特定産業への貸し出し集中の規制などができる権限をもつことである。さらに、金融システムに重大な影響をもつ金融機関が資本不足に陥ったときは、システム不安が起きないような形で、一時国有化し営業を続けながら清算手続きや身売りを進める強力な権限も与えられるべきである。今回の世界金融危機の主要な原因は、欧米の多くの国で金融監督当局が失敗したことにある。
◆◆◆
世界金融危機で欧米の景気は急速に悪化し、それまでのインフレの心配から、あっと言う間にデフレの心配へと変化した。英国の中央銀行であるイングランド銀行(BOE)の08年11月のインフレーションリポートは、2年先のインフレ率予想が1%と、目標中心値から1%ポイントも下回った。
そこでBOEは09年3月に量的緩和政策の導入を決め、国債などの資産を市場から購入し始めた。同年5月には量的緩和を拡大し、インフレリポートでは1250億ポンドの資産購入を条件にインフレ率予想が2%に近付き、8月には1750億ポンド、11月には2000億ポンドの資産購入を条件にインフレ率予想が2%となった。このように英国は量的緩和とインフレ予測を組み合わせることで、デフレ期待に陥らないような金融政策を行っている。量的緩和によってBOEのバランスシートは短期間に3倍に膨らんだ。
米国では「信用緩和」として、買い手がいなくなった証券市場で、連邦準備銀行が民間資産を直接購入するという異例の措置を行った。さらに証券大手ベア・スターンズや保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)の資産管理会社を設置してそこに融資した。こうした政策の結果、米連邦準備制度のバランスシートは危機発生前の2.5倍に達した。また、ECBもカバードボンド(一種の担保付き社債)の購入を進め、バランスシートが5割拡大した。しかし日銀は、今回の危機でバランスシートの拡大を全く行わなかった(グラフ参照)。
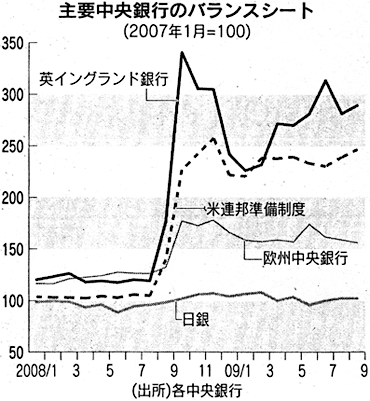
米連邦公開市場委員会(FOMC)のメンバーは半年に1回、将来のインフレ率の予想リポートを公表している。リーマン・ショック直前の08年7月には足元のインフレ率が3%を超えていたものの、2年後のインフレ率はほぼ1.5~2.0%に落ち着くと予想していた。ところがリーマン・ショック発生後、09年2月には、2年後のインフレ率予想の下限が0.2%まで落ち込み、なんらかの追加的な金融政策の必要性を示唆するにいたった。さらなるショックがあればデフレに陥りかねない状況であった。
ここでFOMCはそれまでの「2年先」の予想に加えて、リポートに「長期予想」の欄を設けた。これは「これ以上のショックが起きないという条件で、適切な金融政策のもとで収束する値」という条件付き予測で、1.5~2.0%という数字を公表した。この条件付き長期予測は、ほぼインフレ目標政策の目標範囲と解釈できるだろう。つまり、ここで米国も事実上のインフレ目標政策を採用するにいたった。そのきっかけは、デフレ懸念だったのである。この長期予想の欄はその後も継続している。
◆◆◆
日銀もFOMCと同様、金融政策決定会合参加者の予測をいわゆる「展望リポート」で年2回公表している。昨年10月時点では、2年先(11年度)のインフレ率予想は、もっとも楽観的な人でマイナス0.3%、悲観的な人ではマイナス1%で、デフレ脱却は無理だと考えていたことが分かる。米国のような「長期予測」も形成していない。インフレ率を正の値にすることをあきらめていたのだろうか。
その後、昨年12月には前述の「物価安定の理解の明確化」を発表して、少しデフレ退治にむけて動き出したようではある。今年1月の中間点検ではインフレ率予想もやや上昇した。しかし、まだ十分とはいえない。明確なインフレ目標政策の宣言は無理だと考えているにしても、せめて、米国のような「長期予測」を展望リポートに組み込むことが望ましいのではないか。
デフレから脱却できない日本については、さまざまな提案がされてきた。その多くは、ゼロ金利であっても金利以外の非伝統的な景気刺激手段があるという提案だ。しかし、そもそも平時の目標インフレ率の下限に「のりしろ」をとって1.5%以上の高めにしておけば、ゼロ金利に陥る可能性自体が減る。
今年2月、国際通貨基金(IMF)のチーフ・エコノミストであるブランシャール氏が、さらに「のりしろ」を大きくとって、たとえばインフレ目標の中心を4%に引き上げることは考えられないか、と問題提起し、大論争を巻き起こしている。4%なら、ちょっとやそっとではゼロ金利制約にひっかからないという考え方だ。しかし、多くの中央銀行関係者はこの提案に否定的である。今回のような金融危機は頻繁に起きるものではないし、4%のインフレ率はコストが高く、高インフレスパイラルに陥る可能性が高い、という理由からである。
しかし、ブランシャール氏の問題提起は単に極端だとして切り捨てるのではなく、今回の危機を経てどのような教訓を学んだのか、という視点で考えることが大切だ。ブランシャール論文の主要なテーマもそこにある。筆者の考えるひとつの重要な教訓は、インフレ目標政策が金融危機を経ても決して色あせることなく、むしろその重要性が確認できた、ということである。
2010年4月15日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


