不安仮説
以下の仮説(不安仮説)は、不安によって人間の行動が過剰にリスク回避的で不合理なものになるというものである。
ホモ・エコノミカスと呼ばれる合理的で利己的な人間を前提に、経済学の多くの理論は組み立てられてきた。ところが、現実の人間の意思決定には、人間の合理性を前提とした典型的な理論である期待効用理論と乖離した不合理なパターンがあることが明らかになってきた。更に、最近の心理学では、このような不合理な人間の行動が人間の感情によって引き起こされているという仮説が唱えられるようになった(注3)。
期待効用理論が示す合理的なリスク評価から主観的なリスク評価が乖離して、人々が過剰にリスク回避的になるプロセスは2つある。第1は過大評価(overestimation)であり、これは、発生する確率が主観的に認識されていないネガティブな出来事についてその確率を高く見積もることである。たとえば、航空機事故で死亡する確率が客観的に0.0009%であるとした場合に、ある人がその確率を0.09%だと思った場合である。第2はカーネマンとトゥヴェルスキーがプロスペクト理論によって明らかにした過重視(overweighting)である(注4)。これは既に発生する確率がわかっているものについて、低い確率を主観的に高く見積もる一方で、中程度の確率について主観的に低く見積もる傾向であり、この傾向をプロスペクト理論では確率加重関数で表す(一例として図1)。たとえば、1000発の銃弾を込めることができる特別な銃に、1000発の銃弾を込めて、ある人に、自分の太腿に向けて1度だけその銃の引き金を引くこと(つまり、確実に1発の銃弾が太腿に向けて発射されること)を求めて、それを避けるためにいくら支払うつもりがあるかと聞いて、その人が1億円と答えたとしよう。次に、一種のロシアンルーレットとして、その銃に、1発の銃弾と10発の銃弾と100発の銃弾を込めて、自分の太腿に向けて1度だけその銃の引き金を引くことを求めるという3つの事例を設定した場合、期待効用理論によれば、銃弾が1発入ったロシアンルーレットを避けるための支払額は10万円(=1億円×1/1000)、銃弾が10発の場合には100万円(=1億円×10/1000)、銃弾が100発の場合には1000万円(=1億円×100/1000)となるが、確率加重関数によればそうならない。低い確率が高く見積もられるので、銃弾が1発の場合に84万円、10発の場合には119万円、100発の場合には138万円となることが起き得る(注5)。
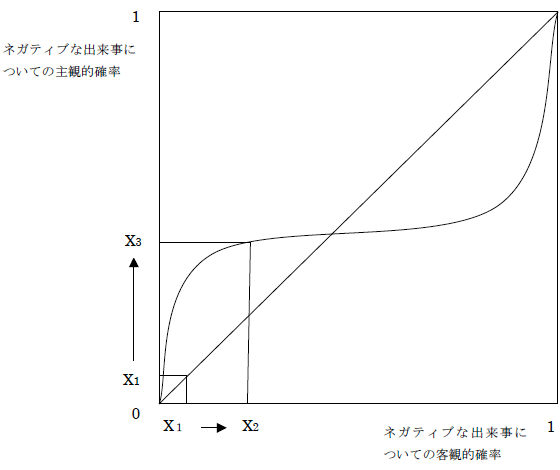
心理学の研究によれば、過大評価と過重視はネガティブな感情、特に不安感と密接な関係があることが明らかになってきた。ここにおける不安感には、2つの意味があり、1つ目は、ある時点においてその人がたまたま抱いている感情としての不安感(incidental emotions)であり、2つ目は、何らかの出来事や情報に遭遇したことによって抱かれた不安感(anticipatory emotions)である(注6)。incidental emotionsとしての不安感について、不安感が強い人はそうでない人に比べて、望ましくないことが起きる確率を高く見積もる、つまり過大評価されることが既存研究で示されている(注7)。anticipatory emotionsについては、電気ショックを避けるためにどれだけのお金を払うかという実験によって、不安感を惹起させるような出来事についての方がそうでない出来事に比べて、小さい確率を大きく評価する傾向が強くなること(過重視されること)を示唆した研究がある(注8)。
以上の研究を踏まえると、何らかのネガティブな出来事がAという人物にとって生じるリスクが低確率ながらも存在し、そのことがAの不安感を惹起させるようなものであれば、また、その時点においてAが既に何らかの不安感を抱いていれば、その出来事が起こる確率がX1%である場合において、Aは、そのネガティブな出来事が起こる確率がX2%であると過大評価し、更に、過大評価した確率を過重視してX3%であると主観的に見積もることになる(図1)。この場合、そのネガティブな出来事が起こる確率が本当はX1%であるにも関わらず、主観的にはX3%と過大に受け止められることになるため、Aは、期待効用理論において想定されるような合理的なアクターが行う以上に、リスク回避的な行動を取ることになる。
不安仮説で説明できる現象
不安仮説によって説明できる現象は多い。たとえば、中国産のギョウザで食中毒が発生した結果として日本の中国食品の輸入が激減したことは記憶に新しいが、専門家が指摘するとおり、中国産の食品が一般的に危険ということはなく、これは、不安仮説のようなアプローチをしないと説明しにくい。原子力発電の安全性に対する専門家の見方と一般的な見方の乖離、新型インフルエンザに対する反応なども同様である。このように、安全と安心の乖離が見られる現象、つまり、専門家が安全だ、あるいはリスクは極めて低いと指摘しているにも関わらず、人々は安心できずに、過剰なリスク回避を行う現象は、このような不安仮説による説明が可能である。
実は、不況も同じように説明することができる。人々が不安に駆られて、自分が失業する確率や失業した場合に生じる不都合を過大に評価すれば、リスク回避行動として節約に走り消費を減らす。これは需要の減少を引き起こし景気を悪化させる。同様のことは、企業の投資縮小や金融機関の貸し渋りについても起きている可能性がある。
このように、不安という人々の感情によって生じる社会の損失は極めて大きい。
不安に起因する問題への認知療法的アプローチ
不安に起因する問題、たとえば、現在世界が直面している不況にどう対処したらいいだろうか。経済学者の多くは、福祉や医療などの公的制度の見直しによって不安を解消すべきだと考えているようである。
しかし、経済学者には知られていない、あるいはタブー視されているようだが、制度をいじらなくても人々の感情を変えることは可能である。20世紀後半以降の臨床心理学や精神医学の世界において、特に、認知療法と呼ばれる治療法が開発されたことによって、薬を使わなくても、ネガティブな感情をポジティブなものへと変えることが可能になってきた(なお、認知療法は認知症とは無関係である)。
認知療法の発想は極めてシンプルで常識的である。人間のネガティブな感情はネガティブな思考を信じることによって引き起こされるというものであり、たとえば、「私は失業する」という思考を信じる人は不安感を抱くようになる。「私の人生は終わった」という思考を信じる人は絶望感を抱くようになる。ネガティブな感情を引き起こす思考は、そのほとんどが現実離れしたものであり、認知療法においては、その思考に根拠があるのかどうか、その思考に反する証拠がないかを確かめることによって、その思考を信じる程度を減らしていき、それによって不安などのネガティブな感情を低減させていく。気付かれた方もいるかもしれないが、感情の背後にある思考は、経済学に登場する「期待」や「予想」に極めて近いものである。たとえば、「景気は良くならない」という思考を多くの人々が信じれば、彼らは憂うつと不安を感じることになるが、この思考は、経済学における「期待」や「予想」として、経済を不況に突き落とす。このように、経済学と認知療法を結びつけることは意外と簡単である。
経済対策としてのラジオ体操型認知療法
仮に、認知療法を誰もが日常的に行えるようなラジオ体操のようなものにアレンジすることができて、心の病気でない人々が日常的に行うようにすることができれば、うつ病などの心の病気の予防や自殺の防止につながるとともに、人々が抱く将来見通しが楽観的なものとなって、景気の回復につながるかもしれない。つまり、複数の社会問題を同時に解決できる可能性がある。
残念ながら、私の知る限り、アカデミズムの世界では、ラジオ体操型認知療法と呼べるような、心の病気でない人が手軽に行えるようなメソッドの開発に向けた取り組みは不十分である。ただ、アカデミズムから離れれば、これは使えそうだと思えるものはいくつかある。たとえば、バイロン・ケイティのワーク(The Work of Byron Katie)というものがある(注9)。このメソッドは、うつ病患者だったアメリカ人女性が作ったもので(この人は心理学者でも精神科医でもない)、ネガティブな感情を引き起こす思考に対して、4つの質問と置き換え(turnaround)という作業をすることによって、ネガティブな感情を和らげていく。私自身も日常生活の中でこのワークを行っているが、確かに心が軽くなるのがわかる。このように、アカデミズムの制約から離れて、いろいろなところに目を向ければ、ラジオ体操型認知療法としての役割を果たせそうなものは既に存在している。
終わりに
大恐慌の最中の1933年にアメリカ大統領に就任したフランクリン・ルーズベルトは、就任演説において、「我々が恐れるべき唯一のものは恐怖そのものである」と述べた。残念ながら、ルーズベルトの時代には、恐怖や不安を低下させる効果的な手法は開発されておらず、大恐慌は第二次世界大戦という悲劇によって解決されることになった。大恐慌当時と比べれば、恐怖や不安を低下させる手法は格段に進歩したが、そうした手法は経済学者や政策決定者からはタブー視されているようであり、心の病気の治療法という枠を超えて有効活用されそうな雰囲気はない。しかし、大恐慌の轍を二度と踏まないようにするためには、人間の心や感情をタブー視するのではなく、経済学や社会政策の最後のフロンティアにする必要がある。


