農業が衰退して農協は発展した
農業は高い関税で競争力のあるアメリカやオーストラリアの農業から保護されてきた。それにもかかわらず農業、特に米農業が衰退するということは、その原因がアメリカやオーストラリアにあるのではないことを示している。その原因は日本の国内にある。というより“いる”と言った方が適切かもしれない。
日本の農業は政治に翻弄されてきた。農業がその潜在能力をいかんなく発揮して発展することを、政策が妨げてきたのである。
農協は、農業資材を安く購入するために農家が作った組織のはずなのに、独占禁止法の適用を受けないという特権を利用して、アメリカの倍もする肥料、農薬、農業機械、飼料などの資材を農家に販売してきた。農業生産に必要な資材が高くなれば、コストが高くなるので、農産物価格も高くなる。農協が、日本農業の高コスト体質を作り上げてきた。
国際競争力がなくなるのは、当然だろう。国際価格よりも高い農産物価格を維持するためには、海外からの輸入農産物に高い関税をかける必要がある。農産物価格、つまり食料品の価格が上がって、困るのは、消費者だが、農業界の人たちは、誰もそんな心配はしない。
こうして高い関税で、国内の農業資材や農産物の価格を高くすれば、これらを販売する農協は、それに比例して多くの販売手数料収入を得ることができる。逆に、関税がなくなり、価格が下がれば、販売手数料収入は減少し、農協経営を圧迫する。
農業界は、米を最も保護してきた。しかし、次の図が示すように、日本農業の中で最も弱体化したのは、米である。米は50年前までは農業生産額の半分を占めていたのに、今では、畜産にも野菜にも抜かれ、2割のシェアを維持できるかどうかの農業となってしまった。
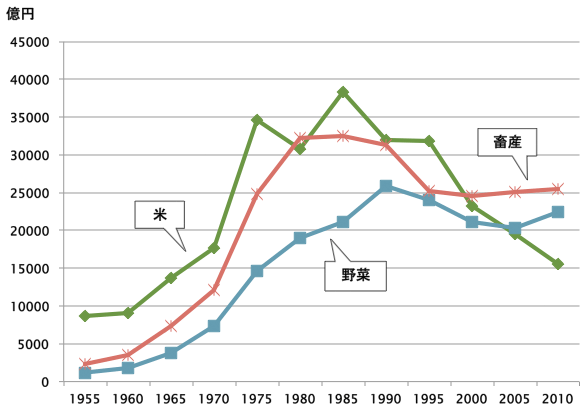
所得とは、価格に生産量をかけた売上額から、コストを引いたものである。売上額を増やすか、コストを下げれば、所得は増える。政府は1961年に“農業基本法”を制定し、農業の規模拡大によってコストダウンを図り、農業所得を増加させて、農業と工業の所得格差の是正を図ろうとした。つまり、農業の構造改革による生産性向上を目指したのだった。
しかし、農業基本法の考え方とは逆に、実際の農政は、農家所得の向上のため、米の価格を上げた。農地面積が一定で規模を拡大することは、農家戸数を減少させるということである。農家人口を減らして規模拡大・構造改革を行うというのは、政治的に人気のない政策である。なにより、農民票が減ってしまう。
組合員の圧倒的多数である米農家の戸数を維持したい農協も、農業基本法の構造改革に反対した。農協は、「米価は農民の春闘(労賃引き上げ)だ」と叫び、生産者米価引き上げの大政治運動を展開した。米価が上がれば農協の販売手数料収入も増加する。また、農林中金は、政府から農家に代わって代理受給する米代金も増えるので、これを農家に渡す前に、コール市場で運用して、利益を得た。
政治は、農協が組織する農民票に突き上げられた。農政は農家所得の向上のため、規模拡大ではなく米価を上げた。水田は票田となった。
しかし、需給を考えることなく、米価を上げたために、生産は増え、消費は減少した。この結果、1970年頃から深刻な米の過剰を招くことになり、とうとう減反政策が導入された。
生産者米価引き上げによって、本来ならば退出するはずのコストの高い零細農家も、小売業者から高い米を買うよりもまだ自分で作った方が安いので、農業を継続してしまった。零細農家が農地を出してこないので、農業で生計を立てている農家らしい農家に農地は集積せず、規模拡大は進まなかった。主たる収入が農業である主業農家の販売シェアは、酪農で95%、野菜や畑作物では82%にもなるのに、米だけ38%と極端に低い。
米価引き上げが、兼業農家の滞留、米消費の減退、米過剰による減反政策の実施などをもたらし、米農業を虫食んでいった。農家の7割が米を作っているのに、2割の生産しかしていない。いかに米が非効率な産業となってしまったかが分かるだろう。これこそが日本農業の最大の問題である。
図2は、さまざまな農業の中で、米だけ農業所得の割合が著しく低く、農外所得(兼業収入)と年金の割合が異常に高いことを示している。酪農の場合、農家所得のほとんどは農業所得である。つまり、酪農家はほんど兼業を行っていない専業農家である。これに対して、米を作っているのは、サラリーマン(兼業農家)や年金生活者である。米の販売農家のなかで主業農家の戸数は10%にも満たない。
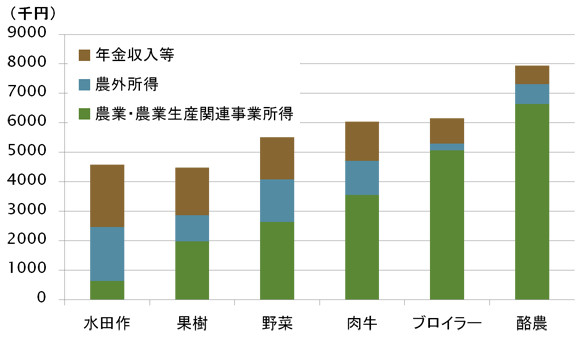
コストの高い非効率な米の兼業農家や高齢農家を滞留させ、米農業を衰退させたことが、さらなる農協の発展につながった。零細な米の兼業農家の農業所得は、極めて低い。しかし、その農外所得(兼業収入)は他の農家と比較にならないほど高い。しかも、米は農家戸数の7割を占め、他の農業に比べると、戸数も圧倒的に多い。したがって、全農家では、米の兼業農家の所得が、支配的な数値となってしまう。
さらに、兼業農家や高齢農家は農業から足を洗おうとしている人たちなので、農地を宅地に転用したいので高く売ってくれと言われると、喜んで売ってしまう。これは、銀行業務を行える農協経営には好都合だった。兼業収入や年金収入だけでなく、農地を転用して得た年間数兆円に及ぶ利益も、JA農協バンクに預金してくれた。
こうして、農協バンクの貯金残高は約90兆円まで拡大し、我が国第二を争うメガバンクとなっている。しかし、農業は衰退しているので、そのうち1~2%しか農業には融資されない。農家でなくても、地域の人をだれにもなれる准組合員に勧誘することで、預金の3割を住宅ローンなどとして貸し出した。残りの7割は農林中金がウォールストリートで運用している。
銀行業務以外にも、農協保険事業の総資産は47.6兆円で、生命保険最大手の日本生命の51兆円と肩を並べる。農産物や生活物資の売り上げでも中堅の総合商社に匹敵する。米農業を弱体化し、脱農化することで、農協は発展した。
農政改革を阻む者
EUは加盟国が27カ国にものぼり、合意形成は相当困難であると思われるのにもかかわらず、なぜEUでは農政改革が進み、日本では進まないのだろうか。
それはEUになくて日本にあるものがあるからである。JA農協である。
農協の政治的・経済的利益が、高い価格維持とリンクしている。このように価格に固執する圧力団体は、EUにもアメリカにも存在しない。どの国にも、農業のために政治活動を行う団体はあるが、その団体が経済活動も行っているのは、日本のJA農協をおいて、他にない。
日本の圧力団体として、農協と並び評されるのは医師会である。しかし、医師会は医者の集まりであって、それ自体が事業を行っているわけではない。医師会が守ろうとしているのは医者の利益である。ところが、農協はそれ自体多くの事業を行っている企業体である。農協が守ろうとしているのは、組合員である農家の利益というより、農協自体の組織の利益であることが多い。
農協発展の基礎が、高米価なので、関税がなくなり、減反という高価格カルテルが存続できなくなることは、農協の存立基盤を奪いかねない悪夢である。だから、農協は、1000万人もの署名を集め、一大TPP反対運動を展開したのだ。
協同組合らしからぬピラミッド型組織
JAグループの特徴は、上下関係によって、階層的に秩序づけられた、全国組織、都道府県組織、単協という序列のピラミッド型の組織となっていることである。
政府は、戦時中の国策協力機関として、全農家を加入させ、農産物販売、貯金の受け入れなど幅広い事業を行なった“農業会”という統制団体を、1948年に衣替えさせ、農協とした。
食糧難の時代、農家は高い値段がつくヤミ市場に、米を流してしまう。そうなると、貧しい人にも米が届くように配給制度を運用している政府に米が集まらなくなる。このため、政府は農業会を農協に衣替えし、この組織を活用して、農家から米を集荷させ、政府へ供出させようとしたのである。こうして、農協は、行政の下請け機関となるとともに、行政と同じく全国、都道府県、市町村の3段階で構成される、上意下達の組織となった。
協同組合は、本来資本主義からのセイフティネットとして、弱者が自己防衛的に作った組織である。農家は弱者であったかもしれないが、国家統制団体を引き継いだ農協は、設立の時点で既に弱者ではなく、農産物の集荷、肥料など資材販売、農業金融など多方面で、独占的な地位を持っていた。
本来協同組合は、組合員が自主的に作った組織である。消費者が生協を作り、生協は必要があれば、連合会組織を作る。ボトム・アップの組織が、協同組合である。生協にも連合会はあるが、上位、下位の関係はない。対等の関係である。
しかし、農協は前身が統制団体であるため、上意下達、トップ・ダウンの組織となった。全国連合会から、都道府県連合会を通じて、地域農協へと、指揮・命令が下る、ピラミッド型の組織になったのである。
しかも、戦後のある事情によって、これはさらに強化された。戦後農協を作って間もなく、農協が破たんする事態が相次いだ。これはインフレを収束しようとしたドッジ・プランによって農産物価格が低迷し、戦後乱立した小規模の農協がこれを処理できなかったことに加え、農協の前身である戦前の統制団体から、多くの不良資産を引き継いでいたからである。
農協の経営破たん問題をきっかけとして、今後再び赤字を出さないようにするという名目で、JAグループは、単協―県連―全国連の農協系統を、全て利用することを促進することとなった。農業関連事業である“経済事業”について説明すると、単協や県連が、全農を通さないで、独自に、肥料や農薬を買ったり、農産物を販売したりすることを禁じたのである。この方式は「整促事業方式」(「整促」とは「整備促進」の略である)と呼ばれ、今日でも農協系統の基本原則として扱われている。
農協には、“系統”農協とか農協“系統”という耳慣れない言葉がある。全国、都道府県、市町村の3段階が、まとまって統一ある組織の流れになっていることを意味している。これに対して、“系統”生協という言葉はない。下(現場)からの運動という協同組合の性格から、このようなヒエラルキー的な関係がないのは、当然だろう。
協同組合の原則は、利用者である組合員が組合をコントロールするというものだった。この組合とは、単協のことである。しかし、単協は組合員ではなく、上位の農協連合会によってコントロールされている。農協職員の給料も、末端から、都道府県連合会、全国連合会に行くほど、高くなる。その上、末端の農協の職員は、上位の団体から降ってくるノルマを、一生懸命になってこなしている。
地主制と農協制
地主制に代わり、戦後の農業・農村を支配してきたのは、農協制である。
農協は独占的な市場支配力によって、本来主人である組合員に、高い資材価格を強要した。零細な兼業農家も、農協の販売努力のおかげで、各戸ごとに年に1週間も使わない田植え機などを備えている。しかし、年間ほとんど稼働させない農業機械を、農家が一軒ずつ持つ必要はない。機械を共同利用すればコストは安くなり、無駄は省けるが、農協組織の利益には反する。これは、小規模で力のない農家が、多数団結して農協を作り、農業資材を安く購入するという、本来の農協の設立目的とは逆の結果となった。
主業農家がいくら品質の良いものを作っても、他の農家の農産物と一緒に販売され、同じ金額しか受け取れない。これに、主業農家は不満を持つようになり、次第に農協から離れるようになった。農協を通さないで、農業資材を購入したり、産直活動などで農産物を販売したりするようになったのである。
しかし、農協を通さないで出荷したり資材を購入したりすれば、農協に手数料が落ちない。また、これらの農家が農薬や化学肥料の投入を抑える有機農業に取り組もうとすれば、農協からのこれらの資材の購入額が少なくなるので、ますます農協に手数料が落ちなくなる。
このような農家は、農協からすれば、好ましくない異端者である。農協はさまざまな手段を使って、かれらに圧力をかけてきた。農産物の販売や資材・サービスの提供から融資業務まで、ありとあらゆる業務を行える農協は、圧力をかける手段に事欠かない。総合農協であるJAは、その総合性を、組合員に対して発揮した。農協の意に反した農家が、小学校のPTAの会合でいじめられたりするなど、ムラ社会の機能を使った締め付けも行われた。ムラ八分になることを恐れて、不利でも農協を使うという農家も、少なくない。今の農協は、利用者のための組織という協同組合原則に反するどころか、利用者を圧迫する組織となっている。
アベノミクスの農協改革
2014年とうとう、河野一郎も小泉純一郎も果たせなかった、戦後政治における最大の圧力団体である農協の改革が、政治のアジェンダに載った。
2014年5月政府規制改革会議がまとめた農協改革案は、文書化されただけではなく、その内容も、驚くほど、大胆かつ画期的なものだった。
第1に、農協の政治活動の中心だった全中(全国農業協同組合中央会)に関する規定を農協法から削除する。全中は系統農協などから80億円、都道府県の中央会が徴収するものをいれると300億円超の賦課金を、徴収してきた。農協法の後ろ盾がなくなれば、全中などは義務的に賦課金を徴収して政治活動を行うことはできなくなる。
第2に、全農やホクレンなどの株式会社化である。これは、協同組合ではなくすということである。日本の農業には、農協によって作られた高コスト体質がある。肥料・農薬、農業機械の価格は米国の2倍である。全農を中心とした農協は、肥料で8割、農薬、農業機械で6割のシェアをもつ巨大な企業体である。このように大きな企業体であるのに、協同組合という理由で、全農やホクレンには独占禁止法が適用されてこなかったし、一般の法人が25.5%なのに19%という安い法人税、固定資産税の免除など、さまざまな優遇措置が認められてきた。
これは、政府と与党との検討過程で、農協の意向を強く反映したものに変更された。全中は新たな制度に移行するが、「農協系統組織での検討を踏まえ」るのだから、農協に都合の悪い組織変更にはなりえない。全農の株式会社化も、単なる選択肢の1つとなったうえ、「独占禁止法が適用される場合の問題点を精査して問題がなければ」という条件も付けられ、株式会社化を促すとされた。判断するのは、農協となった。そうであれば、やらないと言っているのと同じである。全中は勝利宣言した。
JAから、民間組織である農協に政府が関与するのはおかしいという反論が、出されている。しかし、銀行は他の業務の兼業は禁止されているし、生命保険会社は損害保険業務をできない。農産物の販売だけでなく、生活物資の販売も、銀行、生命保険、損害保険の業務も、全ての業務が可能な法人は、日本国内で農協しかない。
この特別の権能を認めている農協法は、戦後の食糧難時代に米を政府に集荷するために、農林省がGHQと交渉して作った法律であって、農協が作ったものではない。GHQが農協に金融事業を認めると独占力が高まると反対したのに、農林省は、農家に米代金を払うために金融業務が必要と主張して、認めさせた。今の時代の農協法のあり方について、政府や国会が議論するのは当然である。
しかし、安倍首相は2014年6月、「中央会は再出発し農協法に基づく現行の中央会制度は存続しない。改革が単なる看板の掛け替えに終わることは決してない」と発言した。さらに、佐賀県知事選で農協がバックアップした候補に自民党候補が敗北した直後の、今年1月16日にも、「地域の農協を主役として、農業を成長産業に変えていくために、全力投球できるようにしていきたい。その中において、中央会(農業協同組合中央会)には脇役に徹していただきたい」と発言し、強気の姿勢を崩さなかった。
安倍総理は、全中の規定を農協法から削除すると主張してきた。これに対して、全中は、自己改革案を公表して、他の権限は譲っても、監査が重要なので、農協法に規定すべきだ、したがって、全中の規定を農協法に位置付けるべきだと主張した。しかし、図らずも、末端の農協を支配し、ピラミッド型の“トップ・ダウン”の農協系統組織を維持するために、全中監査が中央の連合会が地域の農協をコントロールする重要な手段として機能していることを、自ら認めることになった。そして、これが今回の改革の大きな争点となった。
ボトム・アップ組織の生協には、全国連合会による強制監査などない。また、農協は、株式会社の場合の公認会計士又は監査法人による外部監査は、投資家保護のためであり、組合員を抱える農協では十分ではないというが、生協の外部監査も、公認会計士又は監査法人によるものである。
法律的には、地域農協は全農を通じなくても、農業資材を購入できるし、農産物を販売できる。JA越前たけふが、全農を通じないで、肥料を購入したら、3割も安くなったという。JA越前たけふは、全農を通じて売ると、品質の良い米も悪い米も同じ金額しか受け取れないとして、独自で販売している。これらは、以前生産者が行ってきた対応である。
かつては、農協を通じないで、資材を購入したり、農産物を販売したりした生産者が、農協から圧力を受けた。しかし、農協から自立してきた主業農家は、資材の購入でも生産物の販売でも、農協系統、商人系統、あるいは輸入・輸出など、有利なところを通じて、購入、販売をしようとしている。地域農協は、生産者に有利な条件を提示できない農協系統については、これを通じては、買わない、あるいは販売しない、という対応をせざるをえなくなる。生産者の自立が地域農協の自立を促しているのである。
しかし、上位のJA組織から、相当な締め付けを受けたと、JA越前たけふの組合長は述べている。地域の農協が、かつての生産者と同様の取り組みをしようとして、全国連合会から締め付けを受けているのである。JA越前たけふを視察した、地域農協の人たちは、「私達には、とてもこんなことはできません」という。強制監査を受ける地域農協は、JAグループ内で、締め付けられ、孤立するのが、怖いのだろう。
結局、地域農協は、高くても、全農から資材を買うしかない。農家の生産コストは高くなる。農産物価格が高くならなければ、農家の経営は圧迫される。農産物価格を高くすれば、消費者は高い食料品価格を払うことになる。国際価格よりも高いので、関税が必要になる。したがって、JA農協は、TPP交渉に反対するという構図だ。
JA全中の義務監査をなくし、全農やホクレンなど連合会を株式会社化すれば、コストが低下するので、農家の所得は向上する。価格が安くなれば、消費者は利益を受ける。農協改革は、農家だけではなく、国民にとっても必要なのである。
決着した農協改革
安倍総理の意向を背景に、自民党農林幹部と全中会長との間で協議が行われた結果、全中に関する規定を農協法から削除し、全中を経団連と同様の一般社団法人とする、地域農協は全中監査と監査法人の監査を選択できるようにする、都道府県の中央会は引き続き農協法で規定する、株式会社化は全農の選択とする、准組合員の事業規制については見送るという内容で、決着した。
全中監査を強制監査ではなくしたことで、全国団体の統制が弱まることは、期待される。どれだけJA越前たけふのような農協が現れるかは分からないが、以前よりも、地域農協の自由度は増すだろう。
しかし、全中の政治力は、依然として排除されない。全中は一般社団法人に移行するものの、農協法の付則で、JAグループの代表、総合調整機能を担うと位置づけることとした。また、都道府県の中央会は、そのままである。全中自体は、強制的に賦課金を徴収する法律上の権限はなくなったが、都道府県の中央会は、依然として強制的に賦課金を徴収できる。都道府県の中央会は全中の会員なので、都道府県の中央会が集めた賦課金は従来通り、全中に流れて行く。
全農等の株式会社化は、全農等の判断に任されることとなった。協同組合であり続けるメリットのほうが大きいので、全農等があえて株式会社化を選ぶとは思えない。
准組合員の事業規制は、見せ球だったように思われる。地域農協や都道府県の組合からすれば、准組合員がいなくなれば、融資先に困ってしまう。准組合員の事業規制を提案したとたん、かれらにとって、准組合員が維持できるのであれば、全中監査などどうでもよいという判断になったのだろう。
しかし、准組合員の方が多い“農業”協同組合というのは異常である。本来なら、農業協同組合法と地域協同組合法の2法を制定すべきだ。地域協同組合は、これまでJAが行ってきた信用・共済事業や地域住民への生活資材供給を行う。地域協同組合となれば、今のJA農協の正組合員と准組合員の区別はなくなる。准組合員も正組合員になるのである。JA農業部門は、解散するか、新たに作られる農協に移管する。農協は、必要があれば、主業農家が自主的に設立するだろう。それが本来の協同組合である。
海外の農協は、組合員の利用度に応じて組合員に発言権が与えられるという組織に転換しつつある。今のJAでは、主業農家も零細な兼業・高齢農家も、同じく一票の決定権を持つため、少数の主業農家ではなく、農業をやっているとはいえない多数の兼業・高齢農家の意見が、農協の意思決定に反映されてしまう。JAが主業農家の規模を拡大するという農業の構造改革に反対してきたのは、このためである。この一人一票制の改革やJAの地域協同組合化など、本質的な部分はまだ提案もされていない。これで、農協改革を終わらせてはならない。
※本稿は執筆者個人の責任で発表するものであり、執筆者所属機関あるいは経済産業研究所としての見解を示すものではありません。


