震災と食料危機
東日本大震災は、食料の重要性を改めてわれわれに教えてくれた。物流が途絶している被災地では、食料品自体が手に入らない状態となった。被災地から遠く離れた東京でも、一部の消費者は食料を買い占めた。
他の物資と異なり、食料は、人間の生命・身体の維持に不可欠なものなので、わずかの不足でも、人々はパニックになる。平成の米騒動の際は、75年前の大正の米騒動の時より食生活に占める米の比重は大幅に低下しており、また、パン等他の食料品は潤沢にあったにもかかわらず、米が足りないというだけで、社会問題化した。
日本で生じる食料危機とは、お金があっても、物流が途絶して食料が手に入らないという事態である。今回これは震災で生じたし、最も重大なケースは、世界全体では食料生産能力が十分あったとしても、日本周辺で軍事的な紛争が生じてシーレーンが破壊され、海外から食料を積んだ船が日本に寄港しようとしても近づけないという事態である。これに対処するためには、一定量の備蓄と国内の食料生産能力を確保しておかなければならない。
世界全体では食料生産能力が十分あるはずだから、食料危機を論じる必要がないという主張も誤りである。世界で食料が潤沢にあっても、輸送の途絶で入手できない場合があるのである。
日本人にとって「水と安全はタダだ」という言葉がある。今回の震災や原子力発電所の事故に対しては、その道の「専門家」と言われる人たちから「想定外」という言葉が頻繁に発せられた。しかし、日本が戦争に巻き込まれることが可能性としては少なく、想定外だからといって、防衛力を持つ必要がないという人は少ないだろう。発生の可能性としては低くても、生じたときには国民の生命そのものに危害が及ぶほど被害が重大なものであれば、それを「想定外」としてはならないのである。食料も同じである。日本のような食料輸入国で軍事的な危機が生じているときには、食料の輸入も行えないので、必ず食料危機も発生する。
誰のための食料安全保障か?
ところで、食料安全保障とは、誰のための主張なのだろうか。1918年、米価高騰のなか米移送に反対して暴動を起こしたのは、魚津の主婦であって農家ではなかった。終戦後の食糧難の際、食料の買出しのため着物がひとつずつ剥がれるようになくなる「タケノコ生活」を送ったのは、都市生活者であって農家ではなかった。近くは1993年の平成の米騒動の際、スーパーや小売店に殺到したのは主婦であって農家ではなかった。
それなのに、農家団体である農協の強い要求により、2000年に今後10年で40%の食料自給率を45%に引き上げる計画が閣議決定されている。消費者団体よりも農協のほうが、食料自給率の向上、食料安全保障の主張に熱心である。農協の主張の裏には、農業保護の維持・拡大がある。
農協をはじめとする農業界は、食料自給率向上を唱えながら、実際には自給率を低下しかねない政策を採り続けている。農業界の利益を反映して、政府は、WTOドーハ・ラウンド交渉では、高関税の大幅な削減を回避する代償として、低い関税率で輸入される関税割当て数量(ミニマム・アクセス)をさらに拡大してもかまわないという対処方針を採っている。これは食料自給率を確実に低下させる。WTO交渉での対処方針は、食料自給率向上の閣議決定に反している。農協が食料自給率を犠牲にしてまでも守りたいのは、高い関税に守られた国内の高い農産物価格である。農業を保護するためには、消費者に負担や犠牲を強いてもかまわないとする立場に他ならない。
我が国にとって食料安全保障とは、海外から食料が来なくなったときに、どれだけ自国の農業資源を活用して国民に必要な食料を供給できるかという問題である。このとき必要な農業資源、特に農地が確保されていなければ飢餓が生じる。
戦後、人口わずか7000万人で農地が500万ヘクタール以上あっても飢餓が生じた。農地は1961年に609万ヘクタールに拡大し、その後も公共事業等により105万ヘクタールの農地造成を行っている。714万ヘクタールあるはずなのに、現実には459万ヘクタールの農地しかない。現在の水田総面積とほぼ同じ250万ヘクタールもの農地が、耕作放棄や宅地などへの転用によって消滅したのである。小作人に転用させて莫大な利益を得させるためではなく、農地を農地として利用させるために農地改革は実施されたはずなのに、小作人に開放した194万ヘクタールをはるかに上回る農地が潰されてしまった。
農家は潤ったが、農業は衰退し、食料安全保障に赤信号が灯っている。現在ある農地では、肥料や農薬も十分にあり、天候不順もないという条件に恵まれた場合に、イモと米だけ植えてやっと日本人が生命を維持できるだけである。不作になれば、餓死者が出る。
農業界は農業保護を維持したり増やそうとするときだけ、食料安全保障の主張を利用してきた。だから、農業界は、高い農産物価格やそのために必要な関税という農業保護を確保しようとすると、それと矛盾する食料自給率向上という主張は振り捨ててしまうし、食料安全保障の基礎となる農地を転用・潰廃してきたのである。2000年の閣議決定より10年たった今も、食料自給率は40%から上がる気配はない。しかし、農協も政府も、誰一人として計画未達成の責任を取ろうとしないばかりか、問題提起さえ行わない。しかし、不思議なことに、農業界の欺瞞を消費者団体が指摘することはまれである。
関税で農業を守るべきか?―柳田國男の反論
国民に食料を安定的に供給することは、農業の重要な役割である。そのためには十分な収益をあげられる持続可能な産業でなければならない。1900年に農商務省に入り、後に民俗学者となった柳田國男は、「農をもって安全にしてかつ快活なる一職業となすことは、目下の急務にしてさらに帝国の基礎を強固にするの道なり」と主張した。
しかし、現実の農業は、零細農家が多く、農業収益の低下により、70歳以上の高齢農業者が半数を占めるとともに、埼玉県の総面積に匹敵する39万ヘクタールの農地が耕作放棄されるなど、衰退の一途をたどっている。農協は、TPP(環太平洋パートナーシィップ協定)に加入すると、日本の非効率な農業は壊滅すると主張し、1000万人を目標にTPP反対の署名運動をしている。末端の農協職員には、署名集めのノルマが課されている。
現在の農協と同じく、100年前も、地主階級は高関税による農業保護を主張した。地主には収穫物の半分の米が小作料として集まった。寄生化していた地主勢力は、農業の生産性を向上させて農業所得を増加させるという方法ではなく、米の供給を制限することにより米価を引き上げ、彼らに集まった米を売却し利益を増やそうとした。具体的には朝鮮、台湾という植民地からの米の輸入を制限しようとしたのである。国防強化を口実として食料の自給が必要であると主張された。食料自給率向上、食料安全保障、高関税の確保、いずれも現在の農協、農業界の主張と同じである。地主階級が高関税導入のために政治活動を行った“農会"組織が、現在の農協の母体の1つとなったことからすれば、これはある意味で当然のことである。
これに対し、柳田國男は次のように反論して、農業の構造改革を提言した。「旧国の農業のとうてい土地広き新国のそれと競争するに堪えずといふことは吾人がひさしく耳にするところなり。然れども、之に対しては関税保護の外一の策なきかの如く考ふるは誤りなり。吾人は所謂農事の改良を以て最急の国是と為せる現今の世論に対しては、極力雷同不和せんと欲するものなり。今の農政家の説はあまりに折衷的なり、農民が輸入貨物の廉価なるが為め難儀するを見れば、保護関税論をするまでの勇気はあれども、保護をすればその間には競争に堪えふるだけの力を養い得るかと言へば、恐らくは之を保障するの確信はなかるべし」。柳田は、農業所得の向上は農業の効率化・生産性向上によるべきであって、消費者の家計を考えるのであれば、外国米を入れても米価が下がるほうがよいと主張したのである。柳田以来戦前の農政本流の人たちには、農産物価格を上げ消費者の負担を増大させることで、農業を保護してはならないという信念があった。
柳田の論文の中で、旧国とは日本、新国とはアメリカ、農事の改良とは農業の効率化や構造改革のことである。今回のTPPを巡っても、農家一戸当たりの農地面積は、日本を1とすると、EU9、米国100、豪州1902となっているので、規模の大きいアメリカや豪州の農業には勝てないとか、100年前と同じ議論が行われている。しかし、この主張が正しいのであれば、米国も豪州の19分の1なので、競争できないはずだ。この議論は、各国が作っている作物、単位面積当たりの収量(単収)、品質の違いを無視している。作物についていえば、豪州は牧草による畜産、アメリカは小麦、トウモロコシ、日本は米主体の農業である。米についての脅威は主として中国から来るものだが、その中国の農家規模は日本の3分の1に過ぎない。また、同じ作物でも単収や品質に大きな格差がある。フランスの小麦の単収はアメリカの3倍なので、フランスの100ヘクタールの農家の方がアメリカの200ヘクタールの農家より効率的である。
日本の農業保護の特徴
貿易自由化に対して農業界が常に反対するのは、我が国の特異な農業保護のやり方に原因がある。
OECD(経済協力開発機構)が開発したPSE(生産者支持推定量)という農業保護の指標は、財政負担による「納税者負担」の部分と、国内価格と国際価格との差(内外価格差)に生産量をかけた「消費者負担」の部分 ― 消費者が高い国内価格を農家に払うことで農家を保護している額 ― から成る。各国のPSEの内訳をみると、消費者負担の部分の割合は、1986~88年の、アメリカ37%、EU86%、日本90%に比べ、2006年ではアメリカ17%、EU45%、日本88%(約4.0兆円)となっている。アメリカやEUが価格支持から財政による直接支払いに移行しているにもかかわらず、日本の農業保護のほとんどは依然価格支持で、消費者が負担している。国際価格よりも高い国内価格を農家に保証するため、多くの品目で200%を超える高関税(コメは778%)を設定している。これに対し、米国やEUは直接支払いという補助金で農家を保護しているために高い関税は必要ない(表1)。
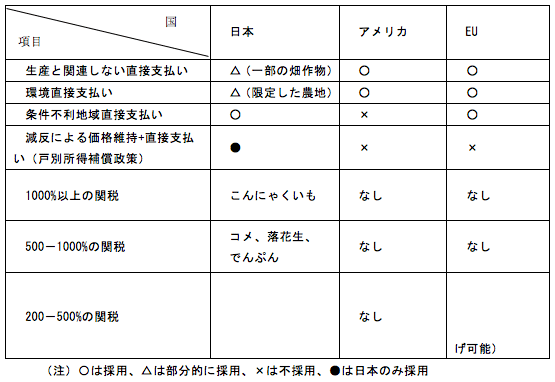
なお、日本の平均関税率は12%であり、韓国62%やEUよりも低く、農産物については既に解放された国であるという主張が行われている。しかし、この平均関税率の計算には、米等の高関税品目は含まれていない。100%以上の関税のタリフライン(品目)は169品目で、全農産物のタリフライン1332の12.7%を占めている。
価格支持か直接支払いか(消費者負担か財政負担か)
価格支持は消費者負担、直接支払いは財政負担による農家保護である。消費者負担型の政策の場合、消費者は、関税がゼロであれば国際価格で購入できたのに、関税があるために高い価格で国産農産物を購入せざるを得ない。しかし、消費者は、この内外価格差に相当する負担を行っていることを認識しながら、農産物を購入しているわけではない。いうなれば、こっそり消費者のポケットから負担させているのである。
これに対し、財政負担型の政策は、負担と受益との関係が国民の前に明らかになる。農業が農産物の生産以外に果たす水資源の涵養や洪水防止の機能を多面的機能という。農業界が主張する多面的機能や食料安全保障に国民の支持があるのであれば、国民は財政によって必要な負担を行うことに賛成するはずである。
また、消費者負担による価格支持は、貧しい消費者も等しく負担する逆進的なものであるのに対し、財政負担による直接支払いという手法は、累進課税制度の下では裕福な者が多く負担する公平なものである。
OECDが農業保護のうち消費者負担額として計測した約4.0兆円は消費税に換算すると1.6%に相当する。しかも、この4.0兆円は国産農産物に対してのみ消費者が負担している部分である。消費者は関税や課徴金が課されている外国産農産物に対しても内外価格差部分を負担している。小麦でいうと、消費者は、消費量の14%を占める国産小麦と同様の負担を、86%の外国産小麦についても負担している。国産農産物についての消費者負担を財政負担による直接支払いに置き換えると、外国産農産物に対する負担は財政負担に置き換える必要なく消滅する。財政負担型の政策へ転換すれば、食料品価格は低下し、消費者は大きなメリットを受ける。これはリストラなどで所得が低下し生活に困っている人たちには朗報となろう。
価格支持はすべての農家に広く薄く効果が及ぶのに対し、直接支払いは、受益の対象を政策支援が必要な農業者に限定することができる。農家の所得支持が問題ならば、勤労者世帯よりも高い所得を確保している兼業農家まで、所得補償する必要はない。また、規模を拡大してより効率的な農業を実現したいと考えるのであれば、規模拡大の意欲がない農家にまで、対策を講じる必要はない。対象を限定することによって、農業保護を従来の消費者負担額より少ない額で財政負担に置き換えることが可能となるばかりか、これによってコスト・ダウンを図ることができれば、必要な財政負担をさらに圧縮することが可能となる。
農政の失敗
これまで、輸入数量制限や米の778%という関税に代表される異常に高い関税で国内農産物市場を外国産農産物から守ってきた。にもかかわらず、農業が衰退するということは、その原因が海外ではなく国内にあるということを意味している。しかも、それは農業を振興するはずの農政そのものだった。
所得は、価格に生産量をかけた売上額からコストを引いたものであるから、所得を上げようとすれば、価格または生産量を上げるかコストを下げればよい。農産物のコストは、1ヘクタール当たりの肥料、農薬、機械などのコストを1ヘクタール当たりの単収で割ったものである。規模の大きい農家の米生産費は零細な農家の半分以下である(図-1で物財費とは肥料、農薬、機械など実際にかかったコスト、全算入生産費とはこれに労働費を計算して加えるなどしたものである)。コストを下げる方法としては、規模拡大による1ヘクタール当たりのコスト削減と単収向上の2つがある。
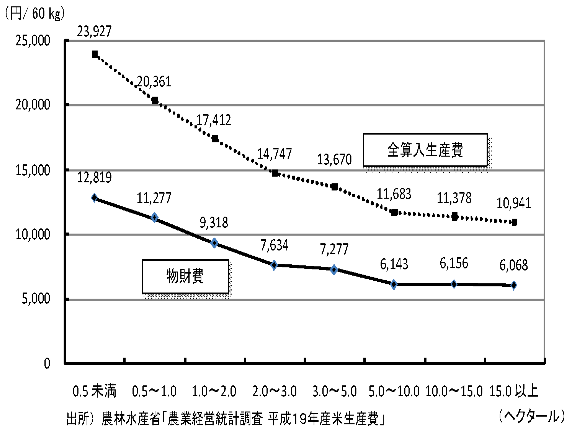
我が国農政は、コストを下げるのではなく食管制度の下で米価を上げて農家所得を向上させようとした。総農地面積が一定で一戸当たりの規模が拡大すると、農家戸数は減少する。組合員の圧倒的多数が米農家で、農家戸数を維持したい農協は、農業の構造改革に反対し、食管制度の時代、生産者米価引き上げのため一大政治運動を展開した。高い米価で販売手数料収入が増加するほか、少数の主業農家ではなく多数の兼業農家を維持すれば、農外所得や農地転用利益の農協口座への預け入れなどを通じて、農協経営の安定につながるからである。もちろん、政治力も維持できる。
農協の思惑通り、1960年代以降の生産者米価引き上げによって、本来ならば退出するはずのコストの高い零細農家も、小売業者から高い米を買うよりもまだ自分で作った方が安いので、農業を継続してしまった。零細農家が農地を出してこないので、専業農家に農地は集積せず、規模拡大は進まなかった。主業農家の販売シェアは、野菜や酪農では8割、9割を超えているのに、米だけが4割にも満たない。農業で生計を立てている農家らしい農家が、コストを引き下げて収益をあげようとする途を農政が阻んでしまったのである。
都市化の急速な進展により、大多数の消費者が農家・農村の実態から隔離された。かれらが農家・農村に持つイメージが戦前の貧しい小農=小作人のイメージのままだったことは、農協に有利に働いた。零細な兼業農家のほうが専業農家よりも高い所得を上げ、かつ専業農家の規模拡大による所得増加を妨害し、また、土日農業のため手間ひまかけない農薬・化学肥料多投の農業を実施しているにもかかわらず、消費者団体の多くは、零細な農家のほうが貧しく、農薬・化学肥料も使わない環境に優しい農業を行っているという認識をもったのである。農業の多面的機能や食料安全保障を強調する文化人も、農協がこれと矛盾する減反政策を強力に推進していることや、兼業農家が農地の転用で莫大な利益を得ていることなどについては、無知か、あるいは発言することはない。
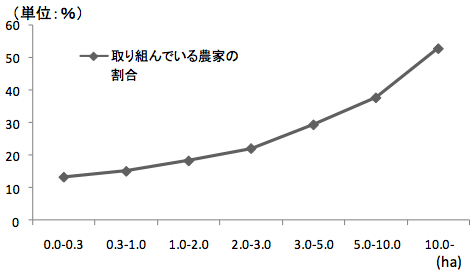
米価引上げによって、消費は減り生産は増えたので、米は過剰になり40年も減反している。食管制度が1995年に廃止されて以降、米価は生産量を制限する減反政策によって維持されている。減反は生産者が共同して行うカルテルである。しかし、およそカルテルというものは、カルテル参加者に高い価格を実現させておいて、その価格で制限なく生産するカルテル破りのアウトサイダー生産者が必ず得をする。拘束力のあるカルテルが成立するためには、アウトサイダーが出ないよう、アメかムチが必要となる。現在、年問約2000億円、累計総額7兆円の補助金が、他産業なら独禁法違反となるカルテルに、農家を参加させるためのアメとして、税金から支払われてきた。国民は高い米価という消費者負担と減反補助金という納税者負担の二重の負担をしている。
今では、減反面積は今では100万ヘクタールと水田全体の4割に達している。500万トン相当の米を減産する一方、700万トン超の麦を輸入するという食料自給率向上とは反対の政策が採り続けられている。減反政策が導入されるまで増加してきた水田は減反開始後一転して減少し、100万ヘクタールの水田が消滅した。戦前農林省の減反政策案に反対したのは食料自給を唱える陸軍省だった。真の食料自給は減反と相容れない。農業界が唱える多面的機能の主張も、そのほとんどは水田の機能なのに、減反によって水田を水田でなくしてしまう政策が採り続けられている。
減反はコスト削減にも悪影響をもたらした。総消費量が一定の下で単収が増えれば、米生産に必要な水田面積は縮小するので、減反面積を拡大せざるをえなくなり、農家への減反補助金が増えてしまう。このため、単収向上のための品種改良は、行われなくなった。今では空から飛行機で種まきしているカリフォルニアの米単収より日本米の平均単収は3割も少ない。高米価、減反政策が米の競争力を奪ったのである。
今では既に減反が限界に近いところにきているので、消費が減少しても、減反を十分には拡大できない。当然、米価は低下する。このため、米を作ると赤字になるコストの高い零細農家は農地を手放している。しかし、受け手の主業農家も、米価の低下によって地代負担能力が低下しているため、農地を引き取れない。両者の間に落ちた農地が耕作放棄地である。
こうすれば国際競争力は向上する
減反を段階的に廃止して米価を下げれば、コストの高い兼業農家は耕作を中止し、農地をさらに貸し出すようになる。そこで、一定規模以上の主業農家に面積に応じた直接支払いを交付し、地代支払能力を補強すれば、農地は主業農家に集まり、規模は拡大しコストは下がる。
減反がなくなるので単収向上への制約もなくなる。これから農業技術の研究者は思う存分に品種改良などの研究に励むことができる。60年代に米作日本一に輝いた農家の10アール当たりの単収は1トンを超え、現在の平均単収の約2倍である。そこまでいかないにしてもカリフォルニア米並みの単収となれば、6000円のコストは4000円へと低下する。日本の米は世界でもっともおいしいという評価がある。現在の価格でも、台湾、香港などへ輸出している生産者がいる。品質の良さに価格競争力がつけば鬼に金棒である。
主業農家のコストが下がり収益が増えれば、地代が上昇し農地の出し手の兼業農家も利益を受ける。よく農協は6割の生産シェアを持つ兼業農家がいなくなれば食料供給に不安が生じると主張するが、零細農家が退出した後の農地は主業農家が引き取ってより効率的に活用するので、食料供給にいささかも問題は生じない。40年間で酪農家の戸数は40万から2万に減少したが、牛乳生産量は200万トンから800万トンへ拡大している。減反をやめて生産を拡大すれば多面的機能も向上する。
真の食料安全保障のために
1993年、それまで価格低落時に市場から買い入れることで穀物価格を維持してきたEUは、直接支払いを導入することで穀物支持価格を29%引き下げて、アメリカから輸入してきた餌用の穀物需要を域内の穀物で代替した。価格を下げると、別の需要を取り込むことができるようになる。
日本の米にとってそれは「輸出」である。日本ではこれまで国内の食用の需要しか視野になかったことが農業生産の減少をもたらしてきた。日本の人口は減少するが、世界の人口は増加する。しかもアジアには所得増加にも裏打ちされた拡大する市場がある。高齢化、人口減少時代に、日本農業を維持、振興し、食料安全保障に必要な農業資源を維持・確保しようとすると、輸出により海外市場を開拓せざるを得ない。
平時には農業生産は需要・消費に規定される。需要がないものは生産しても市場で消化できないからである。輸入国では、国内農産物に対する需要・消費は、全体量から輸入量を差し引いたものである。しかし、緊急時には作られるもの、あるいはあるものしか食べられないので、消費は生産、供給に規定される。輸入が途絶するという緊急時には、これまで輸入してきた食料を国内で供給しなければならなくなるが、その供給は、平時の輸入量を差し引いた需要に対応して継続されてきた生産・供給力に規定されてしまう。危機が起こった時に、十分な農地がないのである。
ここに日本のような輸入国における、農地を含めた農業資源確保の困難さがある。しかも、今後人口減少により、日本農業は縮小し、農地資源も減少する。緊急時の消費を規定する国内の生産力が大幅に減少してしまうのである。これは国内価格を高く維持しているため、輸出需要を考えられないからに他ならない。
TPPに参加して最も影響を受けるといわれている米についてさえ、この10年間の国内価格の低下と外国産米の価格上昇によって、価格差は大幅に縮小し(図3)、2010年度では関税ゼロの輸入枠の消化率は大幅に低下するなど、関税なしでも国産米が外国産米に勝っている状況にある。減反を止めれば、さらに価格は下がる。国際価格との差が接近しているのは、米に限らない。麦、いも、牛肉や乳製品等他の重要品目についても、2500億円程度の直接支払いで関税を撤廃できる。
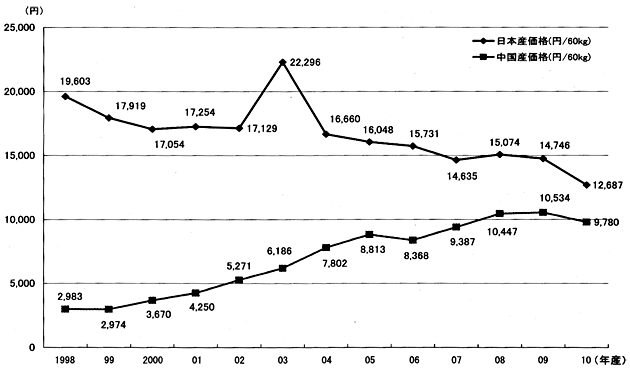
高級車と軽自動車では大きな価格差が存在する。米についても、1993年に輸入されたタイ米が大量に売れ残ったように、ジャポニカ米とタイ米のようなインディカ米とでは消費者の評価に大きな差がある。同じジャポニカ米の中でも、さらには同じコシヒカリという品種であっても、日本市場やアジア市場において、最高ランクの日本米とカリフォルニア産米、中国産米とでは大きな価格差がある。国内でも、魚沼産コシヒカリと他県産コシヒカリとでは、1.7倍もの価格差があるのと同様である。香港では、商社の卸売価格は、キログラム当たり日本産コシヒカリ380円、カリフォルニア産コシヒカリ240円、中国産コシヒカリ150円、中国産一般ジャポニカ米100円となっている。品質の劣る米と日本の米の価格を比較して、米は壊滅すると主張するのは、誤りである。我が国自動車業界は、ベンツもフォードも輸入しながら、トヨタ、ニッサン、ホンダなどを輸出している。低品質の米が100万トン輸入されたとしても、300万トンの高品質米を輸出すればよい。
日本が最も得意とする農産物は米である。将来的に、国内消費の減少と構造改革により日本米の価格が9000円に低下し、中国産米の価格が農村部の所得の上昇と人民元の引き上げによって1万3000円に上昇すると、商社は日本市場で9000円で米を買い付け1万3000円で輸出すると利益を得る。この結果、国内での供給が減少し、輸出価格の水準まで国内価格も上昇する。これによって国内米生産は拡大するし、直接支払いも減額できる。
アメリカやEUは直接支払いという鎧を着て競争している。日本の米だけが徒手空拳で競争する必要はない。減反廃止と主業農家に対する直接支払い、これが正しい政策である。政府からの直接支払いという補助金でコストを下げていけば、国内生産を維持して多面的機能を確保したうえで、関税撤廃による安い農産物価格のメリットを消費者は受けることができる。
自由貿易の下での農産物輸出は、人口減少時代に日本が国内農業の市場を確保する道である。人口減少により国内の食用の需要が減少する中で、平時において需要にあわせて生産を行いながら食料安全保障に不可欠な農地資源を維持しようとすると、自由貿易のもとで輸出を行わなければ食料安全保障は達成できない。しかし、国内農業がいくらコスト削減に努力しても輸出しようとする国の関税が高ければ輸出できない。農業界こそ貿易相手国の関税を撤廃し輸出をより容易にするTPPに積極的に対応すべきなのである。
『都市問題』2011年5号に掲載


