1.衰退する農業
1960年から最近年まで、GDP(国内総生産)に占める農業生産は9.0%から1.0%へ、農業就業人口は1196万人から252万人へ、食料自給率は79%から41%へ、いずれも減少した。65歳以上の高齢農業者の比率は1割から6割へ上昇し、農外所得(兼業所得)の比重の多い第2種兼業農家の割合も32.1%から61.7%へと増加した。
2006年の農業の生産額は8.5兆円、農業のGDPはこれから農業中間投入額を差し引いた4.7兆円である。しかも、関税や価格支持等の農業保護によって守られたところが大きく、OECDが計測した日本の農業保護額は4.5兆円で、農業のGDPとほぼ等しい。農業保護がなければ、農業のGDPはなくなってしまう。農業のGDPは水増しされたものである。
高齢化が進んで人手不足だからという理由で、農業が雇用の受け皿として注目を浴びている。しかし、農業のGDPを就業人口で割れば、農業者1人あたりの平均所得は年間187万円、1月当たりでは15万5000円に過ぎない。人手不足ではなく、過剰就労している人たちが高齢化しているのが実態である。農業の収益が低いから、農家の跡継ぎも農業をやろうとはしないし、新規就農しようという人も出てこない。高齢化はその結果である。農業の収益を上げることに成功できない現状では、農業での雇用創出は困難である。
農業の衰退に高齢化・人口減少が追い打ちをかける。米を例にとろう。米の1人当たりの消費量は過去40年間で半減した。今後は、高齢化し1人が食べる量がさらに減少する一方、これまで増えてきた総人口も減少する。今後40年で1人当たりの消費量が現在の半分になれば、2050年頃には米の総消費量は今の850万トンから350万トンになる。250万haの水田のうち減反は200万haに拡大し、米作は50万ha程度で済んでしまう。国内市場の縮小は米に限らない。これまでの農業保護は、高い関税を維持して国内市場を守ろうとするものだった。しかし、国内市場に頼る限り、日本農業はさらに衰退する。
農業に他の産業にはない手厚い保護が加えられてきたのは、国民への食料の安定供給、つまり食料安全保障という役割があるからである。その食料安全保障の基礎となるのは、農地資源の確保である。しかし、農地法による転用規制、農業振興地域の整備に関する法律による土地利用規制(ゾーニング)という制度はあったものの、ザル法と呼ばれるような運用によって、農地資源は大量に転用、放棄され続けた。
公共事業等により105万haの農地造成を行った傍らで、1961年に609万haあった農地の4割を超える250万haもの農地が耕作放棄や宅地などへの転用によって消滅した。戦後、人口わずか7000万人で農地が500万ha以上あっても飢餓が生じた。現在の総農地面積は終戦時をはるかに下回る461万haに過ぎない。この消滅した面積は、全国の水田面積250万ha(減反しているので、米を作っている面積は150ha)に等しい。農業の衰退は農地をさらに減少させ、食料安全保障を脅威にさらすことになる。
単純な算数だが、農地面積が一定で、農家戸数が減ると、1戸あたりの経営規模は拡大する。規模が拡大すると、コストは下がり、農業収益は増加する。しかし、我が国では、戸数とともに農地面積も大きく減少した。フランスでは、農家戸数は大きく減少したものの、耕地面積はほとんど減少しなかったため、農家の経営規模は拡大した。1980年から2006年にかけて、農家の経営規模は、フランスでは25.4haから52.3haへと拡大しているのに対し、日本では1.2haが1.8haになっただけである。
また、フランスでは、総投下労働時間のうち農業への投下労働時間が半分以上、所得のうち農業所得が半分以上を占めるという企業的農家に、農業政策の対象を限定した。パートタイム・ファーマーはフランス農政の対象ではない。保護に値する農家は真剣に農業をやっている農家だけだというのである。我が国農政は結果的にフルタイマーよりパートタイマーを優遇してしまった。
これまで、輸入数量制限や米の778%という関税に代表される異常に高い関税で国内農産物市場を外国産農産物から守ってきた。にもかかわらず、農業が衰退するということは、その原因が海外ではなく国内にあるということを意味している。しかも、それは農業を振興するはずの農政そのものだったのである。
2.グローバル化で発展する可能性
国内市場が縮小するなら海外市場に目を向けなければならないが、日本農業は国際競争力がないというのが定説となっている。しかし、日本農業が衰退する中で、農産物販売額が1億円を超える農家は2500戸もあり、また、グローバル化をうまく利用して成功した例もある。
内外の需要の違いをとらえたものとして、長いほど滋養強壮剤として好ましいと考えられている台湾で、日本では長すぎて評価されない長いもが高値で取引きされている例、日本では評価の高い大玉をイギリス輸出しても評価されず、苦し紛れに日本では評価の低い小玉を送ったところ、やればできるではないかといわれたというあるリンゴ生産者の話がある。国際分業の点でも、多くの労働が必要な苗までは労賃の安い海外で生産し、それを輸入して日本で花まで仕上げるという経営方法で成功した農家、南北半球の違いを利用して、ニュージーランドがキウイを供給できない季節に、ニュージーランド・ゼスプリ社と栽培契約を結び、同社が開発した果肉が黄色のゴールド・キウイを日本国内で生産・販売している例もある。
他方、日本と隣接する巨大市場である中国の内政上最大の問題は、都市部と内陸農村部の1人当たり所得格差が3.5倍に拡大しているという「三農問題」である。これを我が国から見ると、上海などわが国に近い臨海部に品質の高い米を需要する富裕層がいることは、日本からの輸出に好条件である。他方、中国の農家規模は日本の3分の1に過ぎず、中国農業の競争力は安い農村部の労働に支えられている。三農問題が解決されていけば、農村部の労働費は上昇し、中国産農産物価格も上がる。そうなれば日本農業の競争力が高まる。既に、国産米の値段は需要の減少により1996年までは60kgあたり2万円以上していた米価が、10年間で30%以上も低下し、1万3000円~1万4000円程度になっている。これに対し、中国から輸入している米の値段(60kg当たり)は10年前の3000円から1万500円程度に上昇し、価格差は大幅に接近している。将来ともこのトレンドは継続するものと考えられるので、この価格差はさらに縮小していくだろう。
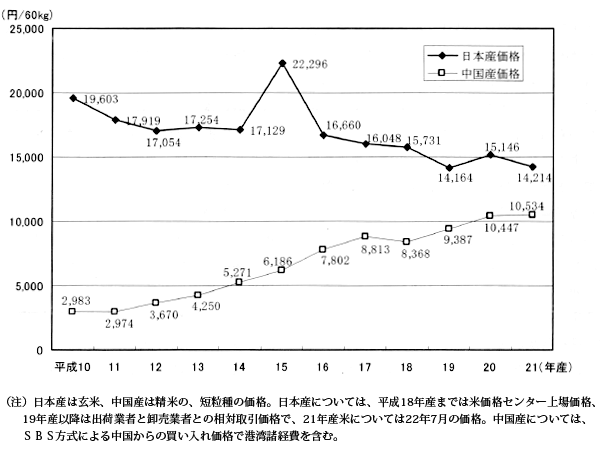
日本農業にポテンシャルはないのだろうか。傾斜地が多く条件が不利と思われてきた中山間地域農業にも可能性がある。農業は季節によって農作業の多いときと少ないとき(農繁期と農閑期)の差が大きいため、労働力の通年平準化が困難だという問題がある。米作でいえば、田植えと稲刈りの時期に労働は集中する。農繁期に合わせて雇用すれば、他の時期には労働力を遊ばせてしまい、コスト負担が大きくなる。しかし、中山間地域の標高差等を利用すれば田植えと稲刈りにそれぞれ2~3カ月かけられる。日本の稲作の平均的な規模は1ha程度であるが、中国地方や新潟県の典型的な中山間地域において、夫婦2人で10~30haの耕作を実現している例がある。また、日本は南北に長い。砂糖の原料であるサトウキビとビートを同じ国で生産できる国は少ない。この特性を活かし、日本各地に点在する複数の農場間で機械と労働力を移動させることで、作業の平準化を実現している企業的経営もある。
3.農政の失敗
所得は、価格に生産量をかけた売上額からコストを引いたものであるから、所得を上げようとすれば、価格または生産量を上げるかコストを下げればよい。農産物のコストは、1ha当たりの肥料、農薬、機械などのコストを1ha当たりどれだけ収穫できるかという単位面積当たりの収量(単収)で割ったものである。コストを下げる方法としては、規模拡大による1ha当たりのコスト削減と単収向上の2つがある。
我が国農政は、コストを下げるのではなく食管制度の下で米価を上げて農家所得を向上させた。総農地面積が一定で一戸当たりの規模が拡大すると、農家戸数は減少する。組合員の圧倒的多数が米農家で、農家戸数を維持したい農協は、農業の構造改革に反対した。少数の主業農家ではなく多数の兼業農家を維持する方が、農協にとって農外所得や農地転用利益の農協口座への預け入れなどを通じた農協経営の安定や政治力維持につながるからである。食管制度の時代、農協は生産者米価引き上げのため一大政治運動を展開した。
農協の思惑通り、1960年代以降の生産者米価引き上げによって、本来ならば退出するはずのコストの高い零細農家も、小売業者から高い米を買うよりもまだ自分で作った方が安いので、農業を継続してしまった。零細農家が農地を出してこないので、専業農家に農地は集積せず、規模拡大は進まなかった。主業農家の販売シェアは、野菜や酪農では8割、9割を超えているのに、米だけが4割にも満たない。農業で生計を立てている農家らしい農家が、コストを引き下げて収益をあげようとする途を農政が阻んでしまったのである。
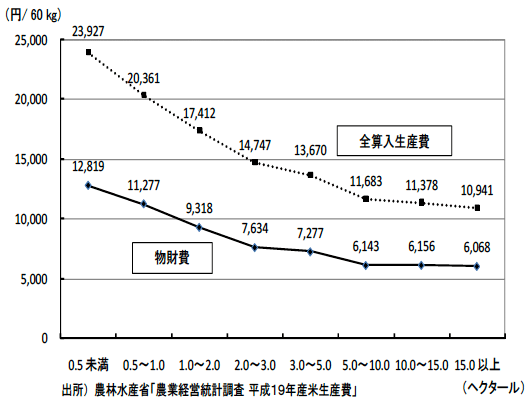
消費は減り生産は増えたので、米は過剰になり40年も減反している。食管制度が1995年に廃止されて以降、米価は生産量を制限する減反政策によって維持されている。減反は生産者が共同して行うカルテルである。しかし、およそカルテルというものは、カルテル参加者に高い価格を実現させておいて、その価格で制限なく生産するカルテル破りのアウトサイダー生産者が必ず得をする。拘束力のあるカルテルが成立するためには、アウトサイダーが出ないよう、アメかムチが必要となる。現在、年問約2000億円、累計総額7兆円の補助金が、他産業なら独禁法違反となるカルテルに、農家を参加させるためのアメとして、税金から支払われてきた。
減反面積は今では100万haと水田全体の4割に達している。500万t相当の米を減産する一方、700万t超の麦を輸入するという食料自給率向上とは反対の政策が採り続けられている。減反政策が導入されるまで増加してきた水田は減反開始後一転して減少し、100万haの水田が消滅した。戦前農林省の減反政策案に反対したのは食料自給を唱える陸軍省だった。真の食料自給は減反と相容れない。農業界が唱える多面的機能の主張も、そのほとんどは水田の機能なのに、減反によって水田を水田でなくしてしまう政策が採り続けられている。
減反はコスト削減にも悪影響をもたらした。総消費量が一定の下で単位面積当たりの収量(これを単収という)が増えれば、米生産に必要な水田面積は縮小するので、減反面積を拡大せざるをえなくなり、農家への減反補助金が増えてしまう。このため、単収向上のための品種改良は、行われなくなった。今では空から飛行機で種まきしているカリフォルニアの米単収より日本米の平均単収は3割も少ない。高米価、減反政策が米の競争力を奪ったのである。
今では既に減反が限界に近いところにきているので、消費が減少しても、減反を十分には拡大できない。当然、米価は低下する。このため、米を作ると赤字になるコストの高い零細農家は農地を手放している。しかし、受け手の主業農家も、米価の低下によって地代負担能力が低下しているため、農地を引き取れない。両者の間に落ちた農地が耕作放棄地である。
米価低落による農業収益の減少こそが、耕作放棄の本当の原因である。食糧管理制度の下での高米価時代には、耕作放棄は話題にも上らなかった。農林水産省が耕作放棄の原因に挙げている高齢化も、農業収益低下の結果である。高齢化と耕作放棄が同時に起こっているからといって、その間に因果関係はない。農林水産省が高齢化を原因に挙げるのは、農業収益の低下を認めたくないからだ。それは、農政の失敗を認めることと同じだからである。
4.あるべき農政―こうすれば国際競争力は向上する
減反を段階的に廃止して米価を下げれば、コストの高い兼業農家は耕作を中止し、農地をさらに貸し出すようになる。そこで、戸別所得補償政策をスクラップし、一定規模以上の主業農家に面積に応じた直接支払いを交付し、地代支払能力を補強すれば、農地は主業農家に集まり、規模は拡大しコストは下がる。今でも15ha以上の規模の農家のコストは米価の約半分の6000円である。新規参入者やこれから規模を拡大しようとする者に対しても暫定的に対象とし、一定期間後の目標面積を提示させ、(土地所有者が貸さなかったなどの不可抗力による場合を除き)目標を達成しなかった場合には、直接支払いを全額返還させるという仕組みとすればよい。
農地が少数の主業農家に集まれば、農地がいろいろな場所に点在しているため、機械の移動などに労力がかかる零細分散錯圃という問題も解決に向かい、コストはさらに下がる。減反がなくなるので単収向上への制約もなくなる。これから農業技術の研究者は思う存分に品種改良などの研究に励むことができる。60年代に米作日本一に輝いた農家の10a当たりの単収は1tを超え、現在の平均単収の約2倍である。そこまでいかないにしてもカリフォルニア米並みの単収となれば、6000円のコストは4000円へと低下する。日本の米は世界でもっともおいしいという評価がある。現在の価格でも、台湾、香港などへ輸出している生産者がいる。品質の良さに価格競争力がつけば鬼に金棒である。
直接支払い自体もコストを下げる効果がある。アメリカやEUは直接支払いという鎧を着て競争している。カリフォルニア米の生産や輸出も多額の補助金によって支えられている。日本の米だけが徒手空拳で競争する必要はない。減反廃止と主業農家に対する直接支払い、これが正しい政策である。
主業農家のコストが下がり収益が増えれば、地代が上昇し農地の出し手の兼業農家も利益を受ける。よく農協は6割の生産シェアを持つ兼業農家がいなくなれば食料供給に不安が生じると主張するが、零細農家が退出した後の農地は主業農家が引き取ってより効率的に活用するので、食料供給にいささかも問題は生じない。40年間で酪農家の戸数は40万から2万に減少したが、牛乳生産量は200万tから800万tへ拡大している。米農家と異なり、この間、農協が酪農家戸数の減少を問題視したことはなかった。
食料自給率を40%から50%に引き上げるという目標を達成するために、政府は麦等についても戸別所得補償を導入して生産を拡大するとともに、減反水田で米粉や飼料用の米生産を拡大しようとしている。しかし、今では讃岐うどんの原料が豪州産小麦であるように、品質の劣る国産麦の生産を拡大しても製粉会社は引き取れない。また、米粉や飼料用の米価はきわめて低いので、政府は10aあたり8万円の補助金を農家に交付することとしている。しかし、農家への所得補償であれば、生産を要求しないで主食用の米作所得2万6000円を支払ったほうが安上がりである。仮に減反面積の半分に8万円を支払うと4000億円も必要になる。輸出用に米を作ればその半分以下の補助金で済み、同じ予算額では新たに増やそうとした米作付水田面積を倍以上に拡大できる。しかし、このような補助金が出せないのは、これが日本にはWTO(世界貿易機関)上禁止されている輸出補助金に該当するからである。
個別品目ごとに自給率を上げようとしている国も、米を飼料用に向けようとする国も珍しい。アメリカは日本よりも農産物輸入額は多いがそれを上回る輸出を行うことによって、100%を超える自給率を達成している。どの国も得意なものを輸出して不得意なものを輸入している。輸出に向けられる米だけに補助金を交付すれば禁止の補助金になるが、減反を廃止して輸出も可能になるような価格水準とし、国内用、輸出用に限定しないで直接支払いをすれば、それは輸出補助金に該当しない。アメリカやEUは、このような直接支払いで農業の国際競争力をつけている。
日本が最も得意とする農産物は米である。国際的にも、タイ米のような長粒種から日本米のような短粒種へ需要はシフトしている。短粒種に近いカリフォルニア米(中粒種)の方がタイ米より50%も価格は高い。短粒種の中でも日本米の品質は高く評価されている。将来的に日本米の価格が9000円に低下し中国産米の価格が1万3000円に上昇すると、商社は日本市場で9000円で米を買い付けて1万3000円で輸出すると利益を得る。この結果、国内での供給が減少し、輸出価格の水準まで国内価格も上昇する。いわゆる価格裁定行為である。これによって国内米生産は拡大するし、直接支払いも減額できる。国際価格との差が接近しているのは、米に限らない。麦、いも、牛肉や乳製品等他の重要品目についても、2500億円程度の直接支払いで関税を撤廃できる。
政府も国内市場堅持一辺倒ではなく海外市場の開拓に努めるべきである。特に、関税が引き下げられる中で、動植物の検疫措置が農業保護のために使われるようになっている。中国からは大量の農産物が輸入されているが、わが国から中国に輸出できる未加工の農産物は、米、リンゴ、ナシ、茶に限られている。米についても2007年4月に輸出解禁となったばかりであり、依然として厳しい検疫条件が要求されている。農政は発想を大胆に転換し、組織・人員をこれまでとは別の対象に使うべきである。
中山間地域のような条件不利地域についてはどうするのか? 既に述べたように、中山間地域農業には可能性があるが、一気に全地域で大規模農業を実現することは容易ではないだろう。中山間地域については2000年度筆者が農林水産省地域振興課長時代に導入した中山間地域等直接支払いで対応すればよい。これは傾斜農地と平坦な農地のコスト差を算出し、その8割を単価とした。しかし、筆者が10年以上前に単価を設定してから、一度も米生産費調査による単価の再計算は行われていない。再計算をすれば単価は増額となるはずである。もちろん、中山間地域等直接支払いは条件不利性の補正のためのものなので、他の政策目的のための別の直接支払いも受けることは可能である。EUの農家は、条件を満足していれば、価格を引き下げた代償としての単一支払いという直接支払い、環境直接支払い、条件不利地域直接支払いの3つの直接支払いを受領している。
経済政策の基本は問題の根源にターゲットを絞ることである。政策目的が所得補償であれば、所得の高い人に補助金を交付することは適切ではない。政策目的が規模拡大による農業構造改革であれば、規模が小さく規模拡大に意欲のない人に補助金を交付すべきではない。同じく政策目的が条件不利性の補正であれば、傾斜のない条件の良い農地にまで補助金を交付すべきではない。価格支持政策の問題は、裕福な農家、貧しい農家、規模拡大に意欲のある農家、ない農家、条件の良い農家、悪い農家のどの農家にも一律の価格が適用されてしまうことである。価格支持政策はターゲットを絞ることができないのである。
5.農政の混迷
以上のような政策と比べて、現実の政策はどのようなものだろうか。
OECD(経済協力開発機構)が開発したPSE(生産者支持推定量)という農業保護の指標は、財政負担によって農家の所得を維持している「納税者負担」の部分と、国内価格と国際価格との差(内外価格差)に生産量をかけた「消費者負担」の部分―消費者が安い国際価格ではなく高い国内価格を農家に払うことで農家を保護している額―から成る。各国のPSEの内訳をみると、消費者負担の部分の割合は、ウルグァイ・ラウンド交渉で基準年とされた1986~88年の数値、アメリカ37%、EU86%、日本90%に比べ、2006年ではアメリカ17%、EU45%、日本88%(約4.0兆円)となっている。アメリカやEUが価格支持から財政による直接支払いに移行しているにもかかわらず、日本の農業保護は依然価格支持である。国内価格が国際価格を大きく上回るため、高関税が必要となる。
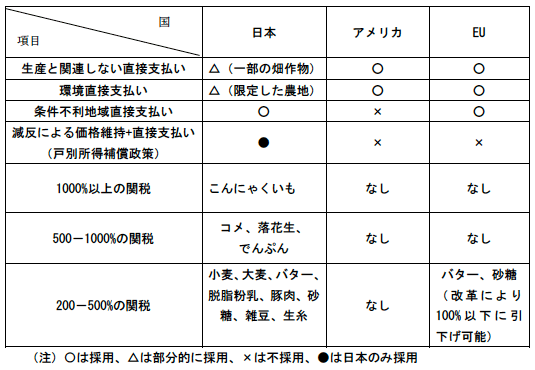
もちろん、このような高価格・高関税政策がいつまでも維持できるものではない。ウルグァイ・ラウンド交渉は各国の輸入割当制度などを関税に転換した(「関税化」である)ものの、1986~88年当時の大幅は内外価格差をそのまま関税に置き換えるという「汚い関税化」を認めた。このため、各国の高い国内価格の引下げまで要求するものではなかった。
しかし、続くWTOドーハ・ラウンド交渉で、関税の大幅削減を要求された農政は大きく動揺した。特に、2003年8月アメリカ・EUは農産物関税に100%の上限を設けることに合意したため、同月末、唐突に「諸外国の直接支払いも視野に入れて」農政の基本計画を見直すという農林水産大臣談話が出された。778%の米の関税率をそこまで下げると、EUのように直接支払いを導入しない限り日本農業は壊滅するからである。
しかし、これは2度後退する。まず、翌9月のWTO閣僚会議で、米は上限関税率の特例にできるかもしれないという淡い期待が生じたため、農水省は米を直接支払いの対象からはずすと表明した。次に、04年8月のWTO交渉枠組み合意で、ミニマムアクセスなどの関税割当量の大幅拡大という代償の見返りとして、一定の品目については関税引下げの例外を設けることができるかもしれないという希望的観測が生じた。関税を下げなくてよいのであれば、国内価格も下げなくてよい。このため、米のみならず麦、牛乳など他の農産物を含め価格引下げのための直接支払いは見送るという内容にさらに後退した。結局、農家保証価格と市場価格の差を補填している不足払いと呼ばれるWTOでは削減対象の麦、大豆などの補助金(黄色の補助金)について、その7割をWTOでは削減しなくてよい直接支払い(緑の補助金)に移行するだけになった。黄色を黄緑にしたのである。
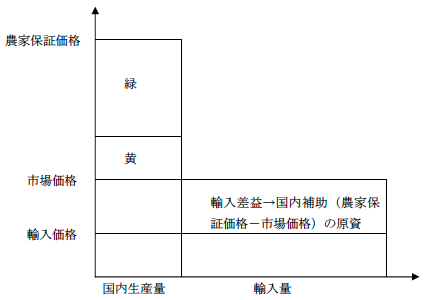
それでも、民主党のバラマキ所得補償案に対抗して、対象農家を4ha以上に限定したことは評価できた。しかし、兼業農家も20ha以上の農地面積を集めて集落で営農すれば対象とするという例外を認めたため、兼業農家が借地で規模拡大してきた主業農家から農地を「貸しはがす」という規模拡大に逆行する事態も発生した。さらに、2007年の参議院選挙に負けた自民党は対象農家について市町村長の特例を認め、「対象者を絞る」政策からいっそう後退してしまった。
民主党はどうか。2003年までの選挙公約は、「減反を廃止して価格を引き下げ、主業農家に対象者を絞って直接支払いを行う」という、筆者が小著『WTOと農政改革』(2000年)で表明した主張を採用していた。しかし、選挙を意識した民主党は2004年参院選のマニフェストで、「対象者を絞る」という要素をはずしてしまった。そして2007年7月、自民党から対象者を絞らないバラマキの直接支払いと批判された「戸別所得補償」の導入と減反の廃止を主張した民主党は参議院選挙で大勝した。
さらに、小沢一郎氏の「関税ゼロでも自給率100%」という主張の前提には減反廃止による価格引下げがあったはずなのに、2008年に民主党「次の内閣」が承認した「当面の米政策の基本的動向」は減反維持への転向を表明し、2009年の総選挙では減反を条件とした「戸別所得補償」の導入を主張した。
結局、両党間の農政に、減反を維持して価格は下げない、また対象農家の限定はしないという点で大きな違いはなくなってしまったのだ。
6.農家への戸別所得補償政策
2010年度から導入される「戸別所得補償政策」は、米生産がコスト割れしているので、コストと米価の差10a当たり1万5000円を農家に支払うというものだ。しかし、コスト割れしているのなら、これまで農家は生産を継続できなかったはずだ。コストが米価より高い理由は、このコストが、肥料、農薬など実際にかかった経費に、勤労者には所得に当たる労働費を農水省が計算して加えた架空・机上のコストだからである。農水省の統計でも販売収入から経費を引いた米農家の農業所得は、平均では35万円、7~10ha規模の農家では414万円、20ha以上の規模では1191万円となる(2009年)など、実際にはコスト割れなどしていない。
そもそも、リストラされた人たちやシャッター通り化した商店主は所得補償されずに、なぜ勤労者世帯よりも高い所得を得ている裕福な兼業農家に国民納税者は何千億円も支払わなければならないのだろうか。政策目的が所得補償なのに、選挙目当てに所得の高い人も対象にしてしまったのである。しかも、50aの小規模農家への補助金は7万5000円に過ぎず、所得補償の名にも値しない。
かつては高い価格で農家を保護していたEUも、ウルグァイ・ラウンド交渉を乗り切るために価格を下げて農家への直接支払いという財政による補てんに切り替えた。消費者負担から財政による農家保護への転換である。しかし、農家が今回の戸別所得補償を受けるためには、生産を減少して高い米価を維持するという減反へ参加することが条件である。米価水準を下げようとするものではない。これまでも農家を減反に参加させるため、補助金が支出されてきた。今回これに3371億円という戸別所得補償を加えるので、減反補助金と合わせると5618億円となる。高い米価という消費者負担に納税者負担が加重されるのだ。価格が下がらないので関税は下げられない。
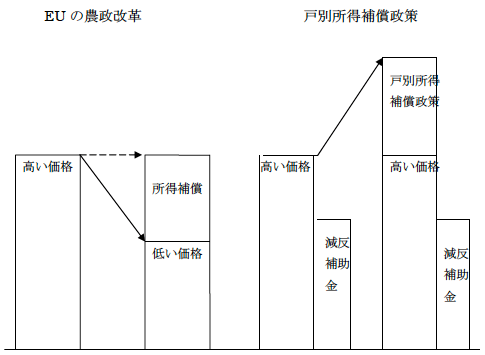
米価が低下すると戸別所得補償は増額される。逆に米価が上がっても、戸別所得補償は減額されない。つまり、農家には、減反で維持されている現在の米価に10a当たり1万5000円を加えた水準を上回る手取りが常に保証されることになる。さらに、バラマキ批判があるように、戸別所得補償は零細な兼業農家を含めほとんど全ての農家に支払われる。実質米価の引き上げで、零細・非効率な兼業農家も農業を続けてしまい、企業的な農家に農地は集まらないので、米作の高コスト構造は改善しない。逆に、これまで主業農家に貸していた農地を兼業農家が貸しはがすという事態も生じている。食管制度への回帰である。
TPP(環太平洋パートナーシィップ協定)に対応するため、規模拡大加算が検討されているが、効果は期待できない。
詳しく説明しよう。主業農家が支払える地代は、農地1単位当たりの米売上高から肥料・農薬代などの諸経費や自己の労働に対する対価(他産業並みの賃金・労働費であり、他の産業で働いていたら得られていただろう報酬)などの費用を引いたもの(「剰余」と言われる)である。諸経費だけではなく、自分の労働報酬も賄えないようでは、農地を借りて農業を行うメリットがないからである。これに対して、零細農家が要求する地代は、米売上高から肥料・農薬代などの諸経費を引いたもの(「剰余」に「労働費」を加えたものでこれまで所得として得ていた金額)に、農地を貸していたなら宅地などへの転用利益を失うかもしれない不利益を加えたものである。零細農家もこれまで所得として得ていた労働費を地代の一部として回収する必要がある。そうでなければ、貸す必要はない。農地は、主業農家が支払える地代が零細農家の要求する地代を上回った場合に、主業農家に貸し出される。しかし、2つの地代の内容を比較する限り、これは、農地1単位当たりの米売上高が同じであれば、主業農家の規模が大きく、農地1単位当たりの諸経費(コスト)が相当低くならない限り実現しない。
半端な規模拡大加算では主業農家が支払える地代は大きなものとはならないので、効果はない。3371億円という戸別所得補償予算(22年度)に対し、伝えられている規模拡大加算額は数十億である。
私が言わんとするところは単純なことである。水を流そうとしても、流そうとする方向への傾きや落差がわずかなものであれば、水は淀んでいるだけで緩慢にしか流れない。思い切って、水を流そうとすると傾斜や落差を大きくしなければならない。農地の流動化や集積も同じである。農地を流す方向と傾斜や落差が逆についてしまっているのが現状だ。この傾斜や落差を反転させ、さらに大きくするためには、減反を廃止して価格(米売上高)を大きく引き下げて、零細農家の要求する地代を大幅に低下させる一方で、主業農家に限って十分な直接支払い(所得補償)を行い、主業農家が支払える地代を高くし、両者の地代の差を政策的に大きくするのである。
米価が下がるとJA農協は米の販売手数料収入を維持できなくなるので、JAは政府に市場から米を買い入れて米価を維持するように求めている。しかし、農水省は、農家が戸別所得補償を受け取るためには減反参加が条件なので米価は下がらないだろうし、下がっても戸別所得補償が増額されるので農家は困らないとして、JAの要求に応じようとはしなかった。この主張は明快だ。戸別所得補償は農家と農協の間に打ち込まれた楔なのである。
しかし、米価はこの10年間で30%以上も低下した。減反を強化しても米消費の減少に追いつかなかったからである。今後高齢化、人口減少時代を迎え、米の総消費量はさらに減少し、米価は下がる。構造改革が進まないでコストが下がらないまま米価が下がれば、戸別所得補償に必要な財政負担は増大する。いずれ財政的に負担しきれなくなり、見直さざるを得なくなる。
その際には、高い所得を得ている兼業農家にも所得補償をするというのではなく、農家らしい農家に支援を限定せざるをえないだろう。こうすれば、規模の大きい農家の平均コストは低いので戸別所得補償の単価を圧縮できるとともに、対象農地も限定できるので、単価と量の両面で財政支出を抑えることができる。減反を廃止すれば、2000億円の財源をねん出できる。こうすれば米農業の構造改革も進み、輸出もできるような強い農業を実現できるだろう。
7.TPPと農業
TPPに参加するかどうかで国内の議論は対立している。TPPは農業にとって黒船なのだろうか?
1993年、それまで価格低落時に市場から買い入れることで穀物価格を維持してきたEUは、直接支払いを導入することで穀物価格を30%引き下げて、アメリカから輸入してきた餌用の穀物需要を域内の穀物で代替し、3300万トンほど積み上がった在庫を完全に消滅させた。現在米価低落に苦しむ農協は市場から政府が米を買い入れて価格を戻すよう主張しているが、もっともよい過剰米対策は、直接支払いと価格の引下げである。しかし、我が国農政はEUの農政改革後20年も経つというのに、価格支持政策の愚かさに気がつかないでいる。価格を下げると、別の需要を取り込むことができるようになる。日本の米にとってそれは「輸出」である。日本ではこれまで国内の食用の需要しか視野になかったことが農業生産の減少をもたらしてきた。日本の人口は減少するが、世界の人口は増加する。しかもアジアには所得増加にも裏打ちされた拡大する市場がある。高齢化、人口減少時代に、日本農業を維持、振興しようとすると、輸出により海外市場を開拓せざるを得ない。
日本を代表する自動車や電機産業は、海外市場に目を向けることによって発展してきた。農業・農政も、国内市場の防御一辺倒から国際市場の開拓に転じるべきである。
平時には農業生産は需要・消費に規定される。需要がないものは生産しても市場で消化できないからである。輸入国では、国内農産物に対する需要・消費は、全体量から輸入量を差し引いたものである。しかし、緊急時には作られるもの、あるいはあるものしか食べられないので、消費は生産、供給に規定される。輸入が途絶するという緊急時には、これまで輸入してきた食料を国内で供給しなければならなくなるが、その供給は、平時の輸入量を差し引いた需要に対応して継続されてきた生産・供給力に規定されてしまう。ここに日本のような輸入国における、農地を含めた農業資源確保の困難さがある。しかも、今後人口減少により、日本農業は縮小し、農地資源も減少する。緊急時の消費を規定する国内の生産力が大幅に減少してしまうのである。これは国内価格を高く維持しているため輸出需要を考えられないからに他ならない。
価格を下げるのだ。「関税は独占(カルテル)の母」という経済学の言葉がある。カルテルによって国内で国際価格よりも高い価格を維持できるのは関税があるからである。TPPに参加することにより、関税がなくなれば、カルテルである減反政策は維持できなくなる。減反をやめて生産を拡大すれば多面的機能は向上する。
消費者負担型農政の問題は、高い価格を消費者に負担させるので消費が減ることである。米以外の農産物は輸出できないかもしれないが、政府からの直接支払いという補助金でコストを下げていけば、国内生産を維持して多面的機能を確保したうえで、関税撤廃による安い農産物価格のメリットを消費者は受けることができる。価格が下がって消費が増えた分だけ海外からの輸入が増える。生産者も消費者も海外の生産者も得をする「三方一両得」である。貿易を自由化したうえで直接支払いによって国内生産を維持すること。これがアメリカやEUも採っている最善の政策である。
自由貿易の下での農産物輸出は、人口減少時代に日本が国内農業の市場を確保する道である。人口減少により国内の食用の需要が減少する中で、平時において需要にあわせて生産を行いながら食料安全保障に不可欠な農地資源を維持しようとすると、自由貿易のもとで輸出を行わなければ食料安全保障は達成できない。しかし、国内農業がいくらコスト削減に努力しても輸出しようとする国の関税が高ければ輸出できない。農業界こそ貿易相手国の関税を撤廃し輸出をより容易にするTPPに積極的に対応すべきなのである。
8.人材確保と農地法
農地法の基本理念は「自作農主義」だといわれている。それは、農地法が、農地改革から農業の構造改革へ進もうという農政の理想を否定し、耕作者である小作人に所有権を与えた農地改革の成果を維持・固定するためにだけ作られたからだった。農地法は、「所有、経営、耕作(労働)」の三位一体の農民的土地所有が最も適当であるとしたのである。このため、農業経営や農地の耕作は従業員が行い、農地の所有は株主に帰属するという、株式会社のような所有形態は、法律の目的や原則から認められないことになるのである。
自作農主義は多様な農業者が農業に参入する道を閉ざしてしまった。2009年の法改正により、農地法第一条から自作農主義を規定した文言は削除された。しかし、自作農主義を否定するのであれば、株式会社等の法人による農地所有を厳しく制限し、家族経営が法人成りしたような、「所有、経営、耕作」の三位一体の農民的土地所有に近い場合しか認めていない農業生産法人に関する規制は撤廃しても良いはずなのに、そのような規制緩和は行われなかった。
本来、土地や農業機械等の資本も含めた農場の「所有者」とその「経営者」は同じである必要はない。素人よりもプロが経営すべきであり、所有者(出資者)はそこに投下した資本で配当を得ればよい。これは、ブラジルなどで普及している農業経営である。
現在では、農業に新しく参入しようとすると、農産物販売が軌道に乗るまでに機械の借入れなどで最低500万円は必要である。しかし、友人や親戚から出資してもらい、農地所有も可能な農業生産法人である株式会社を作って農業に参入することは、これらの出資者の過半が農業関係者で、かつその会社の農作業に従事しない限り、農地法上認められない。農地の所有者は農業従事者に限られるのである。
このため、新規参入者は銀行などから借り入れるしかないので、失敗すれば借金が残る。農業は参入リスクが高い産業となっているのである。株式会社なら失敗しても友人や親戚等からの出資金がなくなるだけである。「所有と経営の分離」により、事業リスクを株式の発行によって分散できるのが株式会社のメリットだが、農政は、株式への出資という方法によって意欲のある農業者、企業的農業者の参入を可能とする道を自ら絶っているのである。大企業の参入がいやなら、資本金が一定額以上の株式会社は許可しないとすればよい。
農家の子弟だと、たとえ都市に住んでいようと、農作業に耐えうるような身体的・精神的な条件を持っていないものであろうと、相続で農地は自動的に取得できるし、耕作放棄してもかまわない。それなのに、農業に魅力を感じて就農しようとする人たちには、農地取得を困難にして、農業という「職業選択の自由」を奪っているのである。
株式会社にも賃貸借による農地利用は認めたが、所有権がなければ、誰も土地に投資しようとはしないし、短期間で農地の返却を求められるのであれば、農業者の地位はきわめて不安定となる。EUのように、都市地域と農業地域を明確に分ける「ゾーニング」さえしっかり行えば、農地価格が宅地用価格と連動して高い水準にとどまるという事態も防止できるため、新規参入者も規模拡大の意欲を持つ農業者も農地の所有権を取得しやすくなる。そうすれば、転用期待が実現した時に農地を返してもらえなくなることを恐れて、農地の所有権だけでなく利用権も渡さないという農家の行動パターンを抑えることができ、賃借権による規模拡大も容易になる。「ゾーニング」を確立したうえで、農地法は廃止すべきである。
終わりに
これまで農政は、食管制度、農地制度、農協制度の3つの柱で構成されてきた。農政が農民票をあてにする政治家によって左右されるに従い、国民に食料を安定的に供給するのだという農政の大義は顧みられなくなってしまった。食料が不足して困るのは農家ではなく都市生活者だということは、戦後の食糧難時代を思い浮かべるだけで十分だろう。
戦前の偉大な農本主義者、石黒忠篤(1884~1960)は、近衛内閣の農林大臣として、農民に次のように語りかけている。「農は国の本なりということは、決して農業の利益のみを主張する思想ではない。所謂農本主義と世間からいわれて居る吾々の理想は、そういう利己的の考えではない。国の本なるが故に農業を貴しとするのである。国の本たらざる農業は一顧の価値もないのである。私は世間から農本主義者と呼ばれて居るが故に、この機会において諸君に、真に国の本たる農民になって戴きたい、こういうことを強請するのである」
食料を安定的に供給するという使命を果たし、国民と消費者のために有益であってこそ"国の本"たる農業・農政といえるのである。食料安全保障の基礎となる農地を転用し、脱農業によって発展してきた今日の農業は、 "一顧の価値もない国の本たらざる農業"ではないだろうか。 "国の本"として国民・消費者のために農業は存在するのだという原点を農政は取り戻す必要があるのである。
『季刊 中国総研』No.53(社団法人 中国地方総合研究センター)に掲載


