WTO(世界貿易機関)やAPEC(アジア太平洋経済協力)などの多国間の交渉であれ、二国間のEPA(経済連携協定)であれ、わが国が貿易自由化を推進しようとすると必ず農業問題が障壁となる。
かつて、アメリカとの牛肉・柑橘交渉、ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉などにおいて、自民党政府は農業界の意見を最大限尊重して農産物の貿易自由化に強く抵抗した。これは民主党政権でも変わらない。
今回の総選挙で日米EPAの「締結」というマニュフェストの表現に対し、農協から農業を滅ぼすと抗議された民主党は、日米EPA「交渉の促進」、「農業、農村には影響を与えない」という表現に変えた。農業界のリーダーたちのなかで、WTOドーハ・ラウンド交渉の妥結やアメリカや豪州とのEPAの締結を望むものはいない。農業のために、WTOやEPA交渉において通商国家である日本が積極的な役割を果たせない事態となっているのである。
日本農業の衰退
その農業の衰退に歯止めがかからない。
1960年から2005年まで、GDPに占める農業生産は9%から1%へ、食料自給率は79%から40%へ、減少した。他方、兼業所得の比重の多い第2種兼業農家は32.1%から61.7%へ、65歳以上の高齢農業者は1割から6割へと大きく増加した。
食料安全保障の前提となるのは、農地資源の確保である。戦後、人口わずか7000万人で農地が500万ha以上あっても飢餓が生じた。国民への食料の安定供給という目的のために農業には手厚い保護が加えられてきたはずなのに、食料安全保障に不可欠な農地は転用、改廃され続けた。
公共事業等により105万haの農地造成を行った傍らで、1961年に609万haあった農地の4割を超える250万haもの農地が耕作放棄や宅地などへの転用によって消滅し、現在の総農地面積は終戦時をはるかに下回る461万haに過ぎない。この消滅した面積は、北は北海道から南は沖縄にいたる、現在のすべての水田面積250万ha(減反しているので、米を作っている面積は150ha)に等しい。
米の778%という関税に代表される異常に高い関税で国内農産物市場を外国産農産物から守っている。にもかかわらず、農業が衰退するということは、その原因が海外ではなく国内にあるということを意味している。
今後の農業を規定する2つの要因
このままでは、グローバル化と人口減少が、農業をさらに衰退させるだろう。
WTO交渉で、わが国は関税引き下げの例外品目を広く認めるよう交渉しているが、例外を認めてもらう代償として低関税の輸入割当量(ミニマム・アクセス)の拡大を要求される。国内の米生産量は850万tだが、ミニマム・アクセスは現在の77万tから消費量の13%に相当する120万t以上に拡大する。これは食料自給率を低下させるばかりか農地資源も減少させる。日本政府や農業界のWTO交渉への対処方針は、食料・農業・農村基本法の食料自給率向上という目標に反しているのである。政府がこうまでして守ろうとしているのは、米の778%に代表される高関税であり、それが守っている高い農産物価格である。農業界の本音は高い農産物価格による農業保護であり、食料自給率向上という主張は農業保護を確保するための方便にすぎないからである。
1人当たりの米消費量は過去40年間で半減した。これまでは総人口は増加したが、今後米の総消費量は高齢化による1人当たりの消費量減少と人口減少の二重の影響を受ける。2050年頃に米の総消費量が今の850万tから350万tになれば、減反は200万haに拡大し、米作は50万ha程度で済んでしまう。これにミニマム・アクセスの拡大が追加されると、30万ha程度で済むことになる。国内の食用の需要が減少するのは、米以外の農業でも同じである。その結果、日本農業は大幅に縮小し、農地資源も大きく減少する。
わが国農政の特徴
所得は、価格に生産量をかけた売上額からコストを引いたものである。わが国農政の特徴は、農家所得を向上させるために、規模拡大や収量の増加によるコスト削減ではなく、手っ取り早い方策として価格を上げたことである。その典型が米である。
総農地面積が一定で一戸当たりの規模が拡大すると、農家戸数は減少する。組合員の圧倒的多数が米農家で、農家戸数を維持したい農協は、農業の構造改革に反対した。少数の主業農家ではなく多数の兼業農家を維持する方が、農協にとって農外所得の農協口座への預け入れなどを通じた農協経営の安定や政治力維持につながるからである。食管制度の時代、農協は生産者米価引き上げのため一大政治運動を展開した。
農協の思惑通り、1960年代以降の生産者米価引き上げによって、コストの高い零細な「兼業農家」も、高い米を買うよりも自ら米を作るほうが得になり、農業を続けてしまった。零細な兼業農家が農地を手放さなかったため、農地は農業だけで生活していこうとする農家らしい主業農家に集積されず、規模拡大による米農業の構造改革は失敗した。生産量も増えずコストも下がらないので主業農家の収益は向上しなかった。
食管制度が廃止された現在も、米価は減反という供給制限カルテルによって維持され、農家をこれに参加させるために、政府から年間約2000億円、累計総額7兆円の補助金が支払われてきた。減反面積は今では100万haと水田全体の4割超に達している。500万t相当の米を減産する一方、700万t超の麦を輸入するという食料自給率向上とは反対の政策が採り続けられている。戦前農林省の減反政策案に反対したのは食料自給を唱える陸軍省だった。真の食料自給は減反と相容れない。
OECD(経済協力開発機構)が開発したPSE(生産者支持推定量)という農業保護の指標は、財政負担によって農家の所得を維持している「納税者負担」の部分と、国内価格と国際価格との差(内外価格差)に生産量をかけた「消費者負担」の部分――消費者が安い国際価格ではなく高い国内価格を農家に払うことで農家を保護している額――から成る。
各国のPSEの内訳をみると、消費者負担の部分の割合は、ウルグァイ・ラウンド交渉で基準年とされた1986~88年の数値、アメリカ37%、EU86%、日本90%に比べ、2006年ではアメリカ17%、EU45%、日本88%(約4.0兆円)となっている。アメリカやEUが価格支持から財政による直接支払い“direct payments”に移行しているにもかかわらず、日本の農業保護は依然、価格支持“price support”である(表)。国内価格が国際価格を大きく上回るため、高関税が必要となるので、WTO・FTA(自由貿易協定)に対応できない。
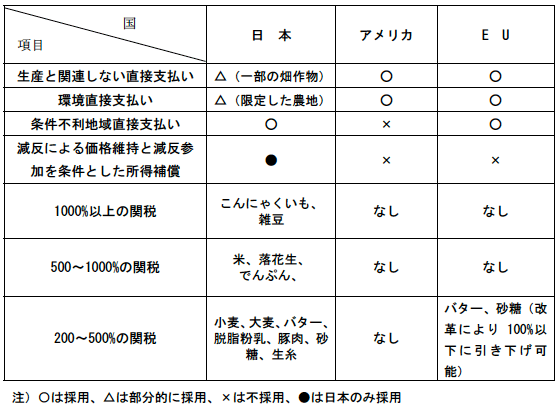
民主党の「戸別所得補償」政策とは、減反参加を条件として、農家に生産費と米価の差を政府から補填しようとするものである(ただし、小沢一郎・民主党幹事長は以前、[減反廃止を前提とする]関税ゼロでも食料自給率100%を主張した)。
しかし、この最大の問題は、実質手取り米価が大幅に上昇するため、零細な兼業農家が農業を続けてしまうことである。主業農家に農地は集まらず構造改革効果は望めない。それどころか零細な農家が主業農家に貸していた農地を貸し剥がして自ら耕作しようという動きも出ている。零細農家温存という食管制度時代の農政の繰り返しである。兼業農家の票が必要なのは自民党も民主党も同じだからである。
民主党は、米以外の農産物については、生産を拡大しようとしている。しかし、日本の農産物は供給力を低下してきた過程で、品質面やロットのまとまりで勝る外国産農産物に日本市場を譲り渡してしまった。麦、大豆についての自給率は、それぞれ13%、6%に過ぎない。品質的に国産小麦はほとんど「うどん」にしか向かない。パンやパスタには使われない。麦などの生産を拡大しても引き取り手がなく在庫が積みあがるだけだろう。「うどん」にしか向かない麦は輸出もできない。そのときには、また財政で過剰農産物の処分をすることになる。
これに対し、日本の米については高い評価が海外にはある。生産を思う存分拡大してよいのは、輸出の可能性がある米なのである。
望ましい政策
正しい政策は減反の廃止による価格低下と主業農家への直接支払いである。減反をやめて米価(60kg当たり)を需給均衡価格9500円程度まで下げれば、高いコストで生産している零細な兼業農家は農地を貸し出すようになる。主業農家に政府から直接支払いという補助金を交付して地代負担能力を高めれば、農地は主業農家に集まり、主業農家の規模が拡大し、コストは低下する。
日本の米価は国内需要の減少により10年前の約2万円から1万4000円~1万5000円台に低下しているが、日本が輸入している中国産の価格は約3000円から1万円台にまで上昇している(図)。このことは、現在でも関税は50%も要らないことを示している。減反を止めれば、米価は約9500円に低下し、中国から輸入される米よりも国内価格は下がるので、77万tの米のミニマム・アクセスのかなりの量は輸入されなくなる。直接支払いを通じた規模拡大によってコストが低下すれば、輸出できるようになり、生産量は拡大する。
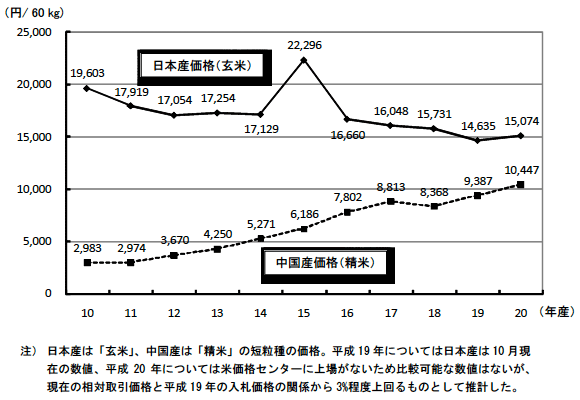
EUは、穀物価格の引き下げでアメリカから輸入していた飼料穀物を域内穀物で代替した。価格を下げると、別の需要を取り込むことができるようになる。日本の米にとってそれは「輸出」である。日本ではこれまで国内の食用の需要しか視野になかったことが農業生産の減少をもたらしてきた。日本の人口は減少するが、世界の人口は増加する。しかもアジアには所得増加にも裏打ちされた拡大する市場がある。
日本を代表する自動車や電機産業は、海外市場に目を向けることによって発展してきた。農業・農政も、国内市場の防御一辺倒から国際市場の開拓に転じるべきである。
中国への輸送経費や日中間の米の品質格差を考慮すると、国内の米価が9500円を下回るようになれば中国等への輸出が可能になるだろう。国内市場だけを考慮した需給均衡価格が国際価格を下回っても、安く買って高く輸出するという価格裁定行為によって、国内の米価も輸出価格と同一にまで引き上げられる。国内農業のコストが規模拡大により低下すれば、米の輸出量、生産量はさらに拡大する。
現在の中国の最大の内政上の問題は、都市部と農村部の1人当たりの所得格差が3.5倍以上に拡大しているという「三農問題」である。これを需要面で見ると、わが国に近い臨海部に高い所得を上げている富裕層が存在しているということである。これはわが国からの米輸出に有利な材料である。
さらに、中国が三農問題を解決していくと、農村部の労働コストが上昇していく。これは中国産農産物価格の上昇につながる。カリフォルニアでも、日本米と品質的に競合できるような米の生産には限界がある。日本のミニマム・アクセス米について、アメリカが中国にシェアを奪われてきたのはここにも原因がある。また、タイ米のような「長粒種」に比べ、日本米のような「短粒種」の国際的な需要は高まりを見せている。アメリカの米の輸出価格について見ると、昨年の穀物価格の低下と同様、長粒種米の価格は低下しているが、短粒種米の価格は逆に上昇しており、価格差は2倍に開いている。これらの要因によって、国際価格(輸出価格)が上昇すれば、国内の価格も同様に上昇し、国内生産は拡大する。
これは人口減少時代に日本が食料安全保障を確保する道である。平時には米を輸出してアメリカやオーストラリア等から小麦や牛肉を輸入する。食料危機が生じ、輸入が困難となった際には、輸出していた米を国内に向けて飢えをしのげばよい。こうすれば平時の自由貿易と危機時の食料安全保障は両立する。というよりも、人口減少により国内の食用の需要が減少する中で、平時において需要にあわせて生産を行いながら食料安全保障に不可欠な農地資源を維持しようとすると、自由貿易のもとで輸出を行わなければ食料安全保障は確保できないのである。
主業農家の規模拡大は、環境にやさしい農業を実現する。規模の小さいサラリーマン農家は週末にのみ農業を行う。このため、労働力(創意工夫も含む)の投入が限定されるので、安易に労働を農薬や化学肥料で代替してしまう。高価な労働という生産要素の利用を節約し、相対的に安価な農薬等の生産要素を多く使用するのである。農地が労働力の制約の少ないフルタイム農家に移動することにより、農薬、化学肥料の投下は減少する。零細農家が除草剤を散布して済ませてしまうところを労働で代替するからである。
農業を保護するかどうかが問題ではない。関税による価格支持か直接支払いか、いずれの政策を採るかが問題なのである。EUは先んじて農政改革を行い、WTO交渉に積極的に対応している。価格を下げることはWTOやEPA交渉に対応するだけではなく、農業の振興、食料安全保障、環境改善にも資するのである。これまでどおりの農政を続け、座して農業の衰亡を待つよりは、直接支払いによる構造改革に賭けるべきではないだろうか。
『商工ジャーナル』2010年6月号(商工中金経済研究所)に掲載


