WTO交渉が進展している。米国の政権が来年交代するので、今年を逃すと2001年から7年間もかけてきた交渉を中止せざるを得ないかもしれないという危機感が関係者にはある。
前回のウルグアイ・ラウンド交渉を振り返ると、米国が妥協する可能性は大いにある。1986年から7年間を費やした同交渉は、日本ではコメの関税化(輸入制限から関税への転換)ばかりが報道されたが、実際の主題は米国とEUの農業をめぐる交渉だったといっても過言ではない。
ブレークスルーは、交渉妥結の前年、92年11月の米国とEU間の農業合意だった。この年、米国ではブッシュ氏が大統領選挙に敗れ、翌年にクリントン氏への政権交代を控えていた。後世に名を残したいブッシュ氏は、花道としてウルグアイ・ラウンド交渉の実質妥結という道を選択した。今年、息子のブッシュ大統領は同じような選択をするかもしれない。
交渉が妥結すると、日本にはどのような影響が及ぶだろうか。
コメをはじめ国内農産物価格が国際価格の数倍も高かったかつての状況では、WTO農業交渉議長が示すように関税を7割引き下げられれば、日本の農業は壊滅的な打撃を受けることになる。これまでの農政が貿易自由化交渉に常に後ろ向きだったのは、このためだ。
ところが、後述するように、近年の国内価格の低下と国際価格の上昇によって、このような関税削減が行われても、国内農業はそれほど影響を受けない状況に変化している。
にもかかわらず、世界的に食糧危機が叫ばれているなか、日本政府は関税削減ではなく、39%を切った食糧自給率をさらに低下させる“別の選択”をしようとしている。この政策誤謬の構造を以下に明らかにしていく。
二重のペナルティで大幅なアクセスの拡大
WTO交渉への各国の対応はそれぞれの農業政策を反映している。
EUは68年に、農産物価格を高く維持することで農家の所得を向上させる共通農業政策を成立させた。農産物の高値安定は需要を抑制する一方で、生産を刺激する。その結果生じた過剰農産物を、EUは輸出補助金を付けて国際市場でダンピングした。
この政策は国際価格を引き下げ、米国など輸出国の農業に打撃を与えた。ウルグアイ・ラウンドの最大の交渉事項は、この輸出補助金による米国・EU間の一大貿易紛争にケリをつけることだった。
米国は60年代に、関税や高い価格による消費者負担型農政から、価格は市場に任せ農家への補助金で所得を保障する財政負担型農政に転換していた。
ウルグアイ・ラウンドで米国に攻められたEUは、92年に穀物などの価格を大幅に引き下げ、農家に対する補助金の「直接支払い」によって補填するという改革を行った。価格が下がれば過剰生産は減るので、EUは米国と輸出補助金削減に合意することができた。
EUは05年にも、40年間手をつけられなかった砂糖の支持価格を36%下げ、直接支払いに転換した。今回の交渉でEUは、輸出補助金の撤廃に合意している。
EUが米国と同じ直接支払い型農政に転換したため、かつての「米国vs EU・日本」という構図が、今では「米国・EU vs日本」という構図になっている。
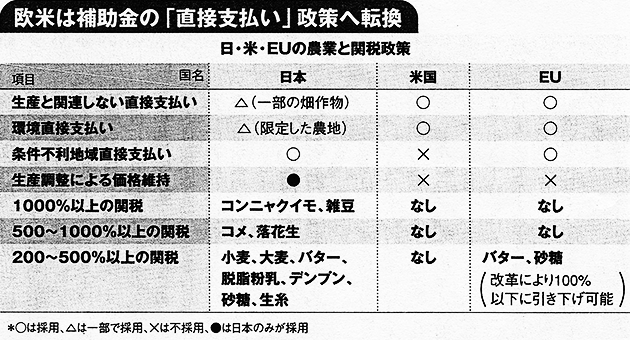
いまやEUは米国産小麦に対して関税ゼロでも対抗できる。03年に米国とEUは、一定以上の関税は認めないという上限関税率に合意。現在、日本を除く主要国のほとんどが、「上限関税率100%」という案を受け入れている。
また、高い関税の品目には高い削減率を課すという方式が合意されている。高関税品目が多い日本は、できる限り多くの品目についてこの原則に対する例外扱いを求めている。しかし、原則に対して例外を要求すれば、代償として低税率の関税割当数量(ミニマムアクセス)の拡大が求められる。これがWTOの交渉ルールである。
ウルグアイ・ラウンド交渉では、コメについて関税化の例外を得る代償として、関税化すれば消費量の5%ですむミニマムアクセスを、年々拡大して8%とする義務を日本は受け入れた。
しかし、その後、ミニマムアクセスの拡大による農業の縮小を回避するため、99年には関税化への移行に政策転換し、現在では7.2%のミニマムアクセスにとどめている。
上限関税と関税引き下げの両方に例外扱いを求めれば、二重の代償により大幅なミニマムアクセスの加重が求められる。この点、筆者は数年来たびたび警告してきた。それが、今回の農業交渉議長案では現実のものとなっている。
コメの自給率は80%台に低下する
議長案では、75%以上の関税については、その関税率に対して66~73%の削減が必要とされる。したがって、日本のコメの関税778%は、210~265%まで引き下げなければならない(以下、幅で示す数字は、この範囲内で交渉が行われ具体的な数字が決定されるよう議長が示したものである)。
「重要品目」について例外も認められるが、それは全関税品目数の4~6%に限定される。日本の全関税品目数は1332あり、その4~6%とは53~80である。
75%以上の関税の対象品目はコメや乳酸品など134品目であり、それ以外の重要品目である牛肉(26品目)を含めると160品目、全関税品目数の12%となってしまう。日本政府はこの例外品目の大幅な拡充を要求している。
しかしながら、ウルグアイ・ラウンド交渉の際のコメと同様、例外扱いの代償としてミニマムアクセスの拡大が要求される。原則として求められる関税削減率(前述の66%~73%)の3分の2の削減率のときは消費量の3~5%、2分の1の削減率のときは消費量の3.5~5.5%、3分の1の削減率のときは消費量の4~6%のミニマムアクセスを新たに設定しなければならない。
3分の1の削減率を適用するとコメの関税率は589~607%となる。現在の77万トンのミニマムアクセスに加え、消費量900万トンの4~6%にあたる36万~54万トンのミニマムアクセスを設定しなければならない。その合計113万~131万トンは国内消費量の13~15%に達する。これを国内で処分すれば、過剰で水田の4割の面積を減反しているにもかかわらず、コメの自給率は85~87%に低下する。
これまでミニマムアクセス米は国内での処分をためらったため、保管料の負担などにより11年間で601億円の差損が生じ、なお175万トンの在庫を抱えている。処分しなければ財政負担が必要だ。
99年に決断したコメ関税化への移行は、7.2%から8%への0.8%のミニマムアクセスの拡大を回避するためだったことを考えると、大幅な拡大である。小麦についてもアクセスは消費量の90%以上になってしまい、麦作振興による自給率の向上の余地は絶たれてしまう。
コメの現状価格差では100%も要らない関税
問題はそれだけではない。日本政府は、議長案に上限関税率の記述がないことを交渉の成果としているが、これは問題だ。
議長案は100%を超える関税品目が全関税品目数の4%を超える場合、関税削減の例外としたすべての「重要品目」についてさらに消費量の0.5%のアクセスを追加すると規定している。上限税率回避の代償はすでに盛り込まれているのだ。
仮にコメを例外扱いしないで73%削減した場合でも、関税は100%を超えてしまう。このとき、乳製品などとともに関税50%の牛肉についても0.5%のアクセスの追加が必要となる。牛肉がコメの犠牲になる。
つまり、前述したとおり、関税削減の例外と上限関税率回避の二重の代償を支払う必要があるのだ。しかも、政府はこのペナルティを受ける品目をさらに拡大するよう交渉している。これによって日本農業は大幅に縮小し、食糧自給率もさらに低下してしまう。
そもそも関税削減の例外や上限関税率反対を主張しなければならないほど、高い関税は必要なのだろうか。
現在の高い関税は、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果である。各国の農業保護がエスカレートし、国際価格が大きく低下した86~88年当時の大きな内外格差を関税に置き換えたため、必要以上の水増し関税が認められた。これは当時、「汚い関税化」といわれた。
コメの60キログラム当たり2万円という関税(前述の778%という数字はこの関税を安いタイ米価格と比較したもの)は、今の国内米価1万4000円より高いので、輸入米価格が0円でも輸入されない。しかも、コメ、麦、砂糖、乳製品などの国際価格は近年上昇している。
日本米と品質的に近い中国産短粒種米の実際の輸入価格は、98年の3000円から1万円まで上昇している(下図参照)。国内米価からすれば、関税は100%も要らないのだ。
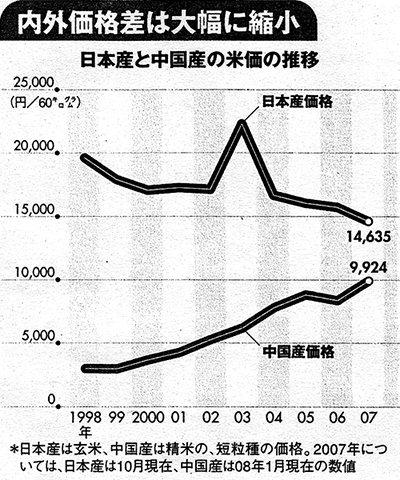
現に農林水産省が徴収しているマークアップといわれる関税見合い額(これが必要な関税率に相当する)はここ3年間、50~80%にすぎない。
世界の農産物貿易が過剰から逼迫へと構造転換しているのに、政府は相変わらず過剰時の低い国際価格を想定した関税による保護という対応しかできないでいる。
生産調整をやめ主業農家に直接補填を
食糧管理法時代の米価引き上げによってコメは過剰になった。その対策としての減反または転作による生産調整は年々拡大し、現在では260万ヘクタールの水田の110万ヘクタールに及んでいる。
この40年間で1人当たりのコメ消費量は半分になったが、今後は人口減少の影響も受けるので、2050年頃にはコメの総消費は現在の900万トンから350万トンにも減少する可能性がある。そうなれば生産調整を210万ヘクタールへ拡大し50万ヘクタールで稲作を行うしかない。
これに先述のミニマムアクセス113万~131万トンが加われば、生産を230万トン、水田面積で33万ヘクタールへさらに縮小せざるをえない。これが、日本政府が実現しようとしている交渉の成果である。
では、生産調整をやめてはどうか。筆者の試算では価格は60キログラム当たり約9500円に低下し、需給は1000万トン以上に拡大する。EUは価格を引き下げて財政による直接支払いで補償した。
食管制度以来、米価引き下げに対しては農業団体から農業依存度の高い主業農家が困るという反論がなされてきた。であれば現在の1万4000円と9500円の差の8割程度を、主業農家に補償すればよい。流通量700万トンのうち主業農家のシェアは4割なので約1600億円の予算額ですむ。これは、生産調整に参加させるために農家に支払っている今日の補助金と同額である。
圧倒的に農外所得の比重が高く土日しか農業に従事しないパートタイム(兼業)農家も、主業農家に農地を貸せば現在の10万円程度の農業所得を上回る地代収入を得ることができる。さらに主業農家の規模が拡大してコストが下がれば、主業農家の所得が上昇するとともに、兼業農家が受け取る地代も増加する。
財政負担は変わらないうえ、価格低下で消費者の負担は大きく軽減される。中国から輸入されるコメよりも国内価格は下がるので、今まで日本を苦しめてきた77万トンのコメのミニマムアクセスのかなりの量は輸入されなくなる。関税も要らない。
それだけではない。価格低下は新しい需要も盛り込むことができる。EUは穀物価格の引き下げで米国から輸入していた飼料穀物を域内穀物で代替した。これまで国内の食用の需要しか視野になかったことが農業生産の減少をもたらした。日本の人口は減少するが、世界の人口は増加する。
しかもアジアには所得増加にも裏打ちされた拡大する市場がある。日本を代表する自動車や電機産業は、海外市場に目を向けることによって発展してきた。農業・農政も、国内市場の防御一辺倒から国際市場の開拓に転じるのだ。
自給率が39%であることは61%の食料を国際市場で調達し、食料輸入途上国の飢餓を増幅させているということにほかならない。
戦後の消費者負担型農政を転換し、生産調整を廃止して輸出で日本農業を縮小から拡大に転じることこそ、日本が食料難時代に行える国際貢献であり、かつわが国の食糧安全保障につながる道である。これは、またWTO交渉に積極的に対応する道でもある。
『週刊ダイヤモンド2008年7月12日特大号』に掲載


